1997年 学界展望
労働経済学研究の現在─1994~96年の業績を通じて(3ページ目)
2. 労働需要
論文紹介(駿河)
宮川努・玄田有史・出島敬久「就職動向の時系列分析」
日本の就職動向は長期的には労働需要量を変動させる要因にのみ支配されていることを、実証的に示している。まず集計マッチング関数の推計を行って、コ=インテグレーション・テストにより労働需要と労働供給いずれの要因が就職動向に長期的な影響を与えているかを検討。就職者と求人数は一つの共通な確率トレンドに従っており、就職行動は長期的には労働需要側の要因にのみ規定されている。
短期的影響を見るためにエラー・コレクション・モデルにより集計マッチング関数を推定。常用雇用者の就職者数の長期均衡からの乖離は1年で調整されることを示している。
浦坂純子・大日康史「新卒労働需要の弾力性分析─3時点間のパネル推定」
パネルデータを使用して、トービット・モデルで経常利益と新卒採用者数の関係を推定している。推定の結果は、次のようになっている。経常利益の黒字の増加に対して、女子の採用増加が男子の増加を上回る。経常赤字の増加に対して女子の採用減は男子を上回る。この結果は、「景気が悪くなれば、女子学生から切る」という議論と整合的である。
男女ともに、文系に比べて理系のほうが弾力性が小さい。理系の男女では、経常黒字期はほぼ同レベルであるが、赤字期には女子の弾力性が著しく大きい。文系の男女間には有意な差はない。短大卒は黒字期に弾力性は文系大卒男子よりも大きく、赤字期には小さくなる。検定では赤字期に文系女子と有意な差はない。
全従業員を使用した分析は、弾力性は新卒採用者に比べて非常に大きいことを示した。したがって雇用調整が主に新卒採用で行われているという仮説を棄却している。ただし、分析期間を長くとると、全従業員による弾力性は小さくなる。
駿河輝和「日本の企業の雇用調整:企業利益と解雇」
雇用調整について、「1期の大きな赤字または2期連続の赤字で企業は解雇を行う」という経験則が確かめられている。この経験則を基に赤字雇用調整モデルを考案した。すなわち、大きな赤字期には解雇を使用し、解雇には組合との調整などかなり大きな固定費用が必要であるため、調整速度は速くなる。それ以外の通常のときには、解雇に対して非常に強い抵抗があり、解雇の実行が不可能なほど固定費用が高くなる。したがって、解雇を使用せずそれ以外の手段により雇用調整を行わざるをえず、雇用調整速度も遅くなる。この赤字調整モデルを個別企業のデータを使って調べている。またその他の代替的モデルと推定結果を比較もしている。その結果、いくつかの企業でこのモデルがよく当てはまることが確かめられた。しかし、大きな赤字でも解雇を行わずに出向で済ます鉄鋼では、調整速度は速くなっておらず、モデルはうまく当てはまらない。
- 駿河
-
では、次に、労働需要関係に移ります。最初の宮川・玄田・出島論文は、就職者数は、労働需要の大きさが主として決めているということを言っているわけで、われわれが雇用分析をするときに、主として企業の労働需要という側面の分析をしていれば大体間違いがなくて、供給側にさほど考慮を払わなくてもいいということを主張されているわけですから、雇用分析をする意味でも非常にありがたいと思います。
2番目の浦坂・大日論文は、経常利益の変化が新規学卒者の就職にどういう影響を与えるかという問題を扱っていまして、現在、不況下で新卒者、特に女子学生の就職難というのが非常に問題になっているだけにタイムリーな論文になっていると思います。女子学生、それも文系の学生のほうが景気の調整に使われているという結果を得ていて、われわれの直感とかなり合う結果になっています。
3番目の駿河論文は、2期連続の赤字、あるいは1期の大きな赤字で解雇が起こるという経験則を労働需要理論の枠組みの中へ取り込もうと試みたものです。一般に雇用調整速度の変化は、大体これまでの議論では生産の大きな変化で起こると言われていましたけれども、雇用調整速度の大きな変化は、生産量ではなく経常利益の変動によって生じるというふうに分析しています。経常利益に対して雇用の変化を入れている点で浦坂・大日論文と共通する点があるわけです。
討論
- 奥西
-
宮川・玄田・出島論文ですけれども、私は時系列分析については素人で、テクニカルな部分は必ずしも十分理解できなかったのですが、結論の一つの理解の仕方として、経済学の入門的教科書にあるトレーディング・ローカス(取引可能軌跡)の考え方が使えないかと思いました。これも図をお配りしたんですけれども(図2)、需要曲線と供給曲線があります。需要と供給が均衡しなくても取引されるとすると、太線のところで取引が行われます。そうすると、需要のほうが効いているというのは、超過供給、言い換えると賃金が均衡賃金に比べて高すぎる、そういう状態が支配的だったというのが一つの理解の仕方だと思うんです。
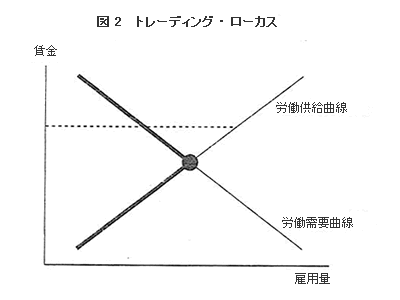
そうすると、1970年から91年という計測期間は、高度成長期の末期と、バブルの時期がちょうど最初と終わりに入っていますけれども、どちらかというと、需要が弱くて、供給はそれなりに増えていた時期だから、その時期だとこういう結果が出ても不思議はないなと思います。しかし、もしこういう理解の仕方が正しいなら、今後、労働力人口が減ると、違う局面があらわれる可能性もあるのかなということを感想として思いました。
- 駿河
-
一般には大企業の労働市場の場合には労働需要だけで採用を決定していて、中小企業の場合には需要側の側面が強く出るときと供給側の側面が強く出るとき、それが交差するという説もあります。それから、バブル経済のときには供給制約ということを盛んに言われたわけで、もう少し期間を区切ってやると違う結果が出る可能がありますね。
- 金子
-
期間を区切るとして、こういうコ=インテグレーション・テストみたいなことをする必要がありますよね。時系列分析独特の手法を期間を区切ってやったとしても、それをやっておかないと。
- 駿河
-
あとはデータですね。特に求職者側のデータがうまく供給側の要因を拾いきれていないかもしれない。いろいろ工夫されて、四つぐらい変数をとられているんですけれども、その可能性はあります。
- 金子
-
あと一つ、重要なのは、宮川・玄田・出島論文は労働市場の需要面で数量割り当てがありうることを示しているし、駿河論文は日本の企業の雇用調整を取り上げているわけで、どちらかというとマクロ経済学のミクロ的基礎づけと関係する労働需要ですよね。1970年代のいわゆるオイルショック後の雇用調整関数を推定した論文は、ほぼ間違いなくマクロ的な生産関数を想定しておいて、そこから雇用調整関数を導いていた。それに対して、駿河論文は調整費用関数を導入するために、ミクロ的な企業行動のモデルづくりから出発して実証分析へ持っていく方法がとられています。大滝雅之さんの『景気循環の理論』での労働市場分析にしても、これらの実証研究にしても、労働需要の把握の仕方がマクロ経済学のミクロ経済学的基礎との関係を随分重視するようになったなという気がするんです。
- 駿河
-
浦坂・大日論文ですけれども、これは今までの労働需要の分析と全然違い、これまでの労働需要の分析というのは、労働需要関数を持ってきて、主要な労働需要の決定要因というのは、一つが生産量の大きな変化、もうーつは、資本と労働の代替、この二つが主として大きな要因として説明変数に入っていたわけです。けれども、この論文では2要因とも入っていなくて、経常利益だけでやっているということで、独創的な反面これまでの労働需要関数との関連がほとんどわからないという問題点があります。
- 金子
-
でも、計量経済学的には、ある仮説を立てて、説明変数と被説明変数を立てておいてやるという点では、別に問題ないわけですね。
- 駿河
-
問題はないですけれども、ただ、これまでの蓄積された研究との関連が不明です。
- 奥西
-
理論的な面で、これは駿河さんの論文のところでお聞きしようかと思っていたんですけれども、この二つの論文は、浦坂・大日論文は採用の話、駿河論文は解雇の話ですけれども、ある意味で共通しているのは、生産量よりもむしろ経常利益というものが何らかの意味で効いているという話なんですね。ところが、経常利益というのは通常の新古典派のモデルから導かれる労働需要関数の変数には入らないですね。それを理論的にどう理解するか。
- 金子
-
双対性アプローチを使って考えれば、制約されたプロフィット・ファンクションを暗黙のうちに仮定していて、制約の一つにある経常利益水準をとると想定すればいいのではないですか。そうするとホテリングの補題によりプロフィット・ファンクションから経常利益水準を制約とする労働需要関数を導くことができるから、労働需要に対する経常利益の弾力性を導くことができます。そうすれば、経常利益を取り上げて労働需要の弾力性を測っても、別におかしくないと思うんです。
- 駿河
-
私の論文は、一応、労働需要は生産量で動くというふうにはなっているのですが、経常利益で調整係数のほうが大きく変動するとなっています。ただし、どうして経常利益により大きく変動するのかは、今までの経験則に頼っていて、その辺の理論づけというのは少し不明瞭かもしれません。
- 奥西
-
そういう見方が間違っていると言っているのではなくて、どういうからくりなのかなということに興味があるので質問したんですが。
- 駿河
-
大きな経常赤字が出た場合には、今までの慣行を保持するコストが非常に高くなる。それでいて、解雇を労働者側も割と受け入れやすくなって、こういう大きな赤字が出ているのであれば解雇もやむをえないなということで、解雇の交渉のコストが、ある程度その時期だけ特別安くなると考えてモデルをつくっています。
- 奥西
-
駿河さんの論文の中で、そういった交渉コストの問題とか、労使協議制の問題を取り上げておられますね。その議論はよくわかるのですが、ただ、その場合も、意地悪な言い方をすると、たとえば労使間で今ほんとうに企業が左前かどうかをお互い確認し合うときに、収益という指標よりは生産という指標のほうが操作のしにくさもあって、合意しやすいという見方はできないでしょうか。
- 駿河
-
私の場合はそうでないと考えているんですね。利益のほうに対しての反応が大きい。生産量の減少ではない。
- 奥西
-
たとえば労使の間で一種の、利潤分配方式のような賃金決定がなされているとか、そういうメカニズムがあるのなら、それなりにわかるんですが。
- 駿河
-
ただ、企業の存続を考える場合には、生産量は減っているけれども、ある程度利潤が出ているというのよりは、利潤がすごく減っている、今後も減りそうだということのほうが、企業の存続に対する危機意識は強くなりますよね。
- 奥西
-
そうすると、当期の利潤がマイナスであることそれ自体というより今後の企業の期待成長のようなものを利潤指標がとらえているということでしょうか。
- 駿河
-
倒産の危機というか、つぶれる危機ということの影響が大きくて、赤字が何期か連続してくると、危機感が募ってくると私は見ています。
- 金子
-
ある意味では、労使ともに学習効果が働いているというんでしょうか。雇用調整や解雇しなければいけないときにしなかったために、赤字が累積してかえってより大きな調整を要したような経験があったとすれば、その経験を学習することによって、雇用調整や解雇しないことの機会費用が高くなることが労使双方に認識されてくるわけですね。
- 駿河
-
そうです。情報をお互いにどのくらい共有しているかが問題です。
- 金子
-
かつ景気循環のプロセスで情報を蓄積していく。でなければ、もし瞬時に学習するのだったら、1年後、2年後とラグをとる必要がない。
- 駿河
-
お互いに労使協議制度を通じて情報のやりとりをし、学習を行っているということですね。
浦坂・大日論文に戻りますけれども、浦坂・大日論文というのはきれいな結果が出ています。これはデータをとった年数が非常にいいのではないか。1993年、94年、95年という不況の時期だったので、余剰設備がたくさんあり、資本と労働の代替があまり問題にならなくて、経常利益に反応して、新規労働需要が変動したためよい結果が出たと解釈しています。ですからこれを別の時期とか、長期に当てはめると、やはり当てはまらないのではないかというのが私の予想なんですけれども。
それともう一つは、新規採用者のところでどのくらい雇用調整が行われているかというのをテストするために、従業員計で同じことをやっているんですね。ですけれども、新規労働者の採用という変数はフローですし、全従業員のところはストックの変数で、同じことをやって弾力性の差で見るというのは少し疑問があるのではないかと思いました。
- 奥西
-
その点については、たとえば「雇用動向調査」などで、一応ストックの変化とフローの変化がわかりますから、それを見るという、単純なやり方のほうがわかりいいのではないかなと思いました。
- 金子
-
いずれにしても、浦坂・大日論文で、先ほど奥西さんが心配したマイクロ・ファウンデーション等のつながりが、もう少し明確になればいいなという意味で、今後、この分野の研究の発展が期待されます。この3論文は実証の手法というのはみな手堅いと思うんです。時系列分析を要するところ、あるいは、浦坂・大日論文のようにデータに即したトービット・モデルを使い、かつ労働需要の弾力性を評価する際にもマージナル効果を区別するように努めています。計量経済学的には評価できる手法をとっています。


