派遣規制を強化
―しかしIAB調査では多くが適用外の可能性も
メルケル首相率いる連立政権は現在、派遣労働の規制を強化しようとしている。無制限だった派遣期間に18カ月の上限を設け、派遣先企業の正規労働者との均等待遇を9カ月以内に実施するよう法律で要請する方針だ。しかし、ドイツ労働市場・職業研究所(IAB)の調査によると、派遣労働者の多くは3カ月以下の短期間しか派遣されておらず、政府が計画する規制の適用から外れる可能性が指摘されている。
規制緩和から強化へ
ドイツの派遣労働は、1972年に労働者派遣法(AÜG)が制定されて以来、数十年間にわたり、主に規制緩和の流れの中で発展してきた(表1)。その目的は、企業から出される柔軟化の要請に対応し、派遣労働の雇用可能性を拡大することだった。
| 施行日 | 主な改正内容 |
|---|---|
| 1982年1月1日 | 建設業の現場作業への派遣禁止 |
| 1985年5月1日 | 派遣期間上限の延長(3カ月→6カ月) |
| 1994年1月1日 | 派遣期間上限の延長(6カ月→9カ月) |
| 1997年4月1日 | 派遣期間上限の延長(9カ月→12カ月) 初回に限り、派遣労働契約期間と派遣期間の一致を容認 有期派遣労働契約の容認(更新は最大3回まで) |
| 2002年1月1日 | 派遣期間上限の延長(12カ月→24カ月) 同一派遣先企業での均等待遇原則の導入(13カ月以降) |
| 2003年1月1日 | 派遣期間上限の撤廃(24カ月→無制限) 派遣労働契約期間と派遣期間の一致の禁止の撤廃 再雇用制限の撤廃 建設現場における派遣制限の緩和(労働協約による容認) 派遣労働初日からの均等待遇原則の導入(失業者派遣や労働協約による例外あり) |
| 2012年1月1日 | 派遣労働者に対する最低賃金の導入 |
| 現在計画中 | 派遣期間の上限再設定化(無制限→18カ月) |
| 同一派遣先企業での均等待遇原則の導入(9カ月以内) |
- 出所:Bundesagentur für Arbeit (2014)をもとに作成。
しかし、規制緩和が進む一方で、一部の使用者寄りの労働組合が不当に低い賃金協約を締結したり(注1)、同一企業で正規労働者が安価な派遣労働者に代替される事態が発生する(注2)など、派遣労働をめぐる問題も増加した。そのため2012年には、派遣労働者に対する最低賃金が導入され、規制の再構築が行われた。今回の計画は、この再構築の流れをさらに強めるもので、派遣期間の上限を再び設定(18カ月)し、派遣先企業における正規労働者との均等待遇を遅くとも9カ月以内に実施するように求めている。
派遣労働者の割合は全労働者の2.5%
派遣労働者数は、変動はありつつも長期的にみると増加している(図1)。特に、2003年に派遣期間の上限撤廃し、大幅な規制緩和を行った結果、企業にとって派遣労働の利用価値が増し、2004年から2008年にかけて派遣労働者数は倍増した。しかし、従属的労働者の総数(全労働者)に占める割合を見ると、従属的労働者約3400万人に対して、派遣労働者は85.2万人と、約2.5%しか占めておらず(2013年6月末時点)、全労働者に占める割合は未だに低い。
図1:派遣労働者数の推移(1973年~2013年)
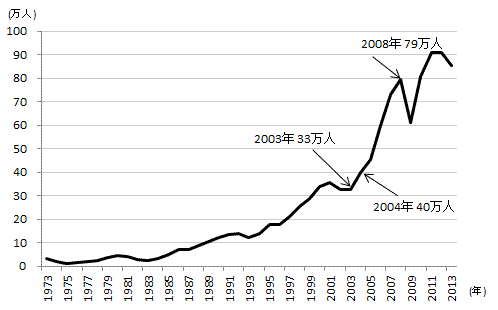
- 出所:Bundesagentur für Arbeit(2014) Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe - Zeitreihe ab 1973
- 注:各年6月の統計
激しい労働移動の実態
このような現状を踏まえて、ドイツ労働市場・職業研究所(IAB)が実施した派遣労働の実態調査、特に「就労期間」に焦点を当てた調査によると、派遣労働者数の推移の背後には、激しい労働移動の実態が隠されていた。例えば2012年には労働者派遣業において、98万件の新規契約が締結されたが、同時に120.5万件の契約が終了していた。また、2000年から2012年までの調査期間において、労働者派遣業は年平均で8.5%の成長率を記録したが、この成長は持続的なものではなく、景気に敏感に反応して乱高下を繰り返していた。例えば2006年には派遣労働者数が32%も増加したが、経済・金融危機の間に再び約23%縮小し、2009年から2010年の間にはマクロ経済よりも早い回復速度で再び32%増加している。
期間は大半が3か月以下
この頻繁な労働移動の実態から、派遣労働者と人材会社との間の契約関係は短期間で締結されていると推測される。実際にIABが分析した結果、派遣労働者の大多数は派遣期間が3カ月以下だった一方で、同じ業種で中断なく、非常に長期間就労する派遣労働者が少数存在していたことが判明した。従って、最も実態に近いと思われるフローベースで算定された派遣期間の中央値の推移を見ると、2000年以降は、2.8カ月から3.4カ月へわずかしか上昇しておらず、長期間就労する派遣労働者はほんの少数で、就労関係が長期化する傾向も非常に弱いことが明らかになった。このことからまた、「派遣先の企業が近年、正規労働者を、長期派遣労働者に置き換えている」という、散見される推測については、今回の調査では確認できなかったとしている。
規制強化の影響予測
IABはこの調査結果を基に、政府が計画している派遣期間の上限設定(18カ月)と派遣先における均等待遇(9カ月以内)の実施については、「大半の派遣労働者が適用対象外になる可能性がある」と指摘している。また、今回の規制強化が派遣労働者の就労期間に影響を与えるかどうかは「現時点では分からない」と結論付けている。
注
- ドイツの派遣労働者は原則として、労働者派遣法(AÜG)に基づいて、同一労働同一賃金の原則に則った賃金を受け取ることができる(均等待遇原則)。しかし、派遣元の人材派遣会社と労働組合の間で特定の労働協約がある場合、この均等待遇原則からの逸脱が許容される。派遣労働者の労働協約は複数存在するが、3つの労働組合(CGM, DHV, GÖD)で構成する連合体で、2002年に結成されたキリスト教派遣人材労働組合 (CGZP)は、設立以来、一貫してドイツ労働総同盟(DGB)など他の労働組合よりも低い条件で労働協約を締結し、問題となっていた。こうした事態に対して連邦労働裁判所(BAG)は2010年12月14日、CGZPの労働協約締結能力(資格)を認めず、当該協約を無効とする判決を下した。
- ドイツ最大のドラッグストア・チェーンであるシュレッカー社は、複数の支店を閉鎖して経営上の理由に基づいて従業員を一旦解雇した後に、同社元幹部が所有する人材派遣会社を通じてこれらの従業員を派遣労働者として雇い入れて、新規店舗を開き、そこで安価な賃金で働かせていることが大きな社会問題となった。同社は、社会的な批判を受けた後、派遣会社との提携を解消したが、企業イメージの悪化や売上の落ち込みなどにより2012年1月に破綻し、最終的には、同社の引き受け先が決まらなかったため6月5日に解体されることが決まった。
参考資料
- IAB-Kurzbericht Nr. 13, Juli 2014 Zeitarbeit in Deutschland Hohe Dynamik und kurze Beschäftigungsdauern (PDF:1.52MB)
 von Peter Haller und Elke J. Jahn
von Peter Haller und Elke J. Jahn - Bundesagentur für Arbeit(2013),Antragsverfahren für die Erteilung und Verlängerung von Erlaubnissen nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz bei der Bundesagentur für Arbeit.
- Koalitionsvertrag zwischen CDU (PDF:1.65MB)
 , CSU und SPD (PDF:1.65MB)
, CSU und SPD (PDF:1.65MB) (18. Legislaturperiode), Deutschlands Zukunft gestalten
(18. Legislaturperiode), Deutschlands Zukunft gestalten - Der Bundeswahlleiter, Vorläufiges amtliches Ergebnis der Bundestagswahl 2013, Pressmitteilung 23. 9. 2013

- Der Bundeswahlleiter, Endgültiges amtliches Ergebnis der Bundestagswahl 2013, Pressmitteilung 9. 10. 2013

- 毛塚勝利「ドイツにおける雇用・労使関係政策の新たな局面」『連合総研レポート No.290(2014年2月号)』
関連記事
- 海外労働情報2013年12月「第三次メルケル政権、SPDと連立協定―労働分野の政策、中道左派色が濃厚に」
- 海外労働情報2013年8月「一時的」でない労働者派遣、従業員代表の判断で拒否が可能に―連邦労働裁判所が新たな判断」
- 海外労働情報2013年5月「社会民主党と左派党、「請負契約の濫用」規制法案をそれぞれ提出」
- 海外労働情報2012年7月「金属産業の派遣労働者に特別手当―IGメタルと派遣事業主団体が合意」
- 海外労働情報2012年5月「派遣労働者に最低賃金、1月に導入」
- 海外労働情報2011年4月「派遣の低賃金協約無効判決」
- 労働政策研究・研修機構 報告書(2011)「諸外国の労働者派遣制度」
2014年10月 ドイツの記事一覧
- 派遣規制を強化-しかしIAB調査では多くが適用外の可能性も
- 父親の育児参加を促す新しい家族政策
関連情報
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2014年 > 10月
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > ドイツの記事一覧
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 非正規雇用、労働法・働くルール、労働条件・就業環境
- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > ドイツ
- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > ドイツ
- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > ドイツ


