貧困と格差めぐり議論が沸騰
―「第3次貧困・富裕報告書」を閣議決定
連邦内閣は6月25日、「ドイツの生活状況――第3次貧困・富裕報告書」を閣議決定した。前シュレーダー政権の実施した労働市場改革の評価と今後の政策方向、当面の政策課題である最低賃金関連法をめぐる議論などが絡んで、最終報告書に至るまでに修正を3回も重ねるほど難航し、公表にようやく漕ぎ着けた。報告書によれば、2005年の貧困率は13%で、2003年時点よりも低下している。しかし、従来のデータソースでは貧困率が上昇するため、データのありかたも含めて論争が展開された経過があり、報告書発表後も「貧困と格差」をめぐる議論は収まりそうもない。日本と同様、ドイツでも「貧困と格差」がいまや社会問題の焦点となっていることを浮き彫りにしたといえそうだ。
相対的貧困率は13%
報告書の相対的貧困率の定義は、所得分布の中央値の60%未満の人が全人口に占める割合である。今回の報告では、貧困層は手取り所得が月額781ユーロ未満の単身者および月額1640ユーロ未満の4人家族世帯、また、富裕層に属するのは、手取り所得が月額3268ユーロ以上の単身者、月額6863ユーロ以上の4人家族世帯(所得分布の中央値の200%以上の層)とされている。
図1EU諸国の相対的貧困率(2005年):EU-SILC
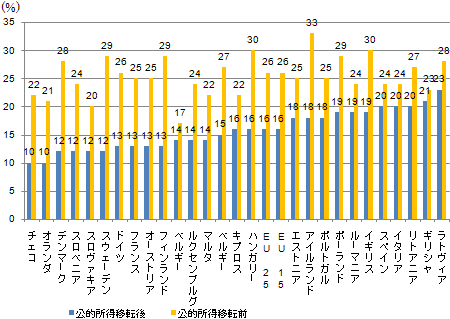
注:EU-SILC: The European Union Statistics on Income and Living Conditions.
出所:Tabell A.1, Lebenslagen in Deutschland- Der 3. Armuts-und Reichtumsgericht der Bundesregierung.
報告書によると、2005年のドイツの相対的貧困率(13%)はEU諸国平均(16%)を若干下回っているが、公的所得移転(失業給付II、社会扶助、児童手当、住宅手当等)前の貧困率(26%)はEU諸国平均と同数値となっており(図1)、社会給付による再分配効果がEU平均より高いことがわかる。
男女別では、男性(12%)より女性(13%)がやや高く、年齢別では16-24歳層(15%)が最も高い。また、児童(15歳未満)の貧困率は12%で、公的所得移転前の場合33%を上回るとの推計だ。就業状況別では、当然ながら失業者が最も高く(43%)、いわゆるワーキングプア(働く貧困層)の貧困率は6%に過ぎない。扶養児童を伴う世帯別でみると、夫婦世帯(9%)に比して1人親世帯(24%)の貧困率が圧倒的に高い。東西の格差は縮小しつつあり、旧西ドイツ地域(12%)、旧東ドイツ地域(15%)となっている。
時系列比較でみると、2005年の貧困率は2003年時点(14%)より1%低下しており、属性別でも50歳以上層、失業者、年金生活者、扶養児童を伴う夫婦世帯で貧困率の若干の上昇がみられたに過ぎず、全体として格差が縮小傾向にあることを示している。ちなみに、富裕層の割合は単身者のみで8.8%と公表されている。
| 貧困率 | 1998年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|
| 所得の中央値の60%未満の人の割合 | ||||
| 合計 | 12% | 14% | 12% | 13% |
| 公的所得移転前 | 22% | 24% | 23% | 26% |
| 女性 | 13% | 14% | 13% | 13% |
| 男性 | 11% | 13% | 11% | 12% |
| 旧西ドイツ地域 (ベルリンを除く) |
11% | 12% | 11% | 12% |
| 旧東ドイツ地域 (ベルリンを含む) |
17% | 19% | 16% | 15% |
| 年齢別 | ||||
| 15歳未満 | 14% | 15% | 11% | 12% |
| 16~24歳 | 15% | 19% | 15% | 15% |
| 25歳~49歳 | 12% | 14% | 11% | 12% |
| 50 歳~64歳 | 10% | 12% | 13% | 14% |
| 65歳以上 | 13% | 11% | 14% | 13% |
| 就業状況別 (16歳以上) | ||||
| 全被用者 | 6% | 7% | 5% | 6% |
| 失業者 | 33% | 41% | 40% | 43% |
| 年金生活者 | 12% | 12% | 13% | 13% |
| 扶養児童を伴う世帯 | ||||
| 一人親世帯 | 35% | 35% | 25% | 24% |
| 夫婦世帯 | 11% | 12% | 8% | 9% |
出所:Tabell A.1及びQ7, Lebenslagen in Deutschland- Der 3. Armuts-und Reichtumsgericht der Bundesregierungより作成。
従来データソースでは貧困率は上昇
こうした結果を受け、報告書は「社会福祉国家ドイツは依然として機能している」と強調し、「失業給付II、社会扶助、基礎保障、住宅手当、家族給付などの社会給付により貧困率が半減し、EU平均を下回った」と評価。そのうえで、「今後の貧困対策の鍵は、教育や雇用の向上を通じた社会参加の機会の拡大にある」と分析している。
しかし、2001年、2005年に政府が公表した第1次、第2次の報告書(注1) では、今回活用されたEU統計(EU‐SILC)ではなく、社会経済パネル(SOEP)に基づいた貧困率を公表してきた。これについて政府は、EUレベルでの国際比較を可能とする目的で異なるデータソースを活用したと説明している。だが、SOEPに基づく2005年時点の貧困率(18%)は2003年(16%)より上昇しており、貧困層が増加し、格差の拡大傾向が続いていることを示している。
児童の貧困率をみると両者の数値の乖離はさらに顕著で、SOEPでは26%であったのに対し、EU-SILCでは12%に過ぎず、時系列の推移でも、SOEPでは2003~2005年に児童の貧困率が3%上昇しているが、EU統計では3%低下している。1人親世帯についても同様で、SOEPが示す数値では過去7年間36%前後で推移しているが、EUデータによれば2005年の貧困率(24%)は、2003年に比して11%低下している。また、いわゆる「ワーキングプア(働く貧困層)」の割合も、SOEPの数値ではEU統計の倍(12%)に及んでいる。
| 貧困率 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得の中央値の60%未満の人の割合 | ||||||||
| 合計 | 12% | 12% | 13% | 15% | 16% | 16% | 17% | 18% |
| 公的所得移転前 | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% |
| 女性 | 13% | 14% | 15% | 17% | 17% | 18% | 19% | 21% |
| 男性 | 10% | 10% | 12% | 13% | 14% | 14% | 15% | 16% |
| 旧西ドイツ地域 (ベルリンを除く) |
11% | 11% | 13% | 14% | 15% | 15% | 16% | 17% |
| 旧東ドイツ地域 (ベルリンを含む) |
15% | 15% | 16% | 18% | 19% | 20% | 22% | 22% |
| 年齢別 | ||||||||
| 15歳未満 | 16% | 16% | 18% | 20% | 22% | 23% | 25% | 26% |
| 16~24歳 | 18% | 16% | 20% | 23% | 22% | 24% | 26% | 28% |
| 25歳~49歳 | 10% | 10% | 11% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% |
| 50 歳~64歳 | 9% | 10% | 11% | 11% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 65歳以上 | 11% | 11% | 12% | 14% | 12% | 12% | 11% | 12% |
| 就業状況別 (16歳以上) | ||||||||
| 全被用者 | 6% | 6% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% |
| 失業者 | 30% | 31% | 36% | 40% | 42% | 44% | 47% | 53% |
| 年金生活者 | 10% | 12% | 13% | 14% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| 扶養児童を伴う世帯 | ||||||||
| 一人親世帯 | 36% | 35% | 36% | 37% | 39% | 36% | 37% | 36% |
| 夫婦世帯 | 10% | 10% | 12% | 13% | 14% | 16% | 18% | 19% |
出所:Tabell A.1, Lebenslagen in Deutschland- Der 3. Armuts-und Reichtumsgericht der Bundesregierungより作成。
最低賃金関連法も影響し、3度の修正も
統計の選択が議論の俎上にのぼったのは、貧困の実態把握が今後の政治の方向を左右しかねないからだ。例えば、最低賃金関連法(注2)のあり方をめぐる論争に影響し、2005年1月にシュレーダー政権が導入したハルツIV法(注3)の政策評価にも関係する。そのため、報告をまとめるにあたって、議論は紛糾し、閣議決定に至るまで3度にわたる修正をよぎなくされた。
シュルツ労働社会相(SPD)が5月に提出した報告原案は、連立内閣内部での対立を呼んだ。連立内閣が原案当初から合意していたのは、(1)格差是正策としての公的所得移転効果、(2)「社会福祉国家は機能している」との分析、(3)教育と雇用の拡大が貧困対策の鍵――といった方向性で、今回の最終案でも維持されている。だが、とりわけ最低賃金論争に関連する記述部分について、経済省が数々の修正を要求。グロース経済相は、2008年の社会の現実はデータの根拠となった2005年より改善されている点を強調し、「社会国家の功績を積極的に評価せず、社会をあまりに暗いイメージで描いている」とコメント。とりわけ、原案の「フェアな労働条件や適正な生活賃金は十分な社会保障の前提だ。最低賃金は貧困撲滅の確実な手段だ」との記述を断固として拒否した。
経済省との事前調整を尽くした今回の報告についてシュルツ労働社会相は、「原案の本質部分は変更されていない」と強調したが、最賃に関する記述が「業種別最低賃金は適正な最低労働条件の確保に貢献し得る」とやや表現が緩和されたほか、政府が低賃金セクターの膨張に「大きな懸念」を抱いているという文言や、「社会給付を受けざるを得ない状況を強いられるフルタイム雇用」が貧困撲滅の鍵であるという文言などが削除され、逆に社会政策の限界に関する記述が新たに盛り込まれた格好となった。グロース経済相は、「原案に比べ報告書はかなり改善された」と評価しつつも、「2005年数値に基づく結果には問題が残る。景気回復の結果、2005年2月~2008年5月までに失業者は200万人減少しており、現在の社会の状況は全く違うものだ。国民に誤った印象が蔓延している」などとコメントし、依然として貧困の実態に関しては批判的だ。
政策評価含めて多彩な見解
メディアの見解も一様ではない。右派系のDie Weltは、「ドイツ国民は不公正な格差の是正を望んでいる。だが、相対的に勤勉で達成度が高い者の所得が高いことがまさに公正であり、必要なことだ。こうした格差が人々のモチベーションを左右する。平等主義に過ぎる政策は、勤勉な者にペナルティを科し、貧困インセンティブを増幅する。大切なことは、頑張れば希望が持てるかどうかだ」と行き過ぎた「福祉国家」に警鐘を鳴らしている。
中道左派のSuddeutsche Zeitungは、「原案をめぐる連立内閣内の当初の議論は、報告書が現実の貧困状況を示したものか否かに焦点があたっていた。しかし、蓋を開けてみると統計数値をいかに政治的に活用できるかが問題だった」と報じ、「社会給付の受給者が増加しているかどうか、福祉国家の財源、税制など本来必要とされる議論が据え置かれた」などとコメントしている。
左派系のDie TageszeitungはSOEPのデータとの乖離に言及したうえで、「格差の実態を把握するには当然ながら貧困の定義が問題となるが、今回の修正をみると権力に左右されるとも言えそうだ。政府がいかにデータを党派的に解釈するかを象徴している」と批判した。
一方、ドイツ労働組合総同盟(DGB)は、「就労しているにもかかわらず貧困生活を送る人々が何百万人もいるのは大スキャンダルだ」とコメント。そのうえで、ドイツ社会福祉連盟(SoVD)とともにハルツIV給付の引き上げと最低賃金の導入を訴え、今国会中に貧困対策緊急プログラムを立ち上げるよう連邦政府に呼び掛けた。SoVDは、「アジェンダ2010の一環である社会給付の大幅削減に言及がない上に、将来的な高齢層の貧困リスクも無視している。年金生活者の貧困リスクは13%にまで上昇している」などと批判を寄せている。また、社会福祉連盟(VdK)は「貧困対策の全体構想」を要請。会長のヴァルター・ヒルリンガー氏は、所得と寿命の相関関係を分析した未公表数値をもとに、「上位所得層の男性が下位所得層に比して寿命が平均11年長い」と述べ、貧困対策の重要性を再確認している。
さらに緑の党は、SOEPとのデータソースの相違を根拠に挙げ、「政府は、貧困対策の失敗を隠蔽しようとしている」などと非難。左翼党はこれに同調している。ドイツ・カリタス連盟からも批判があがっており、同ペーター・ネーヤ会長は「客観的な分析が政治的評価と混在している」として、独立した有識者会議が報告書を作成するよう要請している。
専門家の見解も分かれている。ドイツ経済研究所(DIW)グラプカ氏は、ここ2年間の好景気により貧困の実態が好転したことを容認するものの、貧困問題を今回の報告書が描くよりずっと深刻に捉えている。DIWは、今回の報告書では政府が貧困ラインを大幅に下げたため、貧困率の低下も驚くに値しないと指摘している。前回は月額939ユーロ未満の単身者を貧困層と定義していたが、今回は781ユーロに過ぎないためだ。他方ミュンヘン経済研究所(Ifo)会長・ハンツ=ヴェルナー・ジン氏は、貧困問題を誇張しないよう警鐘を鳴らしている。貧困・富裕報告書が定義する貧困率とは貧困のリスクに晒されている者の割合で、深刻な貧困に実際に陥っているのは人口の4%程度に過ぎないと推計している。
一連の議論は、「貧困と格差」への問題意識が近年の社会労働政策を左右する政治的イシューとなっていることをあらためて示している。
注
- 第1次・第2次貧困・富裕報告については、齋藤純子(2008)「ドイツの格差問題と最低賃金制度の再構築」『外国の立法』236号が詳しく取り上げている。
- 連邦内閣は7月16日、最賃関連2法案(労働者送り出し法及び最低労働条件法)を閣議決定している(詳細については、来月9月の海外労働情報にて公開予定)。
- 2003年に発表された改革プログラム「アジェンダ2010」の一環としてハルツIV法(失業扶助と社会扶助の整理統合)が2005年1月より施行され、失業中の所得保障制度を改革した。この改革による実質的な給付の削減は、長期失業者の生活水準を低下させるものであったと同時に、就業と公的給付を組み合わせる一連の「コンビ賃金」の仕組みが低賃金部門の拡大を引き起こしている可能性が指摘されている。今回の報告の数値はハルツIV法の影響が反映されるものとして注目されていた。
参考資料
- 連邦政府新聞発表資料(2008年6月25日)
- 連邦労働社会省新聞発表資料(2008年6月25日)
- 「第3次貧困・富裕報告書」(Lebenslagen in Deutschland Der 3. Armuts-und Reichtumsbericht der Bundersregierung, 06/25/2008)
- FAZ.NET.(2008年6月25日)
- FR-online.de(2008年6月25日)
- Financial Times Deutschland(2008年6月25日)
- Welt Online(2008年6月25日)
- Spiegel Online(2008年6月25日)
参考レート
- 1ユーロ(EUR)=168.91円(※みずほ銀行ウェブサイト
 2008年8月7日現在)
2008年8月7日現在)
2008年8月 ドイツの記事一覧
- 貧困と格差めぐり議論が沸騰―「第3次貧困・富裕報告書」を閣議決定
- 高齢者パート就労促進制度をめぐり連立政権内で対立―社民党の延長案に反発、首相は拒否強調
- 連邦政府、外国人専門職の受け入れ制限を緩和
関連情報
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2008年 > 8月
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > ドイツの記事一覧
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 雇用・失業問題、勤労者生活・意識、統計
- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > ドイツ
- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > ドイツ
- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > ドイツ


