イギリスの労働基準監督官制度
1. 労働監督制度の概要(注1)
労働基準全般を対象とした包括的な監督制度はなく、複数の領域に、異なる監督制度と機関が設置されている。柱となるのは労働安全衛生制度で、1974年労働衛生安全法(Health and Safety at Work etc Act 1974)を根拠法として、衛生安全局(Health and Safety Executive:HSE)及び地方自治体(Local Authority)が執行を担っている。
また、最低賃金制度については、1998年最低賃金法(National Minimum Wage Act 1998)が根拠法となる。ビジネス・エネルギー・産業戦略省が所管し、税・社会保険料等の徴収全般を担う歳入関税庁(Her Majesty's Revenue and Customs)が執行機関となる。
このほか、一部の事業者を対象とした監督制度として、農業・食品加工など法的に認められた業種における労働力供給事業の事業者(ギャングマスター)を監督するギャングマスター認可局(Gangmasters Licensing Authority(GLA):事業者の認可(ライセンス発行)のほか、供給先となる農場等の状況などの検査を実施)(注2)や、派遣労働・雇用ビジネスを所管する労働者派遣基準局(Employment Agency Standards Inspectorate)などが設置されている。また、原子力(注3)、道路、鉄道、航空、海運などの各分野で、監督機関が設置されている。
以下ではこのうち、主要な分野である労働安全衛生および最低賃金に関する監督機関の概要を紹介する。
2. 監督組織
(1)安全衛生
労働安全衛生制度の執行機関であるHSEと地方自治体は、それぞれ国内の異なる種類の事業所を監督の対象としている(図表1)(注4)。HSEは、工場、農場、建設現場、病院、学校などのほか、石油・ガスの採掘や輸送、配電、危険物質の運搬、原子力などの分野の事業所を監督する。地方自治体は、主に事務所(オフィス)や店舗、ホテル、レストランなどを監督する。
| HSE | 地方自治体 |
|---|---|
| 工場、農場、建設現場、採掘場、学校、催事会場、ガス・電気関連施設、病院・看護付き介護施設、政府施設、海上施設など | 政府以外の事務所、店舗、ホテル、レストラン、娯楽施設、保育所・公園、パブ・クラブ、美術館・博物館(民間)、宗教施設、介護施設 |
- 出所:HSEウェブサイト

(HSE)
HSEは、雇用年金省(Department for Work and Pensions)の所管する公的機関(Non Departmental Public Body)で、リバプールの本部のほか、全国7地域に約30カ所の地方事務所が設置されている。職員数は2574名(2016年3月時点、図表2)で、これには1037人の監督官のほか、現場スタッフ、政策アドバイザー、技術者、法律アドバイザー、統計専門職、エコノミスト、科学者、医療専門職などが含まれる(注5)。2015年度の支出額(total operating expenditure)は、2億2387万ポンドである(注6)。
図表2:HSEの職員数(フルタイム換算)
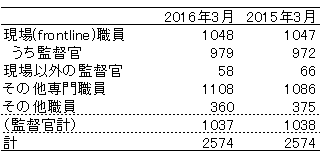
- 出所:HSE (2016) "Annual Report and Accounts 2015/16"
監督機関としての主な業務は、以下の通りである(注7)。
- 職業関連の死亡事故、ケガ・病気や危険の発生などを伴う深刻な事故の調査
- 職場における衛生・安全・厚生の状況に関する労働者や一般からの苦情(complaint)への対応
- 高リスク職場や、違反の多い事業者(dutyholders)に重点を置いた検査の実施
- 一部の危険業務に関する認可制度の実施
- 執行機関としての決定と法令順守の確保のための施策の実施
また、HSEの一部である衛生安全研究所(Health and Safety Laboratory)では、およそ350人の科学的、医学的、技術的専門家が、安全衛生に関する研究に従事し、専門的なアドバイスを提供するほか、企業などを対象とした多様な研修も有料で実施している(例えば、危険物質の取り扱いや危険な作業に関する規制内容、リスク管理等)(注8)。
(地方自治体による監督制度)
グレートブリテンの380カ所の地方自治体が、公衆衛生維持の一環として、上記の業種の事業所における労働安全衛生の監督に責任を負う。監督官の数は、2015年時点で736人である(注9)。自治体によっても活動状況はまちまちとみられ、実態は不明だが、自治体における監督官は、典型的には環境衛生プラクティショナー(environmental health practitioner)として、労働安全衛生のほか、食品の安全、公害、住宅等の検査に携わる(注10)。このため、労働安全衛生に関しては、他業務の傍ら、助言等にとどまる場合も多いとされる(注11)。
HSEは、地方自治体との間で連絡協議会(HSE/Local Authorities Enforcement Liaison Committee (HELA))を設置しており、監督の実施に関する地方自治体向けの準則(National Local Authority Enforcement Code)や、各種ガイダンスなどで地方自治体の支援等を行うほか、自治体から年間の監督業務の実施数などについて報告を受ける。
(2)最低賃金
最低賃金制度は、ビジネス・エネルギー・産業戦略省(Department for Business, Energy and Industrial Strategy:BEIS)が所管し、その執行は、財務省の外局(non-ministerial department)である歳入関税庁(HMRC)に委任されている。HMRCは、所得税、法人税、社会保険料などの徴収、関税に関する業務を担う組織で、5万9000人の職員と全国167カ所の地方事務所を擁する。うち、約30カ所の地方事務所に設置された最低賃金に関する取り締まりチームの監督官(compliance officer)が、事業所に対する検査等を行う。会計検査院(National Audit Office)の報告書(注12)によれば、履行確保に関する人員(監督官を含む)は2015年で269人、予算額は1320万ポンドである(図表3)。
| 年度 | 予算額 (100万ポンド) |
人員数 (フルタイム換算) |
|---|---|---|
| 2006 | 5.8 | 不明 |
| 2007 | 6.8 | 不明 |
| 2008 | 7.6 | 139 |
| 2009 | 8.3 | 140 |
| 2010 | 8.1 | 142 |
| 2011 | 8.3 | 138 |
| 2012 | 8.3 | 142 |
| 2013 | 8.3 | 158 |
| 2014 | 9.2 | 183 |
| 2015 | 13.2 | 269 |
| 2016 | 20.0 | ― |
- 注:2016年度の予算額は推定値。
- 出所:National Audit Office (2016)
3. 労働監督官の権限
(1)安全衛生
HSEの監督官は、原則として全ての事業所に、事前の通告なしに立ち入り検査を行う権限を有する。監督官は、従業員や、労働組合のある事業所においては安全衛生代表者に対する聴取のほか、事業所内の写真撮影やサンプルの収集、また危険と判断される装置や物質を押収することができる。検査の結果、安全衛生基準に問題があると判断される場合、その度合いにより、口頭または書面によるアドバイス、あるいは是正・禁止に関する通告(improvement or prohibition notices)を発行することができる。是正通告は、法律に反する事項について所定の期間内に是正することを求めるもの。また禁止通告は、深刻な怪我などが生じたかまたは生じうると判断される場合に、当該活動をコントロールする権限を有する者に対し、是正策が講じられない限り、即時または所定の期間後に対象となる活動を禁止するもの。
重大な違反や、事業主が上記通告に従わない場合については、裁判所に提訴することができる。イングランド及びウェールズでは、HSEが直接提訴を行うが、スコットランドにおいては、Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS)に報告の上、提訴を提言する形を取る。なお、事業主は監督官による改善・禁止通告に不服の場合、裁判所に異議申し立てを行うことができる。この場合、改善通告は結審まで差し止めとなるが、禁止通告については審理中も有効となる。
なお、通告を要することが判明した場合、検査に係る費用は事業主に請求される(Fee for Interventionスキーム)。2015年度の徴収額は、1471万ポンドであった(注13)。
(2)最低賃金
HMRCの監督官(compliance officer)も、(不適切な時間でない限り)任意のタイミングで事業所への立ち入り検査を実施することができる。検査は通常、給与支払記録その他の関連の記録の閲覧、雇用主や給与担当職員との面談、労働者との面談などを含む。違反があると判断される場合、監督官は、雇用主に対して未払賃金額及び最低賃金違反に対する罰金の支払いに関する通告(Notice of Underpayment)を発行する(注14)。雇用主が通告内容に基づく支払いを怠った場合、HMRCは、民事裁判所または雇用審判所への申し立てにより、支払いの確保を図る。
4. 労働監督官の身分
HSEの監督官は、HSEに直接雇用された公務員である(注15)。また、地方自治体の監督官も、一般的には地方自治体に直接雇用された公務員とみられるが、正確な実態は把握されていない(後述)。
5. 労働監督官の採用試験・研修制度
(1)安全衛生
HSEにおける監督官の求人は、学位レベルの教育資格または職業資格の保有が要件となる。選考評価プロセスは、オンラインによる二種類の適性検査(verbal reasoning test、civil service judgement test)を受けた後、能力判定面接、グループ演習およびこのポストに求められる基準をベースにした文書作成能力と実務能力に関する評価で構成される(注16)。
採用後は、現場での監督業務と座学を組み合わせた4年間の訓練プログラムが提供され、大学院レベルの資格取得が目指される。うち最初の2年間で、技術的専門性、法的知識、法の執行や適切な助言の実施に関するプログラムを修了し、労働安全衛生に関する公的な資格(National Examination Board in Occupational Safety and Health(NEBOSH)が発行)を取得することで、正式に監督官となることができる(注17)。
(2)最低賃金
不明。
6. 監督対象労働者数
(1)安全衛生
グレートブリテンのほぼ全ての労働者が対象となるが、正確な規模やHSEと地方自治体の内訳は不明。なお、2017年2~4月期の就業者数は3113万人。
7. 監督対象の事業所数
対象事業所数は不明。地方自治体が対象とする事業所は、全国で約100万カ所強とされており(注18)、それ以外の事業所はHSEの所管となる。なお、グレートブリテン全体の企業数は、2016年時点でおよそ537万社である(注19)。
8. 年間の監督件数
(1)安全衛生
HSEによる年間の検査実施件数は2015年度でおよそ1万8000件(注20)。地方自治体による実施件数は不明だが、HSE及び地方自治体によって発行された通告の件数は、1万1403件となっている。業種別には、製造業と建設業が全体の過半数を占める。また、地方自治体の通告の発行件数はHSEのおよそ3分の1で、HSEによれば、近年、地方自治体における発行件数の減少により、全体の件数も減少傾向にある(注21)。
図表4:HSE及び地方自治体による通告の発行件数
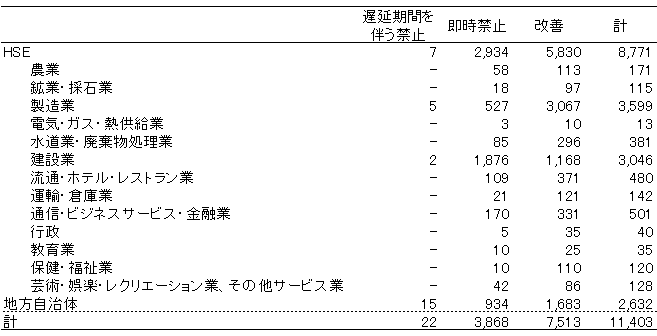
- 出所:HSEウェブサイト

また、同年度におけるHSE及びCOPFSによる裁判所への訴追件数は696件、うち95%に相当する660件で有罪判決があった(図表5)。罰金額は全体でおよそ3827万ポンド、1件当たりの平均額が約5万8000ポンドとなっている。ここでも、製造業と建設業における件数が多いものの、1件当たりの平均罰金額は鉱業・採石業や電気・ガス・熱供給業、運輸・倉庫業などで際立って高い。なお、有罪判決の大半は罰金(fee:84%)で、4%が拘禁(immediate custody)、6%が執行猶予(suspended sentenses)となっている。
図表5:HSE及びCOPFSによる訴追件数、罰金額(2015年度)
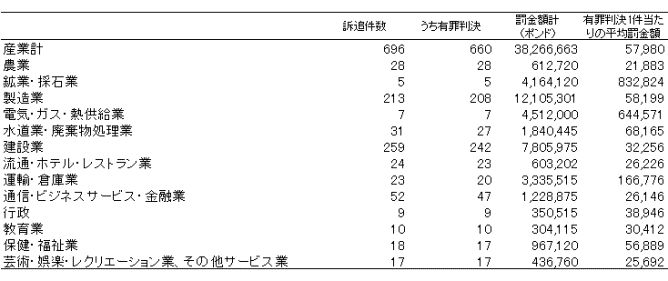
- 出所:同上
(2)最低賃金
HMRCによる2015年度の年間の検査実施件数は2667件であった。2009年の罰金制度導入以降、年間の罰金額の合計は増加傾向にある(図表6)。
| 年度 | 実施件数 | 未払金額 (100万ポンド) |
対象労働者数 | 平均未払額 (ポンド) |
罰金 (ポンド) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3,643 | 4.39 | 19,245 | 228 | 111,183 |
| 2010 | 2,901 | 3.82 | 22,919 | 167 | 520,568 |
| 2011 | 2,534 | 3.58 | 17,371 | 206 | 766,807 |
| 2012 | 1,696 | 3.97 | 26,519 | 150 | 776,517 |
| 2013 | 1,455 | 4.65 | 22,610 | 205 | 815,269 |
| 2014 | 2,204 | 3.29 | 26,318 | 125 | 934,660 |
| 2015 | 2,667 | 10.30 | 58,080 | 177 | 1,679,240 |
| 合計 | 17,100 | 34.0 | 193,062 | 176 | 5,604,244 |
- 出所:National Audit Office (2016)
一方、違反事業主に対する刑事訴追(注22)の件数は、1999年から2016年2月までの間で9件にとどまる。National Audit Office (2016)によれば、BISとHMRCはともに、制裁措置として起訴を用いるには慎重な立場をとっている。これは、最終的受益者である労働者が、裁判にかかる長い期間、未払賃金の回収を待つこととなり、またもし裁判の結果として企業が倒産に追い込まれた場合、回収自体が不可能になる可能性があることによる。
9. 労働監督官の業務と活動(年間の監督件数や日々の業務の流れ等)
(1)安全衛生
HSEの監督機関としての業務は、大きくは上述のとおりである。監督官による事業所への検査は、事故や病気などの発生に対応して実施される検査と、それ以外の立ち入り検査に大きく分かれる。後者は、安全衛生に関する問題が多いことがわかっている事業所や、相対的に危険度の高い業種(海上、原子力、鉄道、一部の化学産業、爆発物を扱う業種など)などが対象となることが多い。
監督業務の目的や手法などに関する原則をまとめたEnforcement Policy Statement(注23)は、安全衛生に関する基本的な考え方として、リスク評価とその相応な管理を掲げており、明確な基準に基づくリスク評価が重視されている(注24)。リスク評価等の具体的な手法は、Enforcement Management Model(注25)に集約されている。
(2)最低賃金
履行確保は、通報に基づく立ち入り検査を基本とする。労働者(または第三者)は、雇用主の最低賃金違反について、ビジネス・エネルギー・産業戦略省傘下の公的機関であるACAS(Advisory, Conciliation and Arbitration Service:雇用上の斡旋・仲裁等のほか、雇用分野の法制度に関する情報提供を行う)が実施している雇用分野の法制度に関する電話相談(ヘルプライン)またはHMRCに対して苦情申し立てや通報を行うことができる(注26)。最低賃金違反が疑われる場合、HMRCの監督官(compliance officer)は、不適切な時間でない限り任意のタイミングで雇用主の事業所に立ち入り検査を実施することができる。
検査に際しては一般に、給与支払記録その他の関連の記録の閲覧、雇用主や給与担当職員との面談、労働者との面談が含まれる。最低賃金違反があると判断される場合、監督官は、雇用主に対して過少支払通告(Notice of Underpayment)を発行する。これには、未払賃金額及び最低賃金違反に対する罰金が記載されている。雇用主が通告内容に基づく支払いを怠った場合、HMRCは、民事裁判所または雇用審判所への申し立てにより、支払いの確保を図る。
通報に基づく検査以外に、最低賃金違反のリスクが高い業種をリスク・プロファイリングにより選定し、重点的に検査を行う場合もある。例えば、HMRCは2011~2013年の期間、介護事業者に対する検査を重点化、およそ半数の雇用主が最低賃金違反の状態にあることを明らかにした(注27)。調査は、2014年以降も継続されており、2015年には、BEISがこれを優先課題としてサービス協定に盛り込むに至っている。
このほか、HMRCは予防的な事業として、雇用主向けに最低賃金制度に関する啓発活動を行うこともある。例えば2015年には、理容業の雇用主を対象に、最低賃金の計算方法等などの情報を提供し、最低賃金制度の遵守を促すキャンペーンを実施した(注28)。
注
- イギリスでは、監督機関により所管する地理的範囲が異なる。HSEおよび後述の労働者派遣基準局は、グレートブリテン(イングランド、ウェールズ、スコットランド)を、また歳入関税庁、ギャングマスター認可局は北アイルランドを含むイギリス全体を、それぞれ所管している。
なお、安全衛生制度およびHSEの概要については、中央労働災害防止協会のウェブサイト で詳細な情報が提供されている。
(本文へ)
で詳細な情報が提供されている。
(本文へ) - 現在は、組織名がGangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA)に改称され、権限や所管領域が拡大されている。(本文へ)
- 原子力施設については、従来はHSEが所管していたが、2011年に新設されたOffice for Nuclear Regulationに移管されている(HSEの原子力安全部門を吸収)。(本文へ)
- Health and Safety (Enforcing Authority) Regulations 1998による。(本文へ)
- HSE (2013)(本文へ)
- HSE (2016a)(本文へ)
- HSE (2013)(本文へ)
- HSL (2016) “Health & Safety Training Courses 2016/17”(本文へ)
- HELA (2015)(本文へ)
- HSE (2013)(本文へ)
- HELA (2015)、HSE (2013)(本文へ)
- National Audit Office (2016)(本文へ)
- HSE (2016a)(本文へ)
- 罰金額は未払賃金額の2倍で、違反対象となった労働者1人当たり100~2万ポンドの範囲で決定される(通告の発行から14日以内に支払う場合、罰金額は50%に減額される)。なお、未払い額が100ポンド以上の全ての違反雇用主は、政府のウェブサイトで氏名が公表される(“name and shame”)ほか、当該の事業に従事することが一定期間禁止される場合もある。2013年10月から2016年2月の期間には、490の雇用主名が公表された(未払賃金額でおよそ300万ポンド相当)。(本文へ)
- 1974年法第10条。(本文へ)
- ILOウェブサイト
 。なお、政府の求人サイト
。なお、政府の求人サイト から、直近の求人を参照できる。(本文へ)
から、直近の求人を参照できる。(本文へ) - HSEウェブサイト
 による。(本文へ)
による。(本文へ) - HSE (2013)(本文へ)
- House of Commons Library (2016) “Business Statistics”による。(本文へ)
- HSE (2016a)(本文へ)
- HSE (2016b)(本文へ)
- 法律上は、以下が刑事訴追の対象となりうる:最低賃金の支払い拒絶または故意に無視すること、記録の保存義務に反すること、あるいは虚偽の記録の作成・指示・容認、監督官の検査の妨害、文書提出の要求を拒絶または無視すること。(本文へ)
- http://www.hse.gov.uk/enforce/enforcepolicy.htm
 (本文へ)
(本文へ) - なお、雇用主には、職場における安全衛生に関する方針の設定が義務付けられ、従業員5人以上規模の組織はこれを書面化しなければならない。また、職場における死亡事故、ケガ、職業上の病気、その他潜在的に害を及ぼしかねない事故等が発生した場合、事業主(雇用主のほか、事業所の管理者、自営業者)にはこれを報告する義務がある(Reporting of Injuries Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995による)。(本文へ)
- http://www.hse.gov.uk/enforce/enforcement-management-model.htm
 (本文へ)
(本文へ) - ACASヘルプラインへの最低賃金違反に関する相談は、相談者が希望する場合、HMRCに紹介され、HMRCはこれに関する調査を行う。相談者が調査に当たって、氏名の公表に難色を示す場合、公表可能な場合に比して時間を要するものの、当該の雇用主に対する調査は実施される。なお、労働者は雇用主の最低賃金違反について、雇用審判所等に直接申し立てを行うことも可能。(本文へ)
- HMRC (2013)(本文へ)
- HMRCプレスリリース 'Hair and beauty sector targeted in new national minimum wage campaign' July 29, 2015
 (本文へ)
(本文へ)
参考資料
- ACAS (2015) “Annual report and Accounts 2014/15”
- HSE (2013) “A guide to health and safety regulation in Great Britain”
- HSE (2016a) “Annual Report and Accounts 2015/16”
- HSE (2016b) “Enforcement in Great Britain 2016”
- HELA (2015) “Data Collection – analysis of LAE1 2014/15 data from Local Authorities”
- HMRC (2013) “National Minimum Wage compliance in the social care sector”
- National Audit Office (2016) “Ensuring employers comply with National Minimum Wage regulations”
- Gov.ukウェブサイト

- HSEウェブサイト

- 中央労働災害防止協会ウェブサイト

参考レート
- 1英ポンド(GBP)=151.76円(2018年4月12日現在 みずほ銀行ウェブサイト
 )
)
2018年4月 フォーカス:諸外国の労働基準監督制度
- アメリカ:アメリカの労働基準監督官制度
- イギリス:イギリスの労働基準監督官制度
- ドイツ:ドイツの労働基準監督官制度
- フランス:フランスの労働基準監督官制度
- スウェーデン:スウェーデンの労働基準監督官制度
- 韓国:韓国の労働基準監督官制度
関連情報
- 海外労働情報 > フォーカス:掲載年月からさがす > 2018年の記事一覧 > 4月
- 海外労働情報 > フォーカス:カテゴリー別にさがす > 労働法・働くルール、労使関係
- 海外労働情報 > 国別労働トピック > 国別にさがす > イギリス
- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス
- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス
- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス


