国際フォーラム開催報告:「日米比較:コーポレートガバナンス改革と雇用・労働関係」
コーポレートガバナンス、雇用システムの変化と労働法の役割
荒木尚志
(東京大学法学部教授)
日本のコーポレートガバナンスモデルの特徴
日本のコーポレートガバナンスは、法律上はシェアホルダーモデル、すなわち株主価値を重視した制度設計をしている。しかし、実態として企業がどのように運営されているかを見ると、これはまさにステークホルダーモデル、とりわけ重要なステークホルダーである従業員の価値を重視した経営を今までやってきたといってよい。このことは、法律家の間でも共通した認識となっており、商法の権威である江頭憲治郎東大教授も1994年の論文で、「法律には会社は株主のものということになっているが、実際は従業員の利益を最優先に運営されてきたことにつき、商法学者の見解は一致している」と述べられている。
日本はシェアホルダーモデルとステークホルダーモデルという観点からいうと、ステークホルダーモデル、すなわちドイツと似たようなコーポレートガバナンスモデルをとっていると言うことができる。しかし、実はドイツ型と日本型にも大きな違いがある。
ドイツ型は、法律によってステークホルダーモデルが担保されている、共同決定法とか事業所組織法といったもので、従業員の経営参加あるいは従業員の声を聞きながら経営をすることが法律上要求されている。それに対して日本の特徴は、ステークホルダーモデルが何ら法制度的な担保なく、慣行に依存して展開されてきたということである。
コーポレートガバナンスで重要な3つのアクター、すなわち株主と経営者と従業員に着目してみる。まず株主構造はご承知のとおり配当目的の株主所有ではなくて、経営の安定のための株式持ち合いが顕著であった。長期安定株主によって長期的な経営を可能にするための持ち合いである。
それから、経営者、経営陣をみると、内部から昇進した者が出世の最終ゴールとして経営者になるということで、従業員と価値観を共有した人たちが経営にあたっている。
大企業の場合は、ユニオン・ショップ協定があるので、従業員は会社に入社すると必ずその企業別組合に入ることが義務づけられ組合員となり、組合の経験者が最終的に経営陣になる。日本の団体交渉は、昔の組合員と今の組合員の間の交渉という様相を呈している。これは諸外国ではあり得ない。
労使関係については、長期雇用システムのもとで雇用の安定が確保されていることも特徴である。諸外国では労使のコミュニケーションがなかなか実現しないため、法律によって情報を与えなさいということになっているが、日本の場合は法が要求していないにもかかわらず、労使が任意に労使協議制を発達させて、密な意思疎通を図ってきた。
こうした株主、経営陣、労働関係の特質はすべて何ら法が要求していることではなく、慣行によって定着してきたものである。この慣行に依存したステークホルダーモデルであることが日本モデルの特徴だといえる。
日本のコーポレート・ガバナンス・モデルの変化
さて、そうした慣行がどう変化しているかについてだが、まず株主は、株式持ち合いが解消され、安定株主も減少していることが統計的に確認できる。また、個人株主の数も増えてきている。株式市場を見ると、外国人投資家の比率が高まる傾向にあり、株主構造が変わってきている。
経営陣の状態については、2002年の商法改正により、それまでの伝統的な日本の統治機構システムに大きな変化が見られた。すなわち、委員会設置会社、これはよくアメリカをモデルにした制度だと言われるが、指名委員会、報酬委員会、監査委員会という3つの委員会を取締役会の中に設けている。この委員会の過半数のメンバーは社外取締役でなければいけないということになっている。
図表1:選択可能な2つのガバナンスモデル
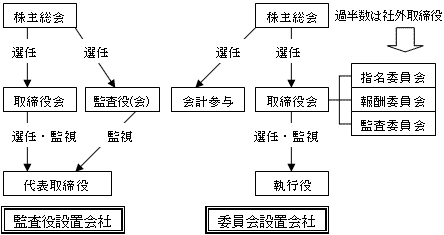
監査役設置会社という伝統的なガバナンスモデルでは、内部昇進取締役が経営者であったが、監査役設置会社という新しいガバナンスモデルでは委員会委員の過半数が社外取締役となり、より株主の利益を反映させた経営をすべきだという考えに立っている。新モデルでは、経営陣の質に大きな変化が見られる可能性がある。
ところが、新しいガバナンスモデルを採用している会社はまだ限られていることから、実際どの程度その変化が起こっているかについてはいろいろ議論がある。新モデルを採用している少数の企業には、ソニーや日立など日本のトップ企業が含まれており、そのパフォーマンスいかんによっては新しいモデルがより普及していく可能性もあるというのが現状ではないかと思う。
雇用関係、労使関係の変化とコーポレート・ガンバナンス
日本では、バブルがはじけて以降、雇用関係が厳しかったわけだが、1997年ぐらいまでは、なるべく雇用を維持しながらほかの方法で対処する従来と同じような雇用調整を行ってきた。しかし、消費税が3%から5%になった1997年から経済状況にも質的な変化が生じ、失業率も急上昇し、史上最悪の記録を更新していった。
もっとも、「長期雇用システムの終焉」とメディアで議論されているものの、日本では、正規従業員がアメリカのように簡単にレイオフできるようになったのかというと、そうではない。むしろ生じている変化は、正規従業員の比率が1990年は8割程度あったところ、現在は3分の2の66.2%の水準にまで落ち、かわって非正規従業員の比率が2割であったものが、3割を超えるところまで高まってきている。
正規従業員が自由に解雇できるのであれば、非正規従業員を用いる必要性もそう高くないわけだが、むしろ正規従業員はコストがかかって雇用調整が難しいという状況が続いているからこそ、非正規従業員活用の方向に企業は動いていったといえるのではないか。
フレキシビリティーについては、日本の労働市場は非常に硬直的であるがゆえに規制緩和をするべきだといった議論もあるが、これはやや一面的な議論である。むしろ日本の労働市場のフレキシビリティーを見るためには、フレキシビリティーの2つの側面、すなわち、外部市場における量的な調整の柔軟性と内部市場における機能的な柔軟性、この両方を見る必要がある。そうした場合、日本は確かに雇用の維持は重視されているが、雇用を維持した上で労働条件の調整をどうするかという点について柔軟な対応をしてきたことがわかる。それを可能にしたのは、労働の場所や内容を特定しない雇用慣行が一つあり、さらに判例法が就業規則の合理的変更によって労働条件を調整するというルールを確立したことが大きい。
フレキシビリティーとセキュリティーという観点から、アメリカ、日本、ヨーロッパを比較してみると、アメリカは、”Employment at will doctrine”(随意雇用原則)が現在でも基本的には維持されている。その結果、差別に当たらない限りは、意のままに雇い入れ、意のままに解雇することができる。
アメリカでは、労働条件の調整も容易である。使用者の労働条件変更の申出に対して、ノーと言うとその労働者は有効に解雇され、解雇されたくなければ変更に同意せざるを得ないからである。
他方、ヨーロッパでは解雇には正当事由が必要だという立法をほぼすべての国がとっている。また、労働条件の調整は、雇用契約で具体的に合意をするという慣行があるので、労働者の同意なく労働条件を変更することもできない。雇用において労働者の保護に手厚いモデルを採用していると言える。
図表2:フレキシビリティーvsセキュリティー
| Flexibility | Security | |
|---|---|---|
| アメリカ 外的柔軟性モデル |
随意雇用原則 | |
| 随意雇用原則によって合意を取り付けることによる柔軟な労働条件変更 | ||
| 日本 内的柔軟性モデル |
雇用保障 | |
| 合理的変更法理 | ||
| ヨーロッパモデル 労働者保護モデル |
雇用保障 | |
| 労働条件保障 |
これらのモデルと比べると、日本のモデルは、一方で雇用の保障を重視したモデルであり、同時に雇用を維持した上で労働条件の変更については最高裁の判例があり柔軟に対応する、このようにフレキシビリティーとセキュリティーをうまくバランスさせるというのが特徴だったのではないかと思う。実はこうしたモデルを法律上もきちんと位置づけようというのが、現在労働契約法で議論している内容にもなるわけである。
さて、労使関係に目を転じてみると、労働組合の組織率が2006年には18.2%の水準にまで下がってきている。(図表3)
図表3:労働組合員数・組織率の推移
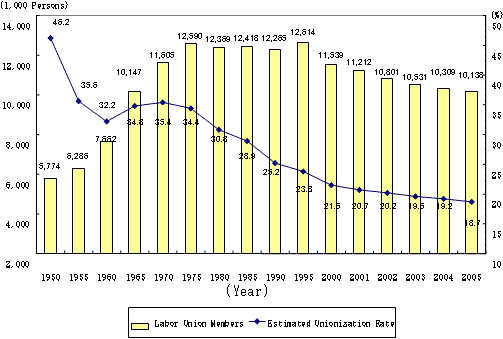
日本では労使協議制で労使がきちんとコミュニケーションをとることができた。この背景には、使用者が組合をパートナーとしてきちんと扱わなければ、いつでも法で保障された団体交渉(団体交渉はストライキによって組合員の権利行使が担保されている)という力と力のパワーゲームに移行できるということがあった。これにより労使協議が自発的に設けられ、それが機能してきた。しかし、組合自体の組織率が下がり力を失いつつあるなかで労使協議も形骸化してきているという指摘もある。
このように株主、経営陣、それから雇用、労使関係に大きな変化が生じているとすると、従来慣行に依存したステークホルダーモデルだった日本のコーポレートガバナンスはどこにいくのだろうかということになる。
コーポレートガバナンスの現状については、日本能率協会が2006年8月に行った新任の役員に対する意識調査では、「だれの利益を最も重視するか」について、2005年から2006年の比較で変化が一番、大きかったのは、「従業員の利益を重視する」で31%から42%に増えている。これに対して、「株主の利益を重視する」は、37%から25%に減っている。意識においては、伝統的な日本の雇用を重視したシステム、その価値を再認識する、そういう経営者が増えてきているという一つの証左といえる。(図表4)
図表4:誰の利益を重視するか
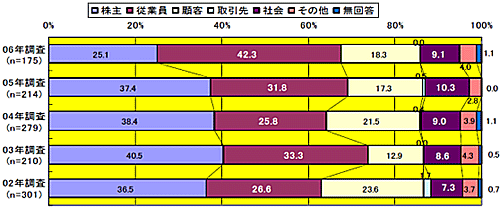
(出所)新任役員調査2006年8月、日本能率協会
また、米国型経営と日本型経営を質問した同協会の別の調査では、納得性を重んじた意思決定の合議制とか、全社員の経営参加とか、長期雇用の重視とか、こうしたものを重視している企業が利益を上げているという結果になっていて、アメリカ・モデルと日本モデルの融合をうまく行っている企業がパフォーマンスもいいということが言える。
コーポレートガバナンスの変化と労働法の役割
さて、法の観点からこうしたガバナンスの問題を考えるときにどういうことが言えるのか。慣行に依存したステークホルダーモデルについては、商法・会社法分野で株主価値を重視したモデルに向けての法制度の変更が進んでいるという点が重要である。
株主価値モデルの制度化が進む中で、従来慣行によって守られてきた従業員利益について、労働法がきちんと制度上の位置づけを与える必要があるのではないかが大きな検討課題となる。
この点については、日本の労働法も動きだしていることを確認できる。すなわち、ステークホルダーの価値を守るための適切な対応措置が実はとられ始めているということである。具体的には、会社の組織再編を簡易、迅速にできる制度である2000年の会社分割法制導入に対しては、労働者の利益を擁護するために労働契約承継法が制定された。また、判例法であった解雇権濫用法理が2003年の労基法改正で立法化された。2004年には公益通報者保護法が制定された。さらに、2006年4月からは労働審判制度がスタートした。これは、職業裁判官と労使から推薦された審判員のあわせて3人が簡易、迅速に3回の期日で、3カ月以内に労働紛争について判断を下す制度である。敷居が高いと言われた裁判制度を利用しやすくして労働者の権利侵害があった場合には救済を得られやすくする法制度の整備といえる。
そして現在、労働契約法という労働関係を規律するルールを透明化するための法案が提出されようとしている。このように、従業員の利益を守るための法制の展開がある。
図表5:交渉レベルと労使関係
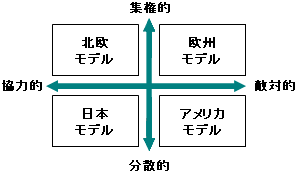
そこで、この動きがさらに集団的労使関係にまで及ぶか、従業員の価値を守るためにドイツのように従業員代表制というものを導入するということになるのかどうか。これは非常に難しい問題である。欧州モデルは、労働組合が産業別、集権的なレベルで存在するため、企業レベル、事業所レベルでは事業所委員会、ワークス・カウンシルを設定しても矛盾が生じないが、日本は企業レベルで企業別組合があるため、そこに新たに従業員代表制を持ってくる場合には、組合と従業員代表の権限をどう調整するかという難しい問題がある。(図表5)今後はそういう問題についても議論していかないといけない。
2007年3月 フォーカス: 日米比較:コーポレートガバナンス改革と雇用・労働関係
- はじめに
- コーポレートガバナンスと雇用関係の日米比較
- コーポレートガバナンス、雇用システムの変化と労働法の役割
- 日本の労働の未来とコーポレートガバナンスのあり方を考える


