低賃金労働からの脱出は6人に1人
―諮問機関報告書
政府の諮問機関である社会階層移動委員会は10月、低賃金労働者の労働市場における移動状況に関する報告書を公表した。2016年までの10年間で、7割近くが一度は低賃金労働から脱出してより賃金の高い仕事に移動するものの、大半は再び低賃金の仕事に戻っているという。報告書は、低賃金の仕事が必ずしもより高賃金の仕事への橋渡しとして機能していない状況を指摘、より良質な雇用を作り出す雇用主の取り組みの支援を政府に提言している。
半数近くが再び低賃金の仕事に
社会階層移動委員会(注1)の報告書「The Great Escape? Low pay and progression in the UK’s labour market![]() 」は、金融危機に伴う景気低迷の時期を含む2006年から2016年の期間における個々の労働者の賃金水準の推移を類型化して、分析を行っている。2006年時点の低賃金(注2)労働者のうち、対象期間を通じて低賃金労働に従事していた「滞留者」('stuck')が全体の25%、最後の3年間は常に低賃金水準を上回る賃金を得ていた「脱出者」('escaper')が17%(6人に1人)であったのに対して、一度はより高い賃金の仕事に就いたものの持続せず、再び低賃金の仕事に戻った「循環者」('cycler')は48%と半数近くにのぼることが明らかとなった(注3)。報告書は、低賃金の仕事が必ずしもより賃金の高い仕事への橋渡しとして機能しておらず、大きくは滞留者から循環者への移行に留まっている状況を指摘している。また、女性は相対的に低賃金労働から脱出しにくく、特に若年女性労働者でこの傾向が顕著だ。報告書は、期間中の累計就業年数が長いほど脱出しやすい傾向にある(脱出者で8.3年、循環者で5.9年、滞留者で4.5年)ことなどから、出産・育児に伴う長期の労働市場からの離脱や、良質なパートタイムの仕事の不足などが、女性の滞留に影響している可能性を指摘している(注4)。
」は、金融危機に伴う景気低迷の時期を含む2006年から2016年の期間における個々の労働者の賃金水準の推移を類型化して、分析を行っている。2006年時点の低賃金(注2)労働者のうち、対象期間を通じて低賃金労働に従事していた「滞留者」('stuck')が全体の25%、最後の3年間は常に低賃金水準を上回る賃金を得ていた「脱出者」('escaper')が17%(6人に1人)であったのに対して、一度はより高い賃金の仕事に就いたものの持続せず、再び低賃金の仕事に戻った「循環者」('cycler')は48%と半数近くにのぼることが明らかとなった(注3)。報告書は、低賃金の仕事が必ずしもより賃金の高い仕事への橋渡しとして機能しておらず、大きくは滞留者から循環者への移行に留まっている状況を指摘している。また、女性は相対的に低賃金労働から脱出しにくく、特に若年女性労働者でこの傾向が顕著だ。報告書は、期間中の累計就業年数が長いほど脱出しやすい傾向にある(脱出者で8.3年、循環者で5.9年、滞留者で4.5年)ことなどから、出産・育児に伴う長期の労働市場からの離脱や、良質なパートタイムの仕事の不足などが、女性の滞留に影響している可能性を指摘している(注4)。
報告書は、より高賃金の仕事への移動を促進するためには、賃金上昇が見込める仕事をより多く作り出すための雇用主の取り組みを、政府が後押しすべきであるとしている。低賃金が蔓延しており、賃金上昇の余地も小さいとみられるホスピタリティ業や小売業などの雇用主の一部は、昇給を可能とするキャリア経路の整備や、より多くの良質なパートタイムの仕事を提供する取り組みなどを既に開始しているという。女性の低賃金労働の滞留を改善する観点からも、また今後のEU離脱によりこれらの業種に多く従事するEU労働者の減少が想定され、人手不足への対応には国内労働者にとっての魅力を増す必要があることからも、こうした取り組みの拡大に向けた政府の支援が重要である、と報告書は提言している。
最低賃金近辺の労働者は増加
雇用の持続的な好調(注5)にもかかわらず、賃金水準は金融危機以降、低迷が続いており、実質賃金は金融危機以前の水準を依然として下回っている。イングランド銀行は、好調な経済活動を背景に雇用主の間では人員調達の困難さが増しており、このことが賃金上昇に寄与しつつある可能性を報告している(注6)。一方、シンクタンクのCIPDは、現在の人手不足の大半は技能人材の不足ではなく、単純な人員不足とみられることから、雇用主の多くは必ずしも賃金引上げの圧力にさらされていない、と分析している(注7)。
図表1:賃金上昇率の推移
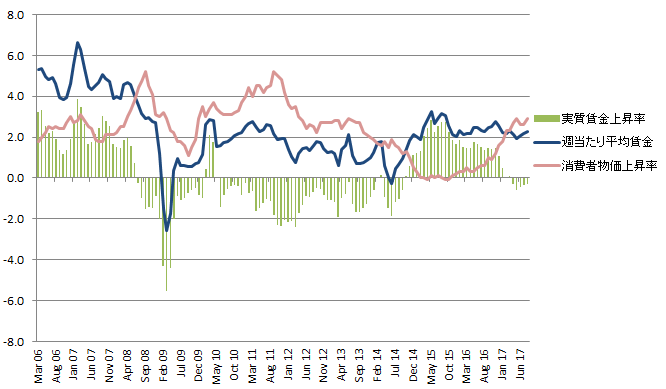
出所:Office for National Statistics "UK labour market: October 2017"![]() 、Resolution Foundation “Low Pay Britain”
、Resolution Foundation “Low Pay Britain”
低賃金をめぐる状況について、シンクタンクResolution Foundationがまとめた報告書「Low Pay Britain 2017![]() 」によれば、被用者全体に占める低賃金層(平均賃金の3分の2未満)の比率は、既に1980年代後半以降から2割を超える状況が続いてきた。しかし、2016年にはこの比率が大きく減少、過去30年間で初めて19.3%と2割を下回ったという。これには、25歳以上層向けの新たな最低賃金制度として、昨年導入された「全国生活賃金」(注8)の影響が大きいと報告書はみている。全国生活賃金は、25歳以上の労働者について、従来の全国最低賃金額(21歳以上に適用、2016年4月時点で時間当たり6.50ポンド)より高い最低賃金額(7.20ポンド)を設定するもので、2020年までに平均賃金の6割の水準への引き上げが目標とされている。報告書の試算によれば、制度導入時点の2016年4月における低賃金被用者は510万人で、前年からおよそ30万人減少している。相対的に低賃金層の比率が高い女性における減少が全体の6割(18万人減)を占めており、業種別には、低賃金労働者を多く雇用する卸売・小売業や、宿泊・飲食業などでの減少が大きい。
」によれば、被用者全体に占める低賃金層(平均賃金の3分の2未満)の比率は、既に1980年代後半以降から2割を超える状況が続いてきた。しかし、2016年にはこの比率が大きく減少、過去30年間で初めて19.3%と2割を下回ったという。これには、25歳以上層向けの新たな最低賃金制度として、昨年導入された「全国生活賃金」(注8)の影響が大きいと報告書はみている。全国生活賃金は、25歳以上の労働者について、従来の全国最低賃金額(21歳以上に適用、2016年4月時点で時間当たり6.50ポンド)より高い最低賃金額(7.20ポンド)を設定するもので、2020年までに平均賃金の6割の水準への引き上げが目標とされている。報告書の試算によれば、制度導入時点の2016年4月における低賃金被用者は510万人で、前年からおよそ30万人減少している。相対的に低賃金層の比率が高い女性における減少が全体の6割(18万人減)を占めており、業種別には、低賃金労働者を多く雇用する卸売・小売業や、宿泊・飲食業などでの減少が大きい。
ただし、低賃金水準未満の労働者が減少したことは、必ずしも賃金水準の低い層全般の減少を意味するわけではない、と報告書は指摘する。低賃金業種を中心に、最低賃金相当額の賃金水準の労働者はむしろ増加しているとみられることが理由だ(注9)。報告書は、低賃金水準未満の労働者の比率は2020年までに被用者全体の16%(430万人)まで低下すると予測、ただし同時に、最低賃金相当額の賃金水準の労働者は190万人から370万人に倍増するとの予測を示している。
また、貧困問題を扱うジョセフ・ローンツリー財団は、全国生活賃金の引き上げなど(注10)による低所得世帯の所得水準へのプラスの効果は、物価上昇や社会保障給付の削減などで相殺され、結果として低所得世帯の所得水準は必ずしも改善しない、と指摘している。特に、従来の低所得層向け給付を統合する制度として現在導入が進められているユニバーサル・クレジット(注11)をめぐっては、歳出削減に伴う制度内容の変更により、給付水準が従来の給付制度を下回るとみられること(注12)や、申請から支給まで最低でも6週間前後、または手続きの遅滞等によりそれ以上の待機期間が生じ、その間申請者が収入のない状態に置かれること、さらになどが問題として指摘されており、このまま全国での導入(2022年を予定)を進めれば、低所得層にさらなる経済的な困難を招きかねないとの懸念がある(注13)。
生活賃金、インフレを考慮した引き上げ
なお11月には、最低限の生活水準を維持するための賃金額として、非営利団体などが雇用主に導入を求める、従来の「生活賃金」の改定額が公表された。ロンドンでは10.20ポンド(45ペンス、4.6%増)、それ以外の地域では8.75ポンド(30ペンス、3.6%増)で、生活必需品などの価格が平均(注14)を上回って上昇している状況などを反映したもの。
生活賃金の改定と併せて公表されたKPMGの報告書は、今回の改定に先立つ2017年4月時点において、生活賃金未満の賃金水準にある労働者を全体の21%、550万人と推計しており、同推計が開始された2012年以降で初めて、前年の560万人から改善がみられたとしている(注15)。減少は主にフルタイム労働者(240万人、フルタイム労働者全体の13%)で生じており、パートタイム労働者(310万人、同42%)については、前年からほとんど変化が見られないという。年齢階層別には、18~21歳層の7割近く(66%)が生活賃金未満の賃金水準にある。また、生活賃金未満の労働者が多い職種は、販売・小売補助職(74万3000人)、キッチン・ケータリング補助職(40万7000人)、清掃・家事職(39万1000人)、介護職(27万9000人)、未熟練倉庫職(18万1000人)などとなっている(注16)。
図表2:生活賃金・最低賃金額の推移(ポンド)
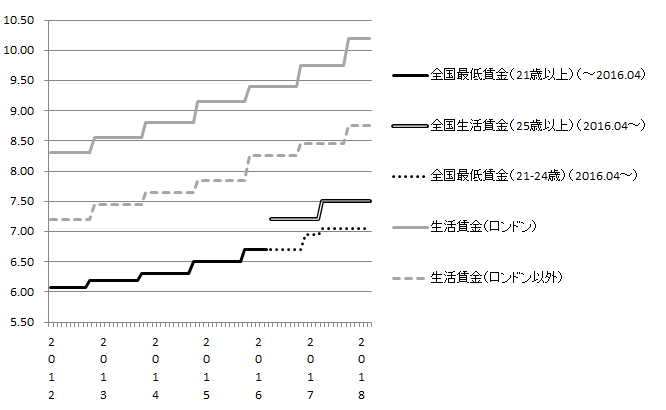
注
- 社会階層移動委員会(Social Mobility Commission
 )は、階層移動の進捗やその阻害要因、促進策等に関する政府の諮問機関で、前身は2010年児童貧困法に基づいて設置された階層移動・児童貧困委員会(Social Mobility and Child Poverty Commission)。2010年法は、貧困世帯に属する児童比率の削減に関する各種の目標を設定していたが、期限となる2020年には達成困難であることが予想され、結果として2016年の法改正により、目標が廃止となったほか、委員会の名称からも児童貧困が削除された。(本文へ)
)は、階層移動の進捗やその阻害要因、促進策等に関する政府の諮問機関で、前身は2010年児童貧困法に基づいて設置された階層移動・児童貧困委員会(Social Mobility and Child Poverty Commission)。2010年法は、貧困世帯に属する児童比率の削減に関する各種の目標を設定していたが、期限となる2020年には達成困難であることが予想され、結果として2016年の法改正により、目標が廃止となったほか、委員会の名称からも児童貧困が削除された。(本文へ) - 時間当たり賃金の中央値の3分の2を下回る賃金水準の労働者と定義。(本文へ)
- 残り1割は引退者('exiter')。(本文へ)
- ただし、こうした状況は中期的には改善している。例えば1981~1991年に関する同様の分析では、滞留者が35%、脱出者は11%。また、滞留者には女性が多いが、これも比率は48%から30%に減少している。一方でこの間、男性では低賃金パートタイム労働者の増加がみられ、結果として滞留者の比率が20%から25%に増加している。シンクタンクのInstitute for Fiscal Studiesによれば、低賃金層に占める男性パートタイム労働者の比率は、過去20年間で5%から20%に拡大しているという。(本文へ)
- 2017年7-9月期の失業率は4.3%、1975年以降で最低水準。(本文へ)
- Bank of England "Agents' summary of business conditions - November 2017 update"
 (本文へ)
(本文へ) - CIPD "Labour Market Outlook Autumn 2017"(PDF:242KB)
 (本文へ)
(本文へ) - 後述の「生活賃金」とは異なり、実際の生計費の算定に基づき金額が決定されたわけではない。(本文へ)
- 報告書によれば、従来の生活賃金(全国生活賃金より高い金額を設定)を下回る賃金水準の被用者数は、600万人から620万人に増加している(被用者全体の23%)。(本文へ)
- 全国生活賃金のほか、所得税免除額の引き上げが低所得世帯の所得水準向上に関連する施策として考慮されている。(本文へ)
- ユニバーサル・クレジットは、低所得層向けの複数の給付制度(所得調査制求職者手当、所得連動制雇用・生活補助手当、所得補助、住宅給付、就労税額控除、児童税額控除)を統合、簡素化し、就労所得の変化に応じた給付額の調整を従来より緩やかにするなど、就労へのインセンティブを高めることが意図されていた。2013年から一部自治体で試行的に導入が開始され、2018年には旧制度からの移行完了が予定されたが、制度運用の負荷から支給遅滞が生じたほか、ITシステムの整備不足などの問題に直面、移行完了の時期が延期され、現在は2022年の完了が目標とされている。(本文へ)
- 当初示されていた案では、制度の再編と簡素化を通じて、給付受給よりも就労の方が経済的に利益となることを明確に示すことが主な目的の一つとして掲げられていたが、一定額までの就労所得について給付の減額を免除する制度(work allowance)の原則廃止(子供を持つ親や健康問題を抱える就労困難者に限定)や、給付額の改定凍結、児童加算の上限設定(対象とする子供の数を二人までに限定)などの変更が行われた。(本文へ)
- 現在、議会の雇用年金委員会がユニバーサルクレジットの導入に関する検討会を実施しており、同制度が先行的に導入された地方自治体などがエビデンスを提供しているが、一部では、支給遅延の影響で住宅の賃貸料が支払えず、民事裁判に直面する受給者も出ているという。地方自治体は、家賃未納で退去を余儀なくされた受給者がホームレスとして増加する可能性に懸念を示している。(本文へ)
- 報告書が参照している2017年4月時点の消費者物価上昇率は2.7%。なお、物価上昇は2016年のEU離脱をめぐる国民投票以降のポンドの下落が影響しているとみられる。(本文へ)
- 全国生活賃金の導入が影響したものとみられる。(本文へ)
- なお、職業別の比率が高いのは、バー従業員(86%)、ウェイター・ウェイトレス(83%)、クリーニング職(77%)など。(本文へ)
参考資料
- Gov.uk
 、Resolution Foundation
、Resolution Foundation 、Institute for Fiscal Studies
、Institute for Fiscal Studies 、Joseph Rowntree Foundation
、Joseph Rowntree Foundation 、Living Wage Foundation
、Living Wage Foundation ほか各ウェブサイト
ほか各ウェブサイト
参考レート
- 1英ポンド(GBP)=147.58円(2018年3月8日現在 みずほ銀行ウェブサイト
 )
)
2018年3月 イギリスの記事一覧
- 低賃金労働からの脱出は6人に1人 ―諮問機関報告書
- シェアリングエコノミー従事者の権利保護をめぐる議論
- 不安定な働き方の従事者の保護に関する政府の方針
関連情報
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2018年 > 3月
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > イギリスの記事一覧
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 労働法・働くルール、労働条件・就業環境
- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス
- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス
- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス


