基礎情報: イギリス(2005年)
基礎データ
- 国名:グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国
- 人口:6,021万人 (2005年)
- 実質GDP成長率:1.8% (2005年)
- GDP:2兆2,031億ドル (2005年)
- 一人あたりGDP:3万6,429ドル (2005年)
- 労働力人口:3,039万人 (2006年4月)
- 就業者数:2,884万人 (2006年4月)
- 失業率:5.1% (2006年4月)
- 実収賃金:431ポンド (週当たり)
- 組合組織率:29.0% (2005年)
資料出所:英国統計局(ONS)、貿易産業省(DTI)、外務省
Ⅰ. 労働関係の主な動き
Ⅰ-1. 雇用情勢
好調を維持していた英国経済は2004年夏以降、減速傾向に入り、2005年の秋頃まで停滞が続いた。この結果、2005年の実質GDP成長率は、92年(0.3%)以来の最低の伸び(1.8%)となった。(注1)
雇用情勢を見ると2005年の失業率は4.8%(前年同期:4.7%)で、2004年に引き続き、4%台で推移している。2005年の就業者数は2774万人と引き続き増加傾向にあり、過去最高と言われる高水準を維持した。一方、若年層(18~24歳)の長期失業率は上昇傾向にあり、2004年5月のEU拡大に伴い新規加盟した東欧諸国出身の若者が流入したことも要因のひとつと分析されている。
Ⅰ-2. 労使関係
貿易産業省(DTI)が2006年3月に発表した「労働組合調査2005(Trade Union Membership 2005)」によれば、2005年における労働組合の組合員数は639万人で、前年と比較して約12万人減少した。一方、組織率は前年よりも0.2ポイント上昇し、29.0%であった。1980年の調査開始以来、労働条件決定手段として団体交渉を行う職場が一貫して減少している。(注2)この背景には労働組合を介さずに行われる労働者と経営側との直接協議が一般化していることが挙げられる。組織率の低下に歯止めをかけようと英国労働組合会議(TUC)を中心に公共部門労働組合の組合員数の増加を図ろうとしているものの充分な成果を上げていない。
Ⅰ-3. 労働施策をめぐる最近の動向
(1) 新たな移民受入れ制度の内容
2005年2月、内務省(Home Office)は新たな移民受入れ制度「入国管理5カ年計画」を発表した。同制度は技能レベルによって移民を5種類に階層化し、その選定方法として従来高度技能移民の受入れの際に用いている「ポイント制」を全面導入する。
さらに2005年6月には「入国管理5カ年計画」に関連し、「移民・難民及び国籍法案(Immigration Asylum and Nationality)」が公表された。同案は、国境警備強化および不法就労防止の措置として、(1)生体認証を用いた国境管理(e-Border)(2)不法就労者を雇用する雇用主に対する罰金(2000ポンド)、(3)移民受け入れ判定手法の改正等を内容としている。
(2) 労働者への情報提供と労働者との協議に関する規則の施行
2005年4月、労働者への情報提供と労働者との協議に関する規則(The information and Consultation of Employees Regulation)が施行された。同規則は、「労働者に対する情報提供及び協議に関するEU指令」を国内法化したもの。従来、使用者は労組との協約がない限り従業員に情報提供および協議を行なう義務はなく、法的な規制なしに自力で使用者と任意的団体交渉を行う「ボランタリズム(自主主義)」に委ねられてきた。
規則の施行に伴い、150人以上の人員を抱える企業は経営戦略、解雇、合併など従業員に影響を及ぼす事項について、直接または従業員代表(Employee Representative)を通じて協議しなければならなくなり、従業員の経営参加が一定程度法的に保障された。規則の適用範囲は、従業員100人以上の団体(2007年4月)、従業員50人以上の団体(2008年4月)と段階的に拡大される予定である。
(3) ワーク・ライフ・バランス支援
政府は2003年から5年を期間とする「ワーク・ライフ・バランス・キャンペーン」を展開している。これに関連し2005年10月、英国貿易産業省(DTI)は「就業家族法案(Work and Families Bill)」を発表した。同法案は労働者の仕事と育児の両立を支援するとともに、これに伴う事業への影響を最小化することを目指している。同案に盛り込まれた主な施策は以下のとおり。
- 新たな父親休暇の導入。
- 法定出産給付、出産手当等の支給に関する企業の事務処理のサポート
- 出産休暇期間中に休暇・給付の権利を失うことなく出勤できる連絡日の導入。
- 法定出産給付及び出産手当の支給期間を9カ月に延長(2007年4月から)。
- 柔軟な働き方の申請権を介護者にも拡大(2007年4月から)。
Ⅰ-4. EU憲法批准手続きを凍結
2005年6月、英国政府はフランス と オランダの国民投票でEU憲法条約の批准が否決されたことを受け、2006年の実施を予定していたEU憲法の批准手続(国民投票)を一時凍結すると発表した。
当初ブレア首相自身は批准の可否をドイツ同様、議会での審議で決める意向であった。その後「英国が欧州の政策決定の中心にいると決意するかどうかの時だ」と方針転換し、国民投票の実施を決断するに至った。国民投票に関する事前の世論調査では、仏独主導のEUに対して懐疑的な世論が根強いことから、欧州憲法反対派の優勢はゆるがず、国民投票のゆくえは楽観をゆるさない状況にあった。
とりわけ使用者側は、EU脱退までは考えないもののEUが課す様々な規則が経済活動に多大な損害を与えると考えている。英国産業連盟(CBI)はEU憲法草案採択の段階から、自主権の制約になるとして、反対のためのロビー活動を行っていた。一方、TUCをはじめとする労組は、EU憲法の内容を評価しつつも政府の使用者寄りの姿勢を批判、政府とは一線を画する姿勢を鮮明にしていた。そのような中、フランス、オランダで相次いで憲法批准が否決された結果、国民投票凍結という問題先送りの妙案を産むに至った。
EU憲法採択をめぐる動向において、EU統合の主導役であった仏独のシラク、シュレーダー政権が痛手を被ったのとは対照的にブレア政権は政治リスクを回避し、その上EUにおける英国の存在感を高めた。これに対し英国『エコノミスト』誌は「いちばん得をしたのは英国」と評した。
Ⅱ. 分野別動向
Ⅱ-1. 賃金
最低賃金は家内労働者及び派遣労働者を含む全ての労働者に適用されている。(注3)2005年10月、最低賃金の改定が実施され、成人の最低賃金(22歳以上)は5.05ポンド/時間、若年労働者(18-21歳)(注4)については4.25ポンド/同、16-17歳層は3.0ポンド/同となった。2006年の10月にも最低賃金の引き上げが予定されている。
Ⅱ-2. 労働時間
統計局が実施した労働時間・賃金調査(2005 Annual Survey of Hours and Earnings)によれば、2005年4月における週当たり実労働時間は39.4時間(うち所定外労働時間は1.5時間)で、前年同期の39.5時間(同1.6時間で)と比較してわずかに減少した。
英国は欧州各国の中でも長時間労働の慣行で知られている。中でも父親に長時間労働の傾向があると言われ、フルタイムで働く父親の約3分の1が週に49時間以上、7分の1が60時間以上働いているといわれる。
また、英国がEU労働時間指令に対する「オプト・アウト」(注5)を認めている数少ない国のひとつであることも長時間労働の原因のひとつといわれる。
2004年9月、EU委員会は英国企業によるアプト・アウト濫用の防止を内容とするEU指令の修正案を発表したが英国が強く反発した。さらに2005年5月の同問題に関する再討議の際には、欧州議会が「無制限の労働時間制は、労働者の健康と安全だけでなく、仕事と家庭の両立に深刻な危険を及ぼす」として、オプト・アウトの維持に反対したのに対し、ブレア首相が「世界の新興経済との競争に直面している欧州経済には、柔軟性を諦める余裕などないはずだ」とオプト・アウト廃止に同意できない旨を表明した。
現在、長時間労働の問題に対し、政府はオプト・アウトを従来通り維持しつつ生産性を最大化し、かつ労働時間を減らすには個別企業レベルでの取り組みが重要だと考えている。2005年9月に発表された英国貿易産業省(DTI)、英国産業連盟(CBI)、英国労働会議(TUC)による政労使合同プロジェクトの最終報告書『マネージング・チェンジ(変化をマネージする)MANAGING CHANGE practical ways to reduce long hours and reform working practices』では、個別企業の事例を紹介している。
Ⅱ-3. 社会保障
国民保険制度(NIS:National Insurance Scheme)
「国民保険制度(NIS)」は、年金保険、医療保険、労災保険、といった各種社会保険全般を包括する制度である。16歳以上のイギリス居住者には保険料拠出が義務付けられている。
被用者の場合、本人と雇用主がそれぞれ国民保険基金(National Insurance Fund)に保険料を納付する。被用者本人が、収入の一定幅(89~595ポンド/週)につきその11%、雇用主が、一定額(89ポンド/週)以上の収入につき12.8%を負担する。なお、週の収入が89ポンドに満たない被用者については保険料の納付が免除される。週の収入が595ポンドを超える被用者については、超過分の1%を追加納付する。
年金制度
英国の年金制度は、既述のNISを財源とする公的年金とその他年金に区分され、義務教育終了年齢を超えるすべての就業者は公的年金である「(退職)基礎年金」に加入する義務がある。その上で二階部分の年金として(1)国家第二年金(S2P)(2)職域年金(企業年金)(3)個人年金(4)ステークホルダー年金のいずれかを選択する(図参照)。
図:英国における年金体系図
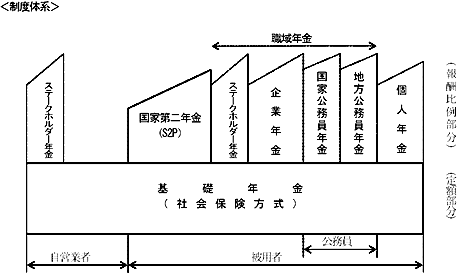
出所:厚生労働省
先進国では一般的に高齢化が進むにつれ公的年金への負担が高まるが、英国では逆に低下している。OECDの試算によれば1995年におけるGDPに占める公的年金支出の割合は日本11%、英国4.5%で、2050年に日本が15%に上昇するのに対して、英国は4.1%に低下する。この理由は英国の公的年金の給付水準がもともと低いことに加え、1980年代サッチャー政権で実施された年金改革に負うところが多い。同改革の下では公的年金を私的年金で代替する施策が採られ、さらに97年に政権についた労働党もこの方針を基本的に継承し、「脱公的年金」を進める方向で年金改革を行ってきた。
(参考)GDPに占める公的年金支出(OECDによる試算)
| 1995年 | 2050年 | |
|---|---|---|
| 英国 | 4.5% | 4.1% |
| 日本 | 11.0% | 15.0% |
2005年11月、政府の諮問機関である年金委員会(注6)は、財政危機が指摘される公的年金の改革を内容とする最終報告「21世紀における新たな年金制度(A New pensions settlement for 21st century)」を政府に提出した。ブレア政権は同報告書をたたき台とし、一定の諮問期間を設けた後、2006年5月に政府案を発表する見通しである。
年金委員会による最終報告における主要な改革案
- 公的金支給開始年齢を68歳に引き上げ
- 公的年金支給開始年齢を現行の65歳から、2030年までに66歳に、2040年には67歳、2050年までに68歳へと段階的に引き上げる
- 基礎年金の引上と受給要件の変更
-
- ・資力調査(ミーンズテスト)を伴わない形式での基礎年金の引き上げ
- ・基礎年金受給要件を現行の拠出要件から居住要件に変更
- スライド方式の見直し
- 現行の物価スライドに加え賃金スライドを導入
- 国民年金貯蓄制度(National Pensions Saving Scheme-NPSS)の新設
- 職域年金の枠組みから外れている被用者を対象とし、被用者と雇用主の双方が拠出する「国家年金貯蓄制度(NPSS)」を新たに設置する。被用者は自動的にNPSSに加入し税引き後所得の4%を積み立てる。企業は3%、国は1%を負担する。
職域年金についてみると、「ファイナルサラリー年金」とよばれる最終給与と勤続年数によって給付額が決定される確定給付型の年金が広く普及してきた。しかし2001年以降の株式市場の低迷を契機に、職域年金を維持できない企業が増加し、国民の間で不安が高まった。これを受け、2002年12月のグリーンペーパー、2003年6月の職域年金制度改革に関する文書など職域年金の見直しが進んでいる。
2005年4月6日に発効した新英国年金法(2004年年金法)には、企業譲渡(雇用保護)規則(TUPE:Transfer of Undertakings Protection of Employment Regulations)(注7)における職域年金権利の保護などが盛り込まれた。
Ⅱ-4. 雇用失業対策 ─長期失業対策「エンプロイメント・ゾーン(Employment Zone)」─
エンプロイメント・ゾーンは、長期失業者の多い地域を対象に通常公共職業安定機関「ジョブセンタープラス」が行う職業紹介業務を外部化するプログラムである。英国雇用年金省(DWP)は、2000年の開始以来2005年5月までの期間、のべ13万6000人がプログラムに参加し、うち5万1000人が同プログラムを通じて職を得たと発表している。またOECDの『雇用アウトルック2005』は同プログラムについて「求職者が就職した時点と、その後3カ月以上就労が継続した時点で報酬を支払うという段階的な報酬システムが、プログラムの運営に良い影響を与えているとする研究結果を引用、一定の効果を挙げていると評価している。
Ⅱ-5. 企業の社会的責任(CSR)関連施策
現在英国政府はCSRに対して積極的な支援策を展開しており、貿易産業省(DTI)内にはCSR担当の閣外大臣のポストが設置されている。施策の最大の特色は「持続可能な開発」をキーワードに、CSR普及のための環境整備やインセンティブ供与といった「ソフトな規制」を行っている点にある。
CSR推進策の実施にあたって重要な役割を担っているのがNPOやNGOなどの様々なCSR関連組織だ。CSRの推進に際して、多くの企業がこれらの組織のコンサルティングサービスを利用している。政府もこれらCSR関連組織による政府や企業とのパートナーシップがCSRの推進に不可欠であると認識しており、企業がこれらの組織を活用することを推奨している。
Ⅲ.リファレンスリスト
- 英国国家統計局(ONS)(http://www.statistics.gov.uk/
 )
) - 英国雇用年金省(DWP)(http://www.dwp.gov.uk/
 )
) - 英国貿易産業省(DTI)(http://www.dti.gov.uk/
 )
) - 英国内務省(Home Office)( http://www.homeoffice.gov.uk/
 )
)
注:
- 外務省各国地域情勢参照
- DTI「2004年職場労使関係調査(Workplace Employment Relations Survey : WERS2004)」に基づく。
- 適用除外となるのは、自営業者、徒弟労働者の一部(26歳未満で徒弟労働者になってから12カ月未満の者等)、学生の一部(就業経験を得ることを目的として働いている者や教育実習として教えている者、政府の教育プログラムに実習生として参加している者等を含む。
出来高払いの労働者、在宅勤務者、派遣労働者、パートタイム労働者及び日雇い労働者を含む - 新たに就職して正式な研修(最長6カ月)を受ける労働者を含む。
- オプト・アウト:労働者の同意を得た場合のみ週48時間の上限を超えて労働させることを認める特例規定。EU加盟国のうち、キプロスとマルタにおいてもオプト・アウトが認められている。
- 年金委員会:年金制度の改革を検討するために2002年に設立された独立機関。3つの部局から構成され、現在の議長は前CBI会長であったターナー卿が就任している。
- 企業間で事業譲渡等が行なわれた場合、新事業主が従業員の賃金水準を(原則として)従前と同様の水準に維持しなくてはならないとする規則。
参考:
- 1米ドル=114.87円(※みずほ銀行ホームページ2006年6月22日現在のレート参考)
- 1英ポンド=211.89円(※みずほ銀行ホームページ2006年6月22日現在のレート参考)
バックナンバー
- 基礎情報:イギリス(最新年)
- 基礎情報:イギリス(2020年)
- 基礎情報:イギリス(2018年)
- 基礎情報:イギリス(2017年)
- 基礎情報:イギリス(2016年)
- 基礎情報:イギリス(2014年)
- 基礎情報:イギリス(2013年)
- 基礎情報:イギリス(2005年)
- 基礎情報:イギリス(2004年)
- 基礎情報:イギリス(2003年)
- 基礎情報:イギリス(2002年)/全文(PDF:789KB)
- 基礎情報:イギリス(2001年)/全文(PDF:331KB)
- 基礎情報:イギリス(2000年)
- 基礎情報:イギリス(1999年)
※2002年以前は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。
関連情報
- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス > 2005年
- 海外労働情報 > 国別労働トピック > 国別にさがす > イギリスの記事一覧
- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書 > 国別にさがす > イギリス
- 海外労働情報 > 海外リンク > 国別にさがす > イギリス
お問合せ先
内容について
調査部 海外情報担当
※内容を著作物に引用(転載)する場合は,必ず出典の明記をお願いします。
例) 出典:労働政策研究・研修機構「基礎情報:イギリス」


