労働紛争・解決システム・労使関係:日本
日本における労働紛争の解決
—最近の展開とその背景、および将来の展望
(本稿は、慶應義塾大学法科大学院教授山川隆一氏がJILPTの国際シンポジウムのために執筆した論文をJILPTの責任において要約したものである。)
著しい個別紛争の増加
最近の日本では、個別紛争の増加が著しい。まず、労働関係の民事訴訟事件をみると、地方裁判所における新規受理件数は、平成3年当時は、通常訴訟と仮処分をあわせて1054件であったが、その後件数はほぼ一貫して増加し、平成16年には約3倍の3168件となっている(図表1)。これらの件数には集団紛争事件も含まれてはいるが、組合組織率の低下や集団紛争の低下にかんがみると、大部分が個別紛争とみられる。
また、紛争には至らない者も含めた行政機関における相談件数はきわめて多数に及んでいる。個別労働紛争解決促進法のもとで、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は、平成16年度で82万3864件に達した。これらの相談のうち、労基法違反等に関わらない民事上の個別紛争は16万166件となっている(図表2)。
図表1:地方裁判所における労働民事事件新受件数(平成3年・16年)
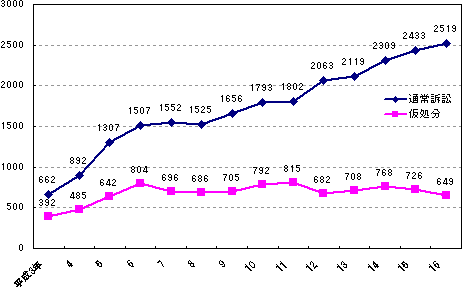
図表2:個別労働紛争解決促進制度における労働相談件数の推移

他方、集団紛争は減少している。たとえば、労働委員会への不当労働行為救済申立ては、1975年には929件あったが、2004年では年間311件程度に留まっている。また、労働委員会へのあっせんなどの争議調整申立ても、オイルショック後の1974年には2249件にのぼったが、2004年では511件である(図表3)。
紛争内容の内訳
個別紛争の内容をみると、訴訟事件のうち、通常訴訟では、解雇事件を中心とした労働契約関係の存在確認請求に関する事件や、賃金請求に関わる事件が多い。地方裁判所における2004年の通常訴訟新受事件2519件のうち、1427件が賃金請求に係わるものであり、労働契約関係の存在確認請求事件は573件である。また、個別労働紛争解決促進法のもとでの民事紛争に係わる相談の内容については、解雇に関わるものが最も多いが(2004年では27.1%)、労働条件の引下げにかかわる相談も少なくない(16.0%?以上については図表4)。
図表3: 不当労働行為事件新規申立件数・争議調整事件新規申立件数の推移
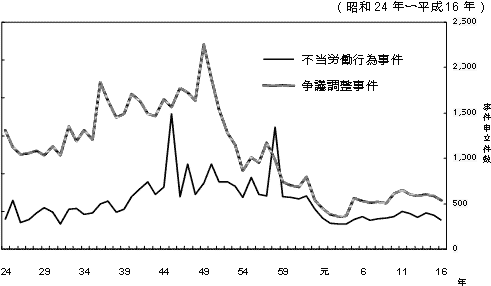
図表4:民事上の個別労働紛争相談の内訳
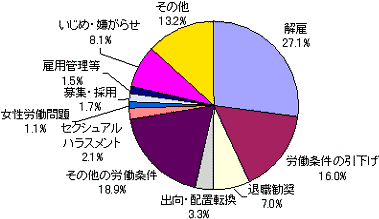
集団紛争については、包括的な統計はないが、2004年における労働委員会への不当労働行為救済申立311件のうち、最も比率の高いのは団交拒否事件であるが、不当労働行為の類型による差はさほど大きくない。
個別紛争増加の背景
最近の個別紛争の増加は、バブル経済崩壊後の不況の長期化・深刻化とほぼ軌を一にしており、そうした不況への対応として、企業が人員削減、労働条件の変更、または組織再編などを行ったことが要因となっていると思われる。景気の回復により、こうした動きも緩和する可能性はあるが、他方で、国内外の市場競争の激化や、コーポレートガバナンスの変貌に伴う企業の株主利益志向の強化などに伴い、企業による労働条件変更や組織再編、あるいは人員削減の動きは続いて行くとみられるので、それによる労働者との利害対立はなお発生し続けることが予想される。
他方、労働者側をみると、労働市場における労働者像の多様化が進んでおり、女性・高齢者・外国人など様々なタイプの労働者が就労するに至っている上、雇用形態としても、いわゆる非典型雇用が増大している。こうした状況のもとでは、従来のような日本人男性の正社員中心の労働市場に比べて、労働者の利害も多様化してゆくので、企業の人事管理においても一律の処理が難しくなり、労働者との利害対立が増加するのではないかと思われる。
「がまんの効用」の変化
以上は労使間の利害対立の増加にかかわる要因であり、それにより労働者の不満をもたらしうるものであるが、利害対立があり、労働者がそれを認識して不満を抱いたとしても、ただちに苦情や紛争に至るとは限らない。労働者が不満を外部に表出せずに「がまん」したり、あるいは、苦情や紛争に至る前に利害対立を解消するなどして、紛争を予防したりすることがありうるからだ。
これらのうち前者に関しては、従来のわが国では、いわゆる日本型雇用システムにおける終身雇用と年功処遇が、紛争の予防ないし抑制機能を果たしてきた。すなわち、不満を抱いた労働者が使用者にそれを苦情として表出すると、職場に居づらくなるなどして転職する可能性が高まるが(そのような状況の評価は別問題である)、日本型の雇用システムのもとでは、退職・転職して長期雇用と年功処遇の利益を失うよりも、現実的には、「がまん」をした方が合理的な選択ともいいうるからだ。
しかし、長期雇用や年功処遇のシステムが変化してくると、そのような「がまんの効用」も意味が小さくなり、労働者側における転職意識の変化ないし労働市場の流動化と相まって、不満が苦情ないし紛争に発展する可能性が高まると考えられる。また、これまでの職場では、不満を抱いた労働者は主に上司を相談相手としてきたが、今後は、成果主義の強化の中で、第1次的評価者である上司本人が紛争の相手方当事者となったり、上司がプレイング・マネジャーとしての役割を強めて相談に応ずる時間的余裕が減少したりすることが予想される。
以上のような背景のもとで、新たな労働紛争解決システムの必要性が指摘されるにいたり、2001年には、個別労働紛争解決促進法により、新たな行政上の個別紛争解決システムが創設された。また、この問題は、司法制度改革の中でも取り上げられた。そこでは、裁判員制度の導入などの争点とともに、個別労働紛争に関する新たな解決システムが議論の対象となり、検討の結果、2004年には、労働審判法が成立するに至った。
労働審判制の創設
欧州諸国とは異なり、日本には、通常裁判所とは別の労働裁判所は存在しない。従来は、労働事件についても、通常事件と同じ手続を利用する他はなかったが、上記のような背景のもとで、労働審判制度が創設されている。
労働審判制度は、地方裁判所に労働審判委員会が設置され、裁判官である労働審判官と、労働関係につき専門的知識経験をもつ2名の労働審判員(労使それぞれの出身であることが想定されている)が委員会を構成する。労働審判委員会は3回以内の期日で個別労働関係事件を解決することとされており、審判を定めて解決を行うほか、随時調停を試みることができる。
審判委員会は、こうした迅速な審理により、多数決により評決を行い、当事者間の権利関係と手続の経過を踏まえつつ、事案の実情に即した内容の審判を定める。当事者が審判に異議を申し立てなければ審判は確定するが、異議の申し立てがあると審判は失効する。しかし、異議の申立てがあった場合、事件は通常訴訟に移行する。
このように、労働審判制度は、職業裁判官と労使の専門家が、迅速な審理に基づき、調停や柔軟な解決が可能な労働審判によって個別紛争を解決しようとする司法的システムであり、しかも、通常訴訟との連携のしくみも用意されている。
個別労働紛争解決の手続
最近に至るまで、日本の労働法制は、個別紛争につき特別の解決システムを用意してこなかった。労働委員会の管轄権限は、不当労働行為事件など集団紛争に限られていた。労働基準法は労働基準監督制度により実効性を図られているが、労働基準監督官は、紛争解決をあっせんする権限等はもっていない。しかし、2001年には、個別労働紛争解決促進法が制定され、(1)都道府県労働局における総合労働相談制度、(2)都道府県労働局長による助言指導、及び(3)紛争調整委員会によるあっせんという3つの要素からなる個別労働紛争解決促進制度が創設された。
まず、都道府県労働局長は、個別労働紛争の未然防止と自主的な解決の促進のため、労働者や事業主等に対して情報の提供、相談その他の援助を行う。これを行う場所は総合労働相談コーナーと呼ばれるが、同コーナーは、いわゆるワンストップサービスとしての機能を果たし、労働関係についての相談等を広く受け付けているが、労基法・職安法・均等法などの法令違反とみられる事案は所轄の行政機関の処理に委ねることとしている。
次に、都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当事者の一方または双方から解決のための援助を求められた場合、当該紛争の当事者に対して、法令や判例等に照らして必要な助言または指導をすることができる。たとえば、解雇された労働者から申請があった場合、都道府県労働局長は、当該解雇が解雇権濫用に当たるおそれが強いと判断されるときには、解雇を撤回したり再考したりするように事業主に助言・指導を行うことが考えられる。
さらに、紛争調整委員会によるあっせんは、紛争調整委員会が指名するあっせん委員が当事者の間に立って、話し合いを促進することを目的とする、非公開の調整手続である(雇用機会均等法上の一定の紛争については調停を行う)。紛争調整委員会は各都道府県労働局に置かれ、学識経験者から任命される委員により組織されている。あっせんは当事者の合意に基づく紛争解決手続であり、相手方が手続に参加する意思を有しない場合などには手続は打ち切られる。
労働委員会の役割
労働組合法は、労働委員会を設置し、不当労働行為事件における準司法的手続を担わせている。不当労働行為があったとして労働組合や労働者から申立てがなされると、労働委員会は、調査や審問等の審査手続により、不当労働行為の成否を判定する。これにより不当労働行為の成立が認められた場合には、労働委員会は救済命令を発し、認められなかった場合には棄却命令を発する。初審は通常の場合都道府県労働委員会が管轄し、中央労働委員会が再審査を行うが、各委員会の命令については司法審査が可能である。
次に、労働関係調整法は、労働争議についての当事者間の自主的な解決を援助するため、労働委員会による、あっせん・調停・仲裁などの争議調整制度を設けている。あっせんは、紛争当事者の申請等に基づいて、あっせん員が当事者双方の主張の要点を確かめ、事件を合意により解決するように努める手続。また、調停は、公労使三者委員で構成される調停委員会が、当事者の意見を聴いて調停案を作成し、受諾を勧告する手続だ。仲裁は、手続の開始は当事者双方の申請によるが、公益委員等からなる仲裁委員会が仲裁裁定を下すと、当事者はそれに拘束される。これらの中では、あっせんが利用されることが多い。
なお、個別労働紛争解決促進法の制定後、都道府県労働委員会の中には、個別紛争のあっせんを行うものが多くなっている。
私的解決システムはまだ
日本の労働者は、労働協約に苦情処理手続が設けられている場合でも、それを利用することは少ない。日本では、紛争が発生した後に解決するよりも、上述したように、上司との相談や労使協議により紛争を防止したり、長期雇用と年功賃金システムのもとで、紛争の発生が抑制されたりしてきたからだ。こうした紛争防止メカニズムの機能は弱くなってきているが、使用者も労働組合も、新たな私的紛争解決システムを構築することにはまだ成功していないようだ。
アメリカ合衆国とは異なり、日本には、労働協約上のものであれ個別契約上のものであれ、私的仲裁の伝統はない。2004年には新仲裁法が制定されたが、使用者と個別労働者の個別紛争に係る仲裁合意は、当分の間無効とされている。
通常訴訟と労働審判の違い
裁判所における通常訴訟は、原告が訴状を提出して訴えを提起することにより開始される。被告が争う場合、弁論準備手続等における争点や証拠の整理を経て、証拠調べがなされ、それに基づいて判決が下される。それまでの間に和解がなされることも少なくない。仮処分手続は、より簡易迅速なものである。
これに対して、労働審判手続は、3回以内の期日における審理に基づいて審判が下される。申立人が地方裁判所に審判の申立てを行うと、裁判所は労働審判官と審判員2名からなる労働審判委員会を指名する。手続のイメージとしては、第1回期日では、争点・証拠の整理と書証の取り調べなどがなされ、第2回期日は、証人等の取り調べが主たる内容となる。第3回期日では、補充的な証拠調べの他、それまでの審理に基づく調停の試みが中心になると予想される。
調停が成立しなかった場合、労働審判委員会は、口頭で、または書面により解決案(審判)を定める。両当事者とも審判に異議がない場合には審判は確定するが、異議が申し立てられた場合は、審判申立ての時点で通常訴訟が提起されたものとみなされる(ただし、記録が自動的に引き継がれるわけではない)。事件が複雑であるなどの理由で労働審判に適さない場合、審判委員会は、審判を行わずに手続を終了させることができる(その場合も事件は訴訟に移行する)。
個別労働紛争におけるあっせん
募集・採用を除く個別紛争につきあっせんが申し立てられた場合、都道府県労働局長は、必要と認めたときに、紛争調整委員会にあっせんを委任する。紛争調整委員会の会長は3名あっせん委員を指名し、同委員(そのうち1名がこれに当たることも多い)があっせんを行う。
あっせん委員は、各当事者の主張の要点を確かめ、実態に即した合意による解決がなされるように努める。また、あっせん委員は、紛争当事者から意見を聴く他、必要に応じて参考人から事情を聴取するなどして、全員一致によりあっせん案を作成し、当事者に提示することができる。相手方が手続に参加する意思がない場合や、当事者間の違憲の隔たりが大きい場合など、紛争解決の見込みがない場合には、あっせん委員は手続を打ち切ることができる。
労働委員会の不当労働行為審査手続
不当労働行為があったとして労働組合や労働者から申立てがなされると、労働委員会は、調査や審問等の審査手続により、不当労働行為の成否を判定する。これにより不当労働行為の成立が認められた場合には、労働委員会は救済命令を発し、認められなかった場合には棄却命令を発する。通常の場合、労働委員会は、和解により事件を解決することを重視しており、和解の試みに当たっては、公労使の三者構成であることを生かして、労使の参与委員が大きな役割を果たしている。
労働事件の処理時間のスピード化
かつては、裁判所における労働事件訴訟は長期間を要するものであった。1984年の時点で、労働事件の通常民事訴訟手続における事件処理の平均期間は22.9カ月であった。しかしながら、事件処理の速度はその後の20年間で相当に改善された。2004年においては、事件処理の平均期間は約11カ月になっている。これは、民事訴訟法の改正や手続の運用の他、迅速処理が可能な個別紛争の増加も背景となっているであろう。仮処分手続の場合はより迅速であり、6カ月以内で事件が終了することが大部分のようである。
しかし、なお手続を迅速化すべきであるとの指摘があり、そこで、2001年の司法制度改革審議会意見書では、労働事件の処理期間を半減することを目指すと述べられている。また、労働審判法のもとでは、労働審判委員会は、3回以内の期日で審理を終了することとされている。同法は来年4月より施行されるので、紛争解決のスピードはより早くなることが期待される。
他方、個別労働紛争解決促進法による行政的紛争解決手続はかなり迅速に行われている。2004年においてあっせんの申立てがなされた事件のうち、66.4%は1カ月以内に終了しており、2カ月以内に92.9%が終了している。ただし、それらのうち約半分は、当事者があっせんに参加することを拒否したことなどにより、手続が不開始または打ち切りとなったものだ。都道府県労働局長による助言・指導の手続に関しては、93.9%が1カ月以内に終了をみている。また、申立てのあった事件のうち、94.7%において、労働局長の助言・指導がなされている。
労働委員会は、事件処理の遅延につき長い間批判を受けてきた。都道府県労働委員会における不当労働行為の審査には、約3年を要している(2004年では906日であった)。中央労働委員会の場合は、平均でおよそ4年間に及ぶ(2004年では1539日)。こうした事件処理の遅延は、人事考課を通じた少数組合員の集団的差別やJR関係事件など、複雑な事件の増加による面もあるが、争点や証拠の整理が不十分であるため審問が長期化することも、遅延の主要な要因として挙げられていた。
そこで、2004年には労働組合法の改正がなされ、労働委員会は、各事件における争点や証人尋問の予定等を記載した審査計画を策定すること等を義務づけられるに至った。まだ改正法が施行されて間もないため、改正が実際上も効果を挙げているかどうかは今後の検証に委ねられるが、中央労働委員会において自ら見聞する限りでは、事件処理の迅速化は現に進んでいるように感じられる。
労働紛争解決システムは利用しやすいか?
個々の労働者は、紛争解決手続のコストが高ければ、それを利用するのを躊躇するだろう。ここでのコストとは、裁判所等に納付する訴訟費用のみならず、弁護士費用なども含まれる。そのため、日本においても、労働紛争解決システムは、正式の訴訟手続よりも簡単でコストの安いものとなる。
たとえば、個別労働紛争解決促進法の下での相談、助言・指導およびあっせんは、いずれも無料で、手続も簡易。特に相談・情報提供は、全国の約300箇所(都道府県労働局や労働基準監督署など)で提供されている(他方、裁判所の本庁は50箇所である)。また、労働審判手続は、地方裁判所における手続ではあるが、手続が迅速である点と手続費用が安い(通常訴訟の約半分)点で、通常訴訟よりも利用しやすいものである。
自主的解決を優先
使用者と労働者は継続的かつ人的な関係にあるので、労働紛争は、可能な限り、第3者による一方的な裁定よりも、当事者間の合意に基づく解決が望ましい。労働組合と使用者間の紛争についても同様のことがいえる。そこで、労働紛争の解決システムは、しばしば、当事者の合意を促進することに重点を置いたものとなる。
たとえば、労働審判手続においては、審判委員会は随時調停を試みることができるものとされている。通常訴訟手続においても、裁判所は実際上、和解による解決を重要視している。また、行政的システムでも、個別労働紛争解決促進法は、助言・指導やあっせんなど、調整的な解決手法のみを採用している。労働委員会は、労働争議についてあっせん・調停・仲裁の権限をもつほか、不当労働行為事件においても、命令よりは和解の方が労使関係にとって有益な紛争解決手法であることについてはおおむね共通の理解が存在する。そこで、2004年の労組法改正は、労働委員会の和解の権限と手続について明文の規定を置くに至った。
労使が参加する価値
日本においても、労働関係における専門的知識経験をもつ者が、労働紛争の解決手続に参画することがある。これは、そのような専門家は、職場の実態に詳しく、その専門的知識経験は、事件についての判定や和解の促進についても有用だからだ。こうした理由から、労働委員会は、三者構成の長い伝統をもっている。労働委員会の不当労働行為審査手続では、労働者側および使用者側を代表する委員が審問に参与したうえ、公益委員が行う判定の前に意見を提出する。また、三者構成の価値は、労使各側委員が当事者を説得して和解を促進する場面においてとりわけ大きく現れる。労働関係調整法のもとでの労働争議のあっせんや調停においても、こうした労使の委員のスキルが発揮されている。
さらに、労働審判手続においては、労使の専門家2名が労働審判委員となり、職業裁判官とともに審理に加わり、審判の評決を行う。しかしながら、ここでの専門家の参加は、労働委員会におけるそれとは意味が異なる。労使の専門家はここでもその知識経験を生かすことが要請されており、事実認定や判断、あるいは調停の試みなどにおいてその意味は大きいといえるが、彼(彼女)らは中立公正な立場から審判を行うべきものとされているからだ。また、労使の参加は、当事者が日常的に接している者が手続に関与するという点で、労働審判制度をより親しみやすく、かつ信頼しやすいイメージのものにするであろう。
加えて、労働紛争の司法的な解決の場において労使が参加することは、職場に有益なフィードバックをもたらすことが期待されている。そうした労使の専門家が、法的ルールの適用により紛争を解決することに慣れれば、職場における紛争についても同様の解決を行い、あるいはむしろ、職場において法的ルールをより意識することによって、紛争を予防するようになると考えられるからだ。
労働紛争解決システムの評価
ごく最近に至るまで、日本の労働紛争解決システムは集団紛争に焦点を当ててきた。すなわち、労働委員会は、不当労働行為の審査と労働争議の調整において大きな役割を果たしてきたが、他方で、審査の遅延について厳しい批判を受けてきた。より重要なことに、個別紛争については、労働法上特別のシステムはなく、通常裁判所がその解決権限を有していたが、手続に要する時間やコストの点で必ずしも利用しやすいものではなかった。
しかしながら、個別紛争の増加する中で、司法システムにおいても行政システムにおいても、新たな個別紛争解決制度が導入されることになった。労働審判制度と個別労働紛争解決促進制度である。いずれのシステムも個別紛争を対象としており、迅速でかつ利用しやすいものである。不当労働行為の審査手続に係わる労組法の改正と相まって、日本の労働法における紛争解決システムは相当に改善されたものと評価することができる。
もっとも、これらのシステムが導入されたのは、ごく最近である。個別労働紛争解決制度は2001年10月から運用を開始したものであり、改正労組法が施行されたのは今年1月である。労働審判制度は2006年1月から実施される予定である。それゆえ、これら新たなシステムの成功は、将来における運用如何にかかっている。
将来の展望
まず、将来におけるこれら紛争解決システムの成功にとって鍵となるファクターの1つは、システムにかかわる人的資源の質と量である。とりわけ、労働審判制度における審判員は極めて有益な役割を果たすものであり、適切な知識経験をもつ人々を選任することは重要となる。また、労働審判員については、手続に関与する意味や労働法の基本的知識、あるいは中立公正であることの意味について研修を行うことも重要だ。現在、合計約1000名の審判員候補者につき研修を実施中。加えて、裁判官(労働審判官)や弁護士の新たな手続につき準備を進める必要がある。たとえば、労働審判手続では、大量の書面を交換することは迅速な手続の進行とは調和しないので、口頭での審理がより重要になるからである。
次に、日本においては、個別労働紛争の解決システムとして、司法上の労働審判制度と行政上の個別労働紛争解決促進制度という2つの主要なシステムが用意されることとなったので、両者の関係が問題となる。すなわち、両者は競争関係に立つのか、あるいは何らかの棲み分けがなされるのかである(両者の連携が考えられることはいうまでもない)。この点については、少額で単純な紛争の当事者は行政システムを利用することが多くなると予想される。行政上のシステムは無料であり、また、とりわけ、少額で強制的な解決までは求めない紛争については、総合労働相談コーナーを訪れた相談者が助言・指導やあっせん手続に進むことが少なくないものと予想されるからである。
他方、労働審判手続は、審判に異議が申し立てられた場合には通常訴訟に移行するものであり、また、代理人として弁護士が必要になる場合が多くなると考えられる。したがって、上記のような場合よりも係争利益が大きい紛争につき、迅速だが強力な解決を求める当事者は、労働審判手続を利用することが予想される。したがって、解雇事件のような典型的な労働紛争については、労働審判制度が主要な解決システムとなるだろう。集団的な解雇や差別事件のようにより複雑な紛争は、通常訴訟手続が当初から利用されることが予想される。裁判所の通常訴訟手続は、利用される件数は少ないかもしれないが、職場のルールを設定するものとして重要な役割を果たし続けるだろう。集団紛争における労働委員会の役割についても同様のことがいえる。
最後に残された将来の課題は、企業内の、または私的な労働紛争解決システムである。日本の使用者は従来、紛争の事後的な解決よりも、労使協議などを通じた事前の予防を重視してきたが、上述したように、紛争の予防メカニズムは弱まってきているように思われる。労働者が公的な紛争解決システムをより容易に利用できることを認識するようになると、使用者としては、紛争が外部に出る前に組織内で解決しようと考えるかもしれない。こうした現象はアメリカ合衆国において実際に起こっており、企業内苦情処理手続や個別契約上の仲裁などのADR(裁判外紛争解決制度)の発展をもたらした。日本では、企業内紛争解決システムの設計や私的仲裁についてあまり議論がなされていないが、将来的には重要な問題になると予想される。
2006年1月 フォーカス: 労働紛争・解決システム・労使関係
- 日本: 日本における労働紛争の解決-最近の展開とその背景、および将来の展望
- 韓国: 韓国の労使紛争解決システムと労使関係
- アメリカ: アメリカにおける個別雇用紛争解決
- ドイツ: 労働、雇用関係における紛争解決:ドイツの事例


