組合活動の規制を強化
政府が5月末に公表した労働組合の組織状況に関する統計によれば、2016年における労働組合員数は前年から27万5000人と記録的に減少して621万6000人となり、組織率は1.2%減の23.5%となった。調査開始以降で最大となる減少は、政府の歳出削減策に伴い、教育業で人員削減や非正規労働者が増加している影響が大きいとみられる。労働争議の参加者数や損失日数も低い水準で推移する中、政府は昨年成立した労働組合法に基づき、この3月から、労働組合に対するさらなる規制強化を進めている。
組合員の減少は歳出削減が影響か
労働組合員数は、1970年代末以降減少が続いており、過去20年間で組合員数は696万2000人(1996年)から2016年には621万6000人に、また組織率は34.1%から23.5%に、それぞれ低下している(図表1)。この間、2000年代の前半には、公共サービス関連部門(教育、行政、保健・福祉など)を中心に組合員数の増加もみられたものの、製造業における継続的な減少を背景に、民間部門では減少が続いた。また、金融危機以降の民間部門(製造業のほか、建設業、運輸・倉庫業、金融保険業、情報通信業など)における急速な減少と、続く歳出削減の時期における公共部門での減少が、組合員数をさらに押し下げる要因となった(図表2)。
調査開始以降で最大の減少幅となった昨年からの減少(27万5000人減)は、その大半が教育業(15万5000人減)で生じたものだ。正確な理由は不明だが、労働組合は、教員の高い離職率や、補助教員の大幅な削減、継続教育カレッジや高等教育機関における臨時雇い労働者やパートタイム労働者の増加、さらにここ数年の賃金抑制策により給与水準が停滞する中で、組合費を負担に感じる労働者が拡大している可能性などを指摘している。
図表1:労働組合員数と組織率の推移 (千人・%)
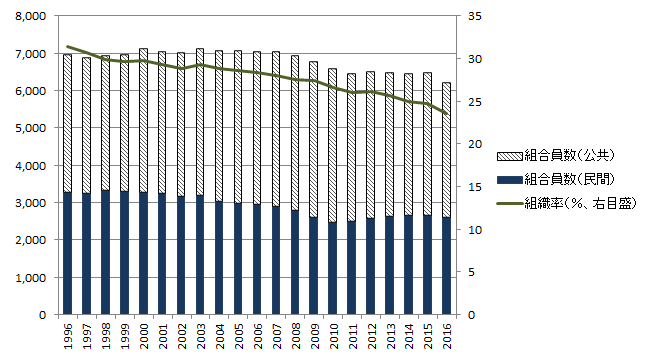
- 出所:Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2017) "Trade union membership 2016"
図表2:業種別労働組合員数と組織率の変化 (千人・%)
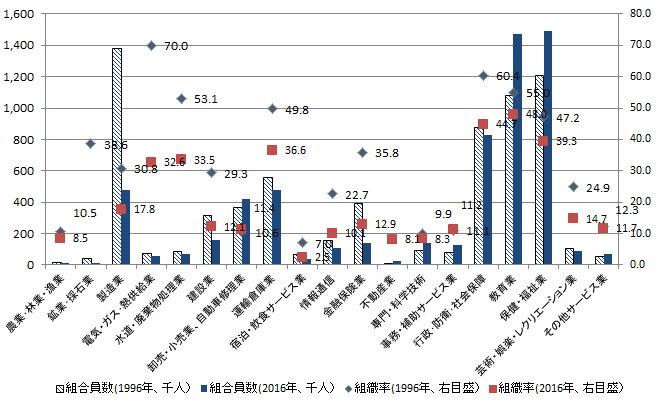
- 出所:Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2017) "Trade union membership 2016"
なお、統計局が公表している労働争議に関する統計によれば、労働損失日数は90年代以降、低い水準で推移しており、労働争議の参加者数についても、2015年には約8万人と120年ぶりともいわれる低水準に達している(図表3)。
図表3:労働争議参加者数と労働損失日数の推移
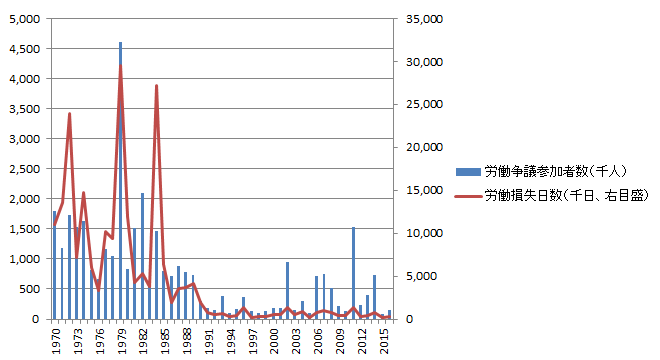
- 出所:Office for National Statisticsウェブサイト
ストライキの実施をより困難に
こうした中、昨年5月に成立した労働組合法に基づき、労働組合に対する各種の規制強化策の導入が3月から開始された。公共部門ではここ数年、歳出削減の一環として実施されている賃金抑制や人員削減、年金に関する条件の切り下げなどをめぐって、労働組合によるストライキやデモが発生しており、政府は新たな規制の導入をこうした状況への対応策と位置づけている。
3月に導入された制度改正の柱は、ストライキの実施手続きに関する規制強化だ。労働組合には、ストライキに先立って組合員に実施の賛否に関する投票を行うことが義務付けられているが(注1)、従来は投票率にかかわらず、投票者の過半数が賛成票を投じることが要件となっていた。新たな規制は、対象となる組合員による投票率が50%以上であることを投票成立の要件とするもの。これを下回る場合、ストライキの実施は違法となり、雇用主はストライキによって生じた損失を労働組合に請求することができる。特に、医療、教育、消防、交通、入国管理といった「重要性の高い」公共サービス部門については、組合員全体の4割相当の賛成を義務付ける(注2)。投票には有効期限を設け、ストライキ等を実施しないまま6カ月(雇用主の合意がある場合は9カ月)を経た場合は、改めて投票を実施しなければならない。このほか、投票用紙には、交渉の争点や、賛否を問う行動の内容(争議、争議未満の抗議行動など)および期間を含むより詳細な情報を記載することが求められる。
また、ストライキの実施に際して、使用者側に行うこととされている事前通告の時期も、従来の7日前から14日前に延長されている(注3)。ピケッティングの実施に際しては、代表者を決めて警察当局に連絡先などを登録することが義務付けられる。政府は、ストライキに参加しない労働者に対する脅迫や嫌がらせの予防をその目的に挙げている。
このほか、労使団体の活動の監査を目的として設置されている認証官(Certification Officer)の権限が強化された(注4)。労使団体により詳細な活動報告を義務づけるとともに、監査に際して要件とされていた組合員等からの苦情や通報がなくとも(さらに、雇用主やメディアなど第三者からの通報によっても)、監査を行う権限が与えられた。また、監査制度の運用に関して労使団体に負担金の拠出が義務付けられることとなった(注5)。
組合費徴収や職場委員の活動にも規制を強化
ストライキ以外の活動についても、各種の規制の導入が予定されている。例えば2018年3月には、組合員から徴収される組合費のうち、政党への献金や、組合・非営利団体等の政治的な活動などの財源となる「政治基金(political fund)」に関して、組合員の合意(opt-in)が義務付けられる。現在、486万人の組合員から年間でおよそ2450万ポンドの基金が徴収され、多様な活動のほか、一部は労働党への献金にも充てられており、その財源に影響を及ぼすとみられる(注6)。加えて、公共部門における組合費のチェック・オフについても、実施にかかる費用を労組による負担とするほか、組合員がチェック・オフ以外の方法によって支払いを行うことができるよう対応することが求められることになる(注7)。
また、公共部門における労働組合の職場代表の活動時間を制限する制度改正も、今後の実施が想定されている。国務大臣は、公共部門の雇用主に対して、職場における組合代表の数や就業時間に占める組合活動時間(facility time)の割合などの情報の公表を求めるとともに、この割合を制限する権限を雇用主に付与する二次法の制定を行うことができることになる(注8)。
注
- 保守党政権下で行われた法改正により、1984年に組合員投票の制度が導入され、その後1993年には、職場においてではなく郵送によることとなった。手続きの複雑化により、ストライキの抑制をはかる措置とみられる。なお、労働組合には法律上、いわゆる争議権は付与されておらず、合法的な手続きを経て実施される争議について、労働契約違反による雇用主側の損失に関する賠償の免責、という形を取る。(本文へ)
- 例えば組合員の半数が投票に参加した場合、賛成票は8割を超える必要がある。なお、労組側は投票率の要件化を承諾する替わりに電子投票を認めるよう求めている。政府はセキュリティを理由にこれを拒否していたが、専門家によるレビューを実施することを認め、昨年11月にこれを開始した。(本文へ)
- 欠員補充の準備により長い期間を提供することが目的とみられる。なお、政府は2015年の労働組合法案の議会への提出に際して、ストライキ中の人員不足を派遣労働者により充足することを認める制度改正を行うとの方針を示し(現在は法律により禁止されている)、コンサルテーション(一般向けの意見聴取)も実施していたが、政府は方針を明確にしておらず、これまでのところ制度改正の動きはみられないものの、労働組合はこれを警戒している。(本文へ)
- ナショナルセンターのイギリス労働組合会議(TUC)が作成した、2016年労働組合法による制度改正に関するガイドによる。(本文へ)
- さらに、違反が認められた場合には、最高で2万ポンドの罰金を科す権限の付与も予定されている。(本文へ)
- 実質的に労働党の資金源である政治基金にのみ手を加え、与党保守党の資金源である企業等からの献金に関する規制(献金額の上限設定等)を議論しないことは、公正さを欠いている、と労働党側は批判していた。(本文へ)
- 政府は当初、チェックオフの廃止を盛り込む意向を示していた。組合員は自ら支払い手続きを行うことが求められるため、チェック・オフによる自動的な徴収に比して、組合費を支払う組合員や徴収される組合費の減少は不可避と推測されている。(本文へ)
- TUCのガイドによれば、この施策の実施時期は2020年4月以降とみられる。(本文へ)
参考資料
- Gov.uk
 、UK Parliament
、UK Parliament 、Trades Union Congress
、Trades Union Congress 、BBC
、BBC 、The Guardian
、The Guardian ほか各ウェブサイト
ほか各ウェブサイト
参考レート
- 1英ポンド(GBP)=145.75円(2017年7月20日現在 みずほ銀行ウェブサイト
 )
)
2017年7月 イギリスの記事一覧
- 組合活動の規制を強化
- シェアリングエコノミー従事者の特徴と権利
- 不安定な働き方に関する議論
関連情報
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2017年 > 7月
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > イギリスの記事一覧
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 労使関係
- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス
- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス
- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス


