労働時間制度改革に関する提言
―フランス戦略庁が労働力率引上げや失業対策など示唆
フランスは失業率が恒常的に高い水準にあり、雇用情勢が比較的良いヨーロッパの6カ国(ドイツ・オーストリア、デンマーク、オランダ、イギリス、スウェーデン)と比べてほぼ2倍に相当する10%に達している。15歳以上65歳未満の労働力率は71%(2015年)で、6カ国より7ポイント低い(図表参照)。このため労働市場の課題に対応する政策を検討する必要性が急務であるとして、労働市場改革のためには労働時間制度の改革を検討すべきとする報告書『Quelle politique du temps de travail(どのような労働時間政策が必要か)』が、2017年1月フランス戦略庁(France Stratégie)によって公表された(注1)。
図表:主要欧州諸国の労働力率の比較(単位:%)
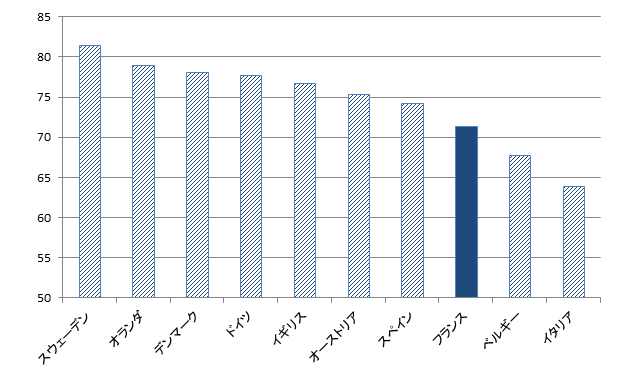
- 出所:Commission Européenne (2015)より作成。
労働時間短縮から一転、延長へ
フランスの労働時間政策の変遷を振り返れば、時には矛盾した様々な方針が打ち出されており、財政的な負担につながるものもあった。1990年代初頭には、社会保険料の軽減によるパートタイム労働の促進が行われた。2000年代初めにはフルタイムの法定労働時間を週39時間から週35時間へ短縮し、低賃金労働者の時間当たりの労務費を抑えるために社会保険料雇用主負担が軽減された。こうした税・社会保険負担の減免を通じてパートタイム労働の促進とフルタイムの労働時間短縮がはかられてきたが、それから一転してフルタイムの長時間労働を後押しするかたちで、2007年から2012年までの間、労働時間の延長と給与の引き上げを目的として超過勤務手当に関する税・社会保険料を免除した。このように、パートタイムとフルタイムに関連して労働力率を高める施策としては矛盾するかっこうになった。
ワークシェアリングの促進、若年者と高齢者の就業支援
労働力率を高めるためには、失業者のパートタイム就労や副業の促進、とりわけ若年者を対象とする職業訓練を受けながらの就業、高齢者を対象とした年金受給しながらの就労を促進する取り組みが必要である。
パートタイム就業で十分な収入が得られないために、とりわけ熟練労働者の就労意欲が減退しているという問題があるが、これに対しては、低所得者に対する就労報奨金(手当)などの制度を整備することによって、パートタイム労働に起因する最低限度の生活以下の勤労収入を補填し、就業に対するインセンティブを引き上げる対策が考えられる。
フランスでは管理職のパートタイムの比率が10%に満たないが、スイスやイギリスの官公庁やアメリカで広く行われている「ワークシェアリング」を導入し、1人のフルタイムの管理職の仕事をパートタイム2人で担うことで、それぞれの私生活を充実させることができるようになる。
フランスでは25歳以上50歳未満の年齢層に労働力が集中しており、25歳未満と50歳以上の両極の年齢層の労働力率が低い。そのため若年者層に対して、職業訓練を受けながらの就労を促進する施策を、高年齢者層に対してパートタイム就労を促進することにより、若・中年層への技能の伝承や経済の活性化、生きがいづくりなどにつなげるといった施策が考えられる。また、現在公的年金制度の改革が行われているが、年金を受給しながらの就労を一層促進させることにもつながる。
生産性向上と企業負担軽減
長期的な失業率の低下のために、労働時間の延長または短縮し、企業の生産性(収益性)を改善する施策を必要性が指摘されている。
労働力の増加が見込まれている局面では、法定労働時間を短縮させてワークシェアリングを推進することが、雇用の創出につながり短期的に失業率が低下する。フランス企業の国際競争力を確保する観点からは、労務費の増加を抑え製品価格を維持しなければならない。このことは、企業が従業員採用意欲を高め、失業率の改善につながる。
一方で景気後退期には失業対策として、時短とは反対に労働時間を長時間化させることも有効であるとしている。そのためには、時間当たりの労務費が低下させるための公的支援が必要不可欠となる。サルコジ政権時に行われた法定労働時間を維持しつつ、超過勤務手当に対する税・社会保険料の免除はこの考え方に基づいている。労働時間の延長は、失業者の増加の恐れがある一方で、企業が負担する労務費の低下によって競争力が高まり、中期的に生産や利益、投資、ひいては雇用の増加につながると考えられる。
個々人の就業観に即した労働時間の調整
報告書は雇用の質の向上についても指摘している。そのためには、労働者個々人の年齢や人生設計に沿った希望や企業の需要や景気動向に対応した経営が求められる。具体的には、労働時間を柔軟かつ現場の状況に即して調整することが可能な仕組みを構築しなければならない。雇用労働者のライフワークバランスや柔軟な経営判断を可能にすることが、その目的である。2016年8月に成立したエル・コムリ法(注2) がその役割を担っている。企業レベルの労使交渉を重視し、企業内の労使合意に基づいて労働時間などの労働条件を決定できるようにすることで、雇用の質を改善することをめざしている。
在宅勤務やフレックスタイム制に基づく働き方をしているのは3割弱であり、5割から6割のドイツや北欧諸国と比べて低い割合にとどまる。
在宅勤務や労働時間の柔軟な運用により、需要が減少する時期の部分的失業(一時帰休)を回避できる可能性がある。例えば、デンマークでは、職業訓練を受講するために休暇に入った労働者のポストを失業者が一時的に務める施策を実施している。在宅勤務やフレックスタイム制を普及させることにより、追加費用を伴わずに、労働者や企業の要求に応えることのできる政策立案の余地がフランスには残っている。
注
- フランス戦略庁ウェブサイト参照(35 heures : la mise en garde de France Stratégie, Social, Les Echos France Stratégie
 )(本文へ)
)(本文へ) - LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
 (2016年8月9日付官報に公示)(本文へ)
(2016年8月9日付官報に公示)(本文へ)
参考文献
- Commission Européenne (2015) Rapport De La Commission, Au Parlement Européen, Au Conseil, À La Banque Centrale, Européenne et Au Comité Économique et Social Européen, Rapport sur le mécanisme d'alerte 2016, p. 51.(PDF:1.2MB)

(ウェブサイト最終閲覧日:2017年7月4日)
2017年7月 フランスの記事一覧
- 日曜・夜間就労に関する労使合意、小売業での成立の動向
- 労働時間制度改革に関する提言 ―フランス戦略庁が労働力率引上げや失業対策など示唆
関連情報
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2017年 > 7月
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > フランス記事一覧
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 雇用・失業問題、労働条件・就業環境
- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > フランス
- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > フランス
- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > フランス


