EU離脱の影響をめぐる議論
EU加盟継続の是非をめぐる6月下旬の国民投票で、離脱を支持する票が過半数を占める結果となった。投票に先立っ ては、離脱に伴う経済・財政への損失などを予測する政府や野党、労使団体などの残留派と、離脱による経済的利益や、移民の流入防止などの効果を主張する離 脱派の間で、議論が対立していた。
離脱の影響をめぐり対立
国民投票は、与党保守党が2015年の総選挙における公約として掲げたもので、党内の離脱派への配慮とともに、移民の増加に対する国内の懸念の高まりを受けたものだ。投票に先立って、保守党議員のおよそ半数が離脱支持を表明し、離脱派の政治的な主力を担った(注1)。EUからの過剰な規制や、多額の拠出金の負担は、イギリスの経済や財政の足かせとなっており、離脱によりこれらを排除することで、経済成長や各種の公的サービスの拡充が見込める、というのが離脱派の主張するところだ。また、近年のEUからの移民の急速な拡大も、EU法により国境管理が不可能な状態にあることが要因であるとして、国政や司法へのEUからの影響力を排し、国としての主権を取り戻す必要性を掲げていた。
一方、EUへの残留を主張する政府は、離脱による経済・財政への損失は加盟継続のコストを上回るとしていた。財務省は短期的な影響について、国民投票を受けて離脱手続きが開始された場合、その期限となる2年後までに、GDPは加盟継続の場合に比べて3.6~6%縮小、失業者は52~82万人増加し、実質賃金も2.8~4.0%低下するとの予測結果を示している。また長期的には、単一市場圏からの離脱により、GDPは15年後で6.2%縮小、年360億ポンドの税収減となると予測している。この予測は、離脱後の貿易条件についてEUとの間で二者間協定が締結された場合(例として、スイスやカナダ)を想定したものだが、これ以外のケースとして、現在のノルウェーなどと同様、欧州経済圏(European Economic Area)に加盟する場合には、経済への影響はより小さく(GDPは3.8%縮小)、逆にEUとの間で協定が成立しなかった場合、より大きな影響が想定されている(同7.5%縮小)。
世論は賛否が拮抗
国内外の多くの組織も、残留支持を表明していた。これには、労働党など主な野党のほか、イングランド銀行、主要な労使団体やシンクタンク、OECDやIMFなどの国際機関も含まれる。いずれも、イギリスのEU離脱に伴う経済への負の影響の可能性を重く捉えている。シンクタンク等は、大半が政府と同様、短期あるいは中長期に及ぶ経済の低迷を示している(注2)。
また労働党や労働組合は、EU指令により整備の進んだ労働者の権利に関わる法制度が、離脱に伴って廃棄される可能を危惧している。ナショナルセンターのイギリス労働組合会議(TUC)がまとめたレポート(注3)は、とりわけリスクの高い分野として、労使協議や労働時間規制、安全衛生、事業譲渡に関わる労働者保護、派遣労働者など非正規労働者の保護、差別禁止法制の一部などを挙げている。
一方、経営側はより複雑な立場を示していた。調査などからは、多くの企業がEUの単一市場からの離脱による影響への懸念から、残留を望んでいるとみられる(注4)ものの、小規模企業の間では離脱支持層が相対的に多い傾向にあるともいわれる。例えば、小企業連盟(Federation of Small Businesses)の昨年の調査では、会員企業の41%が離脱に投票すると回答している(残留支持は47%)。FSBの分析によれば、輸出入関連の業種や、EUからの労働者を雇用している事業主は、EUに好意的な回答をする傾向が相対的に高いという。
また、各種の意識調査の結果によれば、世論は残留支持と離脱支持がほぼ拮抗している状態にあった(注5)。シンクタンクのNatCenは、離脱支持層に関する傾向を分析、高齢者や教育資格水準の低い層が相対的に多い点を指摘している(注6)。EUがイギリスの文化的アイデンティティを脅かしていると回答する傾向は、離脱支持層のみならず残留支持層にも強く、現状のEUとの関係で改善を求める内容として、回答者の7割近くが「EU移民の社会保障給付の受給権の削減」に、また5割が「自由な居住・就労の権利の廃止」に、それぞれ賛成している(注7)。近年のEUからの移民増に対する懸念が、広範な層に共有されていることがうかがえる。
焦点は移民問題
統計局によれば、2015年における外国人等の純流入数(流入者数から流出者数を差し引いたもの)は33万3000人で、流入抑制を掲げる政府の意向に反して、ここ数年拡大が続いている。その半数近くをEU域内の出身者が占め、特に財政危機以降、就労を目的とするEUからの人の流入が急速に増加する状況にある。こうした移民は、イギリス人に比べて就業率が高く、相対的に若い層が多く、さらに教育水準も高い傾向にあるとみられるが、移民抑制を掲げる政府は、いわゆる「社会保障ツーリズム」(自国より手厚い社会保障給付等を目当てとした移民の流入)による社会保障支出の増大や、医療や教育など公共サービスの圧迫、住宅への需給のひっ迫などの弊害が生じているとの理由を掲げ、流入抑制策としてEU市民に対する給付受給権の制限を強化してきたところだ。今回の国民投票に先立っても、加盟継続の条件としてEUに要求した各種の改革案の中で、受給権の制限に関するさらなる裁量権を加盟各国に認めるよう求め、一定の配慮に基づく合意をEUから得ていた(注8)。政府は、この合意を成果として主張、残留が選択された場合でも、EUからの移民流入のコントロールは可能であると述べていたが、その実効性は疑問視されていた。
これに対して、離脱派はEU離脱による国境管理の回復を通じた移民流入の抑制を主張、ポイント制(所得や保有資格、年齢などの基準によるポイントを設定、受け入れの可否を判定)の適用を示唆していたが、具体的なプランは示していなかった。
図表:出身地域別純流入数の推移(千人)
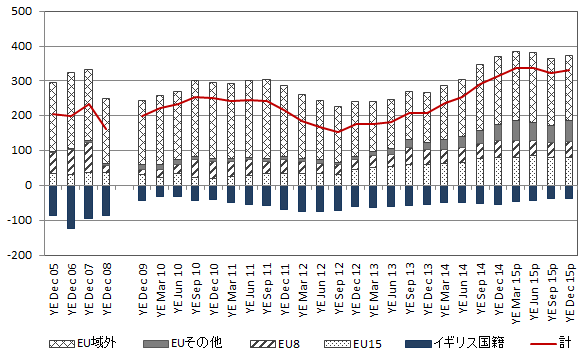
- 注:1年以上の滞在(予定)者に関する推計。各期のデータは直近12カ月のもの。2015年のデータは速報値。
- 出所:Office for National Statistics 'Migration Statistics Quarterly Report - May 2016'
離脱への道筋は不透明
6月23日に実施された国民投票は、残留支持票48.1%に対して、離脱支持票は51.9%と離脱支持が上回る結果となった。ロンドンや一部の都市圏、またスコットランド、北アイルランドでは残留支持票が多かったものの、イングランドやウェールズの広範な地域で離脱支持票が過半数を占めた。経済的な困難を抱える地域や、移民人口が近年急速に増加した地域などで、離脱支持票の比率は7割前後にものぼっている。事前に予測されていたとおり、年齢や教育水準が投票行動を大きく左右したとみられる。調査会社Yougovが国民投票後に行った調査では、18~24歳層における離脱支持者の比率は29%(残留支持71%)であったのに対して、65歳以上層では64%、50~64歳層でも60%と中高年齢層の離脱支持が顕著だ(24~49歳層では46%)。教育水準別には、大卒相当(学位取得者)層で残留支持者の比率が7割を占める一方、中卒相当以下では7割が離脱支持と回答している(注9)。
離脱多数の結果を受けて、英ポンド(対ドルレート)は30年来の水準に下落、株価も銀行株などを中心に急落した。政府として残留を主張してきたキャメロン首相は辞意を表明、離脱をめぐるEUとの交渉は10月以降、新たな首相があたるべきであると述べた。また、首相とともに残留キャンペーンを推進したオ ズボーン蔵相は、離脱の影響により歳出削減と増税は不可避、との見通しを改めて示した。加えて、全域で残留支持票が過半数を占めたスコットランド政府 は、スコットランド単独でのEU加盟を主張しており、このため2014年に続き2度目のイギリスからの分離独立を問う国民投票の実施に意欲を示している。同時に、国民投票の結果には法 的拘束力はないことから、イギリス議会において離脱に関する法案を否決することで、離脱手続きを阻止する構えだ。
一方、離脱派は、EU離脱に伴う各種の利益や離脱後の方針に関するこれまでの説明を翻し始めている。例えば、離脱により節約されるEUへの拠出金の額や離脱後の用途(注10)について、複数の離脱派の議員が国民投票直後から、金額が不正確であったことや、必ずしも離脱派が主張したようには公的医療サービスに充当できないことなどを認めている。また、移民 流入の抑制をめぐっても、コントロールはすべきだが大幅に削減するとは言っていない、といった発言が一部の議員から出ている。EUとの貿易条件の交渉において、引き続き単一市場への参加の維持を希望する場合、人の移動の自由を保障することが要求されるとみられるためだ(注11)。交渉をめぐる今後の方針は、保守党の党首選を経て新たに首相となるメイ内務相が決定するとみられるが、国民投票で残留を支持した同氏は、単一市場との関係を重視する立場を取りつつ、同時に移民流入にはコントロールが必要であるとも述べている。
欧州委員会や加盟各国の首脳は、政治的・経済的混乱の早期収拾をはかるため、早急な離脱手続きの開始をイギリス政府に求めている。6月末に開催され た欧州理事会では、公式な手続きの開始まで、非公式な交渉には応じないとの方針とともに、単一市場への参加には人の移動の自由を引き続き尊重することが条件となるとの強 い姿勢が示された。
現地メディアは、国内に広がりつつある混乱や不安、また社会的な分断を報じている。離脱支持層と残留支持層、典型的には高齢者層と若年層の間の世代間対立や、既にイギリス国内にいるEU市民をはじめとする外国人に対する、差別的な風潮の高まり(注12)が懸念されている。
注
- このほか、反EU・反移民を掲げて支持を拡大してきた英国独立党、また少数ではあるが、労働党にも離脱を支持する議員がいる。(本文へ)
- 例えば、National Institute of Economic and Social Researchは、加盟継続の場合とのGDPのギャップは、2020年まででマイナス2.1%となると予測、2030年時点でも同等の影響が残るとみている。またInstitute for Fiscal Studiesは、離脱から2年間で、財政収支は200~400億ポンド悪化し、さらなる歳出削減策が必要となるとの予測を示している。(本文へ)
- "Workers' Rights from Europe: the Impact of Brexit"。TUCの委託を受けて、労働分野を専門とする法廷弁護士が執筆。(本文へ)
- 経営者団体CBIは3月、会員企業の8割が残留を支持しているとの調査結果を報告している。CBIが同月に公表したレポートは、離脱により2020年までに1000億ポンドの経済への打撃と、100万人近くの雇用減を予測している。(本文へ)
- 例えば、6月初旬のYougov調査では残留支持、離脱支持とも41%で、2割近くが不明と回答している。投票日が近づくにつれ、離脱を選択するとの回答比率が若干上昇する傾向にはあったものの、双方に決定的な差は生じていなかった。(本文へ)
- British Social Attitudes Surveyの2014年調査に基づく分析。なお同調査では、離脱支持層はおよそ3割で、残留支持層の6割を大きく下回っている。(本文へ)
- 個別の内容に対する賛否を尋ねたもの。このほか、「EUからの企業に対する規制の緩和」、「無料での公的医療サービスの利用」にそれぞれ6割が、また労働時間に関する規制の廃止にも5割強が賛同している。(本文へ)
- EUとの間で2月に合意された内容は、急激な労働者の流入により社会保障制度等に悪影響が生じていると判断される場合に、加盟国が緊急措置として、新規入国者に最長4年間の給付受給権の停止を認める(ただし、制度の実施は7年を限度とし、またこの間の受給制限も、労働市場への定着の度合いを見つつ段階的に緩和することを加盟国に求めている)ほか、児童関連の給付について、出身国の物価水準に合わせた支給額の削減を可能とすること、など。(本文へ)
- 支持政党別には保守党支持層による離脱支持が61%、また労働党支持層でも35%が離脱支持に票を投じたと回答している(このほか、自由民主党支持層で32%、英国独立党支持層で95%など)。(本文へ)
- 離脱派は、EU離脱により節約される拠出金は年間188億ポンド(2014年)、週換算で3億5000ポンドにのぼり、これを財政難の公的医療サービスなどに充当できると主張していたが、EUからの負担軽減策(還付)や補助金によるイギリスへの還流分が考慮されていないとの指摘を受けていた(民間シンクタンクInstitute for Fiscal Studiesの試算では、実質的な拠出額は年間80億ポンド、週あたり1億5000ポンド。また統計局も同様の試算を示している。)。(本文へ)
- 欧州経済圏に留まることを望む場合、現在のノルウェーと同様、人の移動の自由が条件となる可能性が高い。また、EUと二者間協定を締結しているスイスも、貿易協定などと併せて人の移動の自由に関する協定を締結している。ただし現地報道によれば、2014年に実施された国民投票の結果を受けて、現在スイスでは国境管理が復活されており、協定違反の状況の解決をめぐってEU側との交渉が続いているという。(本文へ)
- 国民投票直後から、反移民的な事件に関する警察への届け出が増加しているという。その対象は、EUからの移民に留まらず、イスラム系住民にも及んでいるとみられる。(本文へ)
資料出所
- Gov.uk
 、BBC
、BBC 、The Guardian
、The Guardian ほか各ウェブサイト
ほか各ウェブサイト
参考レート
- 1英ポンド(GBP)=133.53円(2016年7月12日現在 みずほ銀行ウェブサイト
 )
)
2016年7月 イギリスの記事一覧
- EU離脱の影響をめぐる議論
- 待機労働契約による労働者80万人 ―統計局
関連情報
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2016年 > 7月
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > イギリスの記事一覧
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 外国人労働者
- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス
- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス
- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス


