外国人専門技術者の受け入れ縮小へ
政府の諮問機関であるMigration Advisory Committee (MAC)は1月、欧州域外からの外国人専門技術者の受け入れを縮小する方策について答申をまとめた。給与水準などの要件の厳格化や、主要な受け入れルートとなっている「企業内異動」(多国籍企業による国境を越えた異動)カテゴリに関する引き締め策を提言。また、国内での不足人材の育成に充てることを目的とした新たな負担金制度を導入するとの政府方針に賛意を示している。
賃金水準要件の引き上げ、新たな負担金の導入など
MACの答申は、昨年6月の政府からの諮問を受けたものだ。政府は、外国人の増加を抑制するため、純流入者数(過去12カ月間の流入者数から流出者数を差し引いたもの)を10万人未満に抑制するとの方針を掲げており、既にこれまで、受け入れ要件の厳格化や数量制限、また社会保障制度の適用の制限などの方策により削減を図ってきた。しかし、金融危機前後に一旦縮小した純流入者数は、国内景気の復調や欧州各国の財政危機などを背景に再び増加に転じ、このところはむしろ記録的な拡大が続いている(注1)。特に、近年流入者数が拡大している欧州経済圏(EEA)からの外国人については、EU法により域内他国での居住や就労に関する権利が認められていることから、抑制が難しいという問題がある。
こうしたことから、政府はMACに対して、欧州域外からの専門技術者の受入れを行うポイント制の第2階層において、より選択的な受け入れの実施や、各種の負担金制度の適用、また現在主な受け入れルートとなっている企業内異動カテゴリの引き締め策など(注2)、想定される各種の手法について諮問を行っていた。
MACは、外国人労働者の削減と、生産性や競争力の維持の両立を前提に各手法を検討、受入れを優先すべき不足人材の絞込みを職種(職名)によって行うことには限界があるとして、給与水準要件の引き上げを通じた対応を提言している。現行制度での受け入れに要求される高等教育修了相当レベル(注3)の職務に対応した給与水準の下限について、MACは年3万ポンドとの試算を示している(現在の下限は「一般」カテゴリにおける2万800ポンド)(注4)。
また、専門技術者の受け入れの企業内異動による入国許可の発行数は、過去5年間で年1万5000人から3万7000人に増加しており、第2階層の年間の数量制限である2万700人を大きく上回っている。受け入れの9割以上がインドからのIT専門技術者で、多くは顧客企業に派遣されて働いているという。MACは、IT労働者の受け入れにより、企業にはコスト削減という利益があるものの、国内の人材の活用が阻害されている可能性を指摘(注5)しており、受け入れ要件の厳格化を提言している。具体的には、受け入れに係る医療負担金(および後述の技能負担金)を課すこと(注6)、雇用主の元での勤続期間の要件を従来の1年から2年に延長するとともに、申請に際して受け入れ先での詳細な職務内容の記載を求めること、現行の社会保障制度において外国人受け入れが国内労働者の雇用に比べてコスト面で優位になっていないかを検討することなどを提言している。さらに、顧客企業への派遣を前提とした受け入れについては、別途カテゴリを設けて、より高い給与水準要件(年4万1500ポンド)(注7)を課すほか、「一般」カテゴリと同様、労働市場テストの適用を検討すべきであるとしている。一方で、現行制度の部分的な緩和や柔軟な運用を検討することも、併せて提言している(注8)。
加えて、外国人労働者の受け入れ申請の際に、雇用主に「技能負担金」(Immigration Skills Charge)を課すとの政府の方針には、賛意を示している。外国人労働者の雇用主は、国内の労働者の育成に消極的な傾向にあるため、負担金制度による収入を能力開発政策に充てることで、国内人材への過少投資の是正を図ることができる、というのが主な理由だ(注9)。負担金の額については、申請時の年数に応じて年1000ポンドの徴収を提案、これにより年間2億ポンド以上の財政収入の増加が見込めるとしている。
図表:専門技術者向け入国許可の発行数
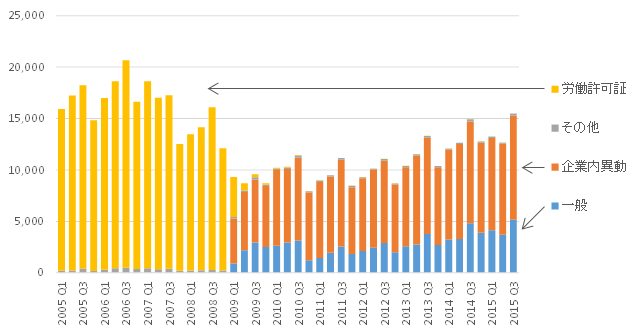
- 出所:Home Office “Immigration statistics, July to September 2015”
域内労働者に対する給付停止も
一方、近年の流入増加の大半を占めるEEA域内からの外国人についても、抑制策が検討されている。域内における自由な移動や居住の権利に基づく流入者の中には、自国より手厚い社会保障給付を目当てとした者が含まれる(いわゆる社会保障ツーリズム)との見方から(注10)、政府はかねてよりEEA国民の給付受給に関する権利を制限する方針を示してきた。とりわけ、EU加盟継続の是非をめぐって予定されている国民投票を前に、政府は一連の改革案をEUに要求しており、その一環として、就労者向け給付の受給などに4年間の居住を要件化することなどを盛り込んだ(注11)。しかし、社会保障制度における自国民と他の加盟国民の間の差別的な扱いは、EU法に反するとの可能性が指摘されており、このため交渉の動向が注目されていた。
2月下旬の欧州理事会において各国首脳が合意したEUにおける対応方針は、イギリス政府のこうした要求に一定の配慮を示すものとなった。労働者の移動の自由に関連して、より手厚い社会保障制度を有する国に労働者が集中する可能性があるとの認識に基づき、急激な労働者の流入に対する保護メカニズムの導入などに向けて法改正を行うとの方針を示している。メカニズムを利用する加盟国は、大量の労働者の流入により社会保障制度や労働市場、あるいは公共サービスの機能に悪影響が生じている旨を欧州委員会および欧州理事会に通知し、理事会の承認を得た場合、新規入国者に対して最長4年間、就労者向け給付の支給を制限することが可能となる。ただし、制度の実施は7年を限度とし、またこの間の受給制限も、労働市場への定着の度合いを見つつ段階的に緩和することを加盟国に求める内容となっている(注12)。
注
- 2015年6月までの12間で33万6000人、過去5年間で1.4倍の増加。(本文へ)
- このほか、労働力不足職種リストに記載する職種を一定期間後に自動的に削除する制度案や、また主申請者の被扶養者(家族等)に対して就労権が自動的に付与されていることに関する是非を諮問していた。MACはいずれについても、現状維持を提言している。(本文へ)
- 専門技術者として受け入れ可能な職務レベルの下限は、2010年以降、従来の義務教育修了相当(全国資格枠組み(NQF)レベル3相当)から高等教育修了相当(同レベル6相当)の職務へと段階的に引き上げられた。(本文へ)
- 対応する職種(NQFレベル6以上)の賃金統計に基づく第25百分位の賃金水準。なお、新入社員や研修生に関してはこれとは別途、年2万3000ポンドを下限とすることが併せて提案されている。(本文へ)
- BISによる報告書は、コンピュータ・サイエンス分野における高等教育修了者の失業率が、他分野に比して高い傾向にあるとしている。(本文へ)
- 2015年に導入された医療負担金制度(Immigration Health Surcharge)は、一定の滞在期間を超える入国申請全般について、主申請者やその家族に一人当たり年200ポンド(学生の場合は年150ポンド)を課すもの。ただし、現在は「企業内異動」カテゴリなど一部のルートについてこれが免除されている。(本文へ)
- 現行の企業内異動カテゴリのうち長期滞在に関する要件と同等。(本文へ)
- 高等教育修了者の研修生の受け入れ(最長12カ月)に関する1社あたりの数量制限(5名)の見直し、企業内異動に課されている5年の年限について、企業業績にとりわけ貢献度が高い労働者に関して延長を認める、など。(本文へ)
- このほか、受け入れに関わる費用増による流入抑制の効果や、外国人の増加による交通、医療、教育といった公共サービスへの圧迫の緩和にも利用可能であるとしている。(本文へ)
- 給付制度を所管する雇用年金省は、2013年3月までの4年間にEEA移民として国民保険に登録した者のうち、37~45%(19万5000人~23万5000人)が給付受給世帯に属し、また66%は本人か配偶者が就労者であったとしている。(本文へ)
- このほか、経済運営や立法に関する各国の自律性の尊重や、競争力強化に向けた規制緩和などが併せて要求されている。(本文へ)
- 加えて、労働者が他の加盟国に居住する児童について児童手当を申請する場合についても、当該国の物価水準により手当の支給額を調整する制度を新規申請者から適用する旨、法改正案が示される見込み。(本文へ)
参考資料
- Gov.uk
 、BBC
、BBC 、The Guardian
、The Guardian ほか各ウェブサイト
ほか各ウェブサイト
参考レート
- 1英ポンド(GBP)=156.23円(2016年2月25日現在 みずほ銀行ウェブサイト
 )
)
2016年2月 イギリスの記事一覧
- アプレンティスシップ拡充に向け負担金制度など導入
- 外国人専門技術者の受け入れ縮小へ
関連情報
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2016年 > 2月
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > イギリスの記事一覧
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 外国人労働者
- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > イギリス
- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > イギリス
- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > イギリス


