地域格差と地域雇用:イギリス
雇用政策と地域雇用政策
- カテゴリー:地域雇用
- フォーカス:2007年1月
本稿では、サッチャー政権以降におけるイギリス国内の雇用・失業をめぐる地域政策について、失業者対策をX軸、地域雇用政策をY軸に定め、概観する。
失業者対策の推移 (注1)
戦後イギリスの失業率は年1~3%の完全雇用状態が続いていたが、1973年のオイルショック以降失業情勢が悪化、82年には10%を突破するに至った(図表1)。こうした中で79年にスタートしたサッチャー政権は従来の労働市場政策を大きく転換、失業給付の引き締めと求職活動支援による、積極的な失業削減政策を開始した。この結果、失業給付受給者の削減にはある程度の成功を収めたものの、若年者や長期失業者の失業率の高止まりの傾向に変わりはなく、また求職活動や政府のプログラムへの参加を諦め他の福祉手当を受給する層が増加する結果となった。
97年に誕生したブレア労働党政権は、「福祉から就労へ」という政策目標のもと、就労支援策として、個別の就労支援を特徴とするニューディール政策(注2)を導入、求職者手当(注3)受給者に職業訓練への参加を義務づけるなどの就労促進施策を積極的に進めた。同政策については、開始直前の97年に6.5%であった失業率が01年には5.1%に低下するなど、一定の成果があったものの、会計検査院が「求職者手当受給者の大半は良好な経済状況によって早かれ遅かれ就職できたのであって、ニューディール政策が直接これに寄与したわけではない」と厳しい見方を示すなど、その評価は未だ限定的である。
地域別に見た雇用・失業情勢
一方、地域における雇用・失業状況に目を向けると、70年代以降後徐々にリバプールやマンチェスターといったイングランド北部都市の高失業率地域とロンドンをはじめとする南部都市の安定した失業率地域との格差が拡大した。サッチャー政権は、都市整備事業の実施機関として新たに都市開発公社(UDC:Urban Development. Corporation)を設立、「エンタープライズ・ゾーン(注4)」などの地域復興施策を取ったが89年のイングランド北部地域の失業率が南部地域の2倍以上に達する(図表2)など地域間の経済格差はさらに拡大した。その後90年代に入ると景気後退の影響から南部地域でも失業情勢が悪化し、イギリス全体が高失業となったため、サッチャー政権における市場原理を重視した大規模な都市開発の手法では限界があるとの理由から新たな地域政策を求めての議論が再燃した。
90年に発足したメージャー政権は、地域政策の目標を格差そのものの是正ではなく全地域における経済再生に置き、「シティー・チャレンジ補助金」(注5)や「単一振興予算」(注6)といった地域分権型手法に基づく施策を次々と打ち出した。
ブレア政権はメージャー政権での地域政策の方向性を基本的に踏襲しながらも、中央政府と地方政府とをつなぐ中間支援機関「パートナーシップ(注7)」の手法を導入するなど、地域を主体とした自律的な地域再生策を発展させている。99年の地域開発庁の設立(注8)はその集大成といわれる。同庁の設立により省庁ごとに分かれていた地域開発に関する予算やプロジェクトが統合され、効率的な地域再生策の実施が可能になったためで、06年現在地域別失業率はすべての地域で低下している(図表3)。
地域雇用対策
最近では失業率を下げるためだけでなく、むしろ積極的に競争力のある産業を育成するという観点に立っての地域雇用対策が進められている。イングランド南東部に位置するサザンプトン市は大規模製造業から第三次産業やエレクトロニクスなど高度な技術を必要とする産業への移行が進んだことに伴い、労働者に必要とされる技能の変化が生じたが、新たに必要となった技能についての情報不足が指摘されていた。この問題解決のために、教育訓練機関、ジョブセンタープラス、経営者団体、大学機関などが協同し「サザンプトン総合雇用戦略」を立ち上げ、地域の労働市場に関する包括的な情報データベースを構築、女性と若年者を対象に新しい産業への移行を支援する取り組みが行なわれている。(注9)
地域失業に焦点をあてた対策として知られるのが「エンプロイメント・ゾーン」や「コミュニティ・ニューディール」といった特定地域対象の雇用対策だ。「エンプロイメント・ゾーン」は雇用状況が特に悪化している地域を選定し(注10)、長期失業者向けに教育訓練や職業紹介関連の援助等の様々な便益を提供するプログラムである。2000年の開始以降、05年5月までに13万人以上が参加し、約5万人が就職した。
一方「コミュニティ・ニューディール」は、荒廃地域における住宅、健康、失業などの地域間格差を資金投資によって解消しようとするプログラムである。1998年に第1ラウンド(17地域)、1999年には第2ラウンド(22地域)が認定され、現在39地域で再生プログラムが実施されている。両プログラムの特徴は、実施主体が政府ではなく競争入札によって決定された民間企業や市民団体であることだ。実施主体には予算の使途を含め大幅な裁量が認められており、効率的な運営が行なわれている。
図表1:1970年以降の失業率の推移
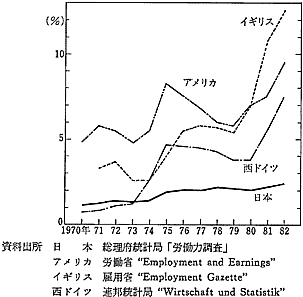
出所:厚生労働省『昭和57年 労働経済の分析』
| 地域(カッコ内は主要都市) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | ||
| イングランド | 北部 | 北東イングランド (ニューカッスル) |
9.9 | 8.7 | 10.2 | 11.1 | 11.9 |
| 北西イングランド (マンチェスター、リバプール) |
8.5 | 7.6 | 9.3 | 10.6 | 10.7 | ||
| ヨークシャー・ハンバーサイド (ヨーク、リーズ、シェフィールド) |
7.4 | 6.7 | 8.7 | 9.9 | 10.3 | ||
| 中部 | イングランド中部 (ノッティンガム) |
5.4 | 5.1 | 7.2 | 9.0 | 9.5 | |
| イングランド中部 (バーミンガム) |
6.6 | 5.7 | 8.4 | 10.3 | 10.9 | ||
| 東部 | 東イングランド (ケンブリッジ、イプスウィッチ) |
3.6 | 3.7 | 5.8 | 7.6 | 8.1 | |
| 南部 | 南東イングランド (ロンドン) |
3.9 | 3.9 | 6.9 | 9.2 | 10.2 | |
| 南西イングランド (プリマス、ブリストル) |
4.5 | 4.3 | 6.9 | 9.2 | 10.2 | ||
| ウェールズ(カーディフ) | 7.3 | 6.7 | 9.0 | 9.9 | 10.3 | ||
| スコットランド(エジンバラ) | 9.3 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | ||
| 北アイルランド (ベルファスト) | 14.6 | 13.0 | 13.2 | 13.9 | 13.9 | ||
| 地域(カッコ内は主要都市) | 雇用率 | 失業率 | ||
| イングランド | 北部 | 北東イングランド (ニューカッスル) |
70.9 | 6.6 |
| 北西イングランド (マンチェスター、リバプール) |
73.2 | 5.6 | ||
| ヨークシャー・ハンバーサイド (ヨーク、リーズ、シェフィールド) |
73.7 | 6.0 | ||
| 中部 | イングランド中部 (ノッティンガム) |
77.3 | 5.4 | |
| イングランド中部 (バーミンガム) |
73.9 | 6.1 | ||
| 東部 | 東イングランド (ケンブリッジ、イプスウィッチ) |
76.9 | 4.9 | |
| 南部 | ロンドン | 70.0 | 7.6 | |
| 南東イングランド (除くロンドン) |
78.7 | 4.4 | ||
| 南西イングランド (プリマス、ブリストル) |
78.1 | 4.0 | ||
| ウェールズ(カーディフ) | 71.7 | 5.3 | ||
| スコットランド(エジンバラ) | 75.2 | 5.2 | ||
| 北アイルランド (ベルファスト) | 68.9 | 4.6 | ||
注
- イギリスにおける失業対策の詳細については、勇上和史「イギリスの雇用政策―失業者対策を中心に」ビジネスレーバートレンド2004年5月号(JILPT)を参照されたい。
- 現労働党政権による「福祉から就労へ(Welfare to Work)」施策の柱であり、職業訓練及び就職促進を目的とする一連の雇用対策を表す。一部の先行地域における導入期間を経て1998年4月から全国的に実施されている。若年失業者や長期失業者対策を中心に開始され、その後、対象を障害者、一人親、高齢者及び失業者の無収入の配偶者へと順次拡大して実施されている。
- 以前の失業給付は、求職者給付(Job Seeker’s Allowance)に改変された(1996年)。
- 特定の都市内の地区をエンタープライズ・ゾーン(事業地区)に指定し、規制緩和、税免除などの優遇措置によって、民間の活力を導入しようとする政策(1980年開始)
- 衰退した都市を復活させるためのアイデアを地方自治体から環境省に提出させ、優れた案を提出した地方自治体に補助金を交付するという制度(91年開始)
- 従来5省庁(環境省、内務省、教育省、貿易・産業省、産業雇用省)が管轄していた複数の補助金を一つに再編・統合した予算(94年開始)
- 一般的には「共通の目的を達成するために協働するパートナー間の合意」を意味する。イギリスの地域再生政策において、政府、地方自治体等の公的機関、住民協議会、ボランティア団体、民間企業などが平等な立場で地域再生事業を推進する運営手法を指す(出所:(財)自治体国際化協会「イギリスにおける地域再生政策の現状」)。
- Regional Development Agency(RDA)のこと。地域の経済発展と再開発、雇用促進等を目的とする中央政府から独立した機関。
- JILPT、労働政策研究報告書№65『地域雇用創出の現状に関する研究』(2006)
- 現在グラスゴー、ノッティンガム、バーミンガム、プリマス等13地域が対象地域となっている。
参考
- 辻悟一、『イギリスの地域政策』、世界思想社(2001)
- 1ユーロ (EUR) =154.93円(※みずほ銀行ウェブサイト
 2007年1月9日現在のレート参考)
2007年1月9日現在のレート参考)
2007年1月 フォーカス: 地域格差と地域雇用
- イギリス: 雇用政策と地域雇用政策
- ドイツ: 東部ドイツの再建と地域経済振興策
- フランス: フランスの地域格差:暴動と郊外問題をキーワードに
- EU: EUにおける地域経済格差とその是正のための政策


