1997年 学界展望
労働経済学研究の現在─1994~96年の業績を通じて(全文印刷用)
目次
- はじめに , 参考文献
- 1. 長期雇用、終身雇用
- 2. 労働需要
- 3. 海外生産活動と国内雇用
- 4. 賃金構造
- 5. 昇進・査定・技能・移動
- 6. 家族構成と就業行動
- 7. 女性の雇用管理
- 8. 福利厚生と税制・社会保障の影響
- 終わりに
出席者紹介
駿河 輝和(するが・てるかず)大阪府立大学教授
1951年生まれ。大阪大学大学院後期課程退学。大阪府立大学経済学部教授。経済学博士。主な論文に“Employment Adjustment in Japanese Firms,” in Internal Labour Market, Incentives and Employment Policy, Macmillan Press, forthcoming など。理論経済学・労働経済学専攻。
奥西 好夫(おくにし・よしお)法政大学助教授
1957年生まれ。東京大学経済学部卒業。法政大学経営学部助教授。主な論文に Internal Promotion, Wage Profiles and Mandatory Retirement in Japan (Ph. D. thesis, Corneell University, 1993)。労働経済学専攻。
金子 能宏(かねこ・よしひろ)国立社会保障・人口問題研究所室長
1958年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修了。経済学博士。国立社会保障・人口問題研究所第3室長。主な著書に『年金の経済分析』(共著、東洋経済新報社)など。財政学・公共経済学・労働経済学専攻。
はじめに
- 駿河
-
本誌では1982年以来3年ごとに労働経済学研究に関する展望討論会を行ってきた。今回は第6回目に当たり、1994年以降に発表された研究論文を取り上げている。
ここで取り上げる論文は、編集部があらかじめ用意したリストと討論会参加者が持ち寄った多数の文献を基礎としている。多数の文献の中から、比較的文献の多いテーマを取り上げ、それを基に論文を選んだ。対象は主として学術誌に掲載された研究論文である。単行書は論文集的なものに限って取り上げ、他は書評などに譲ることにした。
この3年間は、バブル経済崩壊後の低成長・景気停滞期を背景としており、雇用不安や日本型雇用慣行変化についての問題が話題になることが多かった。実際、国際的にはまだ低いものの、完全失業率は1996年に3.5%を超える戦後最高の率を記録した。そこでまず、大きなテーマとして雇用と労働需要を取り上げた。その中で、日本的雇用慣行に関する終身雇用・長期雇用、新卒需要や雇用調整を含む労働需要、円高による海外生産の増加と国内雇用の問題の三つをサブテーマとした。
賃金構造に関する研究はどの時期でも多く見られるが、今回もテーマの一つとした。昇進についての論文が多く見られたのが今回の一つの特徴で、昇進を中心に昇進・査定・技能・移動として一つのテーマを立てた。
1996年に雇用機会均等法10年を迎えたこと、不況期になり女子学生の就職が厳しい状態であること、日本の男女間賃金格差が非常に大きいという指摘を海外から受けていることなどを背景に女性労働に関する論文が多かったのも今回の特徴である。したがって、女性労働を中心に福利厚生を絡ませて大きなテーマとして選んだ。サブテーマとして、低出生率との関連で家族構成と就業行動、均等法や育児休業制度などに関係した雇用管理、主婦パートの就業調整を中心に福利厚生と税制・社会保障の影響の三つを取り上げた。ほかにも取り上げるべきテーマはいくつかあるが、時間や紙面の関係上、別の機会に譲った。
全体に各論文に対して厳しいコメントが多かったかもしれないが、取り上げた論文は各テーマのもとでわれわれが一定の評価をしたものばかりであり、ご容赦願いたい。もちろん、ここで取り上げたテーマについても、重要であるにもかかわらず見落とした論文があるかもしれない。それらについては読者からお教えいただけると幸いである。
参考文献
1. 長期雇用、終身雇用
- 中馬宏之・樋口美雄(1995)「雇用環境の変化と長期雇用システム」猪木武徳・樋口美雄編『日本の雇用システムと労働市場』日本経済新聞社、第1章
- 八代尚宏・大石亜希子(1995)「経済環境の変化と日本的雇用慣行」『日本労働研究雑誌』No.423
- 小野旭(1995)「昇進と企業内賃金構造」一橋大学『経済学研究』第36巻
2. 労働需要
- 宮川努・玄田有史・出島敬久(1994)「就職動向の時系列分析」一橋大学経済研究所『経済研究』第45巻第3号
- 浦坂純子・大日康史(1996)「新卒労働需要の弾力性分析―3時点間のパネル推定」『日本経済研究』No.32
- 駿河輝和(1996)「日本企業の雇用調整:企業利益と解雇」Discussion Paper Series No.1996-2, Osaka Prefecture University, 中馬宏之・駿河輝和編『雇用環境の変化と労働市場』(仮題)東京大学出版会、近刊
- 村松久良光(1995)「景気変動と雇用調整:日本に関する研究展望」京都大学『経済論叢』第155巻第1号
- 鎌田彰仁「中小企業の創業と雇用問題」『日本労働研究雑誌』No.425
- Hashimoto, K. and J. A. Heath(1995)“Estimating elasticities of substitution by the CDE production function : an application to Japanese manufacturing industries.” Applied Economics Vol.27
3. 海外生産活動と国内雇用
- 深尾京司(1995)「日本企業の海外生産活動と国内労働」『日本労働研究雑誌』No.424
- 深尾京司(1996)「国内か海外か─わが国製造業の立地選択に関する実証分析」一橋大学経済研究所『経済研究』第47巻第1号
- 伊沢俊泰(1996)「日本企業の海外進出と労働力コスト―電気機器産業の企業について」『季刊労働法』179号
- 佐野哲(1996)「産業空洞化と製造業」『季刊労働法』179号
4. 賃金構造(女子・パート賃金は徐く)
- 石川経夫・出島敬久(1994)「労働市場の二重構造」石川経夫編『日本の所得と富の分配』東京大学出版会
- 石川経夫・李昇烈(1996)「製造業下請制の賃金効果」『日本労働研究雑誌』No.430
- 大竹文雄(1994)「1980年代の所得・資産分配」『季刊理論経済学』Vol.45、No.5
- 玄田有史(1994)「高学歴化、中高年齢化と賃金構造」石川経夫編『日本の所得と富の分配』
- 玄田有史(1996)「『資質』か『訓練』か?」『日本労働研究雑誌』No.430
- 神代和欣(1996)「大競争時代の賃金決定」『日本労働研究雑誌』No.436
- 中村二朗(1995)「わが国の賃金調整は伸縮的か」猪木武徳・樋口美雄編『日本の雇用システムと労働市場』日本経済新聞社
- 樋口美雄(1994)「大学教育と所得分配」石川経夫編『日本の所得と富の分配』
- 村松久良光(1995)「企業規模間の分業構造と賃金構造:日本と西欧の比較」『南山経済研究』Vol.9、No.3
- Brunello, Giorgio, Ken Ariga, Yoshihiko Nishiyama, and Yasushi Ohkusa(1995) “Recent Changes in the Internal Structure of Wages and Employment in Japan.” Journal of the Japanese and International Economies Vol.9
- Hart, Robert A. and Seiichi Kawasaki(1995) “The Japanese Bonus System and Human Capital.” Journal of the Japanese and International Economies Vol.9
- Ohkusa, Yasushi and Souichi Ohta(1994) “An Empirical Study of the Wage-Tenure Profile in Japanese Manufacturing.” Journal of the Japanese and Intenational Economies Vol.8
- Tachibanaki, Toshiaki and Souichi Ohta(1994) “Wage Differentials by Industry and the Size of Firm, and Labour Market in Japan.” Tachibanaki, Toshiaki(ed.) Labour Market and Economic Performance (Macmillan)
- Tsuru, Tsuyoshi and James B. Rebitzer(1995) “The Limits of Enterprise Unionism : Prospects for Continuing Union Decline in Japan.” British Journal of Industrial Relations Vol.33, No.3
5. 昇進・査定・技能・移動
- 有賀健、ジョルジュ・ブルネッロ、真殿誠志、大日康史(1996)「企業ヒエラルキーと人的資本形成」伊藤秀史編『日本の企業システム』東京大学出版会
- 伊藤秀史、照山博司(1995)「会社役員の意識と目的」橘木俊詔、連合総合生活開発研究所編『「昇進」の経済学』東洋経済新報社
- 伊藤秀史、照山博司(1995)「ホワイトカラーの努力インセンティヴ」橘木俊詔、連合総合生活開発研究所編『「昇進」の経済学』
- 大竹文雄(1995)「査定と勤続年数が昇格に与える影響」『経済研究』Vol.46、No.3
- 太田聡一(1995)「非対称情報下における昇進モデルと『日本的』昇進慣行」『日本経済研究』No.30
- 大橋勇雄(1995)「会社の中の学歴社会」橘木俊詔・連合総合生活開発研究所編『「昇進」の経済学』
- 小林良暢(1995)「課長への道」橘木俊詔・連合総合生活開発研究所編『「昇進」の経済学』
- 鈴木不二一(1995)「ホワイトカラーのキャリアと労働組合」橘木俊詔・連合総合生活開発研究所編『「昇進」の経済学』
- 橘本俊詔(1995)「役員への途と役員の役割」橘木俊詔・連合総合生活開発研究所編『「昇進」の経済学』
- 冨田安信(1995)「理工系出身者の仕事意識と処遇」橘本俊詔・連合総合生活開発研究所編『「昇進」の経済学』
- 中村恵(1995)「ホワイトカラーの異動」猪木武徳・樋口美雄編『日本の雇用システムと労働市場』
- 野田知彦(1995)「会社役員の昇進と報酬決定」橘木俊詔・連合総合生活開発研究所編『「昇進」の経済学』
- 野田知彦(1995)「理工系、文系と昇進」橘木俊詔・連合総合生活開発研究所編『「昇進」の経済学』
- 松繁寿和(1995)「電機B社大卒男子従業員の勤続10年までの異動とその後の昇進」橘木俊詔・連合総合生活開発研究所編『「昇進」の経済学』
- 三谷直紀(1995)「ホワイトカラーの賃金・昇進制度と労働インセンティヴ」橘木俊詔・連合総合生活開発研究所編『「昇進」の経済学』
- Abe, Yukiko(1994) “Specific Capital, Adverse Selection, and Turnover : A Comparison of the United States and Japan.” Journal of the Japanese and International Economies Vol.8
- Endo, Koshi(1994) “Satei (Personal Assessment) and Interworker Competition in Japanese Firms.” Industrial Relations. Vol.33, No.1
- Hashimoto, Masanori(1995) “Investment in Employment Relations in Japanese Firms.” Journal of the Japanese and International Economies Vol.9
- Higuchi, Yoshio(1994) “Effects of Job Training and Productivity Growth on Retention of Male and Female Workers in Japan.” Tachibanaki, Toshiaki(ed.) Labour Market and Economic Performace (Macmillan)
- Ohashi, Isao and Hisakazu Matsushige(1994) “The Growth of the Firm and Promotions in the Japanese Seniority System.” Tachibanaki, Toshiaki(ed.) Labour Market and Economic Performance (Macmillan)
- Rebick, Marcus E. (1995) “Rewards in the Afterlife : Late Career Job Placements as Incentives in the Japanese Firm.” Journal of The Japanese and International Economies Vol.9
6. 家族構成と就業行動
- 今田幸子(1996)「女子労働と就業継続」『日本労働研究雑誌』No.433
- 大淵寛(1995)「女性のライフサイクルとM字型就業」総務庁・人口世帯研究会監修『女性のライフサイクルと就業行動』第2章
- 小椋正立(1994)「2020年までの日本人人口予測」『日本経済研究』No.27
- 小島宏(1995)「結婚、出産、育児および就業」総務庁・人口世帯研究会監修『女性のライフサイクルと就業行動』第4章
- 駿河輝和(1995)「日本の出生率低下の経済分析」『大阪府立大学 経済研究』第40巻2号
- 高山憲之・有田富美子(1996)「共稼ぎ世帯の家計実態と妻の就業選択」高山憲之・有田富美子『貯蓄と資産形成』岩波書店、第4章
- 水野朝夫・吉田良生(1995)「低出生力・労働時間短縮と労働供給」水野朝夫・小野旭編『労働供給制約と日本経済』大明堂、第2章
- 松浦克己・滋野由紀子(1995)「日本の年齢階層別出産選択と既婚女子の就業行動」『季刊社会保障研究』第31巻2号
7. 女性の雇用管理
- 塚原康博(1995)「育児支援政策が出生行動に与える効果について―実験ヴィネットアプローチによる就業形態別出生確率の計量分析」『日本経済研究』No.28
- 冨田安信(1994)「女性が働き続けることのできる職場環境―育児休業制度と労働時間制度の役割―」『大阪府立大学 経済研究』第40巻1号
- 冨田安信(1996)「再雇用制度が女性の賃金に与える効果」『大阪府立大学 経済研究』第41巻4号
- 中村二朗・中馬宏之(1994)「ヘドニック賃金アプローチによる女子パートタイム労働者の賃金決定」『日本労働研究雑誌』No.415
- 永瀬伸子(1994)「既婚女子の雇用就業形態の選択に関する実証分析―パートと正社員―」『日本労働研究雑誌』No.418
- 永瀬伸子(1995)「「パート」選択の自発性と賃金関数」『日本経済研究』No.28
- 樋口美雄(1994)「育児休業制度の実証分析」社会保障研究所編『現代家族と社会保障』東京大学出版会、第9章
- 牧野文夫(1995)「女子の高学歴化と職業選択」総務庁・人口世帯研究会監修『女性のライフサイクルと就業行動』第3章
- 三谷直紀(1996)「均等法施行後の女性雇用」『日本労働研究雑誌』No.433
- 脇坂明(1996)「コース別人事管理の意義と問題点」『日本労働研究雑誌』No.433
8. 福利厚生と税制・社会保障の影響
- 安部由紀子・大竹文雄(1995)「税制・社会保障制度とパートタイム労働者の労働供給行動」『季刊社会保障研究』第31巻2号
- 金子能宏(1997)「高年齢者雇用政策と雇用保険財政」『経済研究』(近刊)
- 田近栄治・金子能宏(1995)「厚生年金の財政と世代間負担―フェア年金の構想―」『季刊社会保障研究』第30巻4号
- 逆瀬川潔(1996)「中小企業における退職金制度の課題」逆瀬川潔『中小企業の労働問題』日本労働研究機構、第4章
- 西久保浩二(1995)「転換期を迎える日本型福利厚生」『日本労働研究雑誌』No.429
- 樋口美雄(1994)「税・社会保険料負担と有配偶女性の収入調整」『高齢化社会における社会保障周辺施策に関する理論研究事業』長寿社会開発センター。八田達夫・八代尚宏編『「弱者」保護改策の経済分析』日本経済新聞社1995年に収録。
- 堀勝洋(1996)「女性と年金」『季刊社会保障研究』第31巻4号
- 丸山桂(1995)「税制改革とパート労働者の就業選択」『日本労働研究雑誌』No.429
- 山上俊彦(1996)「大都市サラリーマンOBの就業行動」『日本労働研究雑誌』No.438
1. 長期雇用、終身雇用
論文紹介(駿河)
中馬宏之・樋口美雄「雇用環境の変化と長期雇用システム」
日本の入・離職率は国際的に見て低いほうの部類に入るが、突出して低くはない。むしろアメリカが突出して高い。日本の平均勤続年数はアメリカより高いがドイツとはさほど変わらない。いろいろな指標(長期勤続者割合、平均勤続年数、残存率)をとっても日本の定着率が極端に高いということはない。むしろアングロサクソン系の国で定着率が低い。30-45歳層のデータを見ると、ヨーロッパでは、長期勤続者が多数存在する反面、最近転職した人も多く、二極分解している。比較的流動的な人の割合が高い。対して、日本は長期雇用者の割合が高い。
次にKanemoto and MacLeord(1989)のモデルを拡張した2期間モデルを使用して理論分析をしている。モデル分析から次のような命題を導いている。技術進歩の上昇は、長期雇用者比率の上昇をもたらす。労働力不足の予想は、短期雇用者比率の上昇をもたらす。将来生産物需要の不透明度拡大は、短期雇用者比率の上昇をもたらす。
このモデルに沿って、実証分析をして、次のような結果を提出している。全体に有意でない変数がかなり多い。将来の不透明度は規模計や大企業で短期雇用者比率を有意に引き下げるという理論と逆の結果が出ている。技術進歩低下は規模計と小企業で短期雇用比率を引き上げている。将来の労働力不足の予想(若年失業率の低下)は中企業のみで有意に短期雇用比率を上昇させていた。
八代尚宏・大石亜希子「経済環境の変化と日本的雇用慣行」
日本的雇用慣行の変化を、企業が固定的な雇用者を流動的な雇用者に置き換える「雇用ポートフォリオ」の組み替えとしてとらえた。「賃金センサス」は、雇用者全体に占める長期勤続者比率の高まりを示している。たしかに中高年層での長期化傾向が見られるが、若年層は1980年代後半以降勤続年数の短縮化を示している。すなわち、二極分解が生じている。最近の勤続年数の上昇は勤続要因ではなくほとんどが年齢構成要因の変化で説明される。
「就業構造基本調査」で見ると、雇用者全体に占める非正規雇用者割合は、過去10年間ですべての年齢層で増加。離職率は、1980年代後半以降緩やかに上昇している。企業の経済合理的なメカニズムにより日本的雇用慣行が形成されたと考えると、企業を取り巻く外的環境の変化に合理的に反応することにより、将来流動化傾向が生じる。外的環境の変化として次のことが考えられる。
- 長期的経済成長の鈍化
- 労働力需給の逼迫
- 女性雇用者比率の高まり
実証分析の結果次のことが確かめられた。労働生産性の伸びが低くなると、非正規雇用者比率は高くなる。生産年齢人口の伸びが低下すると、非正規雇用者比率は高くなる。企業特殊的人的資本の重要な産業ほど、正規雇用者比率が高い。技術導入が盛んであるほど、年齢間賃金格差が大きい。
将来予想される労働力需給の逼迫は、長期的に年齢間賃金格差を縮小し、また平均離職率を高める。女性雇用者の増加は、供給面からの雇用の流動化をもたらす。
小野旭「昇進と企業内賃金構造」
終身雇用制度の一つの特徴は、子飼い重視の雇用慣行である。この論文は、「賃金構造基本調査」により、生え抜きと非生え抜き間で昇進の速度がどのくらい違うか、また時間的にどのような変化が起こっているかを調べている。その結果次のような結果が得られた。[1]1980-90年では、管理職に占める生え抜きの割合上昇。[2]生え抜きは各管理職に到達する昇進速度が速い。[3]生え抜き、非生え抜き間で平均年齢に大きな差があるのは、下位職種。上位のポストほど能力に重点を置いた人材登用で、生え抜きの要因は重要度が低くなる。[4]生え抜きのほうが非生え抜きよりも平均年齢が上昇し、昇進の遅れが目立つ。両者間の年齢差は縮小している。[5]他企業経験は昇進に不利に作用するが、近年この不利益が緩和されつつある。[4]と[5]の結果から、非生え抜き・他企業経験者に対する差別処遇が後退しつつあることを示唆しており日本的雇用慣行の変質の前兆と解釈している。
- 駿河
-
最初は、長期雇用と終身雇用というテーマで、日本の雇用慣行が変質したとか、変わったとか、将来変わっていくだろうという議論が最近、非常に数多く行われています。新聞などを見ますと、終身雇用は終わったというような書き方をしていて、いつ終わったのだろうかと思うわけです。日本の雇用慣行変化をめぐる議論というのは、いろいろありますが、全体としてまだ未整備の状態です。その中で学術的かつ客観的に慣行変化の問題を扱っているという意味で、この三つの論文を取り上げました。
最初の二つ、中馬・樋口、八代・大石論文は、年功賃金の変化についても少し触れていますが、主として正規・非正規、あるいは長期雇用者・短期雇用者の比率が今後どう変わるかということを検討しています。今後、雇用を取り巻く経済環境の変化として、技術進歩の停滞、若年人口の減少、生産物市場の競争が激しくなって生産物需要が不透明化するとか、経済成長が鈍化する。こういうことが長期的に予想されています。
両論文とも、日本の雇用慣行が、その時代の雇用を取り巻く経済環境に対して非常に合理的に対応した結果、現在の日本の雇用慣行が生まれたとしています。そうすると、経済環境が変化した場合に、雇用慣行はどういうふうに変化していくのかという議論の立て方をしていて、適切だと思います。理論を最初に考案して検証をやっています。両方とも多少不明確なところもありますけれども、非正規労働者、あるいは短期雇用者の比率が増加するということを予想しています。
それから、一般にデータで見ますと、長期雇用慣行の変化を明確にとらえているようなデータというのはなかなかないんですね。平均勤続年数はむしろ上昇しているとか、離職率というのは最近やや上昇していますけれども、オイルショック前はもっと離職率が高かった。その中で小野論文は、終身雇用の重要要因である子飼い重視、あるいは生え抜き重視の慣行というのを取り上げて、データで昇進についてチェックしています。生え抜きは昇進に有利であるというのは変わりませんが、時系列的に見ると、生え抜き重視の慣行というのが弱まってきている。そのことが日本の雇用慣行の変質の兆しであると受けとめているわけです。
以上が大体のまとめです。
討論
- 金子
-
まず、中馬・樋口論文の特徴は、従来、マスコミでは、よく景気の不透明感とか、先行き不透明感と言われているけれども、その不透明という言葉を経済学的に不確実性として導入していて、その不確実性下で企業が利潤を最大化するということを前提に企業の労働需要を導くというスタイルをとっているんですね。そういう意味では、マスコミ、あるいは一般の話題として取り上げられている経済環境の変化、この論文の用語では雇用環境の変化と言っていますけれども、そういうものをうまくモデルの中に取り入れているような気がするんです。
- 駿河
-
先ほど言いましたけれども、将来の雇用環境、経済環境の変化のとらえ方としては、私も適切と思っています。特に合理的な行動の結果として、将来こうなるというのが予想されているという点が非常にいいと考えています。ただし、計量の実証結果は必ずしもよくないと思うんです。
- 奥西
-
中馬・樋口論文と八代・大石論文は、似たようなテーマを取り上げていて、全体の構成も似ていますね。ただ、大きな違いは、中馬・樋口論文のほうは理論面でも、実証面でも、より広いフレームワークをつくって、そこから出発しているのに対して、八代・大石論文は各個撃破というか、非常に焦点を絞って切り込んでいることです。そのどちらがいいかは多分微妙なところで、個々の推計式を別物と考え、推計式によって取り上げる変数を変えるなどしたほうが結果がうまく出るということが、この二つの例からする限りは出ているんですが、それをうまいととるのか、あるいは一種のプリテストと言うと失礼になりますが、よく当てはまる変数を選んだという面はないのかといったあたりが私は気になりました。
また、内容的なことでは、流動化の議論をするときには、流動化の中身を具体的にどういう側面でとらえるかということが大事だと思うんですね。この点を特に中馬・樋口論文はかなり丁寧に論じられています。そこで、一つのとらえ方として、正規・非正規の比率で見るというのは、私はわかるんですが、ただ、最近の動きを見ていると、景気が悪いことの影響が大きいと思いますが、中高年を中心に企業にしがみつく傾向がかなり強く出ていると思うんです。ちょっと言葉は悪いですが。 - 金子
-
でも、それは高年齢者雇用安定法を含めて制度がそれを助長している面もあるでしょう。
- 奥西
-
特に中年層の場合には労働者がかなり自発的にしがみついていると思いますよ。
- 金子
-
だから、この中高年を二つに分けて、40代後半から55歳ぐらいまでと、法が保護しようとしている55歳以上の年齢層とに分けて考えて、45~55歳のほうは奥西さんの指摘がまず当てはまると仮定しましょう。そうすると……。
- 奥西
-
だから、仮に景気が先行き悪いとしたとき、勤続年数や移動率でとった企業への定着度は強まる可能性があると思うんです。
- 駿河
-
年齢層によって異なってくるというと、要するに二極分解しているということですか。
- 奥西
-
要は流動化というのをどういう指標でとらえるかによって、経済環境が変わったときに流動化の状況はどうなるかという議論は影響を受けるんじゃないかということを言いたかったのです。その中で、正規・非正規の比率をとるというのは一つの考え方としては理解できます。
そのときに取り上げたい問題は、技術進歩の問題なんですが、八代・大石論文では、ポートフォリオモデルを提起していて、長期雇用者というのは企業にとって大きな固定費用の負担を伴うものなので、リスキーな存在であるというとらえ方をしているわけです。しかし、費用面だけでなく便益面も見るべきであって、技術進歩の創造力やそれへの対応力において、短期雇用者と長期雇用者のどちらがより適しているかということを考えると、別の評価も可能だと思うんですね。実際、たとえば、中馬・樋口論文では、技術進歩率が高まるならば、長期雇用の比率は高まるだろうという含意を出しているわけです。
そうすると、これからの日本企業の技術進歩率はお先真っ暗だと言ってしまうのか、いやこれから労働力人口も伸び悩むか、あるいは減るなかで、日本経済が生きていくとすれば技術進歩率を高めるしかないという積極的な展望に立てば、むしろ長期雇用の重要性を強調すべきだという議論だってできると思うんです。だから、一概に短期雇用が増えるという見方に関しては、私はいろいろ留保をつけたいと思っています。
- 駿河
-
経済環境の変化で前提とされているところが、必ずしもそうとは限らないということですね。一つは、技術進歩が案外停滞せずに伸びてくるかもしれない。もう一つは、たとえば生産物需要の不透明度、これもほんとうに高まってくるのかという点も少し疑問がありますね。
それから、八代・大石論文の雇用ポートフォリオ理論もあまり明快なものではないですね。論文には詳しい内容を書いていないですけれども、人的資本では、技能形成や訓練とかということが必要であるとか、労働努力とか、働かせるためにはインセンティブが必要であるとか、そういう意味では、金融資産と人的資産とはかなり違う面がありますから、その辺をきちんと議論する必要があるのではないかと思いました。
それから、最初に言われたデータの面ですけれども、中馬・樋口論文は被説明変数に長期雇用者と短期雇用者の入職者の比をとっているんですね。ですから、フローの値をとっています。それに対して八代・大石論文は、ストックのほうですね。正規労働者数と非正規労働者数、これをストックでとっていますから、二つのデータの変動の差は大きい。ストックのほうは大分安定しています。フロー変数は、離職者は考えずに入職者だけですから、その辺で問題点がある可能性はありますね。それと、正規・非正規の比率だけでは、それが短期雇用者であるとか、非正規雇用者の数が増えていくというのはわかるんですけれども、必ずしも雇用慣行の変質とは、直接的には関係がないという可能性がありますね。
- 金子
-
その雇用慣行というのは、賃金を含めての雇用慣行ですか。
- 駿河
-
主として長期雇用、終身雇用のことです。
- 金子
-
そうすると、インセンティブの面があるわけですね。今お聞きしたのは、長期雇用というとき、たとえば、長期雇用のために退職金が勤続年数をある程度超えると非常に増加する仕組みになっていますね。その長期雇用が変化するとしたならば、インセンティブのメカニズムも変わると思うんですね。その点については、これらの論文は、あまり明示的には扱っていないような気がするんです。
- 駿河
-
ただ、全体的に、「日本的雇用制度研究会中間報告」などを見ても、終身雇用がドラスティックに崩れていくというふうに考えている企業というのは少ないですね。どちらかというと、部分的には変わっていくという可能性はありますけれども、終身雇用を重視する企業もかなり多いという印象ですね。
では、小野論文のほうはいかがですか。「子飼い重視」という点を取り上げているので、おもしろいことはおもしろいんですけれども。ただ、技能形成の点から見ると、長期雇用は非常に重要であるとは言われますけれど、子飼い重視がどのくらい重要であるかは少し疑問ですね。
それともう一つは、前の二つの論文と違いまして、子飼い重視であるとか、生え抜き重視と言っているときに、経済的な合理性、経済的な意味づけが少し弱いんじゃないかという印象がしました。
- 奥西
-
この論文は昇進と賃金の両面において、生え抜きであるか否かがどれだけ重要な意味を持っているかということを「賃金構造基本統計調査」の個票データを使ってたいへん丁寧に分析したものですね。ただ、昇進のところで1点気になったのは、たとえば小野論文の6頁を見ると、昇進について単に勤続が長い、短いだけではなくて、生え抜きであるか否かが重要ではないかという点を指摘し、その検証が第1の目的であると言われているのですが、実際の分析のところでは、勤続年数自体は説明変数に入っていないため、生え抜き要因が勤続年数から独立して効果があるかどうかというのはよくわからなかったのですが。ここの書き方からすると、勤続が長いほどたしかに昇進において有利だけれども、生え抜きであることが加わると、さらに一層有利になると読めるのですが、その点はいかがですか。
- 金子
-
実証分析では明確にはなっていない?
- 奥西
-
と私は思ったんだけれども。
- 金子
-
たとえば勤続年数については2次関数で近似して、ダミー変数でクロスさせてもよかったかもしれません。あるいは勤続年数のパラメーター自体が生え抜きの度合いに依存する関数にしてもよいかもしれない。ひとひねりしたほうがいいのではないかということですね。
- 奥西
-
もしこれが中心課題であるのならばですが。今のままだと、たしかに生え抜きは非生え抜きより有利である。しかし、それは勤続年数が長いから当たり前じゃないのかと解釈する余地もあるのではないでしょうか。
- 駿河
-
そうすると、勤続年数のところが全くコントロールできていないため、勤続年数の効果か生え抜きの効果かがよくわからない。単に年齢と生え抜き、非生え抜きだけをコントロールしている。
- 奥西
-
もちろん、学歴もありますけれども。ちなみに賃金のところでは、勤続のほかに生え抜き要因を入れたけれども、必ずしも期待したような結果が出なかったという結論ですね。だから、その辺が少し気になったんです。
- 金子
-
いずれにしても、生え抜きと非生え抜き間の昇進の速度の比較研究というのは、個票を使ったものに関しては、ほぼ最初ですね。先駆的業績という位置づけはできると思うんです。
先駆的業績として認めるとして、なぜこれだけ生え抜きの問題が重要なのかというと、先ほど大企業では終身雇用制は変わらないと言っている一方で、マスコミでは流動化、あるいは規制緩和と併せて流動化の議論がありますね。労働市場を流動化させた場合には、生え抜きと非生え抜き間の昇進の速度に差があってはいけないはずですね。いわゆる日本的雇用慣行に対するアンチテーゼが、共通認識になってきたからこそ、この分析はあえてこの時期にやってみなければいけなかったと考えられるんですけれども。
- 駿河
-
「日本的雇用制度研究会中間報告」を見ますと、今後どういう採用方法をとるかという質問に対して、一番重視しているのが、新規大卒男子を重視するというところがほとんどなんです。そういう意味では、急速な変化というのはあまり見られないのではないですか。
- 金子
-
女子労働問題とも関係あるんですけれども、そうすると、やはり男女雇用機会均等法の影響はあまり大きくないと考えられるのか。それとも、男子を重視すると言われたのですが、もう一つ、大卒総合職重視で彼らを生え抜きとして訓練し、よりよい人材に育てて会社の繁栄に結びつけるというスタイルを今後もとり続けるというふうに翻訳したほうがいいんでしょうかね。
- 駿河
-
生え抜きの中に女子が入るかどうかということは疑問なんですね。
- 金子
-
個人的見解ですが、これからは入ると思いたいんです。小野論文では女子の生え抜きは取り上げられていませんが、女子管理職の学歴構成の変化や管理職の年齢構成の変化を均等法施行前後で比較することは中村恵さんの研究、女子パートの生え抜きを考えると基幹型パートの育成が問題になりますが、脇坂明さんの研究があります。だから、今後この分析を拡張するとしたら、男女雇用機会均等法が施行されて、さらにそれを拡充する方向にあるんだから、生え抜きと非生え抜き間の昇進の速度をさらに男女別にやってみるとか、分析を発展させる方法はいくらでもあると思うんです。
- 駿河
-
この分野は、マスコミではよく取り上げられる割に、学術的研究は比較的少ないというので、今後こういう雇用慣行についてのいろいろな側面からの研究というのがもっと必要でしょう。
- 金子
-
特にマイクロデータをとってですね。
- 奥西
-
賃金についても一言いいですか。小野論文では、賃金についてもかなり詳しい分析をされているのですが、ちょっと引っかかったのは、サンプルを職階によって分け、そのサブ・サンプルごとに賃金関数を推計されている点です。こうしたやり方をすると、昔、アメリカの分断的労働市場の研究で問題になったトランケーション・バイアスが出てくる可能性があると思うのです。それを簡単に図に表したものをお配りしたんですが(図1)、横軸に年齢をとって、縦軸に賃金をとる。仮に6個の観測値が×印のように散らばっているとします。それらに回帰式を当てはめると、この実線のような右上がりの直線が引けます。その傾きが年齢の効果です。横軸に勤続をとっても、おそらく似たようなことが言えるでしょう。
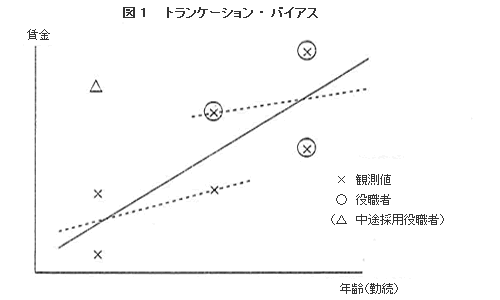
ところが、このサンプルの中で役職者だけを取り出すと、役職者というのはおそらく○印で囲ったような分布になっている。そうすると、役職者と非役職者を分けて賃金関数を推計すると、図の点線のように傾きがいずれも小さくなってしまう。しかも、横軸に勤続をとった場合は、たとえば中途採用で役職者になる人はかなりいるし、そういう人は賃金も高いでしょうから、図の△印のようなサンプルも入れて推計すると一層勤続の効果は低くなる。
高賃金の中途採用役職者の存在によって勤続の効果が小さくなるというのは、たしかに実態を反映しているのですが、小野さんは、結論的に、勤続の賃金に対する効果は非常に小さい、だから、勤続が持つ賃金へのプラス効果を通じた定着効果というのは、あまり評価できないのではないかという結論を導かれているのです。しかし、図1で示したような問題が起きている可能性もありますので、私としてはもう少し留保をつけたほうがいいのではないかと思います。
特に、昇進と絡めると、そのことは一層強く言えると思うんですね。中途採用で役職につく人は、たしかに増えているし、かなりいるとは私も思いますけれども、長期勤続が昇進において有利だということははっきりしているわけで、昇進したら賃金が高くなるということもこれまたはっきりしています。そのことを踏まえると、勤続が持つ企業定着促進効果というのは、小野さんが言われるほどほんとうに小さいのだろうかという疑問を持ちました。
2. 労働需要
論文紹介(駿河)
宮川努・玄田有史・出島敬久「就職動向の時系列分析」
日本の就職動向は長期的には労働需要量を変動させる要因にのみ支配されていることを、実証的に示している。まず集計マッチング関数の推計を行って、コ=インテグレーション・テストにより労働需要と労働供給いずれの要因が就職動向に長期的な影響を与えているかを検討。就職者と求人数は一つの共通な確率トレンドに従っており、就職行動は長期的には労働需要側の要因にのみ規定されている。
短期的影響を見るためにエラー・コレクション・モデルにより集計マッチング関数を推定。常用雇用者の就職者数の長期均衡からの乖離は1年で調整されることを示している。
浦坂純子・大日康史「新卒労働需要の弾力性分析─3時点間のパネル推定」
パネルデータを使用して、トービット・モデルで経常利益と新卒採用者数の関係を推定している。推定の結果は、次のようになっている。経常利益の黒字の増加に対して、女子の採用増加が男子の増加を上回る。経常赤字の増加に対して女子の採用減は男子を上回る。この結果は、「景気が悪くなれば、女子学生から切る」という議論と整合的である。
男女ともに、文系に比べて理系のほうが弾力性が小さい。理系の男女では、経常黒字期はほぼ同レベルであるが、赤字期には女子の弾力性が著しく大きい。文系の男女間には有意な差はない。短大卒は黒字期に弾力性は文系大卒男子よりも大きく、赤字期には小さくなる。検定では赤字期に文系女子と有意な差はない。
全従業員を使用した分析は、弾力性は新卒採用者に比べて非常に大きいことを示した。したがって雇用調整が主に新卒採用で行われているという仮説を棄却している。ただし、分析期間を長くとると、全従業員による弾力性は小さくなる。
駿河輝和「日本の企業の雇用調整:企業利益と解雇」
雇用調整について、「1期の大きな赤字または2期連続の赤字で企業は解雇を行う」という経験則が確かめられている。この経験則を基に赤字雇用調整モデルを考案した。すなわち、大きな赤字期には解雇を使用し、解雇には組合との調整などかなり大きな固定費用が必要であるため、調整速度は速くなる。それ以外の通常のときには、解雇に対して非常に強い抵抗があり、解雇の実行が不可能なほど固定費用が高くなる。したがって、解雇を使用せずそれ以外の手段により雇用調整を行わざるをえず、雇用調整速度も遅くなる。この赤字調整モデルを個別企業のデータを使って調べている。またその他の代替的モデルと推定結果を比較もしている。その結果、いくつかの企業でこのモデルがよく当てはまることが確かめられた。しかし、大きな赤字でも解雇を行わずに出向で済ます鉄鋼では、調整速度は速くなっておらず、モデルはうまく当てはまらない。
- 駿河
-
では、次に、労働需要関係に移ります。最初の宮川・玄田・出島論文は、就職者数は、労働需要の大きさが主として決めているということを言っているわけで、われわれが雇用分析をするときに、主として企業の労働需要という側面の分析をしていれば大体間違いがなくて、供給側にさほど考慮を払わなくてもいいということを主張されているわけですから、雇用分析をする意味でも非常にありがたいと思います。
2番目の浦坂・大日論文は、経常利益の変化が新規学卒者の就職にどういう影響を与えるかという問題を扱っていまして、現在、不況下で新卒者、特に女子学生の就職難というのが非常に問題になっているだけにタイムリーな論文になっていると思います。女子学生、それも文系の学生のほうが景気の調整に使われているという結果を得ていて、われわれの直感とかなり合う結果になっています。
3番目の駿河論文は、2期連続の赤字、あるいは1期の大きな赤字で解雇が起こるという経験則を労働需要理論の枠組みの中へ取り込もうと試みたものです。一般に雇用調整速度の変化は、大体これまでの議論では生産の大きな変化で起こると言われていましたけれども、雇用調整速度の大きな変化は、生産量ではなく経常利益の変動によって生じるというふうに分析しています。経常利益に対して雇用の変化を入れている点で浦坂・大日論文と共通する点があるわけです。
討論
- 奥西
-
宮川・玄田・出島論文ですけれども、私は時系列分析については素人で、テクニカルな部分は必ずしも十分理解できなかったのですが、結論の一つの理解の仕方として、経済学の入門的教科書にあるトレーディング・ローカス(取引可能軌跡)の考え方が使えないかと思いました。これも図をお配りしたんですけれども(図2)、需要曲線と供給曲線があります。需要と供給が均衡しなくても取引されるとすると、太線のところで取引が行われます。そうすると、需要のほうが効いているというのは、超過供給、言い換えると賃金が均衡賃金に比べて高すぎる、そういう状態が支配的だったというのが一つの理解の仕方だと思うんです。
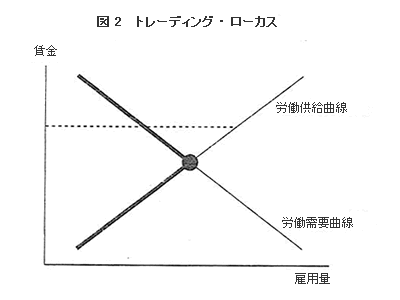
そうすると、1970年から91年という計測期間は、高度成長期の末期と、バブルの時期がちょうど最初と終わりに入っていますけれども、どちらかというと、需要が弱くて、供給はそれなりに増えていた時期だから、その時期だとこういう結果が出ても不思議はないなと思います。しかし、もしこういう理解の仕方が正しいなら、今後、労働力人口が減ると、違う局面があらわれる可能性もあるのかなということを感想として思いました。
- 駿河
-
一般には大企業の労働市場の場合には労働需要だけで採用を決定していて、中小企業の場合には需要側の側面が強く出るときと供給側の側面が強く出るとき、それが交差するという説もあります。それから、バブル経済のときには供給制約ということを盛んに言われたわけで、もう少し期間を区切ってやると違う結果が出る可能がありますね。
- 金子
-
期間を区切るとして、こういうコ=インテグレーション・テストみたいなことをする必要がありますよね。時系列分析独特の手法を期間を区切ってやったとしても、それをやっておかないと。
- 駿河
-
あとはデータですね。特に求職者側のデータがうまく供給側の要因を拾いきれていないかもしれない。いろいろ工夫されて、四つぐらい変数をとられているんですけれども、その可能性はあります。
- 金子
-
あと一つ、重要なのは、宮川・玄田・出島論文は労働市場の需要面で数量割り当てがありうることを示しているし、駿河論文は日本の企業の雇用調整を取り上げているわけで、どちらかというとマクロ経済学のミクロ的基礎づけと関係する労働需要ですよね。1970年代のいわゆるオイルショック後の雇用調整関数を推定した論文は、ほぼ間違いなくマクロ的な生産関数を想定しておいて、そこから雇用調整関数を導いていた。それに対して、駿河論文は調整費用関数を導入するために、ミクロ的な企業行動のモデルづくりから出発して実証分析へ持っていく方法がとられています。大滝雅之さんの『景気循環の理論』での労働市場分析にしても、これらの実証研究にしても、労働需要の把握の仕方がマクロ経済学のミクロ経済学的基礎との関係を随分重視するようになったなという気がするんです。
- 駿河
-
浦坂・大日論文ですけれども、これは今までの労働需要の分析と全然違い、これまでの労働需要の分析というのは、労働需要関数を持ってきて、主要な労働需要の決定要因というのは、一つが生産量の大きな変化、もうーつは、資本と労働の代替、この二つが主として大きな要因として説明変数に入っていたわけです。けれども、この論文では2要因とも入っていなくて、経常利益だけでやっているということで、独創的な反面これまでの労働需要関数との関連がほとんどわからないという問題点があります。
- 金子
-
でも、計量経済学的には、ある仮説を立てて、説明変数と被説明変数を立てておいてやるという点では、別に問題ないわけですね。
- 駿河
-
問題はないですけれども、ただ、これまでの蓄積された研究との関連が不明です。
- 奥西
-
理論的な面で、これは駿河さんの論文のところでお聞きしようかと思っていたんですけれども、この二つの論文は、浦坂・大日論文は採用の話、駿河論文は解雇の話ですけれども、ある意味で共通しているのは、生産量よりもむしろ経常利益というものが何らかの意味で効いているという話なんですね。ところが、経常利益というのは通常の新古典派のモデルから導かれる労働需要関数の変数には入らないですね。それを理論的にどう理解するか。
- 金子
-
双対性アプローチを使って考えれば、制約されたプロフィット・ファンクションを暗黙のうちに仮定していて、制約の一つにある経常利益水準をとると想定すればいいのではないですか。そうするとホテリングの補題によりプロフィット・ファンクションから経常利益水準を制約とする労働需要関数を導くことができるから、労働需要に対する経常利益の弾力性を導くことができます。そうすれば、経常利益を取り上げて労働需要の弾力性を測っても、別におかしくないと思うんです。
- 駿河
-
私の論文は、一応、労働需要は生産量で動くというふうにはなっているのですが、経常利益で調整係数のほうが大きく変動するとなっています。ただし、どうして経常利益により大きく変動するのかは、今までの経験則に頼っていて、その辺の理論づけというのは少し不明瞭かもしれません。
- 奥西
-
そういう見方が間違っていると言っているのではなくて、どういうからくりなのかなということに興味があるので質問したんですが。
- 駿河
-
大きな経常赤字が出た場合には、今までの慣行を保持するコストが非常に高くなる。それでいて、解雇を労働者側も割と受け入れやすくなって、こういう大きな赤字が出ているのであれば解雇もやむをえないなということで、解雇の交渉のコストが、ある程度その時期だけ特別安くなると考えてモデルをつくっています。
- 奥西
-
駿河さんの論文の中で、そういった交渉コストの問題とか、労使協議制の問題を取り上げておられますね。その議論はよくわかるのですが、ただ、その場合も、意地悪な言い方をすると、たとえば労使間で今ほんとうに企業が左前かどうかをお互い確認し合うときに、収益という指標よりは生産という指標のほうが操作のしにくさもあって、合意しやすいという見方はできないでしょうか。
- 駿河
-
私の場合はそうでないと考えているんですね。利益のほうに対しての反応が大きい。生産量の減少ではない。
- 奥西
-
たとえば労使の間で一種の、利潤分配方式のような賃金決定がなされているとか、そういうメカニズムがあるのなら、それなりにわかるんですが。
- 駿河
-
ただ、企業の存続を考える場合には、生産量は減っているけれども、ある程度利潤が出ているというのよりは、利潤がすごく減っている、今後も減りそうだということのほうが、企業の存続に対する危機意識は強くなりますよね。
- 奥西
-
そうすると、当期の利潤がマイナスであることそれ自体というより今後の企業の期待成長のようなものを利潤指標がとらえているということでしょうか。
- 駿河
-
倒産の危機というか、つぶれる危機ということの影響が大きくて、赤字が何期か連続してくると、危機感が募ってくると私は見ています。
- 金子
-
ある意味では、労使ともに学習効果が働いているというんでしょうか。雇用調整や解雇しなければいけないときにしなかったために、赤字が累積してかえってより大きな調整を要したような経験があったとすれば、その経験を学習することによって、雇用調整や解雇しないことの機会費用が高くなることが労使双方に認識されてくるわけですね。
- 駿河
-
そうです。情報をお互いにどのくらい共有しているかが問題です。
- 金子
-
かつ景気循環のプロセスで情報を蓄積していく。でなければ、もし瞬時に学習するのだったら、1年後、2年後とラグをとる必要がない。
- 駿河
-
お互いに労使協議制度を通じて情報のやりとりをし、学習を行っているということですね。
浦坂・大日論文に戻りますけれども、浦坂・大日論文というのはきれいな結果が出ています。これはデータをとった年数が非常にいいのではないか。1993年、94年、95年という不況の時期だったので、余剰設備がたくさんあり、資本と労働の代替があまり問題にならなくて、経常利益に反応して、新規労働需要が変動したためよい結果が出たと解釈しています。ですからこれを別の時期とか、長期に当てはめると、やはり当てはまらないのではないかというのが私の予想なんですけれども。
それともう一つは、新規採用者のところでどのくらい雇用調整が行われているかというのをテストするために、従業員計で同じことをやっているんですね。ですけれども、新規労働者の採用という変数はフローですし、全従業員のところはストックの変数で、同じことをやって弾力性の差で見るというのは少し疑問があるのではないかと思いました。
- 奥西
-
その点については、たとえば「雇用動向調査」などで、一応ストックの変化とフローの変化がわかりますから、それを見るという、単純なやり方のほうがわかりいいのではないかなと思いました。
- 金子
-
いずれにしても、浦坂・大日論文で、先ほど奥西さんが心配したマイクロ・ファウンデーション等のつながりが、もう少し明確になればいいなという意味で、今後、この分野の研究の発展が期待されます。この3論文は実証の手法というのはみな手堅いと思うんです。時系列分析を要するところ、あるいは、浦坂・大日論文のようにデータに即したトービット・モデルを使い、かつ労働需要の弾力性を評価する際にもマージナル効果を区別するように努めています。計量経済学的には評価できる手法をとっています。
3. 海外生産活動と国内雇用
論文紹介(駿河)
深尾京司「日本企業の海外生産活動と国内労働」
製造業における海外労働投入比は約1割(1992年)で、マクロ的に見た国内労働への影響はまだあまり大きくない。電機産業に属する企業のパネルデータによる計量分析によると、過半所有現地法人の純生産(売り上げ-域外からの輸入)が増えるほどアジアでも北米でも純輸出(輸出-現地法人よりの輸入)が減少する結果となった。したがって、現地生産の拡大は本社の生産を減らす可能性が高い。しかし国内における雇用創出の低下は、日系企業による海外での雇用創出の上昇をはるかに上回る規模で、海外進出だけでは説明しきれない。今後海外生産が進行するにつれ、雇用問題が生じる可能性はある。その影響は特定の産業、職種、地域に集中して問題を引き起こすかもしれない。
伊沢俊泰「日本企業の海外進出と労働力コスト─電気機器産業の企業について」
電機産業の企業に焦点を当てて、海外への生産移転が国内の労働者の賃金にどのような影響を与えたかを分析している。比較的賃金の安い不熟練労働を必要とする工程の海外移転が生じているなら、海外移転比率の高い企業ほど、他の条件をコントロールすると国内本社企業で支払われる平均賃金が高まっていくことが観察されるはずである。東洋経済新報社『海外進出企業総覧』等の1978-92年データで実証分析をしている。実証分析の結果、海外労働投入比率の高い企業ほど平均給与が高まっていた。これは、労働集約的部門が相対的に縮小し人的資本集中部門が拡大してゆく産業構造の変化を反映している。したがって、比較的熟練度の低い工程で働く労働者、そのような産業の集中する地域は問題が大きくなると予想される。
- 駿河
-
三つ目のテーマに移ります。これまで海外直接投資と国内雇用の空洞化ということがよく言われていたんですが、言われている割には労働経済学からのこの問題に対する本格的分析は少なかった。この問題について、個別企業データを使った本格的な実証分析がいよいよ始まってきたというのが、深尾、伊沢両論文です。
これまで、本格的な実証分析があまりなかったという意味で価値のある論文だと思いますし、これから発展が期待される分野です。ただし、両論文ともデータが1992年までのものにとどまっており、急激な円高になって、海外生産比率が非常に高まってくるのは、分析対象以降の年になります。そういう意味では、今後、データがそろったところでますます研究が期待される分野です。
それから、どういった産業、あるいは職種、地域の雇用に大きな影響を与えていくのか、打撃を受けるような産業、職種、地域の雇用をどう支えていくのかといったような個別の問題が今後重要な課題となっていくだろうと考えています。
討論
- 奥西
-
深尾論文のほうはサーベイ的な性格もあり、また論旨明快で、私は素直に読めました。伊沢論文のほうは、少々チャレンジングな仮説を提示しています。空洞化ではしばしば雇用不安が問題になるのですが、空洞化によって海外に労働集約的な部門がシフトすると、日本国内にはかなり資本集約的、あるいは技術集約的な部門が残り、したがって、賃金水準は高くなるのではないかという仮説を提示して、それを電機産業について検証したわけです。
実証分析では、海外進出企業の賃金を被説明変数にして、説明変数のほうはいくつかあるのですが、その中に海外への労働投入比率があるわけです。そして、海外への労働投入比率が上がれば、国内における海外進出企業の賃金が高くなるという傾向が確認されたと結論づけられているんですが、ただ、海外生産比率自体は必ずしも外生変数ではないですよね。因果関係の可能性としては、たしかに伊沢さんが言われるように、海外生産比率が上がったから国内賃金が上がったということも考えられますが、逆に国内賃金が高かった企業で海外進出が進み、したがって、海外生産比率が高まったという解釈をする余地もあるのではないでしょうか。
そのような意味からすると、伊沢さんが論文の最後で、今後の課題としていくつかの方向を挙げておられるんですけれども、たとえばこの仮説のより直接的なインプリケーションは賃金というよりは国内の労働者構成が変わるという点ですよね。その点が果たしてどうなっているのか。あるいは、賃金につなげるときも、国内における賃金格差の問題との関係はどうなっているのかというような、実証研究をもう少し積み重ねないと、この結果だけからこの仮説が証明されたというのは、ちょっと強すぎるという感想を持ちました。
- 駿河
-
たしかに逆の因果関係は考えられますね。ただし、前提条件として考えているのは、国内賃金分布は全部一定、動かないという状況ですね。その中で海外へ進出することによって、賃金の低い不熟練の人が減って平均値が上がるという考え方をとっているんですね。
- 金子
-
年齢構成をコントロールしないといけないですよね、もし奥西さんの批判を入れるとしたら。
- 奥西
-
平均年齢とか、平均勤続は一応は入っているんですけれども。属性別の賃金の変化を見るべきだということですか。
- 金子
-
ええ。国内の労働者構成が変わるということに注目すれば、熟練労働者の国際労働移動の経済厚生効果を分析した清野一治さんの論文のように、労働者構成を熟練、非熟練に分けておく必要がある。そして、熟練と非熟練の平均年齢をコントロールする。逆の因果関係かどうか、仮説をもっと厳しく実証しようとしたら、どうしたらいいのでしょうか。奥西さんの批判にこたえることを、この実証方法でやろうとして、東洋経済新報社『海外進出企業総覧』等のデータではできなかったわけですよね。
- 奥西
-
そうならば、解釈に留保をつける必要があるのでは。
- 駿河
-
熟練の人と非熟練の人とを明示的にモデルに入れる必要がありますね。あと、電機も大手だけなら、組合員だけの調査ですけれども、電機連合の調査である程度詳しい属性別賃金というのはわかります。海外進出の分析の場合は、進出の結果、国内にどういう影響を及ぼしたというふうに大体回帰しますが、国内に要因があって外へ出たという逆のことが必ず言えるんですね。そういう意味では、モデルのつくり方は常に難しいですね。
- 金子
-
一つの産業部門を取り上げて、伊沢さんの仮説が適用できそうな産業部門と、そうではなくて、奥西さんの逆の解釈が可能な産業部門というのは明確にあるんでしょうか。産業部門別でも同様の研究をする意義があるのかないのか。
- 奥西
-
いや、とりあえず電機に限ってもいいと思うんです。その中でも企業によって、進出の事情なり何なりをもう少し見ないとという気がしたんですけれども。
- 駿河
-
でも、一番最初にこういうふうにパネルデータをつくって実証した意義は大きい。
- 奥西
-
ファーストカットとしては非常に興味深い論文だと思いましたけれども、ただ、これで結論が出たかというと、もう少し詰めなければならないんじゃないかということです。
- 駿河
-
これからデータ等がそろってきますので、もっと細かい産業、あるいは職種、先ほど言われた職種、それから地域について影響がどうなっていっているかというような細かい詰めがこれからも期待される分野だと思います。
4. 賃金構造
論文紹介(奥西)
石川経夫・李昇烈「製造業下請制の賃金効果」
企業の下請指標を含む通産省「工業実態基本調査」と労働者の賃金情報を含む労働省「賃金構造基本調査」(いずれも1987年)を、県、産業、企業規模別にマージしたデータを用い、製造業で下請制による企業タイプが、労働者の賃金格差にどのような影響を持つかを調べたもの。
主な事実発見の第1は、親企業への依存度が高い「専属タイプ」の下請中小企業の労働者の賃金は、他の中小企業に比べ低いこと。特に女子生産職でそのマイナス効果が大きいこと。下請中小企業の労働者の勤続が特に長いとか、労働時間が短いということはないので、この賃金格差は、いわゆる「均等化差異」からは解釈できない。こうした事実は、いわゆる「収奪仮説」と適合的だが、著者たちはその原因として、労働市場の局地性(買手独占)を示唆している。
主な事実発見の第2は、「独立タイプ」の下請中小企業については、非下請企業に比ベプラスの賃金効果が見られたこと。これは親企業-下請企業間の「情報の共有仮説」ないし、独立タイプ下請企業の「高技術仮説」と整合的だが、一方で、男子生産職の勤続年数が短いなど、それらとは相反する事実も見いだされた。こうした点の一層の解明は、今後の課題だとしている。
玄田有史「『資質』か『訓練』か?」
統計データに直接現れる労働者の属性の違いを調整しても、なお大きな企業規模間賃金格差が残る。それは、統計データには直接現れない労働者の「資質」の違いなのか、企業が提供する「訓練」機会の違いなのか、それぞれの定量的ウェイトを測定するのが目的。
理論モデルは次のような前提から出発する。[1]大企業では採用に際し、ある最低能力水準を課し、採用された労働者には職場訓練を行う。[2]一方、小企業では、採用にあたって最低能力水準を課すことはなく、また職場訓練も行われない。[3]ただし、小企業労働者のうち、大企業の最低能力水準を満たすものは、途中で大企業に中途採用される。こうした中途採用労働者は、大企業の生え抜き労働者に比べ、職場訓練を受けていない分ハンディを持つ。したがって、職場訓練終了後の大企業労働者の賃金と、小企業から大企業に中途採用された労働者の賃金差は「訓練」機会の違いを反映している。一方、小企業から大企業に中途採用された労働者と小企業に残った労働者の賃金差(この言い方は論文のモデルと異なり不正確ですが、より直感的なのでとりあえずこうしておきます)は、大企業による中途採用が能力を基準に行われるなら、労働者の「資質」の違いを反映している。
実証分析では、主として「雇用動向調査・入職者票」(1992年上期)のマイクロ・データを用い、小企業から大企業への転職確率、転職による賃金変化などの推計を行い、上記理論モデルの主張に基づき、賃金格差のうち、「訓練」機会の違いによる部分の割合、「資質」の違いによる部分の割合、その他、を算出している。
その結果、[1]「資質効果」は規模間賃金格差のうち半分もあればいいほうで、多くの場合「訓練効果」が凌駕していること、[2]「資質効果」が比較的高いのは中高年、低学歴、生産労働者で、[3]「訓練効果」が高いのは大卒、事務労働者であること、等がわかった。
- 奥西
-
賃金構造の関係では、マイクロデータとか複数のデータをマージして用いたもの、それからスイッチングモデルなど新たな計量手法を用いたものなど、ここ数年間すぐれた実証研究が数多くあらわれたと言ってよいと思います。駿河さんのセクションで取り上げられたいくつかのすばらしい論文も含め、本来取り上げるべき論文は数多いと思いますが、議論をあまり拡散させないために、ここではいずれも規模別賃金格差についてそれぞれ異なる視点から新たな光を当てた石川・李論文と玄田論文の二つを取り上げてみたいと考えました。
このうち石川・李論文は、二つの統計データをマージして、これまで計量的な分析のほとんどなかった下請の賃金効果を非常に丁寧に検証した統計的研究です。一方、玄田論文は理論と実証の双方を含んでおり、そして何よりもテーマが企業規模間の賃金格差における労働者の能力要因と、企業が提供する訓練機会要因の定量的測定というきわめてチャレンジングなもので、話題性も非常に大きいと思い、取り上げたわけですけれども、いかがでしょうか。
討論
- 駿河
-
両方の論文ともこれまであまり分析対象とされてこなかったような問題にメスを入れていて、非常に意欲的な作品だと思いました。しかも、個票を他のデータとマッチして使うというのはちょっとひねったというか、高級な使い方をしていまして、おもしろいと思いました。反面、こういう賃金構造の分析では、もはや個票を手に入れないといい論文ができなくなったのかなという感じがします。そういう意味で、個票にアクセスできない人には非常にハンディがあるという気がしました。
- 奥西
-
それは同感ですね。
- 駿河
-
それで、最初の石川・李論文なんですけれども、これは要するに専属タイプの中小下請企業は賃金が安くなってしまう。それでいて、均等化差異からは説明できない。純粋に賃金が安くなるんですけれども、これは収奪理論から出てくる結果を支持しているというふうに見ていいですか。
- 奥西
-
その辺について著者の言い方は慎重ですけれども、私の受けた印象では、そういったことが起きているんじゃないかというふうに読み取れたんですけれども。ただ収奪というのは一種の不均衡現象ですが、それがなぜあるかという点は最後の結論部分で説明しています。女子の生産労働者についてはマーケットが狭くて、自分のすぐ近くに就業機会があれば、均衡賃金より低くても自分の留保賃金より高ければすぐそこに行ってしまっているんじゃないか、ただ、今後はモータリゼーションの普及等で、そういったことはなくなるだろうという言い方をしています。
- 駿河
-
女子はある程度わかるんですけれども、男性側にもかなり残っていますよね。
- 奥西
-
ええ、そうですね。男子の生産職の場合は、専属下請と下請じゃない中小企業を比べると、8ポイントぐらいマイナス効果がありますね。
- 駿河
-
それが残っていますから、中小企業関係の労働市場というのは、需給が均衡して賃金が決まっているという印象が強いので、どうして専属タイプ下請の賃金の安さが生じているのかというところが、依然として不明のまま残されていると思います。
- 奥西
-
ええ。新古典派的に言うと理解しがたい現象です。制度学派的な人にとっては都合がいいといいますか、専属タイプの場合は「ほら、見たことか」という結果にはなっていると思うんです。
- 駿河
-
制度学派的というのはやはり収奪が起こっているんだということですか。
- 奥西
-
ええ。能力があるにもかかわらず、悪い仕事に閉じ込められているんだと。なぜそういうことが起き、かつ存続しているのかということは、私個人としては別途説明されるべきと思っていますけれども。
- 金子
-
ただ、この均等化差異から解釈するというのは、いわゆる収奪仮説の理由は適合的だと言うんですけれど、データを使った時点が1987年だけですよね。だから、バブルの始まりか直前ぐらいですか。
- 奥西
-
むしろ製造業については円高不況期と言ったほうがいいでしょうね。
- 金子
-
そうすると、逆に好況期と不況期で、下請関係あるいは下請に出したときの値引き率とかが変わってきますよね。
- 奥西
-
それは大いにおもしろい点で、今後のテーマだと思いますね。
- 金子
-
少なくとも2時点をとってきてやる必要がある。もちろん先ほど駿河さんが言われたように、個票から出したものだけがこういう分析ができる時代になってしまったということで、データを整理すること自体が重要で、お二人も二つの個票をマッチさせる努力をしたと思うんですけれども、今後の発展の方向は少なくとも2時点で比較することだと思います。
- 奥西
-
ところが、残念ながら通産省の調査は1987年が最後です。したがってその前の時点のデータをとるということでしょうね。
- 金子
-
そうですね。下請の関係は二重構造の分析で、数量経済史的な観点から見れば、いくら過去にさかのぼってもいいわけですよね。この二つの仮説というのは、数量経済史的なフレームワークで分析してもおかしくない仮説だから、過去にさかのぼってやってみても意味がある。
- 駿河
-
そうすると、金子さんの意見では、専属タイプの下請の賃金のほうが景気の波にさらされやすいという仮説になるんですね。
- 金子
-
ええ。
- 奥西
-
それが1987年は円高不況の最中だったから、特にしわ寄せが来ていたと。逆に、好況期には賃金も上がっていた可能性があるんじゃないかということですね。それは非常に興味深い視点だと思います。
- 駿河
-
しかし、逆に言えば、親会社があるわけですから、むしろ下請になっているがために、賃金が安定するということは言えないんですか。専属でないために、サポートするところがないから、余計景気の波をかぶるのではないですか。
- 金子
-
金融面に留意すれば、駿河さんの言うことが当てはまるかもしれません。下請に入り、系列に入っていると信用が高まるから不況期で資金繰りが悪くなっても資金が借りられる。賃金は債務ですから、賃金を下げなくてもすむような債務の資金調達能力が下請企業にはあるということを考えれば、もしかすると親会社との関係を持つことによる信用がバッファーになっているかもしれない。先ほど、2時点で比較すればといいと言ったんだけれども、今言ったメカニズムまで比較しようとするならば、さらに一工夫しなければいけないです。資金のフロー、系列かつ金融の関係まで考慮しないといけないかもしれない。
- 奥西
-
でも、いずれにしても2時点を比較すれば、金子さんの言っていることが正しいかどうかがわかります。
- 駿河
-
石川・李論文についてはそのぐらいでよろしいですか。
次に、玄田論文にいきましょうか。
玄田論文はわれわれの考えている通説を覆すもので、普通、規模間格差というとき、どちらかというと訓練差より能力差のほうが大きいんじゃないかというふうに考えていたわけですが、それを完全に覆す結果になっている。もう一つは、われわれの常識で言えば、小企業から大企業へ移るケースはきわめて少ないというふうに考えているわけです。玄田さんの場合は、小企業から大企業へ移るデータを使って仮説を検証している。その二つが意外なところです。
ただ、小企業から大企業へ移った人は、玄田論文の26頁の表2の高校卒の事務職であれば、35~39歳はもちろんのこと、50~54歳ぐらいでも約2割弱の人が中小企業から大企業へ移っているという推定結果になっているんです。これはあまりにも高すぎるんじゃないかという疑問を少し感じます。若い人のデータが非常に多くて、それを使って推定しているために、若い人たちのデータから中高年者の転職率が非常に高く出ている可能性はないかなという疑問がありますね。ただし、この計算で言えば、転職率が少々変わっても訓練効果が大きいという結果には全然影響しないんです。
- 奥西
-
先ほども時期のことが話題になりましたけれども、この論文が扱った時期は1992年の上期なんです。そうしますと、労働市場においてはまだバブル景気の余熱があった時期ですので、いわゆる上方移動というんでしょうか、小規模から大規模への移動は、おそらく景気循環的にはかなり多かった時期なのかなという気がしています。玄田さんのモデルでは景気循環の要因は入っていませんから、そのことは理論モデルには影響はないんですけれども、実証分析の解釈で影響が出る可能性があると思うんです。
- 駿河
-
ただ、転職率が少々高く出ていても、先ほど言いましたけれども、訓練効果のほうが能力効果よりも大きいという結果は計算上変わってこないんですね。
- 奥西
-
それはこの理論をそのまま受け入れるとそうなんですが、たとえば非常に景気が過熱して、大企業が中途採用を活発に行ったときに雇い入れる人の能力基準を下げるというようなことがもし起きたならば、解釈は違ってくると思うんです。理論モデルのほうでは、大企業の中途採用者の採用基準はその企業の新卒の採用基準と全く同じであるという前提からスタートして、それをまさにベンチマークとして訓練効果を測っているわけです。だから、その前提を受け入れるならば景気は関係なくなるんですけれども、実際問題としては、おそらく大企業の中途採用者の採用基準はいろいろな要因によって変わるでしょうし、また採用する労働者のタイプも変わっている可能性がありますね。先ほど駿河さんのセクションで非正規従業員の増大ということが出ましたけれども、正規の内部昇進型として採用するのか、あるいは間接補助的な役割として採用するのか、その構成はいろんな環境要因によって変わると思われますね。だから、実証結果を理解するときにはその辺の注意が要るのかなという気はするんです。
- 駿河
-
大企業が採用した人をそのあとどういうふうに使用するのかというのが、このデータだけでは不明です。
- 奥西
-
もっとその辺の情報が提供されると、より結果の解釈がしやすくなるように思います。
- 駿河
-
結局、小企業から大企業へ転職した人は、一体どういう人なのかという情報がもう少し欲しいということですね。
もう一つは、移動したときの賃金上昇が規模間の賃金格差に比べると低いというところが結局、結果に効いてきています。規模間賃金格差のほうは「賃金構造調査」でとっていて、これはかなり精密です。それに対して「雇用動向調査」の移動ではどのぐらい賃金が上がったかのデータは割と雑ですね。その問題が一つあるのかなと思います。
それと、一番大きい問題は、中途採用をした人に対して企業はどういう賃金の支払い方をするのか。この論文では、一応能力に応じた払い方をしているというふうになっていますけれども、それまでいた人に比べると新しく採ってきた人の能力というのはもう一つ不明なわけですから、能力より多少低い賃金を払うという可能性はあります。これまでずっといた人とポンと入ってきた人と同じ賃金を払うというふうにすると、中にずっといた人のインセンティブが損なわれるという意味で、移動した人の賃金が能力に比べるとやや低めに抑えられるんじゃないかということが考えられると思います。
- 奥西
-
今、言われたことは二つあると思うんです。一つは、中途採用労働者の能力が実際には採用側の企業にとって十分わからないんじゃないかという点と、もう一つは、玄田さんのモデルでは個々人の能力が生産性を決め、その生産性が賃金を決めているという基本的前提が一貫してあるわけですけれども、賃金決定については人で決まっているんじゃなくて、仕事で決まっているとか、あるいはインセンティブの観点から何らかのプレミアムをつけている可能性があるという点ですね。たとえば効率賃金仮説やインサイダー・アウトサイダー理論などがありますけれども、そういう可能性は玄田さんのモデルでは最初から排除されているわけです。玄田さんのモデルの中ではそれでいいわけですけれども、実証分析の結果をどう解釈するかというときには、やはり別の解釈の余地も残されていると見たほうがいいんじゃないかという気はします。
- 金子
-
賃金は人で決まるのか仕事で決まるのかという二つの観点があって、後者の解釈の余地、仕事で決まるという説明もあるのではないかと奥西さんは言われたけれども、パート労働に関してはどちらか一方の立場を支持する結果にはなっていないように思います。この論文では、従来の正規から正規への転職の分析と同時に、パート労働者同士が転職したときの効果を分析しています。この辺が玄田さんの分析の守備範囲の広さを感じさせるところで、パート労働者についても高校卒の生産職の転職率と賃金変化率を用いて賃金格差の要因を資質と訓練の効果に分解しています。規模間で職場訓練に基づく賃金格差があること、規模間のパートの資質に基づく賃金格差が小さいような結果になっている。前者は賃金は人で決まるという見方を支持するけれども、後者は賃金は仕事で決まるという説明の傍証になりますからパート労働市場に限っては、同質的な労働市場をつくっているということを実証しているとも言えます。
- 駿河
-
説明変数としてパート、一般労働者を分けて、それからいろんなタイプの職種という変数が入っていますね。
- 金子
-
それは小企業からの転職者の大企業転職率と賃金上昇率の推計式の変数についてですね。従来、パート労働者の実証分析は、そのほかの正規雇用労働者の分析と分けられていた面が強かったんですけれども、玄田さんはこれを同一のフレームワークでやっている。ただ、奥西さんのコメントに対しては、男子パート労働者として建設業や保安業のような厳しい労働条件のパート労働を対象に含める場合には、たとえ大企業でのパートになったとしても補償差額賃金の効果を含める必要は出てくるかもしれません。そのかぎりでは奥西さんの批判は当たっているんじゃないかなと思うんです。
- 駿河
-
それから、玄田論文の表2ですけれども、訓練投資の差が規模間賃金格差にとってものすごく重要であり、よりウェイトが高いとなると、訓練投資の貢献ウェイトは年齢が高くなるほど大きくなるんじゃないかという気がするんですけれども、むしろ反対に、若い人ほど訓練投資が規模間賃金格差に対する貢献が大きいという結果になっていますね。これは、ちょっと矛盾しているような気がします。いずれにしても、今まで計量的にはまったく扱っていなかった規模間賃金格差は一体どういう要因によるのかというのを、チャレンジングに要因分析したのは非常に価値があって、今後発展が望まれますね。ただし、データがなかなか手に入らないという問題があります。
- 奥西
-
これは今回、読んだ中では最も興奮したものの一つで、理論仮説は大胆、実証分析は緻密という非常に魅力的な論文だと思いました。今後のいくつかの方向を言うとすれば、先ほどの繰り返しになりますが、果たしてどういう人がどういうときに移っているのかという情報がもうちょっと欲しいし、またそれを理解したいなということを感じました。あとは特に大企業側の採用行動の分析ですね。
5. 昇進・査定・技能・移動
論文紹介(奥西)
有賀健、ジョルジョ・ブルネッロ、真殿誠志、大日康史「企業ヒエラルキーと人的資本形成」
まず、労働市場を、技能形成と作業編成の仕組みの違いから「内部労働市場」タイプと「職能別労働市場」タイプの二つに分け、それぞれで企業組織、採用、昇進、賃全体系等がどう異なるかを、定性的に、ついでモデル分析により明らかにしている。たとえば、「内部労働市場」タイプ企業では、昇進時期が遅れ、能力の昇進確率への効果が小さい、複数の職務に必要な技能を習得する。一方、「職能別労働市場」タイプ企業では、昇進時期が早く、(資格など客観的な)能力指標の昇進確率への効果が大きく、キャリアを通じて単一の職務に特化した技能形成が行われる。
上のようなインプリケーションのいくつかに関し、2種類の実証分析を行っている。一つは、『別冊中央労働時報(労働委員会審決)』に含まれる4社の昇進の分析、もう一つは、「賃金構造基本統計調査」を用いた職種別賃金・勤続プロファイルの推定である。
前者の分析からは、「内部労働市場」タイプ企業では「年功」的要素が昇進にプラスに働くが、「職能別労働市場」タイプ企業では逆なこと、そこではむしろ外部の公的資格などが有効なことを見いだしている。後者の分析からは、「内部労働市場」タイプの職種(勤続年数が職種経験年数を上回る)では賃金-勤続プロファイルの勾配が急だが、「職能別労働市場」タイプの職種(職種経験年数が勤続年数を上回る)では賃金・勤続プロファイルの勾配が緩やかなことを見いだしている。
伊藤秀史・照山博司「ホワイトカラーの努力インセンティブ」
いわゆる「インセンティブ理論」では、企業の賃金、昇進、評価制度等が、労働者の努力水準を高めるべく設計されていると論ずるが、果たしてこうした理論が現実に妥当しているかどうかを、労働者に対するアンケート調査(連合加盟民間大手5組合の組合員および管理職約2000人が対象)に現れた彼らのパーセプションを変数に用いて検証したもの。
分析の第1は、労働者の努力水準を被説明変数に、同じ企業内の競争相手との賃金差、労働者の賃金への反応度、業績評価の賃金への反映度合い等を説明変数としたモデルの推計。結果はおおむね、ベーシックな理論に整合的で、たとえば、賃金への反応度が大きい労働者は努力水準が高く、かつ賃金差が大きいほど、また、業績評価の賃金への反映度合いが高いほど努力水準が高まる。さらに、将来の昇進可能性も努力水準を高める。
分析の第2は、賃金プロファイルの議論でおなじみの賃金と生産性の関係についてである。やはりアンケート調査を用いて、賃金と貢献度(業績)との関係を分析し、5社中3社で、勤続が短いうちは賃金が貢献度を下回る傾向が見られた。ただし、賃金と貢献度のギャップと勤続との関係は概してそれほど強くなく、ラジアー流の「後払い賃金プロファイル」が支持されたとは必ずしも言えない。
いわゆる「インセンティブ理論」のいくつかの基本的前提が、少なくとも労働者のパーセプションのレベルでは、それなりに確認された。
- 奥西
-
次に昇進・査定・技能・移動のほうですけれども、賃金同様、非常にいい研究がたくさん出ています。個別企業のデータ等を用いた実証研究がいくつかありますし、かなり先端的な理論研究もあらわれています。おそらくここ数年の日本の労働経済学の中で先ほどの賃金構造も含めて昇進関連は大きな収穫のあった分野の一つと言っていいのではないかと思います。したがって、多数の論文の中からどれを取り上げるかというのはきわめて難しいのですが、ここでは有賀ほか論文と伊藤・照山論文の二つを取り上げてみました。
有賀ほか論文は、理論と実証の双方を含み、サーベイ的な性格も持っております。それから、昇進だけではなくて、ほかの雇用制度との関連を扱っておりますし、さらに企業間で雇用制度がどう違うかも分析しています。いわゆる日本的雇用慣行論では、あたかも日本の企業がすべて同じような制度を持ってやっているような誤解を招きかねない議論が多いわけですが、かなり明示的に企業間の雇用制度の違いといったことを意識して分析しています。それから、最近の流動化論等とも一定のかかわりがあります。そういった点から議論してみてはどうかと考えたわけです。
一方、最近の昇進や査定をめぐる中心的な理論といえば、何といってもいわゆるインセンティブ理論で、その中身はいろいろですけれども、それに触発されていろんな研究が出ていますので、伊藤・照山論文を取り上げてみたわけです。ただ、これは通常の経済分析とは少々色合いが異なります。というのは、アンケート調査を用いているんですが、その中で従業員の意識について尋ねた部分を変数として主に用いているのです。たとえば努力については、与えられた仕事以上にやっていると思っているかどうかとか、労働者にとって賃金が仕事のやりがいを決める上でどの程度重要と認識されているか、といったことです。実証的な経済分析というのは、一般に、労働者なり企業の具体的な行動の結果として選択された変数に焦点を当てるのですが、ここではかなりの程度、意識面を直接尋ねた変数を用いているという点に特徴があります。
討論
- 金子
-
伊藤・照山論文は実証分析の前提にモデルを提示していて、とても示唆に富む研究です。ただし、分析のフレームワークでヘドニック賃金アプローチみたいなものは使ってないわけですね。従業員の意識というとき、主観的な賃金の評価をしているという考えがどこかあるわけで、モデルをつくるとき、推計式を導いてくるときになぜそれを使わなかったのかなと思うんです。
- 奥西
-
このアンケート調査がどういう調査だったかがわかる質問票のようなものがついてないのでわからないんですが、実際の賃金額は聞いてないんじゃないでしょうかね。
- 金子
-
仕事の貢献度として努力を挙げていますが、努力を要する理由には、会社の勤務時間の厳しさや有給休暇の取りやすさや職場環境などの仕事属性があるはずです。そう考えると、貢献度と従業員が比べる賃金はヘドニックアプローチのような主観的な賃金になると思うんです。それから、業績評価するときの企業も仕事属性の割にはよく働いているいないという具合にヘドニックアプローチのような賃金を提示すると思う。推計式を導いていくときのきちっとしたフレームワークがよくわからなかったんです。
- 駿河
-
ヘドニック賃金アプローチでは、具体的にどういうふうな変数が要るかを説明していただけますか。
- 金子
-
伊藤・照山論文は推計作業の前にもモデルを提示していますから、これと関連させるとこうなります。仮に仕事属性を表すベクトルをZとすれば、仕事属性の割には貢献した、しないと判断する企業が提示するヘドニック賃金はW=W(Z)となるとします。企業は賃金を業績に依存させることができると言っていますから、業績が高いときの賃金WH(Z)、業績が低いときの賃金はWL(Z)と表せます。一方、労働者の不効用が立ちっ放しの仕事など仕事属性に依存していると思えるから不効用の費用関数のうちRという項が仕事属性に関係するようになる。つまり、C(e)=e2/2R(Z)と表せると考えられます。企業の提示する賃金と努力水準eを選択したときの均衡条件をこうした考え方で修正してみると労働者の努力水準の決定条件は、
e=R(Z)×[WH(Z)-WL(Z)]
となるのではないか。奥西さんの言われたようにこのアンケート調査のデータには制約があったのかもしれないけれど、ヘドニックアプローチの考え方でモデルがつくれたのではないかと思うのです。
- 駿河
-
企業側のデータが入ってない。企業要因は単にダミー変数で吸収されているという形になっていますけれども、各企業のいろんな制度であるとか、それに関連する変数も入れてきたほうがいいということですね。
- 金子
-
発展方向としてはそう思います。インセンティブ理論のいくつかの基本的前提が、少なくとも労働者のパーセプションのレベルでは、それなりに確認されたと、奥西さんが「それなりに」とおっしゃっている理由がよくわからないです。
- 奥西
-
完全にではないにしろ、ある程度まで確認できたということですよ。といって、完全否定でもないという意味です。
- 金子
-
主観的なことを聞く心理学の立場に立つと、主観的な調査項目を使う分析がこれでいいのかなとは思うんです。
- 奥西
-
その辺の限界は著者も最初のところで断っているんですが、有益な情報を与えていることは確かだと思うんです。ただ、問題は、一方で企業側が賃金、昇進、評価といった制度を設計するわけですが、そのときどういう考え方で設計するのか、それに対して労働者はどういう考えを持ち、実際にどう反応するのか、企業はまたそれをどこまで予測しているのかといったように意識や行動にもいろんなレベルがあって難しい。おそらく心理学の分野では、この手の分析はもっとたくさんあるんだと思うんですが。
- 金子
-
たとえば、心理社会的構造方程式アプローチとかいうのがあります。
- 奥西
-
そういったものが、車の両輪のように進むというのが本来あるべき姿かもしれません。
- 金子
-
心理学的に言うと、インセンティブの理論に似ているんだけれども、エンビー(envy)という概念があって、レラティブ・ディプライベ一ション(relative deprivation)の実証分析があります。ある平均あるいは相手と自分を比較して、自分は満足している、やや満足しているという点数化したようなデータがあれば努力の分析にも応用できるんだろうけれども。
- 奥西
-
そうした分析は心理学ではかなりありますね。心理学の場合は実験も凝っていて、わざとサクラを使っていろんな操作をするとか。報酬とインセンティブの研究は心理学の分野でもかなりあるので、そういう研究と経済学的なインセンティブ理論はどこが合うのか合わないのか、その辺を詰めるのも、この分野の今後の一つの方向性かなという気がします。
- 駿河
-
どういう問いかけをするかということ、それから問いかけに対してどういうふうに答えるのかが問題です。問いかけを変えれば答えは変わってきますね。先ほど言われたように、答える人が比較をどこに置いているかという問題もありますね。与えられた職務と自分の会社への貢献の二つを比較するにしても、同じ職務の人と比べているのか、地位の上の人と比べているのか、下の人と比べているのかといろいろ比べ方があります。自分は会社に職務以上に貢献しているかどうかを判断するのにいろんな基準があるので、結果の解釈はなかなか難しいと思うんです。ただ、努力水準は簡単には計測できないですから、そういう意味ではおもしろい試みという気はします。努力水準は個人の判断と上司の判断で、大分異なっている可能性はありますね。
- 奥西
-
特に賃金と貢献の関係なんかは、本人ではなく上司や人事に聞くと逆の結果が出るかもしれませんね。
- 金子
-
年俸制の企業の割合が少しずつ増えてきているけれども、インセンティブにどういう影響を与えるかというのは、このフレームワークで分析できるのかもしれない。それは将来、時間がたてばもっと細かい分析ができるかもしれないですね。
- 駿河
-
それは賃金格差がどのくらいついているかという説明変数が入っていて、一応やっているんじゃないかと思うんですが。
- 金子
-
いえ、年俸制に限った分析です。雇用管理や賃金体系の変化の議論では年俸制に注目することが多いだけに、インセンティブと年俸制の関係に範囲を限定して、伊藤・照山論文のような分析がされてもいいのではないかと思います。
- 駿河
-
分析の中で賃金に反応する人としない人、これが分かれていて、賃金に反応する人だけに賃金の格差が効いているという結果になっているんですけれども、賃金に反応する人としない人はどのぐらいの割合なんでしょうね。賃金に反応しない人が多ければ、インセンティブがさほど効かないということになります。
- 金子
-
その場合は年齢によっても違うんでしょうね。
- 奥西
-
有賀ほか論文のほうはいかがですか。
- 駿河
-
有賀ほか論文というのは、昇進パターンの違いを上位職種への人的投資と下位職種への人的投資の代替が職業によって異なるとして、昇進を人的資本理論の視点から説明しようとしているという点がおもしろいと思います。大体、われわれは、昇進パターンをどちらかというとインセンティブの理論のほうから説明していますので、こういうふうに人的資本理論から説明しているというのは非常におもしろいと思いました。本文に例がありますけれども、電車の車掌の訓練をしながら、将来運転士になったときの訓練もしているというわけです。プログラマーをやりながらSEの技術を磨くとか、経理の事務をしながら経理の課長のための訓練投資をしている。両方の職種の人的資本の訓練の代替度が高いほど、より内部昇進型になるということを言っているんですね。
銀行業を分析した冨田論文の場合、年功が昇進に非常に効いてくる、それに対して大竹論文のエレベーターの保守点検であれば年功が昇進に効かないという結果を出していますから、この二つの結果を統一的に説明できています。
ただ、銀行とエレベーターの保守点検業の昇進に関する結果の違いを、インセンティブ理論からどのように説明するのか知りたい気はします。
また、ホワイトカラーの職種でも、たとえば大卒の数が非常に少ないようなときには、いろんな職種を短期間順番に回って広い範囲のジョブローテーションをして、上位職種の訓練を初めから行う。大卒でない人は、狭い範囲のジョブローテーションで低い職種の訓練を受ける。ホワイトカラー職種でも、大卒が少ないときは上位職と下位職では分離した訓練の仕方をしているわけです。だから、かなり供給側の要因にも依存しますし、現在は大卒がものすごく増えて、だれか特定の人に上位職種専用の訓練ができないというふうに考えると、訓練法にインセンティブの要因もかなり効いてきているという気がしたのですが。
- 金子
-
モデル分析の結果を全部検証したことになるんでしょうかね。
- 奥西
-
いや、全部ではなくて、その中のいくつかのインプリケーションということですけれども。
- 金子
-
ILM型とOLM型を区別する基準となる昇進の機能や技能形成の関係などについて立証すべき仮説を導くことができるモデルを上手につくっていると思うんです。上位のランクと下位のランクの労働サービス供給は交差項が入っているけれど、人的資本と能力の線型関数として特定化して、一方投資費用は2次関数とすることによって最適化条件が求められるといった具合にモデルのつくり方がすごく適切であると思うんです。従来、インセンティブとか、内部市場論、外部市場論とか、あるいは内部型市場をさらに類型化していろいろ行動分析をすることはありました。そのインプリケーションを言葉で書いて、さらに実証分析するということが多かったけれども、有賀ほか論文が企業の利潤最大化行動からきっちりモデルをつくり上げているところでは、経済学的に非常に強固、あるいは信頼に値するような分析手法だと思います。
あともう一つは、ここで取り上げられた分析はもともとは海外でも読まれる英語の学術雑誌ですよね。最近の傾向は、日本の学者が日本の計量分析をするにあたって日本の実情を海外の学者に知ってもらいたい、あるいは海外の学者と共同研究したいという目的で、英語の学術雑誌に発表することがしばしばあります。労働経済の分野でも最近は大分英語論文が増えました。有賀ほか論文も、 Journal of the Japanese and International Economics に発表されたものです。そういう意味で、研究のスタイルあるいは研究成果の発表の仕方、情報交換の仕方が1990年代に入って一層国際化しました。
- 奥西
-
私もこれは非常にうまくまとめており、好論文だと思いました。
6. 家族構成と就業行動
論文紹介(金子)
駿河輝和「日本の出生率低下の経済分析」
日本経済の高齢化や将来の若年労働者不足の要因として出生率の低下が認識されるようになり、大きな社会問題として議論されるようになった。出生率の低下の背景には、男女の結婚観の変化、晩婚化、あるいは女性の高学歴化に伴う就業率の上昇などの要因が指摘されている。この論文は、こうした要因のうちベッカーの家族の経済学に基づいて導かれる経済的要因が出生率にもたらす影響が認められるかどうかを、実証分析している。
まず、戦後日本の出生率を経済学的に実証分析した研究をサーベイし、Osawa(1988)や大淵(1988)が使用したButz-Wardモデルは、女性が一定年齢で結婚する率は時代が変わっても変化しないと仮定していることに留意すべきことを指摘した。なぜならば、この仮定は、1970年以降のわが国の晩婚化と一致しないからである。1970年代以降、20歳代後半と30歳代の男性、および20歳代後半と30歳代前半の女性の未婚率が上昇している。したがって、このような仮定に依存しない推計式として、原田・高田(1991)と同様に、ログ線形の推計式を用いている。
推計式の被説明変数は、合計特殊出生率であり、説明変数はベッカーの家族の経済学によって出生行動と関係づけられる男子現金給与総額、女子時間当たり賃金、および子供の直接的費用に関する変数と女子の雇用機会に関する変数である。時系列データの回帰分析の推定期間は、晩婚化や少子化が現れ人口再生産出生率を合計特殊出生率が下回るようになった時期を含む、1971年から88年である。推定結果は、家族の経済学の予想するとおり、男子現金給与総額の係数は正で有意、女子の時間当たり賃金は負で有意となった。これから、男子の所得の上昇が結婚の魅力を高め出生率を上げる傾向があること、女子の賃金の上昇は出産育児の機会費用を高めるため出生率を低下させることが確かめられた。
松浦克己・滋野由紀子「日本の年齢階層別出産選択と既婚女子の就業行動」
従来の分析では、女性の就業行動を分析する場合には、出生行動から独立した就業関数を推定していた。また、女性の出生行動を分析する場合には、就業行動と出生行動が同時に影響することを前提として推定を行っていた。これに対して、この論文は、1989年の「家計調査」と「貯蓄動向調査」の個票データを用いて、既婚女性の就業行動と出産行動が同時決定かどうかを年齢階層別に検討し、同時決定が認められる年齢層についてはbivariate probitモデルを適用して出産関数と就業関数を推定し、同時決定が認められない年齢層については出産関数と就業関数それぞれにプロビット・モデルを適用して推定を行った。
出産関数と就業関数の定式化は、駿河輝和(1995)等と同様に、Becker (1965)、Willis (1973)に依拠して説明変数を選択するとともに、遺産動機を考慮して家計の資産も説明変数に加えている。
年齢階層別に既婚女性の個票データを選択したbivariate probitモデルの推定結果によれば、25~29歳層で出産行動と就業行動の同時決定性が認められたのに対して、35~39歳階層では同時決定性が認められなかった。したがって、25~29歳層についてはbivariate probitモデルで就業関数を推定し、35~39歳層についてはプロビットモデルで就業関数を推定した。このような同時決定性の有無を考慮した既婚女性の就業関数の推定結果は、Beckerの家族の経済学が示唆するとおり世帯主(夫)の所得の係数が負で有意、既存子数が負で有意となったの対して、正味資産の係数が有意とならず遺産動機については検出できない結果となった。
- 金子
-
なぜこれらの論文を選んだかという根本の視点は、長期的な日本経済の見方の変化です。最近まで労働力不足が非常に真剣に取りざたされており、重要な研究課題でもあった。それが一転して、景気がなかなかよくならない。しかも、高齢化が進む。そこで将来をいかに考えるかということがごく普通に認識されるようになったわけです。
特に重要な認識の変化は、高齢化の原因を考えるようになったことです。言いにくいことなんだけれども、将来の若年労働力をどう確保するか。高齢者の数が増えていくということは既成事実で、これは変えられないというわけです。高齢化をとめなくていいんだ、人口減少をしてもいいんだという人もいるんだけれども、経済を成長させる、あるいは経済を安定化させるためには、新古典派の理論でも明らかなように、人口成長率がプラスでなければ、1人当たり国民所得や1人当たりの消費が均斉成長経路に維持されるということがありえないわけです。景気後退を回復させ、若年者や高齢者の失業を抑えながら経済成長を持続させようとすると、どうしても、今までタブーに近かったことを検討しなければいけない時代になってきた。
将来の若年人口をどうするかということを考えると、子供の問題が表面に出てくるようになった。そうすると、出生率と経済問題というのを結びつけざるをえない。これは、男性の口から言うのは非常に難しい問題なのだけれども、やはり人口構成の変化と労働問題、あるいは人口問題と長期的な労働市場の動向が深くかかわりあっていることを認めざるをえなくなってきて、かつそれを研究対象にする必要が出てきた。今までも研究対象になっていたんだけれども、大手を振っては研究できなかったんですね。しかし、将来の人口、労働力人口を考えると、子供の問題と労働の問題を関連させて考えざるをえない時期に来たと私は考えるわけです。もちろんこれを批判する人もいますが。
ベッカー流のモデルをいくつか実証してきた人もいるんですけれども、駿河論文が的確に指摘しているように、外国の文献をそのまま持ってきてもいいわけではない。日本の人口構成の変化を踏まえて、外国の研究者が使っている前提が、日本の前提と合致しているかどうかを吟味してからでなければ使うべきではないというわけですね。駿河論文は、この視点からサーベスターの推計式が日本の晩婚化に適切な推計式であることを確かめたうえでベッカーの家族の経済学のインプリケーションが、日本の時系列データにこの式を当てはめた場合に出てくるかどうかを吟味しています。人口構成の変化を慎重に処理しながら、家族の経済学の妥当性を検証しているという意味で、駿河論文を取り上げました。
次に、計量経済学的な問題になるのかもしれないんですけれども、出生行動と経済的な変数が関係しているとするならば、経済的な変数に賃金や所得が入ってきますね。たとえば、夫の所得と女性の賃金が変数に入ってくる。そうすると、簡単な労働供給関数を考えれば、女性は賃金が上かれば働くということになるし、ダグラス=有沢の法則を考慮すれば夫の所得が高くなれば女性の労働供給は減ることになります。女性の出生行動が賃金に依存しているならば、同様に労働供給のほうも影響を受けているのだから、女性の就業行動と出生行動が同時決定なのか、まったく別個な問題なのかというのを考えざるをえなくなる。従来、それは別個の問題として扱っていたわけです。ところが、それも計量経済学の発展で、同時決定かどうか個票データと適当な推定方式を用いれば検証できるようになったわけです。
個票データを女子労働分析に使うことについて言えば、冨田論文、育児休業制度を実証分析した樋口論文でも個票データを使っています。松浦・滋野論文は労働経済学的なインプリケーションは弱いと言われる批判があるかもしれないけれども、このような個票データ利用の流れにのって少なくとも就業行動と出産・育児行動の同時決定性について初めて検定したという意味で意義があるので取り上げました。
討論
- 駿河
-
妻の就業は非常に重要な問題になってきますが、育児休業制度や労働時間の短縮といった政策が出生率にどういうふうに影響するのかについて、両方の論文とも全然考慮していないので、そのあたりの分析が今後必要ですね。
- 奥西
-
たしかに、駿河論文にあるように女子の結婚や出産に関する機会費用は上昇してきているのでしょうが、一方であとから出てくる冨田論文が示すように企業の雇用管理のあり方等によって出産・育児のコストを軽減することもかなりできそうですね。となると、それぞれの効果が計量的にどれくらいで、ネットとしてはどうなるのかといった点は興味がありますね。
- 駿河
-
それでは滋野・松浦論文に行きますが、滋野・松浦論文の場合には、一番肝心の妻の機会費用に使っている変数がものすごく弱い。
- 金子
-
弱い。それはデータの制約にもよるので、利用したデータが「家計調査」と「貯蓄動向調査」の個票ですから、所得はあるけれども、賃金率は得られないというわけですね。
- 駿河
-
だから、妻の機会費用の変数として、夫がホワイトカラーであるかどうかという、夫のほうの変数を持ってくるんですね。夫の変数を代理に使ったことがどう影響しているのかというのが問題ですね。
それからもう一つは、これもデータの制約があるのですが、就業についてフルタイムとパートをきちんと分けていないですね。したがって、母親同居であるとか、持ち家と言った変数が効いていない。大体母親同居や持ち家という変数は、どちらかというと、フルタイムのほうに効いてくるんですね。その辺がごちゃまぜになっていて、きれいな結果が出ていないという気がしますね。
それから、推定結果として妻の就業と子供を生む選択の同時推定の結果だけを提示しています。妻が25~29歳のときに同時推定をする必要があると言っているんですけれども、同時推定せずに、おのおの別々に推定したときとどのくらい推定結果が違うのかというのをできれば示してもらうと、同時推定とそうでない場合で、どのくらい係数が違うのかが明確にわかっていいと思います。
- 奥西
-
滋野・松浦論文は、意欲的な計量研究として興味を持って読んだのですが、あえて言えば2点コメントがあります。いずれも、結局はデータの制約ということになってしまいますが。まず年齢層を区切って、それぞれの年齢層ごとに就業と出産の同時決定性を見ているわけですね。ただ、これはパネルデータがないとできないことですが、たとえば25~29歳のときに産む産まないという決定と、30~34歳で働き続けるか続けないかという決定は何らかの関連がある可能性があると思うのです。そういう異なる時期の間の意思決定の関連も見られたらもっとおもしろいと思います。
もう一つは、「家計調査」のデータのことで、著者も脚注で指摘しているんですが、30~34歳で妻が就業している世帯が約200のサンプル中一つしかないというのは、相当すごいサンプルセレクションがあるといういい証拠ですね。おそらく共稼ぎ世帯とか、小さい子供を抱えているところでは、家計簿なんてつけていられないということだと思うんですが。
- 金子
-
答えられないのでしょうね。
- 奥西
-
その辺がバイアスを生む可能性もあるのかな。いずれもこの「家計調査」の範囲内では解決のつかない問題だと思いますけれども、その辺がちょっと気になりました。
- 金子
-
パネルデータがやっぱり必要ですね。逆に言うと、今の労働経済学の研究者、実証研究をやる人たちというのは、やはりパネルデータが欲しいけれども、得られないから、それに限りなく近いものをつくっていく努力をしているわけですね。奥西さんのご指摘のとおり家計の消費貯蓄行動と就業行動を合わせたデータを含むパネルデータの整備が日本でも必要だと思います。
7. 女性の雇用管理
論文紹介(金子)
冨田安信「女性が働き続けることのできる職場環境─育児休業制度と労働時間制度の役割─」
育児休業法が施行された後、育児休業制度が女性の就業行動に及ぼす影響に関する実証分析への関心が高まった。しかし、就業行動に影響する変数として育児休業に関するデータを利用しようとすると、従来は「女子雇用管理調査」の育児休業実施事業所割合など公表データに依存せざるをえなかった。これに対して、この論文では、大阪府が平成5年に大阪府下の企業に対して実施した「女性の雇用・労働の実態と課題に関するアンケート調査」の個票データを用いている。このデータのメリットは、各企業が育児と就業の両立支援をする制度を導入しているかどうかがわかることと、各企業において出産後もその企業を辞めずに働き続ける女性従業員の割合がわかることである。
1994年時点では、育児休業法の適用が30人未満の事業所では免除されていたので、冨田は30人以上の従業員規模の事業所を対象に、実証分析を行った。被説明変数は女性従業員に占める出産後も働き続けている人の割合をロジット変換した値である。説明変数には、育児休業の実施状況のみならず、育児休業制度の設立時期、および育児に有利な雇用管理をもたらすと考えられる伸縮的な労働時間制度と福利厚生制度(事業所内託児所の有無)に関する変数を加えている。
推定結果によれば、育児休業制度と事業所内託児所の実施に関する変数の係数はそれぞれ正かつ有意であり、短時間勤務制度と半日単位の有給休暇制度の実施に関する変数の係数もおのおの正かつ有意であった。これに対して、フレックスタイム制度の実施に関する係数は有意ではなかった。また、設立時期が早いほど出産後就業継続している女性従業員の比率が高くなる結果が認められた。したがって、育児休業制度が伸縮的な労働時間制度の一部として位置づけられる以上、労働時間を伸縮的にする女子雇用管理を含めた育児と就業の両立支援をする職場環境づくりは、女性の就業希望とも一致する効果をもたらす好ましいものであると結論している。
樋口美雄「育児休業制度の実証分析」
男女雇用均等法の施行により、女性の長期就業を求める雇用制度の整備が進められた。長期就業のためには定着率の上昇が必要であり、育児休業制度を含めた労働時間の柔軟性確保のための政策はそのための施策である。育児休業制度は、子供を持たずに就業継続するかそれとも就業を辞めて育児に専念するかという選択肢に加えて、育児と就業を両立させて継続就業するという第3の選択肢を、女性に用意することを目指した制度である。この論文は、このような目的を持つ育児休業制度が女性の就業行動に効果を及ぼしているかどうかを、1987年の「就業構造基本調査」の個票データを用いて実証分析している。
1987年は育児休業法施行前であるが、「女子保護実施状況調査」により24産業分類の育児休業実施事業所割合のデータを「就業構造基本調査」のデータと組み合わせることによって、育児休業の普及が女性の継続就業確率を上昇させるかどうかを検証することができる。学校卒業後少なくとも1度は正規雇用者として企業に勤めたことのある25~29歳の女性の個票データによる継続就業率関数の推定結果から、育児休業実施事業所割合が高いほど継続就業確率が上昇することがわかり、育児休業制度はその目的を果たす効果を持つと考えられる。
三谷直紀「均等法施行後の女性雇用」
男女雇用均等法が施行されて10年が経過して、同法が女性の雇用管理や就業行動に具体的な効果を及ぼしているかどうかについて関心が高まっている。この論文は、まず、雇用管理上の男女差別を説明する統計的差別理論の帰結が、男女雇用均等法によって男女の取り扱いが均等になったときどのように変わるのかを検討し、この検討から予想される女子雇用管理の変化が均等法施行前後において生じたかどうかを統計データを用いて検証している。
三谷は、まず、統計的差別理論の前提を認めても、均等法の施行によって男女間の賃金格差が是正されることと女性の勤続年数の増加がもたらされるという結論を導くことができることを指摘して、「労働力調査」と「賃金構造基本調査」を用いて女性の雇用管理の変化の影響を調べた。その結果、[1]女性の労働力率は均等法施行以後も上昇傾向を維持しており、特に20歳代後半と40歳代後半で上昇率が相対的に大きい、[2]若年層を除けば、長期勤続者比率が上昇している、[3]役職者比率は、水準は男子に比べて低いものの、均等法施行後は上昇傾向にあることが明らかにされた。次に、男女間賃金格差については、均等法施行時点の1986年と施行後の93年の「賃金構造基本調査」の個票データを用いて、1986年の賃金関数と93年の賃金関数を推定することによって分析している。二つの時点の推定結果を比較すると、均等法施行後に男女間賃金格差が縮小したのは、学歴計の女性労働者についてみると、100~900人規模の中規模企業だけであった。さらに学歴と企業規模をクロスさせた場合には、大企業の大卒者に関する男女間賃金格差が縮小した結果が認められた。
- 金子
-
女性の雇用管理の方向の一つは、男子と対等に戦力化するということです。この視点は正規雇用でもパート労働の分析でも見られます。この目的のために、男女雇用機会均等法が施行されました。その後、育児休業法が施行されました。育児休業が女性の就業行動にどれだけ好ましい影響を及ぼすかについて、この政策の効果を知るためにも実証分析が必要になります。冨田論文を取り上げた理由は、企業調査であるにもかかわらず、まず企業が育児休業制度、あるいはそうした育児と就業の両立支援政策をしているかどうかを一つ一つ答えられるデータであるということと、それから、出産後も働き続けている人のニーズが企業別にとられているので、育児休業の利用実態を個票データによって把握できるからです。育児休業制度が女性の就業行動に及ぼす影響に関するもう一つの重要な実証研究として樋口さんの研究があります。冨田論文と対比する意味で紹介しました。
ただし、樋口論文で検証された効果は育児休業制度の普及の影響をとらえたものであり、女性雇用者が勤めた事業所に育児休業制度があるかどうか、さらに実際に利用したかどうかなど、個別的な育児休業制度の利用が女性雇用者の継続就業確率に及ぼす効果を近似的にとらえていると考えるべきでしょう。
このような留保をするのは、先ほどの冨田論文では、育児休業を実施しているかどうかを企業別に把握することのできる個票データを用いて、育児休業制度およびこれに関連する労働時間の弾力的運用が女性の継続就業に及ぼす効果を実証分析しているからです。
三谷論文のほうは、継続就業をしている女性雇用者の賃金に対する男女雇用機会均等法の効果を分析しています。終身雇用・年功制で今、見直しをされているのは、賃金プロファイルでそれをどうやって平準化させるかという点です。景気が不透明になって、成長率が下がって、賃金を一方では終身雇用・年功制で寝かせようということですけれども、逆に、今度、男女雇用均等法で女性が就業継続していくときには、男性とともに働き続けるわけですから、賃金は上がっていくはずです。たしかに、統計でサービス業務に見るように、女性については、総合職と一般職に分けて雇用するという慣行がまだある。しかも、総合職が伸びているとはいえ、その割合はまだ高くない面は残っています。こうした男女雇用機会均等法以降の女子雇用管理の変化や実態を詳しく見たうえで、その効果を数量的に把握するものとして男女間賃金格差を取り上げています。つまり、均等法施行前と施行後で、賃金格差が是正されているのかについて、特に注意を促しています。
三谷さんがこの問題を重視している一つの理由は、賃金関係の推定について、今まで精力的な研究をされており、その分析のフレームワークの中で、均等法の効果を実証分析することができるからだと思います。均等法の影響については、女性の意識の面からの分析もできるのかもしれないんですけれども、労働経済学的には、賃金に対する影響で見るのが客観的であると考えられますので、三谷さんのこの手法で、均等法の効果を見るのは正しい方法だと思うわけです。もちろん、アンケート調査で、女性の意識の変化とか、ヒアリングで1人1人の女性の働き方がどう変わったかということを聞くのもいいのですが、均等法施行後10年たったわけで、ここである一定の客観的な尺度で、効果を持っているか持っていないかを判定するという作業は非常に重要なことだと思います。しかも、男女間賃金格差というのは、従来、賃金構造論の中で指摘されていた問題で、特に、今回の学界展望でも、企業規模間格差や下請制のところで、二重構造の問題など賃金格差の問題を扱っていますから、それと同様の観点から、男女雇用均等法の効果を分析したという意味で意義があると考え取り上げました。
討論
- 駿河
-
冨田論文は、データを企業側と労働者個人側の両方からとってきて分析しており、その点がいいと思いますね。結婚でやめる人は、本人あるいは家族が望ましいと考えて選択した結果であるけれども、出産でやめる人は、仕事と家庭の両立が難しかった人だという結果が出て、おもしろいと思いましたね。女性の雇用管理、育児休業制度や労働時間の短縮、人材の育成方法などが既婚女性の残留率を高めるという、ものすごくきれいな結果が出ています。
- 金子
-
そうですね。出産後も働く女子ですから、残留率でしょうね。
- 駿河
-
育児休業制度などの制度が効果的にもかかわらず、データで見ると、育児休業制度を採用している企業が50%もないという結果ですね。
- 金子
-
当時はこの程度の水準でした。
- 駿河
-
ええ、この後で改善されているかもしれない。
- 金子
-
その通りだと思います。30人以下事業規模の適用除外が1994年までで、95年からは、30人以下の事業所でも労使協定で育児休業制度をつくることが育児休業法で強制されるようになるから多分変わっていると思います。
- 駿河
-
これは何年のデータですか。
- 金子
-
平成5年で育児休業制度の採用事業所割合は50%くらいでした。
- 駿河
-
50%以下なんですね。そうすると、現在は相当改善されていると見ていいわけですか。
- 金子
-
ただ、急に効果が出ているかどうか。だから、企業規模間格差が、たとえば中小・零細企業だと、育児休業制度で労使協定があっても取りにくいという状況があるかもしれないんですね。要するに、大企業だったらローテーションしやすいから、代替要員をすぐ見つけられるけれども、中小企業や零細企業で従業員が10人、5人のところで、すぐ代替要員ができなければ、育児休業は取れないわけですね。育児休業制度の効果を分析するときに注意しなければいけない点は、育児休業実施事業所割合と育児休業取得者割合を区別する必要があるということでしょう。樋口さんも、育児休業実施事業所割合を使うことに関しては、いろいろ注意するべきだということを指摘しています。やはり育児休業実施事業所割合は、育児休業をとってもいいよということを決めた事業所の割合なんですね。実際にとれるかどうかというのは、そこの雇用管理、職場の個別企業の職場管理の仕方にも依存する。その点は、やはり実際に、企業ごとに聞いてみないとわからないというので、企業別、あるいは取った、取らないということを労働者本人が答えるように工夫された個票データのほうが、より精度が高くなると考えられます。
「女子雇用管理調査」によれば、育児休業実施事業所割合の上昇傾向に比べて、育児休業実施事業所の中の取得比率というのは、あまり急には上がらないようです。最近の3年分のデータしかないのです。
- 駿河
-
そうすると、実態は、あまり改善されていない可能性があるのですね。
- 金子
-
あるかもしれないけれども、今後、データをそろえて実証研究をしてみる必要があるかと思います。しかし、集計的には育児休業実施事業所割合に代表されるこの制度の普及の望ましい効果が出ている。しかも、冨田さんの分析は大阪府だけのサンプルですけれども、樋口さんのほうは「就業構造基本調査」ですから全国ですね。全国平均で見ても、育児休業実施事業所割合が高くなるほど、継続就業率が上がる結果が得られています。だから、平均的に見ることを認めてもらえるならば、育児休業制度の普及は望ましい効果を及ぼしていることが考えられます。
- 駿河
-
先ほども言いましたけれども、育児休業制度がきちんとできれば、出産率あるいは結婚率というのは相当高まってくるのですか。そういう分析があればおもしろいと思うんですけれども。
- 金子
-
育児休業制度があると、出生率が上がるかどうか。それは、人口政策とかかわって、従来は取り上げることが非常に難しかったんですけれども、やはりこれからは、それも一つの研究課題だということを働く女性の人たちに認めてもらいながら、客観的な研究をする必要はあるかと思います。
- 駿河
-
三谷論文に対するコメントがあったらお願いします。
- 奥西
-
広範囲なデータを丹念に拾っておられて、わかりやすく、「ああ、なるほど、こうなっているのか」という感じで、特に異論なく読みました。役職面では大企業でも長勤続の女子を中心に、まだ低いと言えば低いんですが、昇進する人の割合も若干増えているというのは、私も別のある作業でそういう結果が出ているので、それと整合的かなと。ただ、一方で男女雇用機会均等法という一つの大きな画期があった割には、まだまだ大きな格差が残っているなということも、三谷論文を読んで感ずるわけです。
- 金子
-
格差というのは、賃金格差に限定しないでいうことですか。
- 奥西
-
賃金もそうですし、役職への昇進割合も。たとえば係長への昇進者は増えていますね。でも、すぐ課長や部長になる人の割合が増えるかというと、おそらく均等法以前に採った人は、そうしたことを予定した扱いをあまり受けてこなかったでしょうから、時間のかかる話だというのは理解できるのですが。また、賃金のほうについて言えば、まだまだ格差が大きいので、それをどういうふうに考えるのかなということがあります。
- 駿河
-
三谷論文の場合は、均等法ができて、そして、女性の雇用管理が改善されて、賃金格差が減る、勤続は長くなる。こういうワンクッションを置いた議論をしているんですけれども、一つは、雇用管理についてはほとんど何も触れられていないので、できれば雇用管理のどの辺が改善されたかというような具体的内容があったらつけ加えるといいと思いました。男性なみの訓練をするようになったとか、男性と同じ待遇が与えられるようになったとか、それから、昇進チャンスが広がったとか、そういう具体的な雇用管理改善がこの均等法以降どの程度改善されてきたかということです。むしろ、雇用管理の具体的な側面というのは、ヒアリング調査に基づいた研究のほうがいいわけですね。ただ、その辺がちゃんとわからないと、実際、均等法で賃金とか勤続が改善されたのか、単に好景気のときに改善されて、その後不景気になりましたけれども、好況のときの影響が続いてきているのかというのがちょっとわからないという気がしますね。
- 奥西
-
たしかに先ほどの育児休業と同じで、教育訓練等の制度的な面で改善が進んだかどうかというとき、運用面の実態も見る必要があるでしょうからね。統計調査ではちょっと難しいかもしれません。
- 駿河
-
それから、1986年と93年、2年間の賃金関数を推定されて、そして、女性ダミーの係数がどうなったかを見て、賃金格差が縮小したか、大きくなったかとかいうのを見ています。それを企業規模間でも見ているわけです。だけど、2時点だけで見ると、推定係数が不安定で傾向が不明になる可能性があります。また、2時点の推定値の差が割と小さいですから。
- 金子
-
本人はその点留保していますけれども。
- 駿河
-
この結果ではあまり強く言えないのじゃないか。やはりもう1時点くらいの推定が欲しいところです。それから実際有意に係数が違うのかを調べる必要があるんじゃないかという気がします。
- 金子
-
男女雇用機会均等法の影響を見るということで、均等法施行以後10年たてば、最初に採用された総合職の女性が係長とか主任クラスになる時期ですよね。そこで見たかったからじゃないですか。たとえばその3時点、10年の間をもっと細かくした3年おきでは、その影響は出てこないですよね。今は、水準は低いけれども、だんだん役職で男女間差別がなくなってきているということの議論と合わせると、やはりきちっと職位が上がっていくプロセスを見いだせる長い時間が欲しかったと思うのです。だから、駿河さんの批判をあえてこの論文の形式でやろうとすると、もうあと5年先を見る必要があります。そうすれば、均等法施行の5年後に採用された男性と女性で、やはり10年たってみたら賃金格差がなくなっている。そうすると2コーホートですよね。新卒採用の二つの世代で男女間賃金格差がなくなっていれば、それは均等法の影響が出ていることが確かめられると思います。だから、一つのコーホートに依存するこの論文は注意して読む必要があるんですけれども、駿河さんのコメントに対する一つの今後の研究の発展方向というのは、より長いスパンを持ったデータを用いて少なくとも2世代を比較するということだと思うんです。
8. 福利厚生と税制・社会保障の影響
論文紹介(金子)
安部由紀子・大竹文雄「税制・社会保障制度とパートタイム労働者の労働供給行動」
女性の労働力率が高まり就業行動が多様化する中で、既婚女性のパートタイム労働は近年著しく増加し、これに対して税制・社会保障制度が及ぼす影響に対する関心が高まっている。この論文は、パートタイム労働が労働時間を調整しやすい就業形態であるため、税制・社会保障制度が労働供給に及ぼす効果が大きい可能性があるという視点から、税制・社会保障制度が既婚女性に及ぼす効果を1990年「パートタイム労働総合実態調査」を用いて実証分析している。
税制がパート労働に及ぼす影響については、配偶者特別控除に消失控除が取り入れられたので、限界的に所得が増加した場合に家計の手取り収入が純減することはなくなった。しかし、配偶者特別控除が消失していく範囲では、追加的な世帯所得の増加よりパート労働所得の増加による世帯所得増加の割合は低い。しかも、このようなパート労働所得に対する税制の効果は夫の所得にも依存しており、配偶者特別控除と本人の給与所得控除を合わせた所得税の実効的限界税率は複雑である。さらに、社会保険料負担と配偶者手当の支給制限を考慮した場合には、実効的限界税率はより複雑になる。そこで、夫の所得をいくつか設定して、それぞれの所得水準において既婚女性のパート労働に対する実効的限界税率を算出した。これに基づいて、パート労働所得が65万円から100万円となる範囲で実効的限界税率が急増することを指摘した。
このようなパート労働所得に対する税率の急増に対して、限界税率が上がらないように労働時間を調整するパート労働の所得調整が起きていないかどうかを、1990年「パートタイム労働総合実態調査」の個票を用いてパート労働の賃金率弾力性を計測することによって検証している。このデータから推計された25歳以上非学生の女性パート労働者の年間労働時間数に対する時間当たり賃金の弾力性は、-0.5~-0.6であり、限界税率が急増する所得に至ることを回避するために賃金率が上昇する場合に労働時間を減らして女性パート労働者が所得調整する可能性があることが確かめられた。これらの結果から、税制・社会保障制度を女性パート労働者の労働供給になるべく影響を及ぼさないように改める必要があることを指摘している。
樋口美雄「税・社会保険料負担と有配偶女性の収入調整」
この論文は、既婚女性のパート労働に対する税・社会保険料負担の影響を、収入調整への既婚女性の意識的対応の有無、および労働時間の抑制や賃金選択による収入調整の実態を1990年「パートタイム労働総合実態調査」を用いて実証分析している。まず実態を見るために、パート労働者の年間賃金収入分布を4大都市圏とその他の地方それぞれについて調べると、非課税限度額ぎりぎりの収入に分布が偏っている。これから、配偶者特別控除と本人の給与所得控除が受けられなくなることおよび社会保険料負担が課されることに対して、パート労働者が収入調整を行っていることが確かめられた。
収入調整には、賃金率を所与として年間労働時間を調整する方法と、年間労働時間を所与として非課税限度内に収入を抑えられる相対的に低い賃金を選択して世帯所得を引き上げる方法とがある。同調査によれば収入調整に対する既婚女性の意識的対応のうち多くのパート労働者がとる方法は、年間労働時間を計画的に抑制するかまたは非課税限度額を収入が超えそうになる場合には休暇等によって調整する方法であった。こうした収入調整への意識的対応を行う頻度がどのような既婚女性の属性に依存するかをプロビット分析によって見ると、高学歴女性のほうが高く、賃金率の相対的に高い4大都市圏居住の女性のほうが高くなっている。また、収入調整の有無を考慮した時間当たり賃金率の年間労働時間に対する効果はマイナスとなっており、賃金率が高くなっても収入調整をするために年間労働時間が短くなる傾向があることが確かめられている。
以上の推定結果等から、既婚女子パート労働者の15~30%が税・社会保障制度の適用に対して収入調整している可能性があり、このような労働市場への税・社会保障制度の影響を取り除くような改善が求められると述べている。
西久保浩二「転換期を迎える日本型福利厚生」
福利厚生制度は、労働者が企業に定着するように導く手段として利用され、従来から重視されたのは退職金と企業年金と住宅補助(社宅や家賃補助)等であった。この論文は、これらの福利厚生に対する費用の動向を、法定福利費と法定外福利費に分けて、日経連の「福利厚生費調査」によってそれぞれの動向を時系列的に観察するとともに、福利厚生費の変化に対して労働組合が福利厚生要求の対応を変化させた結果、福利厚生の内容が従来の退職金・企業年金・住宅補助中心から多様なニーズにこたえられるものへと転換し始めていることを明らかにしている。
「福利厚生費調査」によれば、福利厚生費は増大しているが、その主たる要因は法定福利費の急増であり、そのためにかえって法定外福利費の福利費用に占める割合は低下している。近年では、法定福利費は法定外福利費の2~3倍に達し、企業の収益が伸び悩んでいる状況では法定外福利費の増加は抑制されるようになった。労働組合は、このような福利厚生費の変化に対して、女性従業員の増加による育児休業に対する要望の増加や従業員の意識の変化による休暇制度の充実など、福利厚生に対するニーズの多様化を踏まえて、要求項目を変化させてきている。「福利厚生要求と妥結状況に関する労働組合調査」(労務研究所『旬刊 福利厚生』)の福利厚生に関する総要求件数に占める項目別要求件数をそれぞれの福利厚生ニーズの要求度合いを示す指標として、1971年、72年、73年の3ヵ年平均値と1993年、94年、95年の3ヵ年平均値とを比較した。その結果、持ち家・財形・社内預金に対する要求や社宅に対する要求が減少したのに対して、「育児休業・短時間勤務制度」「介護休業・短時間勤務制度」や「リフレッシュ休暇制度」など新しいニーズに対応する要求が増加したことが明らかになった。こうした分析から、福利厚生制度は、従来の金銭的手段による従業員定着を主たる役割とするものから、従業員の活力や企業への貢献を引き出すための多面的な役割を担うものへと転換しつつあるという結論が導かれている。
- 金子
-
まず、安部・大竹論文です。今度、消費税が引き上げられ、所得税に関しては、今までの減税分を取りやめることになりました。法定福利費の問題もありますが、企業のコストを税制の面でも下げるという意味で、法人税減税が議論されています。従来からこうした税制改革が行われるたびに、いわゆる配偶者特別控除や税率の刻みが、女性のパート労働に対して悪い影響を及ぼしているのではないかという議論がされていたけれども、それについて、個票データに基づく実証分析で検討することはほとんどなされていませんでした。安部・大竹論文は1990年「パートタイム労働総合実態調査」の個票データを使って、パート労働の労働供給の時間当たり賃金の弾力性を推計することにより、パート税制の影響を検討しています。
パート税制の研究でこれと比較すべきものとして、丸山桂さんは、配偶者特別控除が消失するような仕組みになり、刻みが変化したことによって、パート労働が増えるのか減るのか、所得調整を行っているのか行っていないのか分析しているんですけれども、丸山論文はシミュレーション分析ですね。典型的なモデル賃金やモデル税制に当てはめ、刻みが変わったときに、どう労働供給が変わっていくのかを調べています。ただし、労働経済学的な分析の観点から見ると、安部・大竹論文のほうがより着実な研究をしているかと思います。
安部・大竹論文を取り上げたもう一つの理由は、パート労働者を類型化している点です。パート労働の累型化は、永瀬伸子さんが正社員と対比するために短時間パートと長時間パートに分けて実証分析した例があります。安部・大竹論文は、DINKS・パート労働と、そうでないパート労働に分けている。思考実験をするために、パート労働を類型化した。これが新しいところだと思うんですね。なぜそういうことをしたかというと、DINKSでないパート労働者というのは、生活に追われてパート労働をするということですから、若干行動パターンが違うというわけで、刻みが変わっても働かざるをえなければ相変わらず働き続けるだろうということで、自分の選択に応じて、純粋に弾力性の高い経済行動をするかどうかに関しては疑問が持たれるわけです。労働経済では最近、家族の構成が労働供給に及ぼす影響について、随分慎重に扱うようになったので、そういうものの考え方を延長しながら実験の一つの基準として類型化して比較しているというような感じがします。
西久保論文を取り上げた理由は、ほかにも、山内さんの「フリンジ・ベネフィット課税の経済分析」など、福利厚生制度に関連する論文はあるんですけれども、女性の働き方と、これまでサーベイした文献が取り上げた育児休業制度、介護休業制度などの休業制度のあり方などとを直結する視点を与えているからです。従来、日本型福利厚生の分析では、退職金あるいは社宅の問題に限られていた。松川滋さんの論文が、かつて社宅と離職率の関係を実証分析していましたけれども、そういうことから離れて、広範囲の日本型福利厚生制度のあり方について述べています。
どうして福利厚生のニーズの分散化が進んだかというと、西久保さんが言われているように、法定福利費が急増しているからです。これは厚生年金財政が逼迫してきて、保険料率が引き上げられる。1992年の厚生省人口問題研究所による中位人口推計よりも、もっと出生率が下がったような人口推計の場合には、田近・金子・林(『年金の経済分析』)が分析したように、将来の社会保険料率はもっと引き上げざるをえない。もしそれがだめだったら、スライド制を賃金スライドから物価スライドのほうに引き下げるような、何らかの給付カットが必要になってきます。今は、ネットスライドのような新しい改革の方向に向かっていますが、西久保さんは保険料率が上がってきた過去を見ています。法定福利費がどんどん急増する。西久保さんは、それをはっきりと法定福利費の時系列データを示して警鐘を鳴らしているわけですね。その警鐘を認識したうえで、労働組合の対応も変わったんだ、福利厚生制度の内容も変わってきているんだということを明らかにしているという意味では、新しい視点を出しているというわけで、取り上げたわけです。
討論
- 駿河
-
では、奥西さん、まず安部・大竹論文のコメントをお願いできますか。
- 奥西
-
制度の説明、そこから導かれるインプリケーション、実際のデータを用いた検証と、非常にわかりやすく順を追って書かれていたので、なるほどなと納得させられました。あえて細かいことを言えば、最後のところで、労働時間の賃金弾力性を推計するときに、労働供給関数を推計しているんですが、予算制約線に屈折点(kink)があるとき、1本の供給関数は引けないので、場合分けして推計するというのがアメリカでのこの種の分析ではいくつかあるわけです。この点は著者も脚注で触れていますが、そこまで凝ったことをやらなくても、著者が目的とした、税制がもたらす予算制約線の屈折点が供給行動に有意に影響を及ぼしているという点はかなり明瞭にあらわれているので、これでいいと思いました。
- 駿河
-
この分野のパート税制と妻の就業研究は、ほとんどすべてが配偶者控除や配偶者特別控除、それから配偶者手当、社会保険料などによって妻が就業調整を行っているという結果を示しています。一つは、労働時間が短くなっている。それからもう一つは、そのために賃金も低くなっている、という二つの結果を出していて、もっと抜本的な解決が必要であるということを言っているわけです。今後、実際に配偶者控除や配偶者手当などがなくなった場合、あるいは社会保険料を働いていない主婦も負担するようになった場合に、どうなるかというようなシミュレーションをやっていただけるとありがたいという印象を持ちました。
もう一つは、こういった分析では、税制は専業主婦を優遇しているという議論が主ですね。しかし、家庭での仕事の評価が分析に入っていない。
- 金子
-
そういう議論は入っていないですね。女性の年金権の問題なんかを扱うときは、よく専業主婦がなぜ社会保険を免除するかというと、それ独自の価値があるからという、そういう議論はないですね。
- 駿河
-
そのあたりのアンペイドワークの評価の必要性というのも感じますね。ただ、流れとしては、社会的に労働力不足になってきて、労働供給の増加を図る必要がある。
- 金子
-
だから、所得調整はまずいと……。
- 駿河
-
ええ。全体としては、女性がもっと働くような感じの税制、保険制度に持っていこうという主張が主です。
- 奥西
-
たしかに労働供給関数を見ても、おそらくデータの制約なんでしょうがそういうハウスホールドプロダクションに相当する変数は直接には入っていないようですね。
- 金子
-
多分、「パートタイム労働総合実態調査」の制約かなと思うんだけれども、まだこの質問票を見ていないから、はっきりとは答えられません。
- 駿河
-
西久保論文に移りましょう。人手不足の好況のときには、従業員確保のために福利厚生が充実していないと、若い人は採れませんという感じの議論だったのが、不況になってくると、今度は、福利厚生の目的、効果がどうもあいまいになってきており、不況になって議論が変わってきているなという印象を受けています。
- 金子
-
少なくともちょうど好況期に対応するような時期だと思うんだけれども、清家さんが、退職金が離職率に及ぼす影響について『日本経済研究』の論文などで実証分析をしていますが、従来のそういう分析とはまた違った分析を提示しています。
- 駿河
-
そうですね。だから、現在の企業のリストラクチャリングの中で、福利厚生費というのも、効率化、改革というのが求められているというのがよくわかりました。それから、報酬全体を能力によって格差をつけていこうという動きの中で、福利厚生というのは、そういう動きと逆行する面がありますから、企業の政策および労働者の要求として福利厚生よりは賃金でというふうになっていくのかなという印象を持ちました。
- 金子
-
今回の学界展望では取り上げられなかった労使関係の視点が、この論文には明示的に入っていると思うんですね。今まで取り上げた論文というのは、計量経済学的な手法がテクニカルであるとか、あるいは個票データを上手に利用しているとかという面で、どれも遜色のないもの、あるいはモデルと実証がマッチしているなどのいい点を持っているんだけれども、残念ながら、労使関係論に直接あるいは間接的に非常に関係が深い部分を取り上げることができませんでした。今後、また別の角度からの展望もできるんですけれども、そういう意味では、労使関係、労働組合の動きにも注目した分析は必要かなと思いました。それで、これを取り上げたわけです。
- 奥西
-
福利厚生の問題を経済学的に考えるとき、二つの問題があって、一つはコスト面の話ですね。それは、この論文を読むと、法定福利費を中心に、企業にとってかなりコスト面で圧迫要因になっているというのはよくわかりました。もう一つの話として、たとえば退職金が足どめ効果を持つというように、福利厚生費の仕組みをいろいろ工夫することによって、特定の労働者層を引きつけたりすることができるということが言われていますね。そういった観点から、過去の変化を見ると、どの程度企業がそういう企業の人事労務管理目的に合わせて、福利厚生の中身を変えてきたと言えるのか言えないのか。その辺がいまひとつわからなかったのです。
たとえば西久保論文の表3で、組合からの要望というのを見ると、1971、72、73年の平均と93、94、95年の平均との比較ですが、健康管理、成人病対策、この辺の要求が増えており、住宅関係は特に増えているわけではないのです。一方、前の頁の表2で、1983年から93年にかけての実際の変化を見ると、住宅関連が増えていて、一方、医療・保健関係とか、生活援助の関係が大きく減っている。時期は違うし、医療・保健ということになると、法定福利費のほうに含まれる部分もあるでしょうから、直接の比較はできないんですが、果たして企業がどの程度労働者のニーズにこたえているのか、あるいは企業自身、何らかの人事労務管理目的に即して、中身を変えてきているのかいないのか。この辺がもう少しわかると非常におもしろい研究になるのではないかなと思いました。
また、先ほどの育児休業との関係で言えば、おそらく社会政策的な見地から言っても、あるいは女性労働者のニーズから言っても、育児休業とか介護休業のニーズは非常にあるし、実際、組合の要望事項として高いわけですけれども、果たして企業がそれに対応して、制度を充実させていく方向にあるのか。この辺なんかもわかると非常におもしろいと思ったんですけれども。
- 金子
-
たとえば企業の経営者のヒアリングがマッチしていればよかったですね。せっかく労使関係の観点が入っていて、労働組合の要求項目の変化、要求の度合いの変化というものを調べたのに対して、経営者の立場はこれから何を望んでいるのかというのが不明確ですね。
終わりに
- 駿河
-
最後に総括をお願いします。
- 金子
-
たくさんの論文を見てきたわけですけれども、二つはっきりとした分析手法の変化が見られます。一つは、モデル分析と実証研究をいかに整合的にやるのかということで、パネルデータがないとか、個票データが自由に手に入れられないという範囲の中で、モデルをつくって、モデル分析をして比較静学をする。ある制度変更が労働市場に及ぼす影響がモデルからはっきりとわかるわけですね。そのモデル通りに日本の労働市場が実際に機能しているかどうかを調べるために、研究者はデータの扱い方に対して工夫をしていることがわかります。
それから計量経済学的なテクニックが非常に進んでいる。モデル分析については、3の海外生産活動と国内雇用のところで、深尾論文も、デュアリティー(双対性アプローチ)を使っていて、経済の環境変化が起こるときに、企業がインターテンポラルな費用関数を最小化するということからモデルをつくり、比較静学を行っています。同様の費用関数を使った分析は早見さんの『日本経済研究』の論文があり、モデル分析や実証分析の推計式の導き方でも新しいテクニックが入ってきています。
そういう近年の動向を考えると、一つはますますモデル分析と実証分析をくっつけるセンスをわれわれ労働経済学者は高めていかなければいけないと思います。
最後に、やはり望みたいことは、データをもっと自由に使えるようにするということと、労働経済学者の要望をある程度反映したようなデータが欲しい。一つはパネルデータです。ユーロスタットでは、パネルデータを各国が、少なくとも同じ項目を入れるように整備しましょうというような動向がありますから、わが国でも、パネルデータをつくることに関して努力があってもいいような気がします。家計経済研究所で1993年から始まった「消費パネル調査」の開発を期待しているのですが、これはあくまでも経済学者の要望です。
- 奥西
-
私も、今の金子さんのコメントとほぼ重なります。私の場合、バブル期をはさんで6年ほど日本にいなかったので、日本のこういう労働経済学界の状況はどうなっているかあまり知らないできたんですが、一昨年帰ってみて、かなり進んできているなという印象を率直に言って持ちました。
アメリカにいたとき、労働経済学の研究に関して三つのことを思ったんです。一つは、単にデータを使って計算したらこうなりましたというのではなくて、何がしかの理論モデルに基づいた実証分析ということが非常に強調されている。
それから、実証分析面では、個票データを使うのはほぼ当たり前になっているし、さらにそういうことを前提として、計量手法等もかなり精緻なものが出てきている。
3番目には、非常に政策的な関心が強くて、そのときどきのホットな政策問題に経済学者がどんどんアタックしている。
そういう三つのことを感じたんですが、日本でも、多かれ少なかれ、そういった方向に動いているという意味で、非常にいい傾向だと思いました。
ただ、個別に見ると、問題がなくはない。たとえば今、金子さんが言われたデータ利用の問題。私がアメリカにいたとき、高齢者の年金や健康保険制度のあり方が大きな問題になったとき、何人かの研究者が音頭をとって、政府も協力して早速パネルデータをつくろうということになったのです。そういうことが日本でもあるといいのではないか。現状は、役所のデータは役所が中心に使い、それ以外のことを外部の研究者がやろうとすると、細々とした委託研究等で個別にやる。そうすると、回答する側も非常に大変ですし、社会全体として大きな非効率を生んでいると思うんです。その意味で、もう少し公共財としてのデータの生産、そういったシステムが工夫されていいんじゃないか。
政策的関心についても、同様のことが言えて、パート税制と労働供給の関係等、いくつか政策的な関心に基づいた研究が出てきていますけれども、たとえば最近の規制緩和の問題とか、あるいは各種公的年金・保険制度、助成金等さまざまな政策の費用効果分析ですね。そういったものがなかなか行えない。行政側のデータがなかなか得られないというところに、最大のネックがあると思うんですが、そういう面でも改善が図られていくと、日本の労働経済学研究もますます進むんじゃないかなという感想を持ちました。
- 駿河
-
データについては、私も全く同意見ですね。以前は、日本企業、あるいは日本経済はどうしてこんなに強いんだろうか、それを解明するという形で、労働市場の分析が行われていたのがかなり多かったんですけれども、そういう視点が全然なくなり、日本の労働市場あるいは企業をどういうふうに、いかに効率的にするかというような問題意識でほとんどの問題が取り上げられているという印象です。
ただ、失業率がかなり上がってきているんですけれども、失業率に直接アタックした研究というのが全然見当たらなかったというのは非常に残念ですね。
それから、以前多かった高齢者、外国人労働、それから勤労者生活などの問題を扱った論文が非常に減っている。これらは、労働供給制約化という問題意識で検討されていた問題ですけれども、長期的に見れば、労働供給制約化というのが出てくる可能性があるので、こういった分野の研究も将来必要かと思います。
また、理論、実証両方がある文献が増えてきたのは非常に喜ばしいことで、経済合理的な視点から、日本の労働問題を解明しようという傾向があって、すばらしいと思いました。もともと労働経済学というのは、直接輸入された仮説を調べるというのではなしに、日本独自の仮説というのをかなり生んできた分野です。ただ、以前は、労働経済学の理論的なフレームワークと日本の労働分析がほとんど交流なしに勝手に進んでいるという状況だったんですけれども、そういう状況は脱してかなり両者の密接な関係ができてきているという印象を持っています。今後も一層、労働経済学の理論と日本の分析、これが密接につながるようになることが求められると思います。
もちろん、データはみんながアクセスできるような形になってほしいと思いますけれども、データよりは仮説のほうが重要ですし、日本から世界に通用するような普遍的な仮説が生まれてほしいと思っています。


