資料シリーズ No.66
総合的な労働力需給指標に関する調査研究
平成22年 4月23日
概要
研究の目的と方法
- 労働を巡る環境の変化に伴い、公共職業安定所以外の経路も含めた総合的な労働力需給指標の必要性が指摘され、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(H21.3.13閣議決定)において検討課題となる。
- 厚生労働省からの要請を受け、特に求人に関する統計について、EU、米国等の欠員統計等の状況を現地でヒアリング調査する。
- 諸外国の欠員統計等の作成過程、利用方法、政策判断等を把握することにより、日本における同様の統計の導入可能性や導入意義等の検討材料を提供する。
主な事実発見
- 欠員統計の導入目的 : ITの発達等による職安以外の求人データの増加と総合的な欠員データ把握の必要性等(図表1参照)。
- 欠員の概念・定義: EU規則で定義されているが、各国において有効な求人期間がどの程度か、雇用後にどの程度継続雇用される必要があるかなどで考え方に差異があり、一律比較可能なデータの作成は容易ではない。米国でも別途定義している。
- 対象範囲: 全産業か農林水産業・公的部門を除外するか、企業単位か事業所単位か、費用対効果を考え10人未満事業所を除外するか、雇用形態の区別をどうするか等についての課題がある。
- 調査項目: 欠員のみ聞くか他の項目と合わせて聞くか回収率やデータ分析との関係で要検討。職業別・雇用形態別の構造的な分析が望ましいが、現時点では負担があり困難。
- 調査方法・作業体制: 事業所調査が原則で行政データは補足的。書面のアンケート調査、電話調査、その組合せ等。調査票設計や結果分析等は行政職員が行うが、データ収集は民間委託しているケースが多い。サンプリングは大企業群と中小企業群に分け後者は周期的に入れ替え等。定期的に利用者等からのレビューを実施など。
- 欠員統計のメリット、政策評価: 経済全体の求人統計把握に必要。景気指標作成の材料として有効(図表2参照)。労働市場における求人・求職のマッチング過程の分析に重要。マクロ経済分析等にも有用。
政策的含意
- 各国の実情を踏まえ我が国の欠員統計導入の必要性を検討する際、既存統計の変更利用可能性、コスト面、景気指標・労働市場分析指標等の各側面からの有用性に留意する必要。
- 職安データと経済全体の労働力需給指標との乖離及び関連性について検証が必要。職安データと欠員データの政策への影響の違い、相互補完可能性を評価する必要。雇用保険との結びつき等の観点から我が国と他国との職安データの信頼性の国際比較にも留意。
- 求人、欠員の定義について、求人開始から採用予定までの期間、採用後の雇用継続期間、対象とする雇用形態(正社員、非正規労働者等)などを検討する必要。
政策への貢献
- 平成22年4月27日、厚生労働省で開催された「厚生労働統計の整備に関する検討会」において検討資料として活用された。
図表1 欠員統計の導入目的、経緯等 (調査時期 2009 年9 月~11 月)
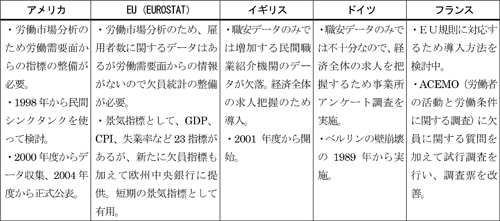
図表2 (米国) 失業欠員比率の動向
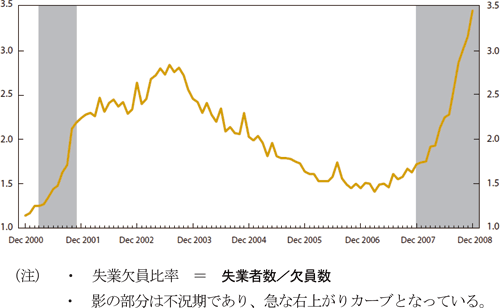
本文
全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。
- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次(PDF:592KB)
- 第1章 総論(PDF:589KB)
- 第2章 アメリカ合衆国の状況 − 求人労働異動調査(JOLTS)の実施状況(PDF:682KB)
- 第3章 ヨーロッパの状況(EUROSTAT 担当者の見解)(PDF:523KB)
- 第4章 イギリスの状況 − 欠員統計の実施状況(PDF:588KB)
- 第5章 ドイツの状況 − ドイツ連邦の欠員統計の実施状況(PDF:566KB)
- 第6章 フランスの状況 − 欠員統計の検討状況(PDF:660KB)
- 第7章 OECD 事務局担当者の見解(PDF:645KB)
- 資 料 編(PDF:835KB)
執筆担当者
- 笹島芳雄
- 明治学院大学経済学部教授
- 三谷直紀
- 神戸大学大学院経済学研究科教授
- 阿部正浩
- 獨協大学経済学部教授
- 大塚崇史
- 労働政策研究・研修機構副統括研究員
研究期間
平成21年度
お問合せ先
- 内容について
- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム



