パネルディスカッション
- パネリスト
-
- 深澤 晶久
- 実践女子大学 文学部国文学科 教授 学長補佐 社会連携推進室長
- 長谷川 洋介
- 株式会社マイナビ 社長室 マイナビキャリアリサーチラボ 研究員
- 西村 純
- 中央大学 商学部 准教授
- 岩脇 千裕
- 労働政策研究・研修機構 主任研究員
- コーディネーター
-
- 池田 心豪
- 労働政策研究・研修機構 副統括研究員
- フォーラム名
- 第139回労働政策フォーラム「多様化する若者の初期キャリアの現在」(2025年7月18日-24日)
- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年10月号より転載(2025年9月25日 掲載)
パネリスト報告へのコメント
池田 はじめに、長谷川さん、深澤さんの報告についてのディスカッションを少ししてから、パネルディスカッションに入っていきたいと思います。研究報告した岩脇さんから、感想やコメントをいただけますか。
岩脇 まず、長谷川さんの報告についてですが、企業の採用充足率が年々下がっている状況は、私が調査で扱った高卒のハローワークのデータでも確認しており、大卒も同じような状況になっているとあらためて思いました。
質問があるのですが、大企業と中小企業の採用充足率にはどれぐらい差があるのでしょうか。また、産業による充足率の差はありますか。
充足率で苦労がより大きいのはマンパワーが少ない中小企業
長谷川 やはり企業の規模によって充足率が変わってくると思います。ただ、大企業のほうが採用数は多いので、例えば100人採らなければいけないけど70人しか採れなくて充足率が70%でしたという会社もあるかもしれません。中小規模の企業では、3人採りたい場合、2人採れれば充足率が6割を超えることになります。
一概に比較できない部分がありますが、やはりマンパワーの面や採用の部署の数を考えても、中小企業のほうが充足率で苦労していると言えます。実際に1人で採用活動をしている担当の方もいらっしゃいますし、新卒だけではなく、中途採用やアルバイト採用もすべて兼任して担当している、いわゆるワンオペの人事・採用担当の方もいらっしゃいます。充足率や実務の負担という面でも、中小企業はそれなりの負担を感じていらっしゃる担当の方が多いと思います。
より多くの学生が応募する業界は実はIT系
実際に応募している学生が多い業界はというと、実はIT系です。それはおそらく、企業数が多いからだと思います。岩脇さんの報告にあったように、いわゆるサービス産業がたくさん広がっていくなかで、サービス業が雇用の吸収力を持っている。それが今は、IT業界になっているのだと思います。実際、内定を得た学生に「どの業種ですか」と聞くと、一番多いのがIT系との答えです。
岩脇 ありがとうございました。
次に深澤さんの報告についてですが、「体験格差」という言葉が流行っているなかで、幼児期から大学生まで、何かに取り組んで成し遂げた経験をものすごく要求される時代になっているのだなと痛感させられる内容でした。これを大学がお世話してくれるのは本当にありがたい一方で、大学というのは科目を自分で選んで受講するという構造なので、プログラムに応募する学生はその時点で結構やる気のある子たちだと思います。そういった講義に登録しなかった学生はその後どうなっているのか、そういった素朴な疑問をお尋ねしたくなりました。
何かこの大学で取り組んでみたい、という思いを持った学生が多い
深澤 もちろん、さまざまなタイプの学生がおり、黙々と自分で設計をして大学生活を過ごしている学生もいっぱいいますが、私が感じるのはやはり、何かこの大学で取り組んでみたい、チャレンジしたいという思いを持った学生がとても多いということです。
では何が提供できるかといったときに、いま本学が行っているように、さまざまな体験機会を用意してあげることでそのきっかけづくりをすることであって、それに飛び込んだら、どんな局面になっても乗り切っていかなければいけない。そこでリーダーシップなどが身につくわけですから、あとは周りは見守っているだけで、入り口をどれだけたくさんつくれるかという考え方でやっています。
池田 私からも長谷川さんに質問があります。地元ではない中小企業というのは保護者からすると縁遠いというか、「どこなの、そこ」となりやすいのかなと思います。そういうことはあるのでしょうか。
中小企業でも知名度があればまだ、保護者の賛同を得られやすい
長谷川 おっしゃるとおりで、保護者に対して、どういった企業だったら子どもが就職してもよいかを聞くと、やはり一番多いのは、知名度の高い大企業になります。
中小企業の場合、知名度があればまだ、賛成すると考える保護者は多いです。知名度もなくて、遠方となってくると、もちろん頭ごなしに反対する保護者が多いわけではないですが、「反対するかもしれない」「どちらとも言えない」という保護者の割合は増えます。
全国転勤する会社だと反対するかもしれないとする保護者も3割程度いますし、これはどこまで子どもに期待しているかわからないのですが、ゆくゆくは地元に帰ってきてもらいたい、老後の手伝いをしてほしいなど、いろいろな思惑や期待もあるのかもしれません。
IT系で多い女性の活躍を応援する企業
池田 深澤さんにおうかがいしたいのは、いま企業は女子学生の採用に熱心な面があると思います。企業の女子学生に対する期待や関心を感じることはありますか。
深澤 かつてはメガバンクの一般職などの定番コースがあったかもしれませんが、コロナ禍明けからそういうのはなくなった一方で、先ほど長谷川さんがおっしゃっていたIT系が増えていると感じています。
プログラマーやエンジニアというよりも、クライアントと技術者を結ぶようなコンサルタント的な領域の仕事でとても活躍しています。しかも、IT系で女性の活躍を応援している会社がいっぱいあると感じており、本学の学生も最近、IT系にかなり入社しています。
池田 西村さんからも、深澤さん、長谷川さんの報告に対するコメントをお願いします。
西村 まず、深澤さんにおうかがいします。FSP研究会は非常にすばらしいプログラムだと思いました。これは、学生が与えられたテーマについて報告するプログラムだと思うのですが、学生の報告に対して、企業の方は実際の社員と同じような態度で接するのでしょうか。
会社の中でしたらプレゼン内容について厳しく詰められることもあると思います。ただ、それによって実力がついていく部分もあると思います。
学生にとって、大学時代に失敗を経験できることは、社会に必要な実践力を養っていくという意味で重要になってくると思うのですが、いい失敗経験ができる機会を提供することは実は難しい。FSP研究会の中で実施されている工夫などがございましたら、ぜひ教えていただけないでしょうか。
最初から社会人としてのマインドセットを行う
深澤 この授業がスタートした頃のコンセプトには、「修羅場体験」をさせようと思い、かなり厳しく突っ込んでいました。今ももちろんその名残は残っていますが、やはり社会環境も学生の気質も変わっているので、当時と同じようにはできないかもしれません。この授業は、1つの企業さんからお題を出していただいて、2週間という期間で中間プレゼン、さらに2週間という期間で最終プレゼンという、かなりのスピード感を持って行っています。
初回の授業のときに、私が「皆さん、入学おめでとう。同時に、今日、皆さん、卒業おめでとう」と言って、学生はびっくりします。「えっ、何」と学生から質問が届いたら、「今日からは近畿日本ツーリストの社員ですよ。だから、来週から来られる近畿日本ツーリストの社員の方はあなたたちを社員として接して下さるからね」と言い、最初から大きなマインドセットを行います。
特に中間プレゼンではかなり厳しいフィードバックやアドバイスがなされています。「社員に対してこのお題を与えて、このプレゼンだったらとてもじゃないけど、何にも通用しないよね」ということを相当強烈に言ってもらっています。それをカバーするのが教員の仕事で、「何であそこまで言ってくれているのか」という意味をフォローし、最終プレゼンに持っていく。この経験は、大学1年生からすると相当きついと思います。
とことん突き詰めるからこそ達成感が大きい
当然、授業内だけでは終わらないので、授業外の時間を使ってメンバーはとことんやっています。深夜までやり取りをしたり、最近はSNSを活用してやり取りしています。最近は高校での探究活動も大分盛んになってきてはいますが、ここまでの経験は求められませんから、高校時代とのギャップに悩みながらも、終わった達成感というのは相当大きなものがあるというのが実感です。
西村 ありがとうございました。
長谷川さんの報告についてですが、感想になってしまうのですが、個人的には、親と子でギャップがあるというのは必ずしも悪いことではないと思いました。自分とは異なる意見に触れることで、自分がどうしたいのかをあらためて考え直す機会につながっていく面もあるのではないでしょうか。ギャップをうまくいかしていくことが大切だと感じました。
親と子のギャップは悪いわけではなく、コミュニケーションによる埋め合わせが重要
長谷川 学生の求めている安定性と保護者のイメージする安定性が若干食い違っているのかなと感じています。会社が大きければいいのか、売り上げが何十億あればいいのか、そういう単純なものではなくなってきています。
学生も多面的に、この企業は安心してキャリア形成できるところなのかをみていると思うので、もちろんギャップが悪いというわけではなく、いいところも悪いところもお互いにコミュニケーションを取りながら埋め合わせていくことができると、親も子も納得するファーストキャリアの形成ができるのかなと今のお話をうかがって思いました。
論点1:サービス業の企業に就職するときの留意点
池田 それでは、パネルディスカッションに入ります。岩脇さんの研究報告が、サービス業を分類して、その特徴をデータに基づいて解説するという内容でした。最初の論点では、サービス業の企業に就職するときの留意点について議論をしたいと思います(シート1)。
シート1
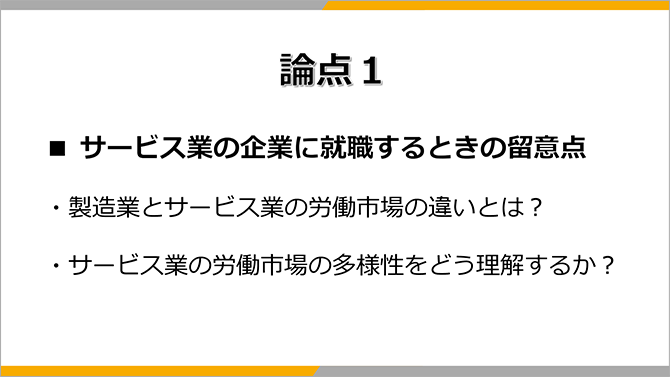
製造業とサービス業では労働市場の性質が違います。私の基調報告でも言いましたが、製造業をモデルに日本のいろいろな制度ができあがっていますので、おそらく保護者が持っているイメージは、製造業をモデルとしたものだと思います。例えば製造業以外のところに就職するとしても、製造業モデルで考える癖がわれわれにはついていて、サービス業はかなり様相が違うという点を岩脇さんに整理していただきました。
報告を振り返りながら、サービス業をどのように捉えて、就職する際にどこに留意すべきか、岩脇さんにあらためて整理してもらいたいと思います。
知識集約型と労働集約型に大きく分けられる新しいサービス産業
岩脇 私の報告では、社会の脱工業化、つまり工業中心の社会からサービスや情報が発展した社会になることで若者のキャリアがどう変わったかを説明しています。製造業や製造業を支えるサービス産業、つまりインフラ・流通産業がかつての高度経済成長期をつくっていきましたが、70年代以降からは新しいタイプのサービス産業が盛り上がっていきました。
新しいサービス産業は、大きく2つに分けられます。1つめは、知識集約型サービス産業という、専門的な知識や技術を使って高付加価値を生み出すタイプの産業です。もう1つは労働集約型サービス産業で、たくさんの労働力が必要でありながら生み出す付加価値は小さい産業です。労働集約型サービス産業が発展した背景としては、女性が賃労働に進出したことで、女性が無償で家庭で担っていた役割が市場化していき、それが産業として発展していったことがあげられます。
製造業が強い時代は、1つの会社で長く勤め続けて、その中で上を目指していくキャリアが模範的なものと認識されていましたが、サービス産業が広がっていくなかで、そういったキャリアイメージに合わないキャリアを歩んでいく人が徐々に増えてきています。
知識集約型サービス産業は少数精鋭で学歴による参入障壁が高い
報告では、新しいサービス業を3つに分けて話しました。1つめは、情報サービスや金融、コンサルティングといった知識集約型の「ビジネスサービス」になります。雇用管理のあり方は比較的製造業に近く、長く働き続けて、技能を身につけていく人が多いけれども、少数精鋭型の産業なので、そんなに人をたくさん雇えない。また、高学歴の人ほど入りやすいという特徴があるので、門戸が皆に開かれているわけではありません。
あとの2つは、労働集約型サービス産業です。1つは医療、福祉、教育など、いわゆるケアの仕事が中心になる「社会サービス」です。この産業では、医師、看護師、教員、幼稚園の先生、保育士、介護士など、資格職の人が大勢雇用されており、女性が比較的活躍しやすいので、女性が多く集まります。ただ、長時間労働になりやすいという特徴があります。
消費者サービスは低賃金、長時間労働である一方、参入障壁が低い
もう1つは、家事労働や家計が豊かになったことで発展したレジャー等の分野で、個人を顧客とするサービス産業が発展した「消費者サービス」です。
ここでは求められる技能レベルがあまり高くなく、また、産業全体での労働生産性が高くないので、給与の原資が少ない分、どうしても低賃金になってしまいます。その労働生産性の低い分を労働の量でカバーしようとするので、長時間労働にもつながってしまいます。一方、悪いことばかりではなく、技能レベルがそんなに高くないということは、いろいろな人に働くチャンスがある産業でもあるわけです。
どの産業に就職するかによってその後のキャリアが大分違ってきます。若者がよい環境で働き続けられる社会にするために、産業ごとに改善すべきポイントがあることや、それぞれ異なる特徴をもつ多様な産業の中から、若者が自分にあった仕事を見つけるためには、客観的な情報収集と周囲の大人による支えが必要であると、報告では締めくくりました。
池田 どの産業に行くのがいいかという話ではなく、それぞれの産業にある特徴をきちんとわかっておくことが、後悔のない選択につながっていくということですね。
岩脇 そうですね。私の研究手法は統計分析なので、全体の大きな傾向をみることしかできません。例えば消費者サービスの中にもいろいろな企業があって、個々にみていったら、すごくワーク・ライフ・バランスの良いところだっておそらくあると思います。
ある産業グループだから安定であるとか、そういう話では一切ないです。個別の企業のことは若者が自分で調べることになるけれど、まずは大きな見取図を皆でみてみようという報告でした。
文卒の就職が多い新しいサービス産業は「ビジネスサービス」や「消費者サービス」
池田 「社会サービス」では、看護や介護など大学にいるうちから取得が必要な資格がありますが、何も資格を持っていない一般学生にとっては、「ビジネスサービス」か「消費者サービス」というのがサービス業で捉える大きな2つの選択肢になりますか。
岩脇 大学進学時点で、社会サービスの専門技術職に就きたい学生は、医療・福祉や教育などの学部にすでに入学しているわけですから、いわゆる社会科学や人文科学など、大学生の中で数の上でボリュームゾーンになる人たちが就職先として考える新しいサービス産業は、「ビジネスサービス」か「消費者サービス」が中心になります。一方で、従来型産業に含まれる、製造業やインフラや卸売・小売に進むこともあり得るわけです。
池田 そういう意味では、「消費者サービス」と「ビジネスサービス」という見取図でみて、それぞれ特徴があるということをわかっておくと、保護者の目からみても、よくわからないところに行こうとしているわけではないという安心感が得られるのかなと思います。
消費者サービスは子どものときからよく目にする会社が多く、保護者からしても、広告もたくさん出ているからとてもわかりやすい。IT企業の場合は、プロ野球球団を持っているメガベンチャーだったらわかりますが、システム会社は事業向けサービスですからわかりづらいみたいなこともあると思います。
深澤さんが学生の就職指導やキャリア教育で注意しているポイントはありますか。
何をどう調べたらいいのかもわからないところから引っ張り上げる
深澤 私どもに相談に来る学生では、一番悩むのはやはり2年次ぐらいで、企業や社会に関して何をどう調べたらいいのか、自分は何に向いているのか、何を目指したらいいのかわからないというところからのスタートをどう引っ張っていくか。
岩脇さんが先ほどおっしゃったとおり、本学でも食系の学部であれば管理栄養士を目指すとか、幼児保育系だったら保育士とか、比較的明確に方向性が決まっている学生は、もうその道に向かって一歩一歩進めばいいわけです。
いわゆる人文系の学生がやはり難しいところです。最近は相当変化しているかもしれませんが、「化粧品」「アパレル」「食品」という女子大生の定番の3業種というのがありました。それは当然で、どこを探すかといったら、「B to C 企業」で、見たことがある企業ということになります。
しかし今回の岩脇さんのお話を聞いて、サービス産業のカテゴライズを勉強させてもらったので、そういう視点も学生に伝えていったら、少し見方が変わるかなと感じました。むしろそういうアドバイスをこれからしたいなと思っています。私の勤務していた資生堂も株式市場としてカテゴリーは化学ですが、実際には営業や小売として働いている社員が多くいます。1つの企業の中にいろいろなサービスの要素もあるので、個別企業の状況もしっかり見てあげる必要があります。
池田 西村さんに質問です。岩脇さんの報告では、従来型ものづくりと消費者サービスでは、人材の育成やキャリア管理というキャリアの基本的な仕組みが違うというお話がありました。ご自身の研究での企業事例を見て、社員に用意しているキャリアの基本的な仕組みや人事制度について製造業とサービス産業での違いはありますか。
じっくり育てる製造業に対し、早く育てて活用する脱工業化以降のサービス産業
西村 製造業などの従来型の産業ほど、じっくり育てていくという文化は強いと思います。一方で、脱工業化以降のサービス産業では、どちらかというと早く育てて早く活用していくという企業も少なくないと思います。
その要因は何なのかと言われるとなかなか難しいのですが、1つは、扱っている製品・サービスの特徴があげられます。例えばインフラなどのいわゆる従来型サービスの電気、ガス、交通系になると、失敗のリスクは大きいですよね。もし都内の電気が全部落ちたとなったら、社会に対して大きな影響を与えてしまいます。
そうなると、人材活用としても、人をじっくり育てて、その中から適切な人を管理的ポジションに上げるなど、本人の適性をじっくり見極めるということにならざるを得ない部分はあるのかなと思います。
一方、脱工業化以降のサービス、特に「B to C 系」だと、まずチャレンジさせてみて、「失敗を糧にして次のアイデアを考えていこう」ということが、従来型サービスに比べるとやりやすい部分があるのではないでしょうか。そういった点も、企業側の人材育成や処遇制度に違いを生んでいる1つの背景としてあるのかなと感じます。
池田 最近、学生は成長実感を求めて、早くチャンスがもらえて活躍したいと思うということがよく言われますが、そういう人が持っているキャリアプランと、やはり扱っている製品やサービスなどに起因する企業が持っている育成プランは性質が違っていて、その特徴をふまえて就職先を選んだほうがいいのでしょうか。
事業特性で変わってくる人材育成の仕方などを自分で見極める
西村 事業特性によって育成方法は変わってくると思いますので、本人がどういう仕事をしたいのか、また、どういう事業に携わりたいのかを考えたうえで、自分自身で判断していく必要はあると思います。
入社後に長い下積みがあるかもしれません。しかしそれは、悪気があってやらせているわけではなく、本当に必要だからやらせている場合もあると思います。業界や企業の事業特性についても考えていくことは、自分のニーズにあった会社の発見やキャリア実現の可能性を高めてくれるかもしれません。
池田 じっくり仕事を覚えたいという学生と、即戦力で来年からぱっと活躍したいと思っている学生とで、キャリアの選択肢が労働市場ごとにいろいろあるというのはいいことだし、うまくマッチングすれば、昔みたいに、早く活躍したくてもとにかく10年は我慢とかということにはならないのではないかと思います。
長谷川さん、学生の就職活動について、サービス業ということを考えたときに、最近の傾向など何か感じることはありますか。
当初の志望が変わってIT系を選ぶ女子学生が多い
長谷川 例えば学生に調査をしたときに、最初に志望していた業界と志望が変わった後の業界を照らし合わせて聞いたりしています。いわゆる従来的な製造業などではあまり変わらないです。それはおそらく志望している学生の層が、専攻が決まっていて、いわゆる理系の機械系にいるからこういったメーカーに行きたいということがあるからだと思います。
一方、志望先として伸びてくるのがIT系で、特に女子だと伸びが大きい。業界研究や大学のキャリア教育、PBL(問題解決型学習)など、いろいろなものを通じて、最初は全く想定していなかったけれども、キャリアを意識した結果、応募先も検討に上がってくるといったことはやはりあるのかなと思っています。
深澤さんがおっしゃっていた、女子学生に典型的な「食品」「アパレル」「化粧品」もやはり女子の人気企業の上位に入ってきます。文系女子では、そこに「マスコミ」が入ってきます。理系の男子学生でいうと、今でも人気がある自動車メーカーをはじめとして、だんだん情報化が進むにつれてIT系など、いろいろな会社が入ってくるようになってきています。
ですので、サービス業の部分の存在感は大きくなってきているように感じます。一番傾向が捉えられないのは文系の男子学生で、彼らは本当にいろいろな業界を見ています。男子学生はわりと幅広く射程をみているところがあります。
いずれにしても、その企業数や種類の多さから、サービス業は近年の学生の人気の企業として挙がってくる率が高く、学生にとってもいい就職先と思われていると感じています。
「B to B」企業を知る機会をつくっていくことも重要
池田 最初の志望先を決める時には、どういうところで情報を入手するのでしょうか。友達や先輩、大学の先生に聞くのでしょうか。それとも保護者に聞くのでしょうか。
長谷川 もちろん親の勧めで志望が変わったという学生も一定数いると思いますが、やはり、「自分に合っていると思ったから」という回答が多いです。大学のキャリア教育や企業のインターンシップに参加して見方が変わるケースもあると思います。
体験を積み重ねていくなかで徐々に価値観が変わっていき、当初考えていなかったような志望先が検討にあがってくると思います。そういった意味でいうと、大学生に対しては消費者サービスのほうが「B to C」でなじみやすいですし、「B to B」の企業だと、大学での授業や企業と実際触れることでしか見えてこない部分があると思いますので、やはりそうした機会を提供して、知るきっかけをつくっていくのが重要なのかなとも感じます。
論点2:親世代と子世代の感覚の違いについて
池田 2番目の論点に移ります。子世代の、今まさに現役の大学生には、親とはまた違った労働市場の世界が見えていて、この感覚の違いについて、バブル世代の親・就職氷河期世代の親と今の学生とではかなり違うみたいだというお話を先ほど長谷川さんからしていただきました。親世代と子世代で何が違うのかについて議論していきたいと思います(シート2)。
シート2
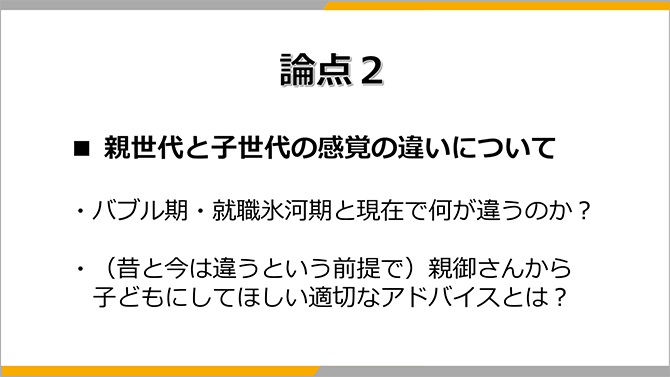
岩脇さんの報告では、産業構造が大きく変わってきているから、親にとってすごく現実的な進路の選択肢であったものと子が考える選択肢とが大分違っているとの話がありました。例えば、私の就職活動期はちょうど就職氷河期の入り口でしたが、そのときに内定を取ればみんなが羨ましいと言っていた企業は、その後の日本経済の大きな変動の中で、統合や再編が起きました。おそらくバブル期や就職氷河期の入り口では、まだ統合・再編が生まれる前の感覚というのがおそらくあり、その感覚は今とは大分違ってきていると思います。
今の労働市場を考えるときに、かつてと比べてここが違いますということを、もしお感じになっていることがあったらうかがいたいと思います。また、今の世代がどういう現実を生きているのか、どういう労働市場に飛び込もうとしているのかということと、それをふまえて保護者ができる適切なアドバイスなどを補足していただきたいです。長谷川さんお願いします。
かつてと違い、業種が他の業種と密接にかかわるようになっている
長谷川 保護者に、子どもに入ってほしい就職先を聞くと、圧倒的1位は公務員です。やはり安定した働き方をしてほしいというのが念頭にあります。学生の人気企業の変遷をみると、バブル期ですと、サービス系もやはり人気で、いわゆる旅行・航空業界などは華やかなイメージがありますので、そういった企業に行きたいという学生が多かったです。
理系では、やはり自動車メーカーなど花形の日本の基幹産業が人気です。そこが就職氷河期になってくると若干変わってきて、就職状況が厳しかったからだと思いますが、どの業界でもいいから安定した一番手の企業を選ぶ傾向が出てきます。
今の学生に目を移すと、もちろん親世代から人気がある航空業界や旅行業界、自動車メーカーも名前は挙がってきます。ただ、自動車メーカーでも、最近はSDV(ソフトウェア定義型車両)という形でよりITと密接になってきたり、親世代に人気の金融業界も、FinTechといったこれまでと違った形でサービスを展開するなど、他の業種と接続するような企業活動が増えていると思います。特定の業界に人気が集中するというよりは、1つの企業の中に複数の業界の要素が含まれるようになってきた、という肌感を持っています。
企業の活動が1つの業種にこだわらず多岐にわたってくると、学生にとっても自分のやりたい職種との接続がより見つけやすくなると思いますので、そういった企業が昨今は学生の支持を得やすいのではないでしょうか。
そういったところをアピールする場として、例えばインターンシップなどがあり、そこで学生にキャリア形成のプログラムを提供することができます。この会社であれば自分なりに安定してキャリアを形成できそうだという安心感を学生に与えられますし、そういった個社の取り組みがわりと功を奏してきている場合もあります。
外資系企業を意識しているのはむしろ親世代
池田 最近よく、外資系企業の人気が上がっているというような話を聞きますが、そういうのを感じることはありますか。
長谷川 外資系企業に関しては、どちらかというと保護者世代のほうがより意識している感じがあります。それはおそらく働いている実感値から、外資系企業の存在感を感じる部分があるのかもしれません。
外資系の大手IT企業などは、どちらかというと保護者のほうから名前が挙がりやすいところがあります。
池田 親の目から見た今風の企業と、学生が実際に自分の進路として現実的な今風の企業とは、必ずしも一致しているわけではないという面があるわけですね。
長谷川 学生の情報収集は結構幅広いです。保護者の情報源がふだんの社会人生活や報道等で目にする社名となってくると、学生のほうがより、実際に企業を訪問したり企業研究して、高い解像度で個社を見ているはずなので、親が知らない企業を見つけてくることもあるかもしれません。
池田 西村さん、企業の仕事内容が、かつてのように業界で区切られているわけではなく、どんな仕事もITが関係しているというふうに、企業の人事管理をみていて境界が曖昧になっていると思うことはありますか。
昔と比べ会社の業種と事業内容のずれが大きくなっている場合もある
西村 はい。アンケートやヒアリング調査では製造業などの業種を用いますが、製造業と言われている企業でも、実際の事業の中身をみたら、IT企業と似たような事業を主力事業として考えているような企業もあります。ですので、以前と比べると屋号としての業種と実際にその企業の中で行われている事業が異なっている面は確かにあると思います。
また、1つの企業の中でも、例えばIT企業のシステム開発についても、従来型の大企業向けの大型システムの開発もあれば、IoTソリューションサービスを展開するためのシステム開発もあり、両者では開発工程や協力会社との関係などが大きく異なります。
仕事の進め方が違えば人材確保の方法なども変わってきます。しかし、外から見ているとなかなか見えにくい部分でもあります。
池田 岩脇さん、若い人のキャリアを考えるときに、労働市場の特徴として、親世代と違う点について何か感じることがありますか。
買い手市場だった親世代は業界ぐらいしか選べないと思っている
岩脇 親世代の頃はメガバンクや大手マスコミなどに就職すると、「すごい」と言われる空気感が文系の大学生にはありましたが、一方でそうならざるを得なかったのではないかと思っています。なぜかというと、まず、買い手市場だったからです。
就職活動をするときに、大人は「やりたいことを見つけろ」と言うじゃないですか。面接で「私は御社でやりたいことをやって御社に貢献します」と言って入社していくけれど、入った後どこに配属されるかはわからない。日本企業というのは基本的にそういうふうにできているわけです。
親世代が就職活動をした時代はそういった雇用管理がされていたので、就職活動のときも業界ぐらいしか選べなかった。やりたいことを聞かれたら言うけれど、でも、入った後それができるとは限らない、それをわかったうえで就活するという状態だったと思います。
子ども世代は売り手市場のため企業が寄り添わざるを得ない
でも、今の子どもたちの世代は、メンバーシップ型、ジョブ型の議論が流行し、若い人の人口が減ってくるなかで、企業側も「やりたいことをやれるよ」と言って採用するから、本当にやらせなかったら辞めてしまう。ある程度、新入社員に寄り添うキャリアプランを用意する企業も徐々に増えていると感じます。
例えば、学生が、「業界の中でもこの会社はDXに力を入れていて、入社したら関わるチャンスがあるかもしれない」と期待を持てるようになってくると、もっと細かに、業界ではなくて個別の企業で「何をさせてくれる会社なのか」をみることの意味が出てくるし、採用側もそういう学生がやってくるという前提で採用活動を行うことになります。
不確実性が高い時代だからこそしっかりした企業の見方に
池田 長谷川さんに質問します。学生の就職先の選択は、華やかなところにぱっと飛びつくのとは違ってもう少し冷静で、最初はここがいいなと思っても途中で変わるというような、かなり現実的な選択になっているという面がありますか。
長谷川 やはり今の学生はキャリア意識が高いと思います。バブル期の頃であれば、いい会社に入っておけば、あとは会社のほうでうまく社員のキャリア形成を手伝ってくれるイメージがあったかもしれません。
一方、今の学生が育っている時代というのは、よくVUCAの時代とも言われますが、いわゆる移り変わりが激しく不確実性が高い。そういった時代に社会人にならなければならないので、大学でのキャリア教育やいろいろなことを通じて、企業に対する見方や、自分が社会人として何ができるのかというところに対する視線がやはりきちんとしているのかなと思います。
もちろん企業選びの入り口として、憧れという要素も当然あると思いますが、最終的に1社選ぶときに、その人ならではの選択軸で決定していきます。終身雇用も前提ではなくなってきた時代ですので、やはり何かあったときには自分で身を立てていかなければならず、自分のキャリア像を確立して、それを発展させていけるようにスキルや能力をより高めていきたいという気持ちがおそらく強いと思います。
池田 親の立場で見たときに、大変な時代になったなと思いましたが、岩脇さんはどう思いますか。
高校生から大卒後の就職を意識させる時代に
岩脇 いろいろなことが前倒しになった時代だと痛感しています。基本的に進学校の高校だと大学受験が目標としてありますが、どこの大学を受けるかを考えるときに、昔の先生はその子の成績でできるだけ偏差値の高い学校に割り振っていくといった進路指導が多かったのが、最近は大学受験のあり方も多様になっていると感じます。
「どんな仕事に就きたいか、どんな業界に行きたいかをまず考えて、そこから逆算して学部を決めなさい、そのためにはオープンキャンパスに夏休みのうちに何校も行ってきなさい」という宿題が高校1年生からあります。15歳でなりたい職業を決めるなんて無理だと思いつつも、やらせないといけない状況になっています。
池田 変化が激しい時代の中で、保護者とのギャップが一番大きいのは、どちらかといえば、男子学生よりも女子学生ではないかと思います。今年はちょうど男女雇用機会均等法ができて40年という節目の年ですが、その後、いろいろな女性労働政策が急速に進展しました。女性活躍といえば、先ほど深澤さんが少しおっしゃっていましたが、かつての女子学生の典型的な進路から幅が急速に広がっている。また、女性が多い職場が必ずしも女性が働きやすいかというと、そうではなく、新しい女性の活躍の場がいろいろな企業に広がっています。
そういうなかで、お母さんの感覚と娘さんの感覚は大分違っているのではないかと思いますが、特に深澤さんは女子学生と接し、いろいろな母と娘の関係をみてきたのではないかと思います。その点について何か思うところがあったら聞いてみたいです。
ここ10年で子、親の意識が変化する一方、二極化もみられる
深澤 私が大学に移った2014年と10年後の2024年の比較についてお話しします。2014年のときの大学2年生、3年生は今30歳ぐらいに届いています。その母親たちは、現在でいうと、50代半ばから60歳ぐらいになると思います。そこから2024年の学生は10歳年代が変化しているので、そのお母さん自身の働き方や雇用環境は変わってきているなと感じています。
2014年の頃はやはり母親も、専業主婦がいいのではないか、何となくそういう空気が流れていて、学生も、女子大を出て一流企業に数年勤めて、何年かしたら結婚する、こういう価値観の中でロールモデルを作っていた雰囲気がありました。
しかし明らかにここ数年で変わってきていると思います。ただ変わってきていますが、ある意味二極化していると感じています。学生も、やはり親元から通いたいし、総合職ではなくて、転勤がなくて、自宅から通えるところがいいという価値観で就職活動を進めている学生もいます。こうしたところでも多様化を感じる昨今です。
酒づくりの職人になる道を選ぶ学生も
例えば今年の4年生の中に1人、島根県の出雲のお酒の職人になるという道を選んだ学生がいます。ご存じのとおり、今まで酒づくりの職人さんは完全に男性社会で、そこに女性は立ち入ってはいけないみたいな空気感のあった世界です。しかし、人手不足などの影響もあってか、初めて大卒の女性の社員を受け入れてくれるということになり、学生が先月その会社に行ったところ、社長さんが至れり尽くせりで、大切なものに触るように、職場から住まいから全部寄り添ってくれたというので、「もう本当にありがたいです」と言っていました。
結局、本人も今まで住んだところと全く違う環境で、自分のやりたかったお酒の職人を選んだということになります。
また、エノキアン協会という、創業から200年以上で、創業家が今も何らかの経営に関わっている企業が加盟できる国際協会があります。この協会に加盟している企業に就職する道を選んだ学生がいます。この学生は国文学科ですから、日本の文化をとことん学びつつ、ずっと教職一本で頑張ってきましたが、ある時企業を探しているうちに、その会社に巡り会って、エントリーシートを提出したのはその会社だけでしたが、御縁があって内定をいただいたというケースもありました。
何十社もエントリーするというやり方もあるし、自分が極めたいところをみつけるやり方もあります。例えば、国文学科の学びとマーケティングをつなぐという授業を私が担当しています。授業のなかで、国文学科の学生を滋賀県にあるお菓子の製造販売を行っている企業に連れて行きました。本当に自然と共生しているような会社で、そこを訪れたことがきっかけで、国文学を勉強していて和に関心があったので、その会社に興味を持ったと同時にその社風に共感して、その学生は今その会社で働いています。
どちらの選択でも学生にとってハッピーなキャリアを選べる環境をつくりたい
何を申し上げたいかというと、やはり自宅から通いたい、転勤がないところなど、家族、保護者の影響も受けているという学生がいる一方で、思い切って未知の世界に踏み出してみようという学生も現れてきているということです。
社会環境も変わり、価値観も多様化するなかで、学生にとって最もハッピーなファーストキャリアを選べるような環境をつくってあげられるかということだと思います。だから、保護者としては大変難しいところだと思います。毎年何人かいますが、複数社から内定をもらって、「母からはこっちがいいと言われていますが、先生、どうですか」と相談してくる学生もいます。
そうした場合は、私としての選択肢は絶対に言わないようにしています。「お母さんがどう言おうと、最後に決めるのはあなただよ」と伝えます。そうしないと、「あのとき先生はこっちの会社がいいと言ったじゃないですか」なんてことになったら、大切な人生の選択ですから大変なことになってしまいますよね。どうか保護者も、最後は子どもに任せるというか、もう社会人ですから、「あなたのやりたい道を選びなさい」と言ってあげるのが一番納得のいくキャリア形成につながるのではないかと思っています。
論点3:女子学生の就職とキャリア選択についての留意点
池田 論点3として、女子学生の就職とキャリア選択についての留意点という議題を用意しています。データではなく、具体的なエピソードを交えて議論を深められたらと思います(シート3)。
シート3
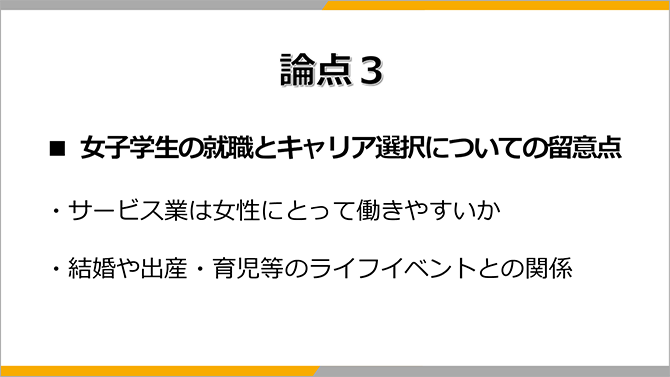
先ほどまでの話の中で、女子学生がかなり思い切った選択をする例が出ました。今回、タイトルを決めるときに、「多様化する」という文言については、労働市場が多様化していることと同時に、就職する選択もまた多様化しているとの意味を含めました。特に今の女性はかつてと比べて労働市場の受け皿が違ってきています。岩脇さんはどう感じられていますか。
情報提供の機会が増えるほど選択肢が増える
岩脇 男性と比べて女性のほうが新しいサービス産業へ就職する割合が高く、親世代から心配される要素が多くなりがちかと思います。一方で、新しい分野で挑戦したいという子どもを応援したい保護者もいらっしゃるかと思います。そういう意味で情報はとても大事だと思います。現在の学校ではキャリア教育が必須とされており、さまざまなキャリアの方の実体験を聞く機会を用意してくれる学校もあります。そういった機会が増えるほど、いろいろな選択肢が子どもの中に増えていくと思います。そうした情報が個人の中で蓄積されると、実現可能性が高いやり方で、できるだけ自分の希望に合うような、理想と現実のすりあわせや就職時の選択をすることが可能になるのではないかと思います。
池田 岩脇さんの冒頭の解説で、サービス業の拡大が女性の雇用の受け皿になり、また、かつて女性が無償で行っていた家事労働やケア労働が市場化されて労働市場を形成しているという話がありました。やはり女子学生にとってサービス業というのは特になじみのある業種なのかもしれないですが、女性という視点に立ったときに、サービス業での就職について思うことや、サービス業を選ぶ女性へのアドバイスがあったら教えてください。
社会サービスは同資格の専門職ならば待遇にジェンダー差が少ない点が魅力
岩脇 女性で最も就職する人が多いサービス産業は医療、福祉、教育です。統計をみても人数が最も多く、学歴もさまざまです。多くの女性が集まるのはそこに魅力があるからだと思います。専門職の資格を取って就職すれば、同じ資格を持つ男性とはほぼ同等の扱いを受けることができ、そこに魅力を感じる女性は大学進学の時点でそういった分野に関連した学部を選ぶと思います。
資格取得を目指して医療・福祉、教育学部に入学している学生であれば、本人がその職業を明確に目指しており、また、大学のカリキュラムの中でその産業で働くことの現実について実習を通じて学ぶので、長時間労働でも頑張るという覚悟を持っていけば長く働けると思います。
ビジネスサービスでは性別職域分離をどう考えるかが課題
新しい産業の中では他にもビジネスサービスと消費者サービスがあり、ビジネスサービスはキャリア形成の環境や賃金も比較的良い傾向にあります。ただ、男女間の賃金格差は社会サービスよりはあります。なぜなら、ビジネスサービスでは業務の配分にジェンダー差があるからです。例えば、男性は企画や営業といった基幹的業務を担う人が多く、女性は顧客サービスや事務を担う人が多いといった役割分担が発生しがちです。
産業全体としては給料の原資が比較的多いので、他の産業で働く女性よりは待遇が良いのですが、会社の中での「特定の仕事しかやらせてもらえない」ことをどう考えるかが課題になってくると思います。
私の報告を聞いて、消費者サービスの望ましくない点だけを強調しているように見られてしまうのが非常に心配ですが、消費者サービスの良いところは、独立起業のチャンスが多いことです。高学歴ではなくても入っていけるという間口の広さに加えて、ビジネスのサイズが小さいので、例えばネイリストやエステティシャンなどのサービス職の場合、新卒時はどこかに雇用されて修業を積んで、お客さんの信頼を勝ち取って、独立して自宅でサロンを開くといったキャリアの選択肢があります。これは大卒よりも専門学校卒の女性がキャリアのゴールとして掲げているケースが結構あります。
雇われているとワーク・ライフ・バランスをとることが厳しい場合もありますが、専門的な技能を身につけて自営すれば、子どもの保育園のお迎えに間に合うように営業時間を設定することもできますし、予約制にしたり、また非都市部の地元でも働けるなど、手に職をつけて細く長く働き続けて、家庭もきちんと守っていきたい人のニーズを、実は消費者サービスはかなえてくれる分野でもあります。
池田 世代によって大きく違っているなと私自身も自分の研究で実感するのが、やはり結婚や出産、育児との兼ね合いについての感覚です。先ほどの長谷川さんのデータでも、結婚する、しないということに関する意識というのが親子で違うとお話しされていましたし、統計的に未婚化は進んでいます。
最近のデータでは、結婚することがキャリアプランの初期段階ではあまり現実的でないという人も増えていると言われます。結婚を考えて就職先を選ぶのか、関係なく、まず飛び込んでみるのか。深澤さんはどうお考えですか。
結婚願望があってもまずはプランを考えずに飛び込んでみるべき
深澤 まずは飛び込んでみることではないかと思います。キャリアに関するアンケートを取ると、若い世代はやはり結婚願望はきちんと持っています。ただ、結婚などをキャリアプランの設計に最初から入れるというより、まずは社会に飛び込んでみるほうが良いのではないでしょうか。
池田 育休制度が充実してきたことなどもありますが、まずはやはり、やりたいことや自分の仕事の中身のほうで選ぶということですね。
深澤 最近の学生をみていると、会社の処遇条件について、やはり女性が働きやすいかどうかは見ています。企業も、男女雇用機会均等法施行から40年もたっているのに、何にも女性に対しての対策が打てていませんということでは生き残れませんから、女性が働きやすい条件を整備しています。ただ、実際に制度が機能して、本当に働きやすいようになっているか、女性社員が活用できているかということをやはり見極める必要があると思います。
学生にアンケートを取ると、最も重視するのは職場の人間関係や雰囲気で、2番目に給与・処遇が来て、3番目が労働時間です。9時に始業して、5時にチャイムが鳴ったらすぐ帰れるという仕事がいいのか、例えば、化粧品の開発に携われて、ある時期はとても忙しく残業もあるけれど、その代わり自分のつくったものがお店に並んで、消費者に買ってもらうというような仕事と比べると、「やりがいはそういう仕事のほうがありますよね」ということになる。
ブラックと言われるような企業は避けたほうがいいですが、若いうちはやっぱり何かにチャレンジしてほしい。自分の情熱をこれにかけてみたいというものに飛び込んでみるところからスタートしていくのがいいのではないかなと思います。
池田 長谷川さんのお話の中で、「結婚せず1人で自由気ままに暮らす」など多様な考えを持った学生がいたと思います。そうすると、仕事と子育ての両立支援などはあまり関係ないように思います。かつてだったら女子学生に人気の先進企業があったと思いますが、そういうのも変わってきているという面はあるのでしょうか。
仕事のやりがいや魅力はキャリアを高めるエンジンになる
長谷川 最近の学生は共働き志向がとても高いです。結婚しても、子どもが生まれても、パートナーそれぞれが仕事を持つのが当たり前だと思っています。これもやはり男女雇用機会均等法など、法律、政策面での効果も当然あるでしょうし、企業側がそういった制度を整えてきたということもあると思います。最近の学生に行きたい会社はどんな感じですかと聞くと、「安定している会社」の次に、「安心して働ける環境である」などがあがります。
安心して働けるかというのは、衛生要因的な部分が大きいのかなと思いますが、やはり自分のキャリアをdrivenしていくときの機動力、エンジンみたいなものが、もしかしたら仕事のやりがいや魅力になってくるのかなと思います。いずれにせよ、キャリアをどんどん上げていこうとか、頑張っていこうと思えるには、ブラックではない、安心して働ける環境も大事になってきます。
最近の学生が共働き志向が高いと考えると、逆に、女性のための制度だけではなく、女子学生のほうでも男性育休取得率を見ることもあるでしょうし、やはりライフイベントに対して片方だけではなく、夫婦ともに関われる環境があるというところは衛生要因の部分でも大事だと思います。キャリアと就業環境のバランスは結構重要になってくるのかなと、いまお話をうかがって思います。
池田 この何十年間を振り返ると、花形企業や女性が活躍できる先進企業が親世代にとっては労働市場におけるシンボリックなイメージとして持ちやすかったと思います。今は女性が働くと一言で言っても、その働く場所もさまざまになっていますし、女性が安心して働けるとか、結婚、出産、子育て、両立支援という面でも、いろいろな企業に取り組みが広がってくると、もうある程度の最低水準としてはあって当たり前だと思います。そのうえで自分が何をしたいかという話になってくると、労働市場の見え方がある意味フラットになっていく面があるのかなという印象を持ちました。
そこで、西村さんにうかがいたいのは企業の人事戦略についてです。両立支援の整備などは伝統的な企業でももう当たり前になっているということでいうと、かつての男性的な企業においても、人事戦略においてフラットになっている面があるのでしょうか。どの業界でもある程度女性が働き活躍できる場所があって、そこの広がりがかなりあるように感じますが、どうでしょうか。
働き方のニーズをどこまで充足してくれるのかを重視している印象
西村 かつてと比べ、その偏りはなくなってきているのではないでしょうか。そのことが影響しているのかもしれませんが、私が知っている範囲の学生にはなりますが、初職を選ぶときに育児支援については、そこまで重視はしていない印象です。
先のことすぎてはっきりとイメージできないというのもあるのでしょうが、それ以上に、長谷川さんの報告でもあったように、「管理職ではなく、現場に携わり続けたい」といった、働き方に対するニーズをどこまで充足してくれるのかを重視している傾向が、男女を問わずあるのかなと思います。
それに関連して言うと、岩脇さんの分類で、消費者サービスが女性の受け皿になっているというお話がありました。かつて企業の中途採用の調査をしたときに印象的だったのが、消費者サービスに属する企業では、自社の管理職をどちらかというとビジネスサービスから中途採用で確保しようとしている企業も見られたことです。
新卒一括採用も行っていますが、基本的には一括採用した人は現場で活躍してもらう。そういう人事管理の大企業もあります。学生と話をしていると、「ずっと現場にいたい」「店舗で接客したい」というニーズが少なからずあります。
そういう意味では、消費者サービスで見られた人材活用が、学生の一定層のニーズとマッチしている部分はあるのかもしれません。
池田 大卒で採用しても、管理職候補としてみていないような人事管理を行っている可能性がある企業がサービス業の中にあるかもしれないということですか。初期キャリアだけではなく、将来を見通した際の管理職養成が製造業など他業種と異なることが、逆に若い人の感覚とマッチしているという点は面白い論点だと思います。
入り口でのエリート・ノンエリートの明確化を望む学生もいる
西村 どちらかといえば欧州タイプの人事管理、つまり、入り口である程度、最高到達点みたいなものが想定されていて、その中で人材活用していくみたいなものに近い人事管理と言ったらいいのでしょうか。
学生と話していても、例えば早期選抜でエリートとノンエリートを明確化するということについてどう思うかと聞くと、明確化してくれたほうが、「自分はノーマルでいいんだと思えていいです」と言う学生もいます。
その意味では、入り口である程度分けてしまう人事管理が、学生の一定層のニーズと合致している部分はあるのかもしれません。
池田 まだまだサービス業の人事管理は整理されていないことも多いので、今日見えてきたことを1つの足がかりにして、これから労働市場に出ていく若い人にとって参考になるような話を、われわれも研究者としてこれから掘り下げていかなければいけないとあらためて思いました。
論点4:これからの若者の就職とキャリアの展望
池田 若年人口が減少していくトレンドの中で、新卒就職だけではなく、中途採用など、若い労働力を確保していこうという考え方が企業にこれから広がっていくのではないかと思います(シート4)。
シート4
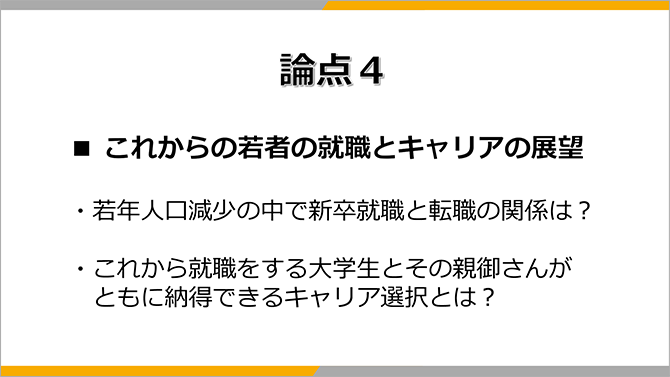
中途採用が少しずつ若い人に広がっていくことで、新卒採用だけに全力集中せず、若いときのキャリアを柔軟化していくということでいうと、新卒就職と転職の関係というのはこれからどのようになっていくでしょうか。
転職すればキャリアがステップアップするわけではない
西村 一言で中途採用といってもいろいろあると思います。新卒採用で十分な数が採れなかったから、それを補充する目的で行われる中途採用もあれば、管理職を外部から直接採るというようなヘッドハンティングに近いような中途採用もあります。新規事業の展開に必要な高い専門技術を持っている人材を中途採用することもあります。新卒代替型の中途採用もあれば、補完型の中途採用もあります。中途採用の多様性を念頭に置いた、冷静な議論が必要なのではないでしょうか。
転職を重ねればキャリアがステップアップするというわけでもないですし、かといって、新卒から定年まで1つの企業に勤め続けることがキャリアとして成功なのかというと、それも違う。
ただ、企業が中途採用をより積極的に活用しようとしていることは事実だと思います。また、労働者側も転職するというハードルは下がってきているのではないでしょうか。しかし、これが新しい動きなのか、それとも、日本でもかつては中途採用が盛んだった時代はありますので、昔に戻ったのかは現時点では正直なところわからないです。中途採用の多様性を考慮したうえで、見極めていく必要があると思います。
池田 すぐ辞めてしまうのではなく、ある程度自分に合った仕事を若いときの何年間かの間で探していく期間を少し長く取るような風潮になってくるのかどうか。岩脇さん、労働市場が変わっていくうえで、これからの若者のキャリアはどう変わっていくと考えられますか。
子世代は「やりたいこと」「したい生き方」を叶えるために転職する
岩脇 私は氷河期世代なので、氷河期まではまだ、従来型産業、つまり製造業中心の時代の定年まで働くようなキャリアのあり方が本来のあるべき姿だ、という社会でした。しかし実際は私たちの世代でも、転職した人は結構います。新卒のときの就職があまりよくなかったので、再チャレンジする人が多く、実は親世代は転職をしている。ただ、「本来するべきじゃなかったけど、転職をした」という感覚なのだと思います。
それに対して今の若い人はそういう感覚はあまりなく、「自分のやりたいことができるところに移動するために転職する」「自分の望む生活のあり方のために転職する」など、シンプルに考えていると思います。転職の意味がまず変わっている。転職が増えるかどうかはわからないですが、転職の心理的なハードルは下がっているとは思います。
日本でのキャリア教育は、そもそも就職氷河期世代がうまく就職できなかったので、これを何とかしようということで始まりました。深澤さんがおっしゃるように、主体性がとても重視されるようになってきて、学校でのキャリア教育も、自分で自分のやりたいことを見つけて、居場所を社会の中で見つけて、そのために就職するんだよと指導するようになっている。
そうすると、職業(やりたいこと)への意識がどんどん高まる反面、就職先でそのやりたいことが叶えられなければ転職するというのは、とても自然な流れだと思います。今のキャリア教育を学校で受けると、そういう流れにならざるを得ない、というか、そうなっていくと思います。そういった教育政策の大きな流れと、長期雇用型の雇用管理をあまり行わない新しいサービス産業が拡大しつつあること、さらに若年人口が減り、転職市場も売り手市場化するなかで、転職へのハードルはきっと下がっていくだろうと思います。
また、社会サービスや消費者サービスなどの分野では、転職しないと新しいキャリアステップができない場合もあります。例えば看護師さんにインタビュー調査したのですが、こういう分野の手術の担当をするオペ看護師になりたいと思ったら、大病院の入院病棟に配属されないとできない仕事なわけだから、最初の就職先がもしクリニックだったら、転職しないとその仕事はできないということでした。
池田 深澤さん、学生はある程度、転職ありきで新卒のときから考えていますか。
最低5年や10年、仕事を経験してから転職すべき
深澤 考えている学生が多いと思います。私も別に転職を否定もしません。特に今、岩脇さんがおっしゃったように、ステップアップして、やりたいことを見つけていくということについては否定しないです。ただ、短い期間でというのが気になります。
当然、新卒採用はポテンシャルでみる。だから、ガクチカ(学生時代に力を入れること)重視になる。でも、転職では、前の企業でどういう成果を残してきたかというエビデンスベースが問われるので、私が学生に伝えているのは、やっぱり最低5年とか、あるいは10年の経験が必要になるということです。今は年齢に関係なく転職できる時代になっているからこそ、やはり実績のことを考えて、じっくりと検討する必要がある。
そして、できれば企業さんにはもう少し採用の時期や今の採用のあり方を考えていただきたいと思います。大学もしっかりとキャリア科目を実施し、本当にここでスタートできると学生が確信を得て就職をし、それでファーストキャリアを5年~10年なり勤めて、そこからキャリアアップを図るというような形に社会構造を変えていかないといけない。
今は人手不足で、少しでも早く採用したいという企業の状況はよく理解できますが、社会全体でもう少し学生が学生らしく学べる期間を取って、社会とシームレスな世の中になればいいと思っています。
池田 長谷川さんのデータでは、保護者は子どもが就職したら子育てが終わったと考えるとありましたが、いろいろ親子で話し合って決めたのに、新卒入社して数年で辞めてしまうとなると、保護者の心配事が増えると思いますがいかがですか。
また、転職がキャリアアップにつながるような業種が増えているとか、転職されてしまうことをある程度織り込んでいる求人もあるなど、若者の転職に関して、そういった印象はありますか。
いまでもファーストキャリアを大事にする学生が多い
長谷川 学生の意識に関していうと、ファーストキャリアで人生のいろいろなことが決まってくるのではないかと思っている学生がいまだに多いです。しかも、「入社した会社で何年働きたいですか」と聞くと、「まだわからない」と言う学生がもちろん多いですが、2番目に多いのが実は「定年まで働きたい」という回答です。
いわゆる就職ファストパスや選考ファストパスのように、新卒採用でタッチした学生に中途採用で優遇する、といった報道もありました。学生の側から見れば選択肢が増え、企業にとっても学生や求職者とタッチポイントが増えるということもあるとは思いますが、やはり学生としては、新卒採用で入社する企業で積むことになるファーストキャリアは、大きな存在感を持っていると言えます。
仮に1社目を経験するなかで、自身のキャリアイメージと齟齬が出たり、あるいは働くなかでキャリアイメージがより変化することによって、結果的に転職することになったとしても、転職するうえで自身が身につけたスキルは重要になります。入社した会社が自身のキャリア観と合致し、安心してキャリア形成できる企業であればそのまま長くキャリアを築いていくこともできると思いますし、もし何かしら違った形で、ほかの仕事や業界に対する興味・関心が生まれたということであれば、その会社で培ったスキルや能力が次の環境で活躍するためのポータブルスキルになっていく、ということだと思います。
そういった意味でも、新卒で能力が生かせるところにちゃんと入るというのは、その後、働き続けるにしても、違うキャリアを歩むにしても、学生にとって重要であることは変わっていないと思います。
典型的なイメージにとらわれることなく親子で対話を
池田 これから就職する大学生とその保護者が納得できる就職活動というのは、労働市場のあり方というものがよくわかったうえで、キャリア選択ができるということだと思います。今回のフォーラムでは、そのためのヒントをたくさんお届けしたいと思って、いろいろな角度から議論してきました。
転職が多いか少ないかではなく、転職のハードル自体が下がっているとか、花形企業じゃなくていろいろな働き方や仕事の選択肢があるとか、いわゆる典型的なイメージにとらわれることなく、フラットに労働市場をみながら、親子で対話していくことが大事なのかなと思いました。
新しい企画で、初めてのことだらけの労働政策フォーラムでした。アカデミックな分析から現場に根差したデータ、そして学生から聞く生の声、いろいろな企業の視点が入り交じったところで、少しでも皆さんのお役に立つ労働政策フォーラムになっていたら本当にうれしいと思います。長時間にわたり、ありがとうございました。
プロフィール
西村 純(にしむら・いたる)
中央大学 商学部 准教授
同志社大学社会学研究科博士課程後期課程修了(博士:産業関係学)。(独)労働政策研究・研修機構研究員、副主任研究員を経て、2025年より現職。専攻は労使関係論、人的資源管理論。『スウェーデンの賃金決定システム:賃金交渉の実態と労使関係の特徴』(ミネルヴァ書房、2014年)で第29回冲永賞を受賞。最近の著書として、『雇用流動化と日本経済─ホワイトカラーの採用と転職』(2022年、労働政策研究・研修機構)〔共著〕、『新・マテリアル人事労務管理』(有斐閣、2023年)〔共編著〕など。


