労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働八二)
2022年4月15日
厚生労働省令 第八十二号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第百十三条及び第百十五条の二の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和四年四月十五日
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
目次 第一編・第二編 (略) 第三編 (略) 第一章 (略) 第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業(第五百九十二条の二-第五百九十二条の八) 第二章~第九章 (略) 第四編 (略) 附則 (保護具) |
目次 第一編・第二編 (略) 第三編 (略) 第一章 (略) 第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業(第五百九十二条の二-第五百九十二条の七) 第二章~第九章 (略) 第四編 (略) 附則 (保護具) |
第三百二十七条 (略) |
第三百二十七条 (略) |
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、腐食性液 体の飛散、漏えい又は
|
(新設) |
3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の保護具の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。 |
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護具の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。 |
(騒音を発する場所の明示等) |
(騒音を発する場所の明示等) |
第五百八十三条の二 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。 |
第五百八十三条の二 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。 |
(立入禁止等) |
(立入禁止等) |
第五百八十五条 事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
第五百八十五条 事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
一~七 (略) |
一~七 (略) |
2 前項の規定により立入りを禁止された場所の周囲において作業に従事する者は、当該場所には、みだりに立ち入つてはならない。 |
2 労働者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入つてはならない。 |
(付着物の除去) |
(付着物の除去) |
第五百九十二条の三 事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。 |
第五百九十二条の三 事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業を行うときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。 |
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化) |
(ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化) |
第五百九十二条の四 (略) |
第五百九十二条の四 (略) |
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとする必要がある旨を周知させなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。 |
(新設) |
(保護具) |
(保護具) |
第五百九十二条の五 (略) |
第五百九十二条の五 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。ただし、第一項ただし書の場合は、この限りでない。 |
(新設) |
(掲示) |
|
第五百九十二条の八 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。 |
(新設) |
一 第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う作業場である旨 |
|
二 ダイオキシン類により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 |
|
三 ダイオキシン類の取扱い上の注意事項 |
|
四 第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う場合においては適切な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具 |
|
第二章 保護具等 |
第二章 保護具等 |
(呼吸用保護具等) |
(呼吸用保護具等) |
第五百九十三条 (略) |
第五百九十三条 (略) |
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(皮膚障害等防止用の保護具) |
(皮膚障害等防止用の保護具) |
第五百九十四条 事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具を備えなければならない。 |
第五百九十四条 事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は
|
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(騒音障害防止用の保護具) |
(騒音障害防止用の保護具) |
第五百九十五条 (略) |
第五百九十五条 (略) |
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、耳栓その他の保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
3 事業者は、第一項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。 |
2 事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。 |
4 事業者は、第二項の請負人に耳栓その他の保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、遅滞なく当該保護具を使用する必要がある旨を、見やすい場所に掲示しなければならない。 |
(新設) |
(ふく射熱からの保護) |
(ふく射熱からの保護) |
第六百八条 (略) |
第六百八条 (略) |
2 事業者は、屋内作業場に前項の溶融炉等があるときは、当該屋内作業場において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該溶融炉等の放射するふく射熱からの保護措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。ただし、加熱された空気を直接屋外に排出するときは、この限りでない。 |
(新設) |
(加熱された炉の修理) |
(加熱された炉の修理) |
第六百九条 事業者は、加熱された炉の修理に際しては、当該炉の修理に係る作業に従事する者が適当に冷却される前にその内部に入ることについて、当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つてはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 |
第六百九条 事業者は、加熱された炉の修理に際しては、適当に冷却した後でなければ、労働者をその内部に入らせてはならない。 |
(有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第二条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(短時間有機溶剤業務を行う場合の設備の特例) |
(短時間有機溶剤業務を行う場合の設備の特例) |
第九条 (略) |
第九条 (略) |
2 事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、送気マスクを備えたとき(当該場所における有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、送気マスクを備え、かつ、当該請負人に対し、 |
2 事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、送気マスクを備えたときは、第五条又は第六条の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができる。 |
送気マスクを備える必要がある旨を周知させるとき)は、第五条又は第六条の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができる。 |
|
第十三条の二 事業者は、第五条の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(有機溶剤の蒸気の発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。 |
第十三条の二 事業者は、第五条の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(有機溶剤の蒸気の発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 前号の有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用する必要がある旨を周知させること。 |
(新設) |
2 (略) |
2 (略) |
第十三条の三 (略) |
第十三条の三 (略) |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。 |
5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。 |
三 前二号に定めるもののほか、事業者は、当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。 |
四 事業者は、当該許可に係る作業場において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。 |
(新設) |
6・7 (略) |
6・7 (略) |
(換気装置の稼働) |
(換気装置の稼働) |
第十八条 (略) |
第十八条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の局所排気装置を設けた場合であつて、有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該有機溶剤業務に従事する間(労働者が当該有機溶剤業務に従事するときを除く。)、当該局所排気装置を第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速以上の制御風速で稼働させること等について配慮しなければならない。ただし、第十六条第二項各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、同項に規定する制御風速以上の制御風速で稼働させること等について配慮すれば足りる。 |
(新設) |
4 (略) |
3 (略) |
5 事業者は、前項のプッシュプル型換気装置を設けた場合であつて、有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該有機溶剤業務に従事する間(労働者が当該有機溶剤業務に従事するときを除く。)、当該プッシュプル型装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
6 (略) |
4 (略) |
7 事業者は、前項の全体換気装置を設けた場合であつて、有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該有機溶剤業務に従事する間(労働者が当該有機溶剤業務に従事するときを除く。)、当該全体換気装置を前条第一項の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる一分間当たりの換気量以上の換気量で稼働させること等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
8 (略) |
5 (略) |
(局所排気装置の稼働の特例) |
(局所排気装置の稼働の特例) |
第十八条の二 前条第一項の規定にかかわらず、過去一年六月間、当該局所排気装置に係る作業場に係る第二十八条第二項及び法第六十五条第五項の規定による測定並びに第二十八条の二第一項の規定による当該測定の結果の評価が行われ、当該評価の結果、当該一年六月間、第一管理区分に区分されることが継続した場合であつて、次条第一項の許可を受けるために、同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、当該局所排気装置を第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で稼働させることができる。 |
第十八条の二 前条第一項の規定にかかわらず、過去一年六月間、当該局所排気装置に係る作業場に係る第二十八条第二項及び法第六十五条第五項の規定による測定並びに第二十八条の二第一項の規定による当該測定の結果の評価が行われ、当該評価の結果、当該一年六月間、第一管理区分に区分されることが継続した場合であつて、次条第一項の許可を受けるために、同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、当該局所排気装置を第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で稼働させることができる。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 前号の有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用する必要がある旨を周知させること。 |
(新設) |
2 (略) |
2 (略) |
(有機溶剤作業主任者の職務) |
(有機溶剤作業主任者の職務) |
第十九条の二 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 |
第十九条の二 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
四 タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号( 第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。 |
四 タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。 |
(掲示) |
(掲示) |
第二十四条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。 |
第二十四条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。 |
一 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 |
一 有機溶剤の人体に及ぼす作用 |
二・三 (略) |
二・三 (略) |
四 次に掲げる場所にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具 |
(新設) |
イ 第十三条の二第一項の許可に係る作業場(同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときに限る。) |
|
ロ 第十三条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場 |
|
ハ 第十八条の二第一項の許可に係る作業場(同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときに限る。) |
|
ニ 第二十八条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所 |
|
ホ 第三十二条第一項各号に掲げる業務を行う作業場 |
|
ヘ 第三十三条第一項各号に掲げる業務を行う作業場 |
|
2 (略) |
2 (略) |
(有機溶剤等の区分の表示) |
(有機溶剤等の区分の表示) |
第二十五条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。 |
第二十五条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。 |
2 (略) |
2 (略) |
(タンク内作業) |
(タンク内作業) |
第二十六条 事業者は、タンクの内部において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第二十六条 事業者は、タンクの内部において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
一 作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部を全て開放すること。 |
一 作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部をすべて開放すること。 |
二 当該有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該有機溶剤業務に従事するときを除く。)は、当該請負人の作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部を全て開放すること等について配慮すること。 |
(新設) |
三 (略) |
二 (略) |
四 当該有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体が有機溶剤等により著しく汚染されたとき、及び作業が終了したときは、直ちに身体を洗浄し、汚染を除去する必要がある旨を周知させること。 |
(新設) |
五 (略) |
三 (略) |
六 有機溶剤等を入れたことのあるタンクについては、作業開始前に、次の措置を講ずること。 |
四 前各号に掲げる措置のほか、有機溶剤等を入れたことのあるタンクについては、作業開始前に、次の措置を講ずること。 |
イ 有機溶剤等をタンクから排出し、かつ、タンクに接続する全ての配管から有機溶剤等がタンクの内部へ流入しないようにすること。 |
イ 有機溶剤等をタンクから排出し、かつ、タンクに接続するすべての配管から有機溶剤等がタンクの内部へ流入しないようにすること。 |
ロ・ハ (略) |
ロ・ハ (略) |
七 当該有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該有機溶剤業務に従事するときを除く。)は、有機溶剤等を入れたことのあるタンクについては、当該請負人の作業開始前に、前号イからハまでに掲げる措置を講ずること等について配慮すること。 |
(新設) |
(事故の場合の退避等) |
(事故の場合の退避等) |
第二十七条 事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当する事故が発生し、有機溶剤による中毒の発生のおそれのあるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を当該事故現場から退避させなければならない。 |
第二十七条 事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当する事故が発生し、有機溶剤による中毒の発生のおそれのあるときは、直ちに作業を中止し、労働者を当該事故現場から退避させなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
2 事業者は、前項の事故が発生し、作業を中止したときは、当該事故現場の有機溶剤等による汚染が除去されるまで、作業に従事する者が当該事故現場に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、安全な方法によつて、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。 |
2 事業者は、前項の事故が発生し、作業を中止したときは、当該事故現場の有機溶剤等による汚染が除去されるまで、労働者を当該事故現場に立ち入らせてはならない。ただし、安全な方法によつて、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。 |
(評価の結果に基づく措置) |
(評価の結果に基づく措置) |
第二十八条の三 (略) |
第二十八条の三 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。 |
3 前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
4 事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(緊急診断) |
(緊急診断) |
第三十条の四 (略) |
第三十条の四 (略) |
2 事業者は、有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに医師による診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(送気マスクの使用) |
(送気マスクの使用) |
第三十二条 (略) |
第三十二条 (略) |
2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
3 第十三条の二第二項の規定は、第一項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。 |
2 第十三条の二第二項の規定は、前項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。 |
(送気マスク又は有機ガス用防毒マスクの使用) |
(送気マスク又は有機ガス用防毒マスクの使用) |
第三十三条 (略) |
第三十三条 (略) |
2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
3 第十三条の二第二項の規定は、第一項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。 |
2 第十三条の二第二項の規定は、前項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。 |
(有機溶剤等の貯蔵) |
(有機溶剤等の貯蔵) |
第三十五条 事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。 |
第三十五条 事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのないふた又は
|
一 当該屋内で作業に従事する者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備 |
一 関係労働者以外の労働者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備 |
二 (略) |
二 (略) |
(鉛中毒予防規則の一部改正)
第三条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
目次 |
目次 |
第一章~第四章 (略) |
第一章~第四章 (略) |
第一節~第三節 (略) |
第一節~第三節 (略) |
第四節 清潔の保持等(第四十五条-第五十一条の二) |
第四節 清潔の保持等(第四十五条-第五十一条) |
第五章~第八章 (略) |
第五章~第八章 (略) |
附則 |
附則 |
(適用の除外) |
(適用の除外) |
第三条 この省令(第一章、第二十二条、第三十二条、第三十五条から第三十九条まで、第四章第三節、第四十六条(第五十八条第三項第五号に係る部分に限る。)、第五十八条第三項、第四項、第七項から第九項まで(同条第三項第五号及び第三十九条第一項ただし書に係る部分に限る。)、第五十六条並びに第五十七条の規定を除く。)は、事業者が次の各号のいずれかに該当する鉛業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。 |
第三条 この省令(第一章、第二十二条、第三十二条、第三十五条から第三十九条まで、第四章第三節、第四十六条(第五十八条第二項第五号に係る部分に限る。)、第五十八条第二項、第四項及び第五項(第二項第五号及び第三十九条ただし書に係る部分に限る。)、第五十六条並びに第五十七条の規定を除く。)は、事業者が次の各号のいずれかに該当する鉛業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。 |
一 鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、五十リットルを超えない作業場における四百五十度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務 |
一 鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、五十リツトルを超えない作業場における四百五十度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務 |
二~四 (略) |
二~四 (略) |
(労働基準監督署長の許可に係る設備の特例) |
(労働基準監督署長の許可に係る設備の特例) |
第二十三条の三 (略) |
第二十三条の三 (略) |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第五十二条第一項の測定の結果の評価が第五十二条の二第一項の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。 |
5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第五十二条第一項の測定の結果の評価が第五十二条の二第一項の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。 |
三 前二号に定めるもののほか、事業者は、当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。 |
四 当該許可に係る作業場については、作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。 |
(新設) |
6・7 (略) |
6・7 (略) |
(換気装置の稼動) |
(換気装置の稼動) |
第三十二条 事業者は、局所排気装置(第二条に規定する局所排気装置及び前章の規定により設ける局所排気装置をいう。以下この条において同じ。)、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒(第二条に規定する排気筒及び前章の規定により設ける排気筒をいう。以下この条において同じ。)を設けたときは、労働者が鉛業務に従事する間、当該装置を厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させなければならない。 |
第三十二条 事業者は、局所排気装置(第二条に規定する局所排気装置及び前章の規定により設ける局所排気装置をいう。次項において同じ。)、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒(第二条に規定する排気筒及び前章の規定により設ける排気筒をいう。次項において同じ。)を設けたときは、労働者が鉛業務に従事する間、当該装置を厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させなければならない。 |
2 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒を設けた場合において、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が鉛業務に従事する間(労働者が鉛業務に従事するときを除く。)、当該装置を前項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させること等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
3 事業者は、前二項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒の稼動時においては、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼動させるために必要な措置を講じなければならない。 |
2 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒を稼動させるときは、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼動させるために必要な措置を講じなければならない。 |
(作業主任者の職務) |
(作業主任者の職務) |
第三十四条 事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 |
第三十四条 事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたことを発見したときは、速やかに、汚染を除去させること。 |
二 鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたことを発見したときは、すみやかに、汚染を除去させること。 |
三・四 (略) |
三・四 (略) |
五 令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条第一項各号に定める措置が講じられていることを確認すること。 |
五 令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。 |
(汚染の除去に係る周知) |
|
第三十四条の二 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたときは、速やかに汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(ホッパーの下方における作業) |
(ホツパーの下方における作業) |
第三十九条 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働者を作業させてはならない。ただし、当該場所において臨時の作業に労働者を従事させる場合において、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるときは、この限りでない。 |
第三十九条 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホツパーに入れる作業を行なう場合において、当該ホツパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働者を作業させてはならない。ただし、当該場所において臨時の作業に労働者を従事させる場合において、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるときは、この限りでない。 |
2 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときであつて、当該場所において労働者以外の者が作業を行うおそれのあるときは、当該場所において労働者以外の者が作業することについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、当該場所において労働者以外の者が臨時の作業に従事する場合において、当該者に有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるときは、この限りでない。 |
(新設) |
(含鉛塗料のかき落とし) |
(含鉛塗料のかき落とし) |
第四十条 事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第四十条 事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 かき落とした含鉛塗料は、速やかに、取り除くこと。 |
二 かき落とした含鉛塗料は、すみやかに、取り除くこと。 |
2 事業者は、前項の鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該鉛業務は、湿式による必要がある旨を周知させなければならない。ただし、当該鉛業務を湿式によることが著しく困難な場合は、この限りでない。 |
(新設) |
3 事業者は、前項の請負人に対し、かき落とした含鉛塗料は、速やかに取り除く必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(鉛化合物のかき出し) |
(鉛化合物のかき出し) |
第四十一条 事業者は、鉛化合物の焼成炉からのかき出しの鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第四十一条 事業者は、鉛化合物の焼成炉からのかき出しの鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
一 鉛化合物を受けるためのホッパー又は容器は、焼成炉のかき出し口に接近させること。 |
一 鉛化合物を受けるためのホツパー又は容器は、焼成炉のかき出し口に接近させること。 |
二 (略) |
二 (略) |
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項各号の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(鉛装置の内部における業務) |
(鉛装置の内部における業務) |
第四十二条 事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第四十二条 事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
一 作業開始前に、当該鉛装置とそれ以外の装置で稼働させるものとの接続箇所を確実に遮断すること。 |
一 作業開始前に、当該鉛装置とそれ以外の装置で
|
二・三 (略) |
二・三 (略) |
四 作業終了後、速やかに、当該労働者に洗身をさせること。 |
四 作業終了後、すみやかに、当該労働者に洗身をさせること。 |
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第一号から第三号までの措置を講ずる必要がある旨並びに作業終了後、速やかに洗身する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(休憩室) |
(休憩室) |
第四十五条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。 |
第四十五条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行なう作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。 |
2 事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。 |
2 事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。 |
一 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去するための設備を設けること。 |
一 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマツトを置く等労働者の足部に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去するための設備を設けること。 |
二 (略) |
二 (略) |
三 床は、真空掃除機を用いて、又は水洗によつて容易に掃除できる構造のものとすること。 |
三 床は、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。 |
3 鉛業務に従事した者は、第一項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去しなければならない。 |
3 労働者は、鉛業務に従事した場合は、第一項の休憩室にはいる前に、作業衣等に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去しなければならない。 |
(作業衣等の保管設備) |
(作業衣等の保管設備) |
第四十六条 事業者は、第五十八条第一項、第三項若しくは第五項又は第五十九条第一項の規定により労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、当該労働者にこれを使用させなければならない。 |
第四十六条 事業者は、第五十八条又は第五十九条の規定により労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、当該労働者にこれを使用させなければならない。 |
2 事業者は、第五十八条第二項、第四項若しくは第六項又は第五十九条第二項の請負人に対し、当該請負人が使用し、又は着用する呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し前項の設備を使用させる等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければならない。 |
(新設) |
(洗身設備) |
(洗身設備) |
第四十七条 (略) |
第四十七条 (略) |
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、必要に応じ、洗身する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し同項の設備を使用させる等適切に洗身が行われるよう必要な配慮をしなければならない。 |
(新設) |
(手洗い用溶液等) |
(手洗い用溶液等) |
第四十九条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、爪ブラシ、石けん及びうがい液(以下この条において「手洗い用溶液等」という。)を作業場ごとに備え、作業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使用させなければならない。 |
第四十九条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、つめブラシ、石けん及びうがい液を作業場ごとに備え、作業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使用させなければならない。 |
2 労働者は、鉛業務に従事したときは、作業終了後及び必要に応じ、手洗い用溶液等を使用しなければならない。 |
2 労働者は、鉛業務に従事したときは、作業終了後及び必要に応じ、前項の硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、つめブラシ、石けん及びうがい液を使用しなければならない。 |
3 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後及び必要に応じ、手洗い用溶液等を使用する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し手洗い用溶液等を使用させる等適切に手洗い用溶液等の使用が行われるよう必要な配慮をしなければならない。 |
(新設) |
(作業衣等の汚染の除去) |
(作業衣等の汚染の除去) |
第五十条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、洗濯のための設備を設ける等作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない。 |
第五十条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、洗たくのための設備を設ける等作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない。 |
2 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(喫煙等の禁止) |
(喫煙等の禁止) |
第五十一条 事業者は、鉛業務を行う屋内の作業場所における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場所の見やすい箇所に表示しなければならない。 |
第五十一条 事業者は、鉛業務を行なう屋内の作業場所で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場所の労働者が見やすい箇所に表示しなければならない。 |
2 前項の作業場所において作業に従事する者は、当該作業場所で喫煙し、又は飲食してはならない。 |
2 労働者は、前項の作業場所で喫煙し、又は飲食してはならない。 |
(掲示) |
|
第五十一条の二 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。 |
(新設) |
一 鉛業務を行う作業場である旨 |
|
二 鉛により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 |
|
三 鉛等の取扱い上の注意事項 |
|
四 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等 |
|
イ 第二十三条の三第一項の許可に係る作業場であつて、次条第一項の測定の結果の評価が第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場 |
|
ロ 第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所 |
|
ハ 令別表第四第九号に掲げる鉛業務を行う作業場 |
|
ニ 第五十八条第三項各号に掲げる業務を行う作業場 |
|
ホ 第五十八条第五項各号に掲げる業務を行う作業場(有効な局所排気装置、プッシュプル型排気装置、全体換気装置又は排気筒(鉛等若しくは焼結鉱等の溶融の業務を行う作業場所に設ける排気筒に限る。)を設け、これらを稼動させている作業場を除く。) |
|
ヘ 第五十九条第一項の業務を行う作業場 |
|
第五章 測定 |
第五章 測定 |
(評価の結果に基づく措置) |
(評価の結果に基づく措置) |
第五十二条の三 (略) |
第五十二条の三 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。 |
3 前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
4 事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(診断) |
(診断) |
第五十六条 事業者は、労働者を鉛業務に従事させている期間又は鉛業務に従事させなくなつてから四週間以内に、腹部の
|
第五十六条 事業者は、労働者を鉛業務に従事させている期間又は鉛業務に従事させなくなつてから四週間以内に、腹部の
|
2 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、鉛業務に従事する期間又は鉛業務に従事しなくなつてから四週間以内に、前項の病状があるときは、速やかに医師による診断を受ける必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(鉛中毒にかかつている者等の就業禁止) |
(鉛中毒にかかつている者等の就業禁止) |
第五十七条 事業者は、鉛中毒にかかつている労働者及び第五十三条第一項又は第三項の健康診断又は前条第一項の診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事させてはならない。 |
第五十七条 事業者は、鉛中毒にかかつている労働者及び第五十三条第一項又は第三項の健康診断又は前条の診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事させてはならない。 |
2 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、鉛中毒にかかつているとき又は鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めたときは、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(呼吸用保護具等) |
(呼吸用保護具等) |
第五十八条 (略) |
第五十八条 (略) |
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
3 事業者は、第一項の業務以外の業務で、次の各号のいずれかに該当するものに労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。 |
2 事業者は、前項の業務以外の業務で、次の各号のいずれかに該当するものに労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。 |
一 第一条第五号イ、ロ若しくはヘに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務 |
一 第一条第五号イ、ロ若しくはヘに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行なう作業場所における清掃の業務 |
二~六 (略) |
二~六 (略) |
4 事業者は、第一項の業務以外の業務で、前項各号のいずれかに該当するものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
5 事業者は、第一項及び第三項に規定する業務以外の業務で、次の各号のいずれかに該当するものに労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。ただし、当該業務を行う作業場所に有効な局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒(鉛等若しくは焼結鉱等の溶融の業務を行う作業場所に設ける排気筒に限る。)を設け、これらを稼動させるときは、この限りでない。 |
3 事業者は、前二項に規定する業務以外の業務で、次の各号のいずれかに該当するものに労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。ただし、当該業務を行なう作業場所に有効な局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒(鉛等若しくは焼結鉱等の溶融の業務を行なう作業場所に設ける排気筒に限る。)を設け、これらを
|
一~三 (略) |
一~三 (略) |
6 事業者は、第一項及び第三項に規定する業務以外の業務で、前項各号のいずれかに該当するものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。 |
(新設) |
7 第一項、第三項若しくは第五項の規定又は第三十九条第一項ただし書の規定により労働者にホースマスクを使用させるときは、当該ホースマスクの空気の取入口を有害な空気がない場所に置かなければならない。 |
4 前三項の規定又は第三十九条ただし書の規定により労働者にホースマスクを使用させるときは、当該ホースマスクの空気の取入口を有害な空気がない場所に置かなければならない。 |
8 事業者は、第二項、第四項若しくは第六項の請負人又は第三十九条第二項ただし書の労働者以外の者がホースマスクを使用するときは、当該ホースマスクの空気の取入口を有害な空気がない場所に置く必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
9 第一項、第三項若しくは第五項に規定する業務又は第三十九条第一項ただし書の作業に従事する労働者は、当該業務又は作業に従事する間、第一項、第三項若しくは第五項又は第三十九条第一項ただし書に規定する呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用しなければならない。 |
5 第一項から第三項までに規定する業務又は第三十九条ただし書の作業に従事する労働者は、当該業務又は作業に従事する間、第一項から第三項まで又は第三十九条ただし書に規定する呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用しなければならない。 |
(作業衣) |
(作業衣) |
第五十九条 (略) |
第五十九条 (略) |
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣又は労働衛生保護衣類を着用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
3 第一項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、作業衣又は労働衛生保護衣類を着用しなければならない。 |
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、作業衣又は労働衛生保護衣類を着用しなければならない。 |
(四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)
第四条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
目次 |
目次 |
第一章 (略) |
第一章 (略) |
第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置(第二条-第二十一条の二) |
第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置(第二条-第二十一条) |
第三章・第四章 (略) |
第三章・第四章 (略) |
附則 |
附則 |
(四アルキル鉛の製造に係る措置) |
(四アルキル鉛の製造に係る措置) |
第二条 事業者は、令別表第五第一号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第二条 事業者は、令別表第五第一号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 作業場所をそれ以外の作業場所その他関係者が立ち入る場所から隔離すること。 |
二 作業場所をそれ以外の作業場所その他労働者が立ち入る場所から隔離すること。 |
三 (略) |
三 (略) |
四 作業場所以外の場所に、作業に従事する労働者のための休憩室並びに当該労働者の専用に供するための洗面設備、洗浄用灯油槽及びシャワー(シャワーを設けない場合にあつては、浴槽)を設けること。 |
四 作業場所以外の場所に、作業に従事する労働者のための休憩室並びに当該労働者の専用に 供するための洗面設備、洗浄用灯油
浴
|
五 装置等を毎日一回以上点検し、四アルキル鉛又はその蒸気が漏れ、又は漏れるおそれのあることが判明したときは、必要な処置を行うこと。 |
五 装置等を毎日一回以上点検し、四アルキル鉛又はその蒸気が漏れ、又は漏れるおそれのあることが判明したときは、必要な処置を行なうこと。 |
六 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染されるおそれのないときは、この限りでない。 |
六 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長
|
七 (略) |
七 (略) |
八 四アルキル鉛を入れるドラム缶等の容器を堅固で四アルキル鉛が漏れるおそれのないものとし、かつ、当該容器に四アルキル鉛用の容器である旨の表示をすること。 |
八 四アルキル鉛を入れるドラムかん等の容器を堅固で四アルキル鉛が漏れるおそれのないものとし、かつ、当該容器に四アルキル鉛用の容器である旨の表示をすること。 |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、当該請負人が四アルキル鉛によつて汚染されるおそれのないときは、第一号の事項については、この限りでない。 |
(新設) |
一 第一項第六号の保護具を使用する必要があること |
|
二 第一項第七号の保護具を携帯する必要があること |
|
三 第一項第八号の措置を講ずる必要があること |
|
(四アルキル鉛の混入に係る措置) |
(四アルキル鉛の混入に係る措置) |
第四条 事業者は、令別表第五第二号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第四条 事業者は、令別表第五第二号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 作業場所の建築物を換気が十分に行われるように少なくともその三側面を開放したものとすること。 |
二 作業場所の建築物を換気が十分に行なわれるように少なくともその三側面を開放したものとすること。 |
三 ドラム缶中の四アルキル鉛を装置等に吸引する作業により当該ドラム缶を空にしようとするときは、その内部に四アルキル鉛が残らないように吸引すること。 |
三 ドラムかん中の四アルキル鉛を装置等に吸引する作業により当該ドラムかんをからにしようとするときは、その内部に四アルキル鉛が残らないように吸引すること。 |
四 ドラム缶中の四アルキル鉛を装置等に吸引する作業を終了したときは、直ちに、当該ドラム缶を密栓し、かつ、その外面の四アルキル鉛による汚染を除去すること。 |
四 ドラムかん中の四アルキル鉛を装置等に吸引する作業を終了したときは、直ちに、当該ド ラムかんを密
|
五 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。 |
五 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長
|
六 (略) |
六 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。 |
(新設) |
一 第一項第三号及び第四号の措置を講ずる必要があること |
|
二 第一項第五号の保護具を使用する必要があること |
|
(装置等の修理等に係る措置) |
(装置等の修理等に係る措置) |
第五条 事業者は、令別表第五第三号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第五条 事業者は、令別表第五第三号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
一 作業のはじめに四アルキル鉛等によつて汚染されている装置等の汚染を除去すること。ただし、作業のはじめに当該装置等の汚染を除去する作業を行うことが当該作業の性質上著しく困難であるときは、この限りでない。 |
一 作業のはじめに四アルキル鉛等によつて汚染されている装置等の汚染を除去すること。ただし、作業のはじめに当該装置等の汚染を除去する作業を行なうことが当該作業の性質上著しく困難であるときは、この限りでない。 |
二 作業(前号の汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、この限りでない。 |
二 作業(前号の汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保 護手袋及び保護長
|
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、同項第一号ただし書の場合は、第一号の事項について、当該請負人が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、第二号の事項については、この限りでない。 |
(新設) |
一 第一項第一号の措置を講ずる必要があること |
|
二 第一項第一号の汚染を除去する作業に従事するときを除き、同項第二号の保護具を使用する必要があること |
|
(タンク内業務に係る措置) |
(タンク内業務に係る措置) |
第六条 事業者は、令別表第五第四号に掲げる業務のうち四アルキル鉛用のタンクに係るものに労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。この場合において、第一号から第五号までに掲げる措置は、作業開始前に、当該各号列記の順に行うものとする。 |
第六条 事業者は、令別表第五第四号に掲げる業務のうち四アルキル鉛用のタンクに係るものに労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。この場合において、第一号から第五号までに掲げる措置は、作業開始前に、当該各号列記の順に行なうものとする。 |
一~八 (略) |
一~八 (略) |
九 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスクを使用させること。 |
九 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長
|
十 第一号から第五号までの措置に係る作業及び第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行う場合を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、この限りでない。 |
十 第二号から第五号までの措置に係る作業及び第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行なう場合を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長
|
2 (略) |
2 (略) |
3 第一項第一号から第五号までの措置に係る作業及び同項第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行う場合を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第十号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。 |
3 第一項第一号から第五号までの措置に係る作業及び同項第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行なう場合を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第十号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。 |
4 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該業務に従事するときを除く。)は、同項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる措置を講ずること等について配慮するとともに、同項第一号から第五号までに掲げる措置は、当該各号列記の順に行われるよう配慮しなければならない。 |
(新設) |
5 事業者は、前項の請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、当該請負人が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、第二号の事項については、この限りでない。 |
(新設) |
一 第一項の業務に従事するときは、同項第九号の保護具を使用する必要があること |
|
二 第一項第一号から第五号までに掲げる措置に係る作業に従事するときは、同項第十号の保護具を使用する必要があること |
|
第七条 前条の規定(第一項第二号、第三号及び第六号の規定を除く。)は、令別表第五第四号に掲げる業務(加鉛ガソリン用のタンクに係るものに限る。)に労働者を従事させる場合及び当該業務の一部を請負人に請け負わせる場合に準用する。この場合において、前条第一項及び第三項から第五項まで中「第一号から第五号まで」とあるのは「第一号、第四号及び第五号」と、同条第四項中「第一号から第六号まで」とあるのは「第一号、第四号、第五号」と読み替えるものとする。 |
第七条 前条の規定(第一項第二号、第三号及び第六号の規定を除く。)は、令別表第五第四号に掲げる業務のうち加鉛ガソリン用のタンクに係るものに労働者を従事させる場合に準用する。この場合において、前条第一項及び第三項中「第一号から第五号まで」とあるのは、#「第一号、第四号及び第五号」と読み替えるものとする。 |
2 事業者は、前項の業務に労働者を従事させるときは、作業開始前に換気装置によりタンクの内部の空気中におけるガソリンの濃度が〇・一ミリグラム毎リットル以下になるまで換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けなければならない。 |
2 事業者は、前項の業務に労働者を従事させるときは、作業開始前に換気装置によりタンクの内部の空気中におけるガソリンの濃度が〇・一ミリグラム毎リツトル以下になるまで換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けなければならない。 |
3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該業務に従事するときを除く。)は、当該請負人が作業を開始する前に、前項の換気を行うこと等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
(残さい物の取扱いに係る措置) |
(残さい物の取扱いに係る措置) |
第八条 事業者は、令別表第五第五号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第八条 事業者は、令別表第五第五号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
一 残さい物(廃液を除く。)を運搬し、又は一時ためておくときは、蓋又は栓をした堅固な容器で、当該残さい物が漏れ、又はこぼれるおそれのないものを用いること。 |
一 残さい物(廃液を除く。)を運搬し、又は一時ためておくときは、ふた又は
|
二 (略) |
二 (略) |
三 廃液を一時ためておくときは廃液が漏れ、又はこぼれるおそれのない堅固な容器又はピットを用い、廃液を廃棄するときは希釈その他の方法により十分除毒した後処理すること。 |
三 廃液を一時ためておくときは廃液が漏れ、又はこぼれるおそれのない堅固な容器又はピツトを用い、廃液を廃棄するときは希釈その他の方法により十分除毒した後処理すること。 |
四 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。 |
四 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長
|
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。 |
(新設) |
一 第一項第一号から第三号までの措置を講ずる必要があること |
|
二 第一項第四号の保護具を使用する必要があること |
|
(ドラム缶等の取扱いに係る措置) |
(ドラムかん等の取扱いに係る措置) |
第九条 事業者は、令別表第五第六号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第九条 事業者は、令別表第五第六号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
一 作業のはじめに、ドラム缶等及びこれらを置いてある場所を点検し、四アルキル鉛が漏れ、又は漏れるおそれのあるドラム缶等について補修その他の必要な処置を行い、かつ、四アルキル鉛により汚染されているドラム缶等及び場所の汚染を除去すること。 |
一 作業のはじめに、ドラムかん等及びこれらを置いてある場所を点検し、四アルキル鉛が漏れ、又は漏れるおそれのあるドラムかん等について補修その他の必要な処置を行ない、かつ、四アルキル鉛により汚染されているドラムかん等及び場所の汚染を除去すること。 |
二 前号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させ、並びに有機ガス用防毒マスクを携帯させること。 |
二 前号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護 衣、保護手袋及び保護長
|
三 (略) |
三 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
4 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。 |
(新設) |
一 第一項第一号の措置を講ずる必要があること |
|
二 第一項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事するときは、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用し、並びに有機ガス用防毒マスクを携帯する必要があること |
|
三 第一項第一号の措置に係る作業以外の作業に従事するときは、同項第三号の保護具を使用する必要があること |
|
(研究に係る措置) |
(研究に係る措置) |
第十条 (略) |
第十条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(汚染除去に係る措置) |
(汚染除去に係る措置) |
第十一条 事業者は、地下室、船倉又はピットの内部その他の場所であつて自然換気の不十分なところにおいて、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第十一条 事業者は、地下室、船倉又はピツトの内部その他の場所であつて自然換気の不十分なところにおいて、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
四 第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させること。 |
四 第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護 衣、保護手袋、保護長
|
五 第二号の換気の作業以外の作業(第三号の措置に係る監視の作業を含む。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、帽子及び送風マスク(加鉛ガソリンによる汚染を除去する作業にあつては、送風マスク又は有機ガス用防毒マスク)を使用させること。 |
五 第二号の換気の作業以外の作業(第三号の措置に係る監視の作業を含む。)に従事する労働 者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長
染を除去する作業にあつては、送風マスク又は有機ガス用防毒マスク)を使用させること。 |
2 事業者は、前項の場所において、同項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合は、次の措置を講じなければならない。 |
(新設) |
一 労働者が作業に従事するときを除き、前項第二号及び第三号の措置を講ずること等について配慮すること。 |
|
二 当該請負人に対し、次に掲げる措置を講ずる必要がある旨を周知させること。 |
|
イ 前項第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する場合は、同項第四号の保護具を使用すること。 |
|
ロ 前項第二号の換気の作業以外の作業に従事する場合は、同項第五号の保護具を使用すること。 |
|
3 事業者は、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるとき(第一項に規定する場合を除く。)は、次の措置を講じなければならない。 |
2 事業者は、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるとき(前項に規定する場合を除く。)は、次の措置を講じなければならない。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。 |
二 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長
|
4 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるとき(第二項に規定する場合を除く。)は、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。 |
(新設) |
一 作業場所に前項第一号の保護具を備える必要があること |
|
二 前項第二号の保護具を使用する必要があること |
|
5 (略) |
3 (略) |
6 令別表第五第八号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、第一項の場合で、同項第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事するときは同項第四号の保護具を、同項の場合で同項第二号の換気の作業以外の作業に従事するときは同項第五号の保護具を、第三項の場合は同項第二号の保護具を、それぞれ使用しなければならない。 |
4 令別表第五第八号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、第一項の場合で、同項第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事するときは同項第四号の保護具を、同項の場合で同項第二号の換気の作業以外の作業に従事するときは同項第五号の保護具を、第二項の場合は同項第二号の保護具を、それぞれ使用しなければならない。 |
(加鉛ガソリンの使用に係る措置) |
(加鉛ガソリンの使用に係る措置) |
第十二条 (略) |
第十二条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、次の措置を講じなければならない。 |
(新設) |
一 第一項第一号の規定により局所排気装置を設けた場合において、当該請負人が当該業務に従事する間(労働者が当該業務に従事するときを除く。)、当該装置を稼働させること等について配慮すること。 |
|
二 当該請負人に対し、第一項第二号の保護具を使用する必要がある旨を周知させること。 |
|
第十三条 (略) |
第十三条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(汚染の除去に係る周知) |
|
第十五条の二 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体又は衣類が四アルキル鉛によつて汚染されたときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用灯油及び石けん等により汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(保護具等の管理) |
(保護具等の管理) |
第十六条 (略) |
第十六条 (略) |
2 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、その日の作業を開始する前に保護具について前項各号の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
3 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、速やかに、当該労働者が使用した保護具、作業衣、器具等を点検し、四アルキル鉛等により汚染されているものについては、焼却その他の方法により廃棄し、又は当該汚染を除去すること。 |
2 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、すみやかに、当該労働者が使用した保護具、作業衣、器具等を点検し、四アルキル鉛等により汚染されているものについては、焼却その他の方法により廃棄し、又は当該汚染を除去すること。 |
4 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後、速やかに、使用した保護具、作業衣、器具等を点検し、四アルキル鉛等により汚染されているものについては、焼却その他の方法により廃棄し、又は当該汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
5 事業者は、令別表第五第一号、第二号又は第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該労働者ごとに二つの更衣用ロッカーを当該業務を行う作業場所から隔離された場所に設け、そのうち一つを金属製で保護具及び作業衣を格納するためのものとしなければならない。 |
3 事業者は、令別表第五第一号、第二号又は第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該労働者ごとに二つの更衣用ロツカーを当該業務を行なう作業場所から隔離された場所に設け、そのうち一つを金属製で保護具及び作業衣を格納するためのものとしなければならない。 |
6 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該業務に従事する者(労働者を除く。)ごとに二つの更衣用ロッカーを当該業務を行う作業場所から隔離された場所に設け、そのうち一つを金属製で保護具及び作業衣を格納するためのものとする必要がある旨を周知させなければならない。ただし、次項の規定に基づく措置として当該請負人に更衣用ロッカーを使用させる場合は、この限りでない。 |
(新設) |
7 事業者は、前項の請負人に対し、第五項の規定により設けた更衣用ロッカーを使用させる等保護具及び作業衣が適切に格納されるよう必要な配慮をしなければならない。 |
(新設) |
(洗身) |
(洗身) |
第十八条 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、速やかに、当該労働者に洗身(令別表第五第六号又は第七号に掲げる業務については、手洗。次項において同じ 。)をさせなければならない。 |
第十八条 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、すみやかに、当該労働者に洗身(令別表第五第六号又は第七号に掲げる業務については、手洗)をさせなければならない。 |
2 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後、速やかに洗身をする必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(立入禁止) |
(立入禁止) |
第十九条 事業者は、四アルキル鉛等業務を行う作業場所又は四アルキル鉛を入れたタンク、ドラム缶等がある場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、これらの場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
第十九条 事業者は、四アルキル鉛等業務を行なう作業場所又は四アルキル鉛を入れたタンク、ドラムかん等がある場所に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
(事故の場合の退避等) |
(事故の場合の退避等) |
第二十条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、作業に従事する者を作業場所等から退避させなければならない。 |
第二十条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、労働者を作業場所等から退避させなければならない。 |
一~四 (略) |
一~四 (略) |
2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる場合には、作業場所等において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場所等に関係者以外の作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる場合には、作業場所等において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場所等に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
3 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人が異常な症状を訴え、又は当該請負人について異常な症状を発見したときであつて当該請負人が四アルキル鉛中毒にかかつているおそれのあるときには、直ちに当該請負人を作業場所等から退避させなければならない。 |
(新設) |
(掲示) |
|
第二十一条の二 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。 |
(新設) |
一 四アルキル鉛等業務を行う作業場である旨 |
|
二 四アルキル鉛等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 |
|
三 四アルキル鉛等の取扱い上の注意事項 |
|
四 令別表第五第一号及び第六号に掲げる業務を行う作業場においては有機ガス用防毒マスクを携帯しなければならない旨 |
|
五 次に掲げる業務又は作業を行う作業場においては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等 |
|
イ 令別表第五第一号に掲げる業務 |
|
ロ 令別表第五第二号に掲げる業務 |
|
ハ 令別表第五第三号に掲げる業務(第五条第一項第一号の汚染を除去する作業を除く。)(第五条第一項第二号ただし書の場合を除く。) |
|
ニ 令別表第五第四号に掲げる業務(四アルキル鉛用及び加鉛ガソリン用のタンクに係るものに限る。) |
|
ホ 第六条第一項第一号から第五号までの措置に係る作業及び同項第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行うものを除く。)(第七条第一項の規定により準用する場合を含み、第六条第一項第十号ただし書(第七条第一項の規定により準用する場合を含む。)の場合を除く。) |
|
ヘ 令別表第五第五号に掲げる業務 |
|
ト 令別表第五第六号に掲げる業務(第九条第一項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業に限る。)を除く。) |
|
チ 令別表第五第七号に掲げる業務 |
|
リ 令別表第五第八号に掲げる業務 |
|
ヌ 第十二条第一項の業務 |
|
第三章 健康管理 |
第三章 健康管理 |
(診断) |
(診断) |
第二十五条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなければならない。 |
第二十五条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなければならない。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 四アルキル鉛等を飲み込んだ労働者 |
二 四アルキル鉛等を飲みこんだ労働者 |
三・四 (略) |
三・四 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の各号のいずれかに掲げる場合には、遅滞なく医師の診断を受ける必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
一 身体が四アルキル鉛等により汚染されたとき(加鉛ガソリンにより汚染された場合であつて、四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときを除く。) |
|
二 四アルキル鉛等を飲み込んだとき |
|
三 四アルキル鉛の蒸気を吸入し、又は加鉛ガソリンの蒸気を多量に吸入したとき |
|
四 四アルキル鉛等業務に従事した場合であつて、第二十二条第一項第四号に掲げる症状が認められるとき |
|
4 事業者は、前項の請負人に対し、同項の診断の結果、異常が認められなかつたときも、その後二週間、医師による観察を受ける必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止) |
(四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止) |
第二十六条 (略) |
第二十六条 (略) |
2 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、四アルキル鉛中毒にかかつている場合又は医師の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた場合は、四アルキル鉛等業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第五条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(第二類物質の製造等に係る設備) |
(第二類物質の製造等に係る設備) |
||||||||||||
第四条 (略) |
第四条 (略) |
||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||
3 事業者は、その製造する特定第二類物質等を取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱うときは、この限りでない。 |
(新設) |
||||||||||||
4 事業者は、その製造する特定第二類物質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第一項及び第二項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第二類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。 |
3 事業者は、その製造する特定第二類物質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、前二項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第二類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。 |
||||||||||||
5 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合において、第一項の規定によること及び隔離室での遠隔操作によること又は粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱うことが著しく困難であるときは、当該請負人に対し、当該作業を当該特定第二類物質等が身体に直接接触しない方法により行う必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
第六条の二 事業者は、第四条第四項及び第五条第一項の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。 |
第六条の二 事業者は、第四条第三項及び第五条第一項の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。 |
||||||||||||
一・二 (略) |
一・二 (略) |
||||||||||||
三 前号の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。 |
(新設) |
||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||
第六条の三 事業者は、第四条第四項及び第五条第一項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第三十六条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。 |
第六条の三 事業者は、第四条第三項及び第五条第一項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第三十六条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。 |
||||||||||||
2~4 (略) |
2~4 (略) |
||||||||||||
5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第三十六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。 |
5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第三十六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。 |
||||||||||||
一・二 (略) |
一・二 (略) |
||||||||||||
三 当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。 |
三 前二号に定めるもののほか、事業者は、当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。 |
||||||||||||
四 当該許可に係る作業場において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。 |
(新設) |
||||||||||||
6・7 (略) |
6・7 (略) |
||||||||||||
(局所排気装置等の要件) |
(局所排気装置等の要件) |
||||||||||||
第七条 事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第一項ただし書の局所排気装置を含む。次条第一項において同じ。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 |
第七条 事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第一項ただし書の局所排気装置を含む。次条第一項において同じ。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 |
||||||||||||
一・二 (略) |
一・二 (略) |
||||||||||||
三 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。 |
三 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のフアンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。 |
||||||||||||
四・五 (略) |
四・五 (略) |
||||||||||||
2 事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 |
2 事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 |
||||||||||||
一~四 (略) |
一~四 (略) |
||||||||||||
(局所排気装置等の稼働) |
(局所排気装置等の稼働) |
||||||||||||
第八条 事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第一類物質又は第二類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。 |
第八条 事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、第一類物質又は第二類物質に係る作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。 |
||||||||||||
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
3 事業者は、前二項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の稼働時においては、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。 |
2 事業者は、前項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を稼働させるときは、バツフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。 |
||||||||||||
(除じん) |
(除じん) |
||||||||||||
第九条 事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第一類物質若しくは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第三条、第四条第四項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。 |
第九条 事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第一類物質若しくは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第三条、第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。 |
||||||||||||
(表略) |
(表略) |
||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||
3 事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。 |
3 事業者は、前二項の除じん装置を有効に
|
||||||||||||
(排ガス処理) |
(排ガス処理) |
||||||||||||
第十条 事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第四条第四項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。 |
第十条 事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。 |
||||||||||||
(表略) |
(表略) |
||||||||||||
2 事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼働させなければならない。 |
2 事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に
|
||||||||||||
(残さい物処理) |
(残さい物処理) |
||||||||||||
第十二条 (略) |
第十二条 (略) |
||||||||||||
2 事業者は、アルキル水銀化合物を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
(ぼろ等の処理) |
(ぼろ等の処理) |
||||||||||||
第十二条の二 事業者は、特定化学物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。次項、第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十五条第二項及び第三項並びに第四十三条において同じ。)により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならない。 |
第十二条の二 事業者は、特定化学物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十五条第二項及び第三項並びに第四十三条において同じ。)により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、ふた又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならない。 |
||||||||||||
2 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定化学物質により汚染されたぼろ、紙くず等については、前項の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
(送給原材料等の表示) |
(送給原材料等の表示) |
||||||||||||
第十七条 事業者は、特定化学設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる第三類物質等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。 |
第十七条 事業者は、特定化学設備に原材料その他の物を送給する労働者が当該送給を誤ることによる第三類物質等の漏えいを防止するため、当該労働者が見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。 |
||||||||||||
(作業規程) |
(作業規程) |
||||||||||||
第二十条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。 |
第二十条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。 |
||||||||||||
一 バルブ、コック等(特定化学設備に原材料を送給するとき、及び特定化学設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作 |
一 バルブ、コツク等(特定化学設備に原材料を送給するとき、及び特定化学設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作 |
||||||||||||
二・三 (略) |
二・三 (略) |
||||||||||||
四 安全弁、緊急遮断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整 |
四 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整 |
||||||||||||
五 蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における第三類物質等の漏えいの有無の点検 |
五 ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における第三類物質等の漏えいの有無の点検 |
||||||||||||
六~九 (略) |
六~九 (略) |
||||||||||||
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の規程により作業を行う必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
(設備の改造等の作業) |
(設備の改造等の作業) |
||||||||||||
第二十二条 事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業(酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第二十二条 事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業(酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)を行うときは、次の措置を講じなければならない。 |
||||||||||||
一・二 (略) |
一・二 (略) |
||||||||||||
三 作業を行う設備から特定化学物質を確実に排出し、かつ、当該設備に接続している全ての配管から作業箇所に特定化学物質が流入しないようバルブ、コック等を二重に閉止し、又はバルブ、コック等を閉止するとともに閉止板等を施すこと。 |
三 作業を行う設備から特定化学物質を確実に排出し、かつ、当該設備に接続しているすべての配管から作業箇所に特定化学物質が流入しないようバルブ、コツク等を二重に閉止し、又はバルブ、コツク等を閉止するとともに閉止板等を施すこと。 |
||||||||||||
四 前号により閉止したバルブ、コック等又は施した閉止板等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。 |
四 前号により閉止したバルブ、コツク等又は施した閉止板等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。 |
||||||||||||
五 作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものを全て開放すること。 |
五 作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものをすべて開放すること。 |
||||||||||||
六 (略) |
六 (略) |
||||||||||||
七 測定その他の方法により、作業を行う設備の内部について、特定化学物質により健康障害を受けるおそれのないことを確認すること。 |
七 測定その他の方法により、作業を行う設備の内部について、特定化学物質により労働者が健康障害を受けるおそれのないことを確認すること。 |
||||||||||||
八 第三号により施した閉止板等を取り外す場合において、特定化学物質が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ、コック等との間の特定化学物質の有無を確認し、必要な措置を講ずること。 |
八 第三号により施した閉止板等を取り外す場合において、特定化学物質が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ、コツク等との間の特定化学物質の有無を確認し、必要な措置を講ずること。 |
||||||||||||
九 (略) |
九 (略) |
||||||||||||
十 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、呼吸用保護具等必要な保護具を使用させること。 |
十 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長
|
||||||||||||
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第三号から第六号までの措置を講ずること等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
3 事業者は、前項の請負人に対し、第一項第七号及び第八号の措置を講ずる必要がある旨並びに同項第十号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
4 事業者は、第一項第七号の確認が行われていない設備については、当該設備の内部に頭部を入れてはならない旨を、あらかじめ、作業に従事する者に周知させなければならない。 |
2 事業者は、前項第七号の確認が行われていない設備については、当該設備の内部に頭部を入れてはならない旨を、あらかじめ、作業に従事する労働者に周知させなければならない。 |
||||||||||||
5 (略) |
3 (略) |
||||||||||||
第二十二条の二 事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備等の設備(前条第一項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。)の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業(酸欠則第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)に労働者を従事させる場合において、当該設備の溶断、研磨等により特定化学物質を発生させるおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第二十二条の二 事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備等の設備(前条第一項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。)の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業(酸欠則第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)を行う場合において、当該設備の溶断、研磨等により特定化学物質を発生させるおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。 |
||||||||||||
一・二 (略) |
一・二 (略) |
||||||||||||
三 作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものを全て開放すること。 |
三 作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものをすべて開放すること。 |
||||||||||||
四~六 (略) |
四~六 (略) |
||||||||||||
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合において、同項の設備の溶断、研磨等により特定化学物質を発生させるおそれのあるときは、当該請負人に対し、同項第三号及び第四号の措置を講ずること等について配慮するとともに、当該請負人に対し、同項第六号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
3 労働者は、事業者から第一項第六号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
2 労働者は、事業者から前項第六号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
||||||||||||
(退避等) |
(退避等) |
||||||||||||
第二十三条 事業者は、第三類物質等が漏えいした場合において健康障害を受けるおそれのあるときは、作業に従事する者を作業場等から退避させなければならない。 |
第二十三条 事業者は、第三類物質等が漏えいした場合において労働者が健康障害を受けるおそれのあるときは、労働者を作業場等から退避させなければならない。 |
||||||||||||
2 事業者は、前項の場合には、第三類物質等による健康障害を受けるおそれのないことを確認するまでの間、作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
2 事業者は、前項の場合には、労働者が第三類物質等による健康障害を受けるおそれのないことを確認するまでの間、作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
||||||||||||
(立入禁止措置) |
(立入禁止措置) |
||||||||||||
第二十四条 事業者は、次の作業場に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
第二十四条 事業者は、次の作業場には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
||||||||||||
一 (略) |
一 (略) |
||||||||||||
二 特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で第三類物質等を合計百リットル以上取り扱うもの |
二 特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で第三類物質等を合計百リツトル以上取り扱うもの |
||||||||||||
(容器等) |
(容器等) |
||||||||||||
第二十五条 (略) |
第二十五条 (略) |
||||||||||||
2~4 (略) |
2~4 (略) |
||||||||||||
5 事業者は、特別有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。 |
5 事業者は、特別有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。 |
||||||||||||
一 当該屋内で作業に従事する者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備 |
一 関係労働者以外の労働者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備 |
||||||||||||
二 (略) |
二 (略) |
||||||||||||
(特定化学物質作業主任者の職務) |
(特定化学物質作業主任者の職務) |
||||||||||||
第二十八条 事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 |
第二十八条 事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 |
||||||||||||
一~三 (略) |
一~三 (略) |
||||||||||||
四 タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第三十八条の八において準用する有機則第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。 |
四 タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第三十八条の八において準用する有機則第二十六条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。 |
||||||||||||
(定期自主検査を行うべき機械等) |
(定期自主検査を行うべき機械等) |
||||||||||||
第二十九条 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置(特定化学物質(特別有機溶剤等を除く。)その他この省令に規定する物に係るものに限る。)は、次のとおりとする。 |
第二十九条 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置(特定化学物質(特別有機溶剤等を除く。)その他この省令に規定する物に係るものに限る。)は、次のとおりとする。 |
||||||||||||
一 第三条、第四条第四項、第五条第一項、第三十八条の十二第一項第二号、第三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定に基づき設けられる局所排気装置(第三条第一項ただし書及び第三十八条の十六第一項ただし書の局所排気装置を含む。) |
一 第三条、第四条第三項、第五条第一項、第三十八条の十二第一項第二号、第三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定に基づき設けられる局所排気装置(第三条第一項ただし書及び第三十八条の十六第一項ただし書の局所排気装置を含む。) |
||||||||||||
二 第三条、第四条第四項、第五条第一項、第三十八条の十二第一項第二号、第三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置(第三十八条の十六第一項ただし書のプッシュプル型換気装置を含む。) |
二 第三条、第四条第三項、第五条第一項、第三十八条の十二第一項第二号、第三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置(第三十八条の十六第一項ただし書のプッシュプル型換気装置を含む。) |
||||||||||||
三 第九条第一項、第三十八条の十二第一項第三号若しくは第三十八条の十三第四項第一号イの規定により、又は第五十条第一項第七号ハ若しくは第八号(これらの規定を第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき設けられる除じん装置 |
三 第九条第一項、第三十八条の十二第一項第三号若しくは第三十八条の十三第三項第一号イの規定により、又は第五十条第一項第七号ハ若しくは第八号(これらの規定を第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき設けられる除じん装置 |
||||||||||||
(測定及びその記録) |
(測定及びその記録) |
||||||||||||
第三十六条 (略) |
第三十六条 (略) |
||||||||||||
2・3 (略) |
2・3 (略) |
||||||||||||
4 令第二十一条第七号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 |
4 令第二十一条第七号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 |
||||||||||||
一・二 (略) |
一・二 (略) |
||||||||||||
三 第三十八条の十三第三項第二号イ及びロに掲げる作業(同条第四項各号に規定する措置を講じた場合に行うものに限る。) |
三 第三十八条の十三第二項第二号イ及びロに掲げる作業(同条第三項各号に規定する措置を講じた場合に行うものに限る。) |
||||||||||||
(評価の結果に基づく措置) |
(評価の結果に基づく措置) |
||||||||||||
第三十六条の三 (略) |
第三十六条の三 (略) |
||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||
3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。 |
3 前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。 |
||||||||||||
一~三 (略) |
一~三 (略) |
||||||||||||
4 事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
第三十六条の四 (略) |
第三十六条の四 (略) |
||||||||||||
2 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第三十六条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。 |
2 前項に定めるもののほか、事業者は、前項の場所については、第三十六条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。 |
||||||||||||
一~三 (略) |
一~三 (略) |
||||||||||||
(休憩室) |
(休憩室) |
||||||||||||
第三十七条 事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。 |
第三十七条 事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行なう作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。 |
||||||||||||
2 事業者は、前項の休憩室については、同項の物質が粉状である場合は、次の措置を講じなければならない。 |
2 事業者は、前項の休憩室については、同項の物質が粉状である場合は、次の措置を講じなければならない。 |
||||||||||||
一 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。 |
一 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマツトを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。 |
||||||||||||
二 (略) |
二 (略) |
||||||||||||
三 床は、真空掃除機を使用して、又は水洗によつて容易に掃除できる構造のものとし、毎日一回以上掃除すること。 |
三 床は、真空そうじ機を使用して、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとし、毎日一回以上そうじすること。 |
||||||||||||
3 第一項の作業に従事した者は、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。 |
3 労働者は、第一項の作業に従事したときは、同項の休憩室にはいる前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。 |
||||||||||||
(洗浄設備) |
(洗浄設備) |
||||||||||||
第三十八条 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。 |
第三十八条 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗たくのための設備を設けなければならない。 |
||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||
3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体が第一類物質又は第二類物質により汚染されたときは、速やかに身体を洗浄し、汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
4 労働者は、第二項の身体の洗浄を命じられたときは、その身体を洗浄しなければならない。 |
3 労働者は、前項の身体の洗浄を命じられたときは、その身体を洗浄しなければならない。 |
||||||||||||
(喫煙等の禁止) |
(喫煙等の禁止) |
||||||||||||
第三十八条の二 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。 |
第三十八条の二 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。 |
||||||||||||
2 前項の作業場において作業に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 |
2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 |
||||||||||||
(掲示) |
(掲示) |
||||||||||||
第三十八条の三 事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の2に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の二に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。 |
第三十八条の三 事業者は、第一類物質(塩素化ビフエニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の2に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の二に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。 |
||||||||||||
一 (略) |
一 (略) |
||||||||||||
二 特別管理物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 |
二 特別管理物質の人体に及ぼす作用 |
||||||||||||
三 (略) |
三 (略) |
||||||||||||
四 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等 |
四 使用すべき保護具 |
||||||||||||
イ 第六条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第三十六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場 |
|||||||||||||
ロ 第三十六条の三第一項の場所 |
|||||||||||||
ハ 第三十八条の七第一項第二号の規定により、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる作業場 |
|||||||||||||
ニ 第三十八条の十三第三項第二号に該当する場合において、同条第四項の措置を講ずる作業場 |
|||||||||||||
ホ 第三十八条の二十第二項各号に掲げる作業を行う作業場 |
|||||||||||||
ヘ 第三十八条の二十一第一項に規定する金属アーク溶接等作業を行う作業場 |
|||||||||||||
ト 第三十八条の二十一第七項の規定により、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる作業場 |
|||||||||||||
(塩素化ビフェニル等に係る措置) |
(塩素化ビフエニル等に係る措置) |
||||||||||||
第三十八条の五 事業者は、塩素化ビフェニル等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 |
第三十八条の五 事業者は、塩素化ビフエニル等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 |
||||||||||||
一 その日の作業を開始する前に、塩素化ビフェニル等が入つている容器の状態及び当該容器が置いてある場所の塩素化ビフェニル等による汚染の有無を点検すること。 |
一 その日の作業を開始する前に、塩素化ビフエニル等が入つている容器の状態及び当該容器が置いてある場所の塩素化ビフエニル等による汚染の有無を点検すること。 |
||||||||||||
二 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該容器を補修し、漏れた塩素化ビフェニル等を拭き取る等必要な措置を講ずること。 |
二 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該容器を補修し、漏れた塩素化ビフエニル等をふき取る等必要な措置を講ずること。 |
||||||||||||
三 塩素化ビフェニル等を容器に入れ、又は容器から取り出すときは、当該塩素化ビフェニル等が漏れないよう、当該容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。 |
三 塩素化ビフエニル等を容器に入れ、又は容器から取り出すときは、当該塩素化ビフエニル等が漏れないよう、当該容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。 |
||||||||||||
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第三号に定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
(インジウム化合物等に係る措置) |
(インジウム化合物等に係る措置) |
||||||||||||
第三十八条の七 (略) |
第三十八条の七 (略) |
||||||||||||
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるとともに、当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等であつて、インジウム化合物等の粉じんが発散しないように容器等に梱包されていないものについては、付着したインジウム化合物等を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
3 労働者は、事業者から第一項第二号の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
2 労働者は、事業者から前項第二号の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
||||||||||||
(特別有機溶剤等に係る措置) |
(特別有機溶剤等に係る措置) |
||||||||||||
第三十八条の八 事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |
第三十八条の八 事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
(エチレンオキシド等に係る措置) |
(エチレンオキシド等に係る措置) |
||||||||||||
第三十八条の十 事業者は、令別表第三第二号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの(以下この条において「エチレンオキシド等」という。)を用いて行う滅菌作業に労働者を従事させる場合において、次に定めるところによるときは、第五条の規定にかかわらず、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。 |
第三十八条の十 事業者は、令別表第三第二号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの(以下この条において「エチレンオキシド等」という。)を用いて行う滅菌作業に労働者を従事させる場合において、次に定めるところによるときは、第五条の規定にかかわらず、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。 |
||||||||||||
一~四 (略) |
一~四 (略) |
||||||||||||
五 当該滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必要な措置を講ずること。 |
五 滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必要な措置を講ずること。 |
||||||||||||
六 当該滅菌作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、第三号の点検をする必要がある旨及び第四号の手順により作業を行う必要がある旨を周知させること。 |
(新設) |
||||||||||||
(コークス炉に係る措置) |
(コークス炉に係る措置) |
||||||||||||
第三十八条の十二 事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 |
第三十八条の十二 事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接してコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 |
||||||||||||
一~五 (略) |
一~五 (略) |
||||||||||||
六 コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口の蓋の開閉は、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作によること。 |
六 コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口のふたの開閉は、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作によること。 |
||||||||||||
七 (略) |
七 (略) |
||||||||||||
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次に掲げる措置を講じなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
一 コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口の蓋の開閉を当該請負人が行うときは、当該請負人がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮を行うこと。 |
|||||||||||||
二 コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、前項第七号の事項について、同号の作業規程により作業を行う必要がある旨を周知させること。 |
|||||||||||||
3 第七条第一項第一号から第三号まで及び第八条の規定は第一項第二号の局所排気装置について、第七条第二項第一号及び第二号並びに第八条の規定は第一項第二号のプッシュプル型換気装置について準用する。 |
2 第七条第一項第一号から第三号まで及び第八条の規定は前項第二号の局所排気装置について、第七条第二項第一号及び第二号並びに第八条の規定は前項第二号のプッシュプル型換気装置について準用する。 |
||||||||||||
(三酸化二アンチモン等に係る措置) |
(三酸化二アンチモン等に係る措置) |
||||||||||||
第三十八条の十三 (略) |
第三十八条の十三 (略) |
||||||||||||
2 事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等であつて、三酸化二アンチモン等の粉じんが発散しないように容器等に梱包されていないものについては、付着した三酸化二アンチモン等を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
3 事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の規定にかかわらず、三酸化二アンチモン等のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。 |
2 事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の規定にかかわらず、三酸化二アンチモン等のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。 |
||||||||||||
一 粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせるとき(三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に、粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせ、かつ、当該請負人に対し、粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱う必要がある旨を周知させるとき) |
一 粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせるとき。 |
||||||||||||
二 次のいずれかに該当する作業に労働者を従事させる場合において、次項に定める措置を講じたとき |
二 次のいずれかに該当する作業に労働者を従事させる場合において、次項に定める措置を講じたとき。 |
||||||||||||
イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
||||||||||||
4 事業者が講ずる前項第二号の措置は、次の各号に掲げるものとする。 |
3 事業者が講ずる前項第二号の措置は、次の各号に掲げるものとする。 |
||||||||||||
一 次に定めるところにより、全体換気装置を設け、労働者が前項第二号イ及びロに掲げる作業に従事する間、これを有効に稼働させること。 |
一 次に定めるところにより、全体換気装置を設け、これを有効に稼働させること。 |
||||||||||||
イ~ハ (略) |
イ~ハ (略) |
||||||||||||
二 前項第二号イ及びロに掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、前号の全体換気装置を有効に稼働させること等について配慮すること。 |
(新設) |
||||||||||||
三 (略) |
二 (略) |
||||||||||||
四 第二号の請負人に対し、有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する必要がある旨を周知させること。 |
(新設) |
||||||||||||
五 前項第二号イ及びロに掲げる作業を行う場所に当該作業に従事する者以外の者(有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用している者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 |
三 前項第二号イ及びロに掲げる作業を行う場所に当該作業に従事する労働者以外の者(前号に規定する措置が講じられた者を除く。)が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 |
||||||||||||
5 労働者は、事業者から前項第三号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。 |
4 労働者は、事業者から前項第二号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。 |
||||||||||||
(
|
(
|
||||||||||||
第三十八条の十四 事業者は、臭化メチル等を用いて行う
|
第三十八条の十四 事業者は、臭化メチル等を用いて行う
|
||||||||||||
一 (略) |
一 (略) |
||||||||||||
二 投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の
|
二 投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の
|
||||||||||||
三・四 (略) |
三・四 (略) |
||||||||||||
五 倉庫、コンテナー、船倉等の
禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。ただし、
|
五 倉庫、コンテナー、船倉等の
その旨を見やすい箇所に表示すること。ただし、
|
||||||||||||
六 倉庫、コンテナー、船倉等の
|
六 倉庫、コンテナー、船倉等の
|
||||||||||||
七 倉庫
|
七 倉庫
|
||||||||||||
イ (略) |
イ (略) |
||||||||||||
ロ 投薬作業を開始する前に、目張りが固着していること及び倉庫又はコンテナーの
|
ロ 投薬作業を開始する前に、目張りが固着していること及び倉庫又はコンテナーの
|
||||||||||||
ハ 倉庫の一部を
作業に従事する者のうち
|
ハ 倉庫の一部を
|
||||||||||||
ニ 倉庫若しくはコンテナーの
立ち入らせる場合又は一部を
る者を立ち入らせる場合には、あらかじめ、当該倉庫若しくはコンテナーの
|
ニ 倉庫若しくはコンテナーの
|
||||||||||||
八 (略) |
八 (略) |
||||||||||||
九 サイロ
|
九 サイロ
|
||||||||||||
イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
||||||||||||
ハ 臭化メチル等により汚染されるおそれのないことを確認するまでの間、
に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該サイロが立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 |
ハ
|
||||||||||||
十 はしけ
|
十 はしけ
|
||||||||||||
イ~ニ (略) |
イ~ニ (略) |
||||||||||||
ホ 投薬作業を開始する前に、居住室等に臭化メチル等が流入することを防止するための目張りが固着していることその他の必要な措置が講じられていること及び
|
ホ 投薬作業を開始する前に、居住室等に臭化メチル等が流入することを防止するための目張りが固着していることその他の必要な措置が講じられていること及び
|
||||||||||||
ヘ
に従事する者を立ち入らせる場合又は
|
ヘ
者を立ち入らせる場合又は
|
||||||||||||
十一 本船
|
十一 本船
|
||||||||||||
イ (略) |
イ (略) |
||||||||||||
ロ 投薬作業を開始する前に、
|
ロ 投薬作業を開始する前に、
|
||||||||||||
ハ
|
ハ
|
||||||||||||
十二 第七号ニ、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)が送 |
十二 第七号ニ、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者を、当該場所に立ち入らせることができる。 |
||||||||||||
気マスク、空気呼吸器若しくは隔離式防毒マスクを使用していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該保護具を使用している作業に従事する者(労働者を除く。)を、当該場所に立ち入らせることができる。 |
|||||||||||||
(表略) |
(表略) |
||||||||||||
2 事業者は、倉庫、コンテナー、船倉等の臭化メチル等を用いて
|
2 事業者は、倉庫、コンテナー、船倉等の臭化メチル等を用いて
|
||||||||||||
一 (略) |
一 (略) |
||||||||||||
二 前号の規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が前項第十二号の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。 |
二 前号の規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が前項第十二号の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。 |
||||||||||||
(ニトログリコールに係る措置) 第三十八条の十五 事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一~三 (略) 四 ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの蒸気が漏れないように蓋又は栓をした堅固な容器に納めておくこと。この場合において、当該容器は、通風がよい一定の場所に置くこと。 |
(ニトログリコールに係る措置) 第三十八条の十五 事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 一~三 (略) 四 ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの 蒸気が漏れないようにふた又は
|
||||||||||||
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第一号から第三号までに定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
(ベンゼン等に係る措置) |
(ベンゼン等に係る措置) |
||||||||||||
第三十八条の十六 (略) |
第三十八条の十六 (略) |
||||||||||||
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行う必要がある旨を周知させなければならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとするときは、この限りでない。 |
(新設) |
||||||||||||
3 第六条の二及び第六条の三の規定は第一項ただし書の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置について、第七条第一項及び第八条の規定は第一項ただし書の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は第一項ただし書のプッシュプル型換気装置について準用する。 |
2 第六条の二及び第六条の三の規定は前項ただし書の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置について、第七条第一項及び第八条の規定は前項ただし書の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は前項ただし書のプッシュプル型換気装置について準用する。 |
||||||||||||
(一・三-ブタジエン等に係る措置) |
(一・三-ブタジエン等に係る措置) |
||||||||||||
第三十八条の十七 事業者は、一・三-ブタジエン若しくは一・四-ジクロロ-二-ブテン又は一・三-ブタジエン若しくは一・四-ジクロロ-二-ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三-ブタジエン等」という。)を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 |
第三十八条の十七 事業者は、一・三-ブタジエン若しくは一・四-ジクロロ-二-ブテン又は一・三-ブタジエン若しくは一・四-ジクロロ-二-ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三-ブタジエン等」という。)を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 |
||||||||||||
一 一・三-ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所に、一・三-ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、一・三-ブタジエン等のガス |
一 一・三-ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所に、一・三-ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、一・三-ブタジエン等のガス |
||||||||||||
の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)に対し呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させる等健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。 |
の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。 |
||||||||||||
二 一・三-ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。ただし、前号の規定により一・三-ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置を設けるとき、又は同号ただし書の規定により全体換気装置を設けるときは、ニの事項については、この限りでない。 |
二 一・三-ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。 |
||||||||||||
イ (略) |
イ (略) |
||||||||||||
ロ 一・三-ブタジエン等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 |
ロ 一・三-ブタジエン等の人体に及ぼす作用 |
||||||||||||
ハ (略) |
ハ (略) |
||||||||||||
ニ 当該作業場所においては呼吸用保護具を使用する必要がある旨及び使用すべき呼吸用保護具 |
ニ 使用すべき保護具 |
||||||||||||
三・四 (略) |
三・四 (略) |
||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||
(硫酸ジエチル等に係る措置) |
(硫酸ジエチル等に係る措置) |
||||||||||||
第三十八条の十八 事業者は、硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「硫酸ジエチル等」という。)を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 |
第三十八条の十八 事業者は、硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「硫酸ジエチル等」という。)を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 |
||||||||||||
一 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所に、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)に対し呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させる等健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。 |
一 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所に、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。 |
||||||||||||
二 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。ただし、前号の規定により硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置を設けるとき、又は同号ただし書の規定により全体換気装置を設けるときは、ニの事項については、この限りでない。 |
二 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。 |
||||||||||||
イ (略) |
イ (略) |
||||||||||||
ロ 硫酸ジエチル等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 |
ロ 硫酸ジエチル等の人体に及ぼす作用 |
||||||||||||
ハ (略) |
ハ (略) |
||||||||||||
ニ 当該作業場所においては呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具 |
ニ 使用すべき保護具 |
||||||||||||
三・四 (略) |
三・四 (略) |
||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||
(一・三-プロパンスルトン等に係る措置) |
(一・三-プロパンスルトン等に係る措置) |
||||||||||||
第三十八条の十九 事業者は、一・三-プロパンスルトン又は一・三-プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三-プロパンスルトン等」という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 |
第三十八条の十九 事業者は、一・三-プロパンスルトン又は一・三-プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三-プロパンスルトン等」という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 |
||||||||||||
一・二 (略) |
一・二 (略) |
||||||||||||
三 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(当該設備のバルブ又はコックを除く。)については、一・三-プロパンスルトン等の漏えいを防止するため堅固な材料で造り、当該設備のうち一・三-プロパンスルトン等が接触する部分については、著しい腐食による一・三-プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、一・三-プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講ずること。 |
三 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(当該設備のバルブ又はコツクを除く。)については、一・三-プロパンスルトン等の漏えいを防止するため堅固な材料で造り、当該設備のうち一・三-プロパンスルトン等が接触する部分については、著しい腐食による一・三-プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、一・三-プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講ずること。 |
||||||||||||
四 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から一・三-プロパンスルトン等が漏えいすることを防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。 |
四 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部については、当該接合部から一・三-プロパンスルトン等が漏えいすることを防止するため、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。 |
||||||||||||
五 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による一・三-プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、次の措置を講ずること。 |
五 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による一・三-プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、次の措置を講ずること。 |
||||||||||||
イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
||||||||||||
六 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによること。 |
六 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ又はコツクについては、次に定めるところによること。 |
||||||||||||
イ (略) |
イ (略) |
||||||||||||
ロ 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(配管を除く。次号、第九号及び第十号において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該設備との間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。 |
ロ 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(配管を除く。次号、第九号及び第十号において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該設備との間に設けられるバルブ又はコツクが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。 |
||||||||||||
七 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる一・三-プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示すること。 |
七 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料その他の物を送給する労働者が当該送給を誤ることによる一・三-プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、当該労働者が見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示すること。 |
||||||||||||
八 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業を行うときは、次の事項について、一・三-プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行うこと。 |
八 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業を行うときは、次の事項について、一・三-プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行うこと。 |
||||||||||||
イ バルブ、コック等(一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備又は容器に原材料を送給するとき、及び当該設備又は容器から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作 |
イ バルブ、コツク等(一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備又は容器に原材料を送給するとき、及び当該設備又は容器から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作 |
||||||||||||
ロ~ニ (略) |
ロ~ニ (略) |
||||||||||||
ホ 蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における一・三-プロパンスルトン等の漏えいの有無の点検 |
ホ 蓋板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における一・三-プロパンスルトン等の漏えいの有無の点検 |
||||||||||||
ヘ~ル (略) |
ヘ~ル (略) |
||||||||||||
九 (略) |
九 (略) |
||||||||||||
十 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する作業場又は当該設備を設置する作業場以外の作業場で一・三-プロパンスルトン等を合計百リットル以上取り扱うものに関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 |
十 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する作業場又は当該設備を設置する作業場以外の作業場で一・三-プロパンスルトン等を合計百リツトル以上取り扱うものには、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 |
||||||||||||
十一~十七 (略) |
十一~十七 (略) |
||||||||||||
十八 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。 |
十八 一・三-プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。 |
||||||||||||
イ (略) |
イ (略) |
||||||||||||
ロ 一・三-プロパンスルトン等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 |
ロ 一・三-プロパンスルトン等の人体に及ぼす作用 |
||||||||||||
ハ (略) |
ハ (略) |
||||||||||||
ニ 当該作業場においては有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具 |
ニ 使用すべき保護具 |
||||||||||||
十九~二十一 (略) |
十九~二十一 (略) |
||||||||||||
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号及び第十七号の措置を講ずる必要がある旨、同項第八号の規程により作業を行う必要がある旨並びに一・三-プロパンスルトン等による皮膚の汚染防止のため、同項第二十号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
3 労働者は、事業者から第一項第二十号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
2 労働者は、事業者から前項第二十号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
||||||||||||
(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置) |
(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置) |
||||||||||||
第三十八条の二十 (略) |
第三十八条の二十 (略) |
||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||
3 事業者が講ずる前項の措置は、次の各号に掲げるものとする。 |
3 事業者が講ずる前項の措置は、次の各号に掲げるものとする。 |
||||||||||||
一 前項各号に掲げる作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。ただし、隔離することが著しく困難である場合において、前項各号に掲げる作業以外の作業に従事する者がリフラクトリーセラミックファイバー等にばく露することを防止するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。 |
一 前項各号に掲げる作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。ただし、隔離することが著しく困難である場合において、前項各号に掲げる作業以外の作業に従事する労働者がリフラクトリーセラミックファイバー等にばく露することを防止するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。 |
||||||||||||
二 (略) |
二 (略) |
||||||||||||
4 事業者は、第二項各号のいずれかに該当する作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、前項第一号ただし書の措置を講じたときは、第一号の事項については、この限りでない。 |
(新設) |
||||||||||||
一 当該作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離する必要があること |
|||||||||||||
二 前項第二号の保護具等を使用する必要があること |
|||||||||||||
5 事業者は、第二項第三号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、第一項から第三項までに定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。 |
4 事業者は、第二項第三号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、第一項から前項までに定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。 |
||||||||||||
一・二 (略) |
一・二 (略) |
||||||||||||
6 事業者は、第二項第三号に掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、前項各号に定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
7 (略) |
5 (略) |
||||||||||||
(金属アーク溶接等作業に係る措置) |
(金属アーク溶接等作業に係る措置) |
||||||||||||
第三十八条の二十一 (略) |
第三十八条の二十一 (略) |
||||||||||||
2~5 (略) |
2~5 (略) |
||||||||||||
6 事業者は、金属アーク溶接等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
7 (略) |
6 (略) |
||||||||||||
8 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、前項の測定の結果に応じて、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
9 事業者は、第七項の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 |
7 事業者は、前項の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 |
||||||||||||
10・ 11 (略) |
8・9 (略) |
||||||||||||
12 労働者は、事業者から第五項又は第七項の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
10 労働者は、事業者から第五項又は第六項の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
||||||||||||
(緊急診断) |
(緊急診断) |
||||||||||||
第四十二条 事業者は、特定化学物質(別表第一第三十七号に掲げる物を除く。以下この項及び次項において同じ。)が漏えいした場合において、労働者が当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。 |
第四十二条 事業者は、特定化学物質(別表第一第三十七号に掲げる物を除く。以下この項において同じ。)が漏えいした場合において、労働者が当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。 |
||||||||||||
2 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人に対し、特定化学物質が漏えいした場合であつて、当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく医師による診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
3 第一項の規定により診察又は処置を受けさせた場合を除き、事業者は、労働者が特別有機溶剤等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。 |
2 前項の規定により診察又は処置を受けさせた場合を除き、事業者は、労働者が特別有機溶剤等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。 |
||||||||||||
4 第二項の診察又は処置を受けた場合を除き、事業者は、特別有機溶剤等を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人に対し、特別有機溶剤等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに医師による診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
5 前二項の規定は、第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務については適用しない。 |
3 前項の規定は、第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務については適用しない。 |
||||||||||||
(保護衣等) |
(保護衣等) |
||||||||||||
第四十四条 事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない。 |
第四十四条 事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長
|
||||||||||||
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護衣等を備え付けておくこと等により当該保護衣等を使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
3 (略) |
2 (略) |
||||||||||||
4 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||
5 労働者は、事業者から第三項の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
3 労働者は、事業者から前項の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
||||||||||||
(高気圧作業安全衛生規則の一部改正)
第六条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(空気槽) |
(空気槽) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第八条 事業者は、潜水業務従事者(潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)及び潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。以下「潜水業務請負人等」という。)をいう。以下同じ。)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水業務従事者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。 |
第八条 事業者は、潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水作業者ごとに、送気を調節するための空気
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 第一項の送気を調節するための空気槽が前項各号に定める予備空気槽の基準に適合するものであるとき、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を潜水業務従事者に携行させるときは、第一項の規定にかかわらず、予備空気槽を設けることを要しない。 |
3 第一項の送気を調節するための空気
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(空気清浄装置、圧力計及び流量計) |
(空気清浄装置、圧力計及び流量計) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第九条 事業者は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水業務従事者が圧力調整器を使用するときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない。 |
第九条 事業者は、潜水作業者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水作業者に圧力調整器を使用させるときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(作業主任者) |
(作業主任者) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十条 (略) |
第十条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 |
2 事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一~四 (略) |
一~四 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第十四条又は第十八条第一項及び第二項の規定に適合して行われるように措置すること。 |
五 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第十四条又は第十八条の規定に適合して行われるように措置すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 (略) |
六 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十条の二 事業者は、前条第一項の高圧室内作業の一部を請け負わせた場合における高圧室内作業に従事する者(労働者を除く。以下この項において同じ。)について、当該高圧室内作業に従事する者が作業室に入室し、又は作業室から退室するときに、当該高圧室内作業に従事する者の人数を点検しなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、作業室及び気こう室において前項に規定する者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講じなければならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(立入禁止) |
(立入禁止) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十三条 事業者は、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方 法により禁止したときは、気こう室及び作業室が立入禁止である旨を潜
|
第十三条 事業者は、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることを禁止し、そ の旨を潜
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(加圧の速度) |
(加圧の速度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十四条 事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者(高圧室内作業者及び高圧室内業務の一部を請け負わせた場合における高圧室内業務に従事する者(労働者を除く。以下「高圧室内業務請負人等」という。)をいう。以下同じ。)に加圧を行うときは、毎分〇・〇八メガパスカル以下の速度で行わなければならない。 |
第十四条 事業者は、気こう室において高圧室内作業者に加圧を行うときは、毎分〇・〇八メガパスカル以下の速度で行わなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ガス分圧の制限) |
(ガス分圧の制限) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十五条 事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室及び気こう室における次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない。 |
第十五条 事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、作業室及び気こう室における次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 酸素 十八キロパスカル以上百六十キロパスカル以下(ただし、気こう室において減圧を行う場合にあつては、十八キロパスカル以上二百二十キロパスカル以下とする。) |
一 酸素 十八キロパスカル以上百六十キロパスカル以下(ただし、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行う場合にあつては、十八キロパスカル以上二百二十キロパスカル以下とする。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二・三 (略) |
二・三 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、高圧室内業務請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、作業室及び気こう室における前項各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(酸素ばく露量の制限) |
(酸素ばく露量の制限) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十六条 事業者は、酸素による高圧室内作業者の健康障害を防止するため、高圧室内作業者について、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、厚生労働大臣が定める値を超えないように、作業室又は気こう室への送気その他の必要な措置を講じなければならない。 |
第十六条 事業者は、酸素による高圧室内作業者の健康障害を防止するため、高圧室内作業者について、厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、厚生労働大臣が定める値を超えないように、作業室又は気こう室への送気その他の必要な措置を講じなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、高圧室内業務請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、前項の厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、同項の厚生労働大臣が定める値を超えないように、作業室又は気こう室への送気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有害ガスの抑制) |
(有害ガスの抑制) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十七条 事業者は、高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室における有害ガスによる高圧室内作業者の危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講じなければならない。 |
第十七条 事業者は、作業室における有害ガスによる高圧室内作業者の危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講じなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、高圧室内業務請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、作業室における有害ガスによる危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(減圧の速度等) |
(減圧の速度等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十八条 (略) |
第十八条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、減圧を終了した高圧室内作業者に対して、当該減圧を終了した時から十四時間は、重激な業務に従事させてはならない。 |
2 事業者は、減圧を終了した者に対して、当該減圧を終了した時から十四時間は、重激な業務に従事させてはならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 事業者は、高圧室内業務請負人等について、気こう室において当該高圧室内業務請負人等に減圧を行うときは、第一項各号に定めるところによらなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 事業者は、高圧室内業務請負人等に対して、減圧を終了した時から十四時間は、重激な業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(減圧の特例等) |
(減圧の特例等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十九条 事業者は、事故のために高圧室内業務従事者を退避させ、又は健康に異常を生じた高圧室内業務従事者を救出するときは、必要な限度において、前条第一項に規定する減圧の速度を速め、又は同項に規定する減圧を停止する時間を短縮することができる。 |
第十九条 事業者は、事故のために高圧室内作業者を退避させ、又は健康に異常を生じた高圧室内作業者を救出するときは、必要な限度において、前条に規定する減圧の速度を速め、又は同条に規定する減圧を停止する時間を短縮することができる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、前項の規定により減圧の速度を速め、又は減圧を停止する時間を短縮したときは、退避させ、又は救出した後、速やかに当該高圧室内業務従事者を再圧室又は気こう室に入れ、当該高圧室内業務に係る圧力に等しい圧力まで加圧しなければならない。 |
2 事業者は、前項の規定により減圧の速度を速め、又は減圧を停止する時間を短縮したときは、退避させ、又は救出した後、速やかに当該高圧室内作業者を再圧室又は気こう室に入れ、当該高圧室内業務に係る圧力に等しい圧力まで加圧しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (略) |
3 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(減圧時の措置) |
(減圧時の措置) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条 事業者は、気こう室において、高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。 |
第二十条 事業者は、気こう室において、高圧室内作業者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 (略) |
一 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 気こう室内の温度が十度以下である場合には、高圧室内業務従事者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。 |
二 気こう室内の温度が十度以下である場合には、高圧室内作業者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 減圧に要する時間が一時間を超える場合には、高圧室内業務従事者に椅子その他の休息用具を使用させること。 |
三 減圧に要する時間が一時間を超える場合には、高圧室内作業者に椅子その他の休息用具を使用させること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、あらかじめ、当該減圧に要する時間を当該高圧室内業務従事者に周知させなければならない。 |
2 事業者は、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、あらかじめ、当該減圧に要する時間を当該高圧室内作業者に周知させなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(連絡) |
(連絡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十一条 事業者は、高圧室内業務を行うときは、気こう室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(次項において「連絡員」という。)を常時配置しなければならない。 |
第二十一条 事業者は、高圧室内業務を行うときは、気こう室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下この条において「連絡員」という。)を常時配置しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 事業者は、前項の通話装置が故障した場合においても連絡することができる方法を定めるとともに、当該方法を見やすい場所に掲示しておかなければならない。 |
3 事業者は、前項の通話装置が故障した場合においても連絡することができる方法を定めるとともに、当該方法を高圧室内作業者、空気圧縮機の運転を行う者及び連絡員の見やすい場所に掲示しておかなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事故が発生した場合の措置) |
(事故が発生した場合の措置) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十三条 事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、高圧室内業務従事者を潜
|
第二十三条 事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、高圧室内作業者を潜
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜
|
2 事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(排気沈下の場合の措置) |
(排気沈下の場合の措置) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十四条 事業者は、作業室内を排気して潜
|
第二十四条 事業者は、作業室内を排気して潜
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜
|
2 事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(発破を行つた場合の措置) |
(発破を行なつた場合の措置) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十五条 事業者は、作業室内において発破を行つたときは、高圧室内業務従事者が作業室内の空気が発破前の状態に復する前に入室することについて、作業室内の空気が発破前の状態に復するまで入室してはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 |
第二十五条 事業者は、作業室内において発破を行なつたときは、作業室内の空気が発破前の状態に復するまで、高圧室内作業者を入室させてはならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(火傷等の防止) |
(火傷等の防止) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十五条の二 (略) |
第二十五条の二 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、高圧室内業務を行うときは、潜
|
2 事業者は、高圧室内業務を行うときは、潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接、溶断その他の火気又はアークを使用する作業(以下この条において「溶接等の作業」という。)を行つてはならない。ただし、作業の性質上やむをえない場合であつて圧力〇・一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うとき、又は厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、この限りでない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 事業者は、高圧室内業務を行うときは、高圧室内業務請負人等に対し、潜
ルド等の内部において溶接等の作業を行つてはならない旨を周知させなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 事業者は、高圧室内業務を行うときは、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物(以下この項において「火気等」という。)を潜
より禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、潜
の内部への火気等の持込みが禁止されている旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合であつて圧力〇・一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うとき、又は第二項の厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、当該溶接等の作業に必要な火気等を潜
|
3 事業者は、高圧室内業務を行うときは、火気又はマツチ、ライターその他発火のおそれのある物を潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合であつて圧力〇・一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うとき、又は前項の厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、当該溶接等の作業に必要な火気又はマツチ、ライターその他発火のおそれのある物を潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことができる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(作業計画等の準用) |
(作業計画等の準用) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十七条 第十二条の二及び第二十条の二の規定は潜水業務(水深十メートル以上の場所における潜水業務に限る。)について、第十五条及び第十六条の規定は潜水業務について、第十五条、第十六条並びに第十八条第一項及び第二項の規定は潜水作業者について、第十五条第二項、第十六条第二項並びに第十八条第三項及び第四項の規定は潜水業務請負人等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |
第二十七条 第十二条の二及び第二十条の二の規定は潜水業務(水深十メートル以上の場所における潜水業務に限る。第四十二条第一項において同じ 。)について、第十五条、第十六条及び第十八条の規定は潜水作業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(送気量及び送気圧) |
(送気量及び送気圧) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十八条 事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水業務従事者に送気するときは、潜水業務従事者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分六十リットル以上としなければならない。 |
第二十八条 事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水作業者に送気するときは、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分六十リツトル以上としなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、潜水業務従事者に圧力調整器を使用させる場合には、潜水業務従事者ごとに、その水深の圧力下において毎分四十リットル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に〇・七メガパスカルを加えた値以上としなければならない。 |
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合には、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下において毎分四十リツトル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に〇・七メガパスカルを加えた値以上としなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ボンベからの給気を受けて行う潜水業務) |
(ボンベからの給気を受けて行なう潜水業務) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十九条 事業者は、潜水業務従事者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。以下この条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条において同じ。)からの給気を受けさせるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第二十九条 事業者は、潜水作業者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。以下第三十四条、第三十六条及び第三十七条において同じ。)からの給気を受けさせるときは、次の措置を講じなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 潜降直前に、潜水業務従事者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせること。 |
一 潜降直前に、潜水作業者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 潜水業務従事者に異常がないかどうかを監視するための者を置くこと。 |
二 潜水作業者に異常がないかどうかを監視するための者を置くこと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(圧力調整器) |
(圧力調整器) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十条 事業者は、潜水業務従事者に圧力一メガパスカル以上の気体を充填したボンベからの給気を受けさせるときは、二段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水業務従事者に使用させなければならない。 |
第三十条 事業者は、潜水作業者に圧力一メガパスカル以上の気体を充てんしたボンベからの給気を受けさせるときは、二段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水作業者に使用させなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(浮上の特例等) |
(浮上の特例等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十二条 事業者は、事故のために潜水業務従事者を浮上させるときは、必要な限度において、第二十七条において読み替えて準用する第十八条第一項第一号に規定する浮上の速度を速め、又は同項第二号に規定する浮上を停止する時間を短縮することができる。 |
第三十二条 事業者は、事故のために潜水作業者を浮上させるときは、必要な限度において、第二十七条において読み替えて準用する第十八条第一項第一号に規定する浮上の速度を速め、又は同項第二号に規定する浮上を停止する時間を短縮することができる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、前項の規定により浮上の速度を速め、又は浮上を停止する時間を短縮したときは、浮上後、速やかに当該潜水業務従事者を再圧室に入れ、当該潜水業務の最高の水深における圧力に等しい圧力まで加圧し、又は当該潜水業務の最高の水深まで再び潜水させなければならない。 |
2 事業者は、前項の規定により浮上の速度を速め、又は浮上を停止する時間を短縮したときは、浮上後、すみやかに当該潜水作業者を再圧室に入れ、当該潜水業務の最高の水深における圧力に等しい圧力まで加圧し、又は当該潜水業務の最高の水深まで再び潜水させなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 前項の規定により当該潜水業務従事者を再圧室に入れて加圧する場合の加圧の速度については、第十四条の規定を準用する。 |
3 前項の規定により当該潜水作業者を再圧室に入れて加圧する場合の加圧の速度については、第十四条の規定を準用する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(さがり綱) |
(さがり綱) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十三条 事業者は、潜水業務を行うときは、潜水業務従事者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を備え、これを潜水業務従事者に使用させなければならない。 |
第三十三条 事業者は、潜水業務を行なうときは、潜水作業者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を備え、これを潜水作業者に使用させなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(連絡員) |
(連絡員) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十六条 事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水業務従事者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水業務従事者と連絡するための者(次条において「連絡員」という。)を、潜水業務従事者二人以下ごとに一人置き、次の事項を行わせなければならない。 |
第三十六条 事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者と連絡するための者(次条において「連絡員」という。)を、潜水作業者二人以下ごとに一人置き、次の事項を行わせなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 潜水業務従事者と連絡して、その者の潜降及び浮上を適正に行わせること。 |
一 潜水作業者と連絡して、その者の潜降及び浮上を適正に行わせること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 潜水業務従事者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、潜水業務従事者に必要な量の空気を送気させること。 |
二 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、潜水作業者に必要な量の空気を送気させること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 送気設備の故障その他の事故により、危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかに潜水業務従事者に連絡すること。 |
三 送気設備の故障その他の事故により、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかに潜水作業者に連絡すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 ヘルメット式潜水器を用いて行う潜水業務にあつては、潜降直前に当該潜水業務従事者のヘルメットがかぶと台に結合されているかどうかを確認すること。 |
四 ヘルメツト式潜水器を用いて行う潜水業務にあつては、潜降直前に当該潜水作業者のヘルメツトがかぶと台に結合されているかどうかを確認すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(潜水業務における携行物等) |
(潜水作業者の携行物等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十七条 (略) |
第三十七条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、前項の潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。)が、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(当該者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、当該者に対し、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物(当該者と連絡員とが通話装置により通話することができるときにあつては、鋭利な刃物)を携行する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (略) |
2 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 事業者は、携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務の一部を請け負わせた場合における潜水業務に従事する者(労働者を除く。)に対し、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行するほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(病者の就業禁止) |
(病者の就業禁止) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十一条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる疾病にかかつている労働者については、医師が必要と認める期間、高気圧業務への就業を禁止しなければならない。 |
第四十一条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる疾病にかかつている労働者については、医師が必要と認める期間、高気圧業務への就業を禁止しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 (略) |
一 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 肺結核その他呼吸器の結核又は急性上気道感染、じん肺、肺気腫その他呼吸器系の疾病 |
二 肺結核その他呼吸器の結核又は急性上気道感染、じん肺、肺気
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三~七 (略) |
三~七 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、高圧室内業務請負人等又は潜水業務請負人等に対し、前項各号のいずれかに掲げる疾病にかかつているときは、医師が必要と認める期間、高気圧業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(設置) |
(設置) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十二条 事業者は、高気圧業務(潜水業務にあっては、水深十メートル以上の場所におけるものに限る。)を行うときは、高圧室内業務従事者又は潜水業務従事者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。 |
第四十二条 事業者は、高圧室内業務又は潜水業務を行うときは、高圧室内作業者又は潜水作業者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(立入禁止) |
(立入禁止) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十三条 事業者は、必要のある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。 |
第四十三条 事業者は、必要のある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(危険物等の持込み禁止) |
(危険物等の持込み禁止) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十六条 事業者は、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となつて可燃物の点火源となるおそれのある物(以下この条において「危険物等」という。)を持ち込むことについて、禁止する旨を再圧室の入口に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、再圧室の内部への危険物等の持込みが禁止されている旨を再圧室の入口に掲示しておかなければならない。 |
第四十六条 事業者は、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となつて可燃物の点火源となるおそれのある物を持ち込むことを禁止し、その旨を再圧室の入口に掲示しておかなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(電離放射線障害防止規則の一部改正)
第七条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(管理区域の明示等) |
(管理区域の明示等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三条 (略) |
第三条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2~4 (略) |
2~4 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 事業者は、管理区域内の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。 |
5 事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(放射線業務従事者の被ばく限度) |
(放射線業務従事者の被ばく限度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四条 (略) |
第四条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条第一項に規定する放射線業務従事者を除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 |
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する者の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び当該放射線業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条第二項に規定する女性を除く。)の受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五条 (略) |
第五条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する者の受ける等価線量が、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六条 (略) |
第六条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、管理区域内における放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該放射線業務に従事する者のうち妊娠と診断された女性の受ける線量が、妊娠中につき前項各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(緊急作業時における被ばく限度) |
(緊急作業時における被ばく限度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七条 事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業(以下「緊急作業」という。)を行うときは、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の放射線業務従事者については、第四条第一項及び第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。 |
第七条 事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業(以下「緊急作業」という。)を行うときは、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の放射線業務従事者については、第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2・3 (略) |
2・3 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 事業者は、緊急作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性については、第四条第三項及び第五条第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて放射線を受けることができる旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 前項の場合において、事業者は、同項の請負人に対し、同項の緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性が当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、第二項各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特例緊急被ばく限度) |
(特例緊急被ばく限度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七条の三 (略) |
第七条の三 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、前条第一項又は第二項の規定により、特例緊急被ばく限度が定められたときは、第七条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、特例緊急作業従事者について、同号に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。この場合において、当該特例緊急作業に従事する間に受ける実効線量は、当該特例緊急被ばく限度を超えないようにしなければならない。 |
2 事業者は、前条第一項又は第二項の規定により、特例緊急被ばく限度が定められたときは、第七条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、特例緊急作業従事者について、同号に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。この場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける実効線量は、当該特例緊急被ばく限度を超えないようにしなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (略) |
3 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 事業者は、特例緊急作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該特例緊急作業に従事する間に受ける実効線量は、当該特例緊急作業に係る特例緊急被ばく限度を超えないようにする必要がある旨及び当該特例緊急作業に係る事故の状況に応じ、放射線を受けることをできるだけ少なくするように努める必要がある旨を周知させなければらない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(線量の測定) |
(線量の測定) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第八条 (略) |
第八条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2~6 (略) |
2~6 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 事業者は、管理区域内における放射線業務、緊急作業及び管理区域に一時的に立ち入る作業(以下この項及び次項において「管理区域内放射線業務等」という。)の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該管理区域内放射線業務等に従事する者が管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を、第二項から第五項までに定めるところにより測定する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 事業者は、管理区域内放射線業務等の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第三項ただし書の場合を除き、管理区域内において放射線測定器を装着する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(立入禁止) |
(立入禁止) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十八条 事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から五メートル以内の場所(外部放射線による実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下の場所を除く。)に、作業に従事する者を立ち入らせてはならない。ただし、放射性物質を装備している機器の線源容器内に放射線源が確実に収納され、かつ、シャッターを有する線源容器にあつては当該シャッターが閉鎖されている場合において、線源容器から放射線源を取り出すための準備作業、線源容器の点検作業その他必要な作業を行うために立ち入るときは、この限りでない。 |
第十八条 事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から五メートル以内の場所(外部放射線による実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下の場所を除く。)に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、放射性物質を装備している機器の線源容器内に放射線源が確実に収納され、かつ、シャッターを有する線源容器にあつては当該シャッターが閉鎖されている場合において、線源容器から放射線源を取り出すための準備作業、線源容器の点検作業その他必要な作業を行うために立ち入るときは、この限りでない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2・3 (略) |
2・3 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 事業者は、第一項の規定により作業に従事する者が立ち入ることを禁止されている場所を標識により明示しなければならない。 |
4 事業者は、第一項の規定により労働者が立ち入ることを禁止されている場所を標識により明示しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(透過写真の撮影時の措置等) |
(透過写真の撮影時の措置等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十八条の二 事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、特定エックス線装置又は透過写真撮影用ガンマ線照射装置(ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。以下同じ。)を放射線装置室以外の場所で使用するとき(被ばくのおそれがないときを除く。)は、放射線を、作業に従事する者が立ち入らない方向に照射し、又は遮蔽する措置を講じなければならない。 |
第十八条の二 事業者は、第十五条第一項ただし書の規定により、特定エックス線装置又は透過写真撮影用ガンマ線照射装置(ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。以下同じ。)を放射線装置室以外の場所で使用するとき(労働者の被ばくのおそれがないときを除く。)は、放射線を、労働者が立ち入らない方向に照射し、又は遮へいする措置を講じなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(放射線源の収納) |
(放射線源の収納) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十八条の十 事業者は、第四十二条第一項第四号の事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業に労働者を従事させるときは、遮蔽物を設ける等の措置 を講じ、かつ、
|
第十八条の十 事業者は、第四十二条第一項第四号の事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業に労働者を従事させるときは、しやへい物を設ける等の措置を講じ、かつ、
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、遮蔽物を 設ける等の措置を講じ、かつ、
との間に適当な距離を設ける必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(飛来防止設備等) |
(飛来防止設備等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十六条 事業者は、放射性物質を取り扱うことにより、放射性物質の飛
|
第二十六条 事業者は、放射性物質を取り扱うことにより、放射性物質の飛
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(汚染除去用具等の汚染検査) |
(汚染除去用具等の汚染検査) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十条 (略) |
第三十条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2・3 (略) |
2・3 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 事業者は、第一項の汚染の除去又は清掃の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、同項の検査により、同項の用具が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまでは、使用してはならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(退去者の汚染検査) |
(退去者の汚染検査) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十一条 (略) |
第三十一条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、前項の検査により労働者の身体又は装具が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認められるときは、同項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、その労働者を管理区域から退去させてはならない。 |
2 事業者は、前項の検査により労働者の身体又は装具が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認められるときは、前項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、その労働者を管理区域から退去させてはならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一・二 (略) |
一・二 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 労働者は、前項の規定による事業者の指示に従い、洗身等をし、又は装具を脱ぎ、若しくは取り外さなければならない。 |
3 労働者は、前項の規定による事業者の指示に従い、洗身等をし、又は装具を脱ぎ、若しくは取りはずさなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 管理区域において作業に従事する者(労働者を除く。)は、その区域から退去するときは、第一項の汚染検査場所において、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 前項の者は、同項の検査によりその身体又は装具が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認められるときは、第一項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、管理区域から退去してはならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 身体が汚染されているときは、その汚染が別表第三に掲げる限度の十分の一以下になるように洗身等をすること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 装具が汚染されているときは、その装具を脱ぎ、又は取り外すこと。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(持出し物品の汚染検査) |
(持出し物品の汚染検査) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十二条 (略) |
第三十二条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 管理区域において作業に従事する者(労働者を除く。)は、管理区域から持ち出す物品については、持ち出しの際に、前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 前項の者は、同項の検査により、当該物品が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第二項ただし書の場合は、この限りでない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(容器) |
(容器) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十七条 (略) |
第三十七条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、前項本文の容器については、次の表の上欄に掲げる用途に用いるときは、当該用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる構造を具備するものを用いなければならない。 |
2 事業者は、前項本文の容器については、次の表の上欄に掲げる用途に用いるときは、当該用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる構造を具備するものを用いなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3・4 (略) |
3・4 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(保護具) |
(保護具) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十八条 (略) |
第三十八条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、その空気の汚染の程度に応じて同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十九条 (略) |
第三十九条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 労働者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。 |
2 労働者は、前項の作業に従事する間、同項に規定する保護具を使用しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(作業衣) |
(作業衣) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十条 (略) |
第四十条 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、専用の作業衣を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(保護具等の汚染除去) |
(保護具等の汚染除去) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十一条 事業者は、第三十八条第一項、第三十九条第一項及び前条第一項の規定により使用させる保護具又は作業衣が別表第三に掲げる限度(保護具又は作業衣の労働者に接触する部分にあつては、その限度の十分の一。以下この条において同じ。)を超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により別表第三に掲げる限度以下になるまで汚染を除去しなければ、労働者に使用させてはならない。 |
第四十一条 事業者は、前三条の規定により使用させる保護具又は作業衣が別表第三に掲げる限度(保護具又は作業衣の労働者に接触する部分にあつては、その限度の十分の一。以下この条において同じ。)を超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により別表第三に掲げる限度以下になるまで汚染を除去しなければ、労働者に使用させてはならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、第三十八条第三項、第三十九条第三項及び前条第二項の請負人に対し、それぞれの規定に基づく周知により使用する保護具又は作業衣が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ洗浄等により同表に掲げる限度以下になるまで汚染を除去しなければ使用してはならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(喫煙等の禁止) |
(喫煙等の禁止) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十一条の二 事業者は、放射性物質取扱作業室その他の放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。 |
第四十一条の二 事業者は、放射性物質取扱作業室その他の放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 前項の作業場において作業に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 |
2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(保護衣類等) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十一条の八の二 処分事業者は、事故由来廃棄物等を取り扱うことにより、事故由来廃棄物 等の飛
袋又は履物を備え、これらを当該事故由来廃棄物等を取り扱う作業に従事する労働者に使用させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 処分事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合であつて、事故由来廃棄物等 の飛
効な保護衣類、手袋又は履物を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(準用) |
(準用) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十一条の九 第三条第四項(第三十三条第三項において準用する場合に限る。)、第二十五条、第二十七条第一項及び第二項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第二項及び第四項、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項(第三十四条第二項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十七条(第四項を除く。)並びに第三十八条から第四十一条の二までの規定は、処分事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |
第四十一条の九 第三条第四項(第三十三条第三項において準用する場合に限る。)、第二十五条、第二十六条本文、第二十七条第一項及び第二項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項(第三十四条第二項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十七条(第四項を除く。)並びに第三十八条から第四十一条の二までの規定は、処分事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(除染特別地域等における特例) |
(除染特別地域等における特例) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十一条の十 (略) |
第四十一条の十 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 除染特別地域等において事故由来廃棄物等の処分の業務を行う場合における前条において準用する第二十八条、第三十一条、第三十二条、第三十三条第二項(第三十五条第二項において準用する場合に限る。)、第三十五条第一項及び第三十七条(第四項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
2 除染特別地域等において事故由来廃棄物等の処分の業務を行う場合における前条において準用する第二十八条、第三十一条、第三十二条、第三十三条第二項(第三十五条第二項において準用する場合に限る。)、第三十五条第一項及び第三十七条(第四項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(加工施設等における作業規程) |
(加工施設等における作業規程) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十一条の十一 (略) |
第四十一条の十一 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。 |
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(原子炉施設における作業規程) |
(原子炉施設における作業規程) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十一条の十二 (略) |
第四十一条の十二 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。 |
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業における作業規程) |
(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業における作業規程) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十一条の十三 (略) |
第四十一条の十三 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。 |
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(退避) |
(退避) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十二条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、作業に従事する者を退避させなければならない。 |
第四十二条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、労働者を退避させなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 第三条の二第一項の規定により設けられた遮蔽物が放射性物質の取扱い中に破損した場合又は放射線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な場合 |
一 第三条の二第一項の規定により設けられた遮へい物が放射性物質の取扱い中に破損した場合又は放射線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な場合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 (略) |
二 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 放射性物質が多量に漏れ、こぼれ、又は逸散した場合 |
三 放射性物質が多量にもれ、こぼれ、又は逸散した場合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四・五 (略) |
四・五 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 事業者は、作業に従事する者を第一項の区域に立ち入らせてはならない。ただし、緊急作業に従事する者については、この限りでない。 |
3 事業者は、労働者を第一項の区域に立ち入らせてはならない。ただし、緊急作業に従事させる労働者については、この限りでない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(診察等) |
(診察等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十四条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。 |
第四十四条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 (略) |
一 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 第四条第一項又は第五条第一項に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者 |
二 第四条第一項又は第五条に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三~五 (略) |
三~五 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (略) |
2 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 事業者は、放射線業務、緊急作業及び管理区域に一時的に立ち入る作業(以下この項及び次条第四項において「放射線業務等」という。)の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、放射線業務等に従事する者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事故に関する測定及び記録) |
(事故に関する測定及び記録) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十五条 事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じたときは、労働者がその区域内にいたことによつて、又は緊急作業に従事したことによつて受けた実効線量、眼の水晶体及び皮膚の等価線量並びに次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。 |
第四十五条 事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じたときは、労働者がその区域内にいたことによつて、又は緊急作業に従事したことによつて受けた実効線量、目の水晶体及び皮膚の等価線量並びに次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一~四 (略) |
一~四 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2・3 (略) |
2・3 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 事業者は、放射線業務等の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第一項に規定する区域が生じた場合であつて、放射線業務等に従事する者がその区域内にいたことによつて、又は緊急作業に従事したことによつて受けた同項の実効線量又は等価線量が明らかで |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ないときは、第四十二条第一項の区域内の必要な場所ごとの外部放射線による線量当量率、空気中の放射性物質の濃度又は放射性物質の表面密度を放射線測定器を用いて測定し、その結果に基づいて、計算により第一項の実効線量又は等価線量を算出する必要がある旨を周知させなければならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 事業者は、前項の請負人に対し、同項の線量当量率を放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務) |
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五十二条の三 事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 |
第五十二条の三 事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一~八 (略) |
一~八 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九 作業中、放射線測定器を用いて放射線源の位置、遮蔽の状況等について点検すること。 |
九 作業中、放射線測定器を用いて放射線源の位置、遮へいの状況等について点検すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十・十一 (略) |
十・十一 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二 第四十二条第一項第四号に掲げる事故が発生した場合において、放射線源を線源容器そ の他の容器に収納する作業を行うときは、第十八条の十第一項の措置を講じ、かつ、
|
十二 第四十二条第一項第四号に掲げる事故が発生した場合において、放射線源を線源容器そ の他の容器に収納する作業を行うときは、第十八条の十の措置を講じ、かつ、
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(線量当量率等の測定等) |
(線量当量率等の測定等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五十四条 事業者は、前条第一号の管理区域について、一月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているとき、又は三・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、六月以内)ごとに一回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。 |
第五十四条 事業者は、前条第一号の管理区域について、一月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は三・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、六月以内)ごとに一回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一~八 (略) |
一~八 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2・3 (略) |
2・3 (略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 事業者は、第一項の測定又は第二項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、管理区域に立ち入る者に周知させなければならない。 |
4 事業者は、第一項の測定又は第二項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(準用) |
(準用) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六十二条 第三条第四項(第十五条第三項、第二十二条第二項、第三十三条第三項、第三十六条第二項、第四十一条の四第二項及び第四十一条の八第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項から第五項まで、第八条、第九条、第十八条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項及び第二項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(これらの規定を第四十一条の九(第四十一条の十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十一条の二第一項(これらの規定を第四十一条の九において準用する場合を含む。)、第四十一条の六第一項、第四十一条の七第一項、第四十一条の八第一項、第四十二条第一項及び第三項、第四十四条、第四十五条、第五十九条の二並びに第六十一条の二第一項の規定は、放射線業務を行う事業場内において放射線業務以外の業務を行う事業の事業者(除染則第二条第一項の事業者を除く。)及びその使用する労働者に準用する。 |
第六十二条 第三条第四項(第十五条第三項、第二十二条第二項、第三十三条第三項、第三十六条第二項、第四十一条の四第二項及び第四十一条の八第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項、第八条、第九条、第十八条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(これらの規定を第四十一条の九(第四十一条の十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十一条の二(これらの規定を第四十一条の九において準用する場合を含む。)、第四十一条の六第一項、第四十一条の七第一項、第四十一条の八第一項、第四十二条第一項及び第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第五十四条第四項、第五十九条の二並びに第六十一条の二第一項の規定は、放射線業務を行う事業場内において放射線業務以外の業務を行う事業の事業者(除染則第二条第一項の事業者を除く。)及びその使用する労働者に準用する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様式第一号の二を次のように改める。
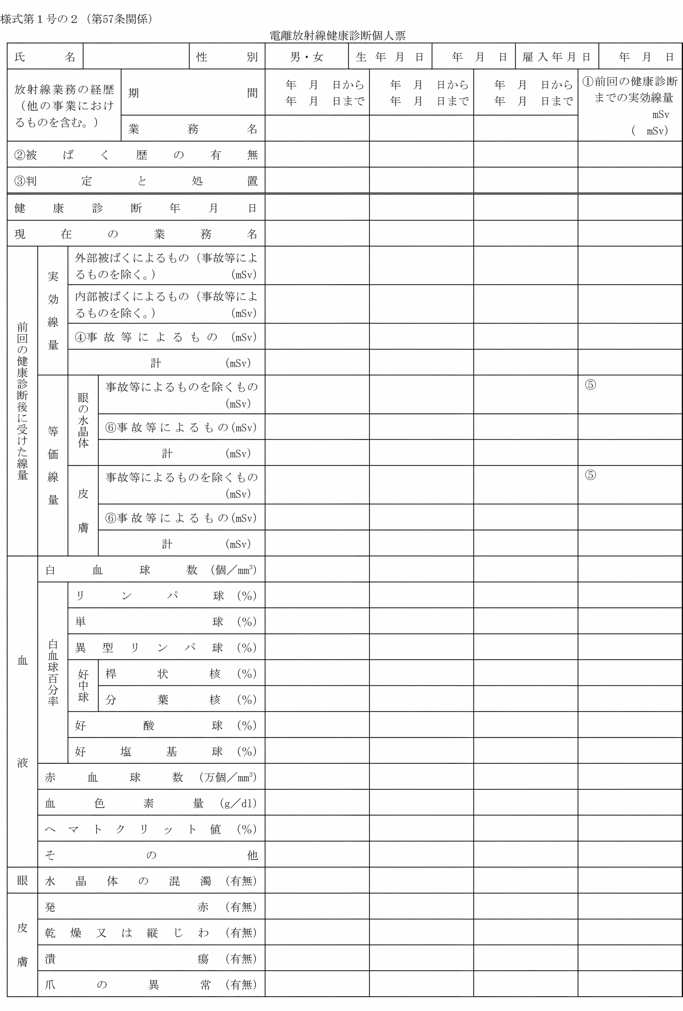
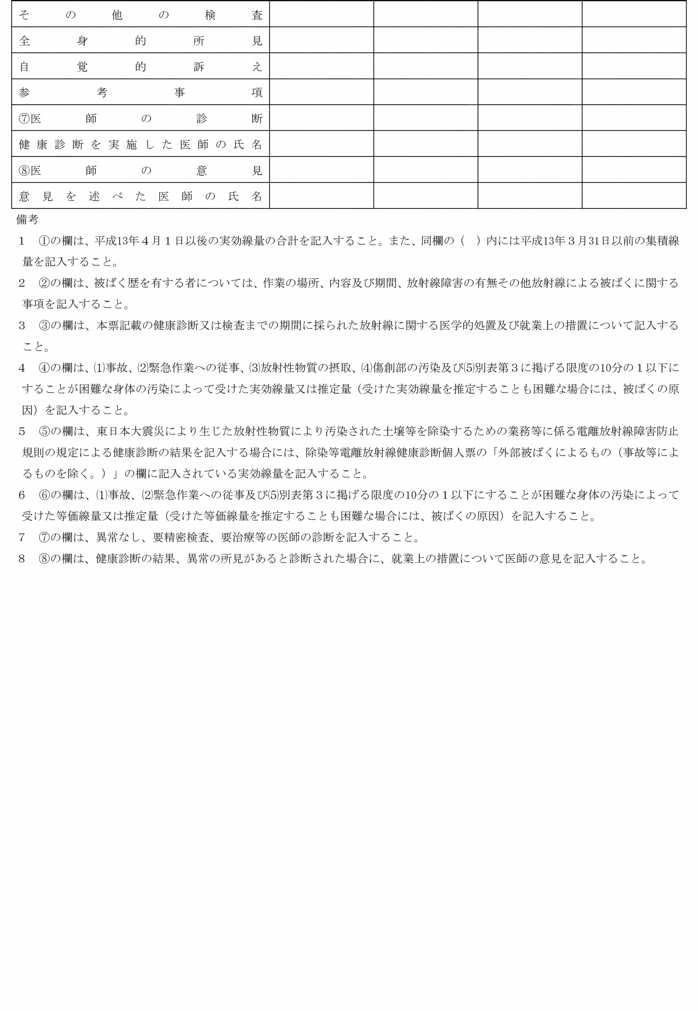
(酸素欠乏症等防止規則の一部改正)
第八条 酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(換気) |
(換気) |
第五条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上(第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあつては、空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上、かつ、硫化水素の濃度を百万分の十以下。次項において同じ 。)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。 |
第五条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上(第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあつては、空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上、かつ、硫化水素の濃度を百万分の十以下)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。 |
2 事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること等について配慮しなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。 |
(新設) |
3 事業者は、前二項の規定により換気が行われるときは、純酸素を使用してはならない。 |
2 事業者は、前項の規定により換気するときは、純酸素を使用してはならない。 |
(保護具の使用等) |
(保護具の使用等) |
第五条の二 (略) |
第五条の二 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、前条第二項の請負人に対し、同項ただし書の場合においては、空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(要求性能墜落制止用器具等) |
(要求性能墜落制止用器具等) |
第六条 (略) |
第六条 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
4 事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせる場合で、酸素欠乏症等にかかつて転落するおそれのあるときは、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(人員の点検) |
(人員の点検) |
第八条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。 |
第八条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行なう場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。 |
2 事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業を行う場所に入場し、及び退場する時に、人員を点検しなければならない。 |
(新設) |
(立入禁止) |
(立入禁止) |
第九条 事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する者以外の者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該酸素欠乏危険場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
第九条 事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
2 酸素欠乏危険作業に従事する者以外の者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入つてはならない。 |
2 酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入つてはならない。 |
3 (略) |
3 (略) |
(監視人等) |
(監視人等) |
第十三条 (略) |
第十三条 (略) |
2 事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるとき(労働者が当該作業に従事するときを除く。)は、当該請負人に対し、常時作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を事業者及びその他の関係者に通報する者を置く等異常を早期に把握するために必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
(退避) |
(退避) |
第十四条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、当該作業を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者をその場所から退避させなければならない。 |
第十四条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、当該作業を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、労働者をその場所から退避させなければならない。 |
2 事業者は、前項の場合において、酸素欠乏等のおそれがないことを確認するまでの間、その場所に特に指名した者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
2 事業者は、前項の場合において、酸素欠乏等のおそれがないことを確認するまでの間、その場所に特に指名した者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
(救出時の空気呼吸器等の使用) |
(救出時の空気呼吸器等の使用) |
第十六条 事業者は、酸素欠乏症等にかかつた作業に従事する者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。 |
第十六条 事業者は、酸素欠乏症等にかかつた労働者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。 |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の救出作業を、酸素欠乏等の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)が行うときは、当該者に対し、空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(診察及び処置) |
(診察及び処置) |
第十七条 (略) |
第十七条 (略) |
2 事業者は、酸素欠乏症等にかかるおそれのある場所における作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、酸素欠乏症等にかかつたときは、直ちに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(消火設備等に係る措置) |
(消火設備等に係る措置) |
第十九条 事業者は、地下室、機関室、船倉その他通風が不十分な場所に備える消火器又は消火設備で炭酸ガスを使用するものについては、次の措置を講じなければならない。 |
第十九条 事業者は、地下室、機関室、船倉その他通風が不十分な場所に備える消火器又は消火設備で炭酸ガスを使用するものについては、次の措置を講じなければならない。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 みだりに作動させることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、みだりに作動させることが禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。 |
二 みだりに作動させることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 |
(冷蔵室等に係る措置) |
(冷蔵室等に係る措置) |
第二十条 事業者は、冷蔵室、冷凍室、むろその他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させる場合は、労働者が作業に従事する間、当該施設又は設備の出入口の扉又は蓋が締まらないような措置を講じなければならない。ただし、当該施設若しくは設備 |
第二十条 事業者は、冷蔵室、冷凍室、むろその他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させる場合は、労働者が作業している間、当該施設又は設備の出入口の扉又はふたが締まらないような措置を講じなければならない。ただし、当該施設若しくは設備 |
の出入口の扉若しくは蓋が内部から容易に開くことができる構造のものである場合又は当該施設若しくは設備の内部に通報装置若しくは警報装置が設けられている場合は、この限りでない。 |
の出入口の扉若しくはふたが内部から容易に開くことができる構造のものである場合又は当該施設若しくは設備の内部に通報装置若しくは警報装置が設けられている場合は、この限りでない。 |
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、同項の措置を講ずること等について配慮しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。 |
(新設) |
(溶接に係る措置) |
(溶接に係る措置) |
第二十一条 事業者は、タンク、ボイラー又は反応塔の内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン、炭酸ガス又はヘリウムを使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 |
第二十一条 事業者は、タンク、ボイラー又は反応塔の内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン、炭酸ガス又はヘリウムを使用して行なう溶接の作業に労働者を従事させるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 |
一 作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること。 |
一 作業を行なう場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること。 |
二 (略) |
二 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
4 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 |
(新設) |
一 請負人が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること等について配慮すること。 |
|
二 請負人に対し、空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させること。 |
|
(ガス漏出防止措置) |
(ガス漏出防止措置) |
第二十二条 事業者は、ボイラー、タンク、反応塔、船倉等の内部で令別表第六第十一号の気体(以下「不活性気体」という。)を送給する配管があるところにおける作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第二十二条 事業者は、ボイラー、タンク、反応塔、船倉等の内部で令別表第六第十一号の気体(以下「不活性気体」という。)を送給する配管があるところにおける作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
一 バルブ若しくはコックを閉止し、又は閉止板を施すこと。 |
一 バルブ若しくはコツクを閉止し、又は閉止板を施すこと。 |
二 前号により閉止したバルブ若しくはコック又は施した閉止板には施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示すること。 |
二 前号により閉止したバルブ若しくはコツク又は施した閉止板には施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示すること。 |
2 事業者は、不活性気体を送給する配管のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による不活性気体の漏出を防止するため、配管内の不活性気体の名称及び開閉の方向を表示しなければならない。 |
2 事業者は、不活性気体を送給する配管のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による不活性気体の漏出を防止するため、配管内の不活性気体の名称及び開閉の方向を表示しなければならない。 |
3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、同項各号の措置を講ずること等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
(空気の稀薄化の防止) |
(空気の稀薄化の防止) |
第二十三条 事業者は、その内部の空気を吸引する配管(その内部の空気を換気するためのものを除く。)に通ずるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させるときは、労働者が作業に従事する間、当該施設又は設備の出入口の蓋又は扉が締まらないような措置を講じなければならない。 |
第二十三条 事業者は、その内部の空気を吸引する配管(その内部の空気を換気するためのものを除く。)に通ずるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させるときは、労働者が作業をしている間、当該施設又は設備の出入口のふた又は扉が締まらないような措置を講じなければならない。 |
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、同項の措置を講ずること等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
(ガス配管工事に係る措置) |
(ガス配管工事に係る措置) |
第二十三条の二 (略) |
第二十三条の二 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、次の措置を講じなければならない。 |
(新設) |
一 第一項第一号の措置を講ずること等について配慮すること。 |
|
二 請負人が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること等について配慮し、又は請負人に空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させること。 |
|
4 (略) |
3 (略) |
(設備の改造等の作業) |
(設備の改造等の作業) |
第二十五条の二 事業者は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質を入れてあり、若しくは入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
第二十五条の二 事業者は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質を入れてあり、若しくは入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 作業を行う設備から硫化水素を確実に排出し、かつ、当該設備に接続しているすべての配管から当該設備に硫化水素が流入しないようバルブ、コック等を確実に閉止すること。 |
三 作業を行う設備から硫化水素を確実に排出し、かつ、当該設備に接続しているすべての配管から当該設備に硫化水素が流入しないようバルブ、コツク等を確実に閉止すること。 |
四 前号により閉止したバルブ、コック等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。 |
四 前号により閉止したバルブ、コツク等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。 |
五 (略) |
五 (略) |
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるとき(労働者が当該作業に従事するときを除く。)は、当該請負人に対し、同項第三号及び第四号の措置を講ずること等について配慮するとともに、同項第五号のおそれがあるときは、当該請負人に対し、換気その他必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
(粉じん障害防止規則の一部改正)
第九条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外) |
(臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外) |
第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。以下この項において同じ 。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。 |
第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあつては、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)を使用させたときは、適用しない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
2 第五条から前条までの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第三号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。以下この項において同じ 。)を使用させたとき(当該粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。 |
2 第五条から前条までの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、当該粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表第三第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあつては、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)を使用させたときは、適用しない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
(研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外) |
(研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外) |
第八条 第四条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。この場合において、事業者は、屋内作業場にあつては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあつては換気装置による換気を実施しなければならない。 |
第八条 第四条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、適用しない。この場合において、事業者は、屋内作業場にあつては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあつては換気装置による換気を実施しなければならない。 |
一~四 (略) |
一~四 (略) |
(作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外) |
(作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外) |
第九条 第四条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。この場合において、事業者は、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させ )、かつ、屋内作業場にあつては全体換気装置による換気を、内作業場にあつては換気装置による換気を実施しなければならない。 |
第九条 第四条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。この場合において、事業者は、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、屋内作業場にあつては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあつては換気装置による換気を実施しなければならない。 |
2~5 (略) |
2~5 (略) |
(局所排気装置等の稼働) |
(局所排気装置等の稼働) |
第十二条 事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、労働者が当該局所排気装置に係る粉じん作業に従事する間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。 |
第十二条 事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、当該局所排気装置に係る粉じん作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。 |
2 事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
3 前二項の規定は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設けるプッシュプル型換気装置について準用する。 |
2 前項の規定は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設けるプッシュプル型換気装置について準用する。 |
(湿式型の衝撃式削岩機の給水) |
(湿式型の衝撃式削岩機の給水) |
第十五条 事業者は、第四条の規定により設ける湿式型の衝撃式削岩機については、労働者が当該衝撃式削岩機に係る特定粉じん作業に従事する間、有効に給水を行わなければならない。 |
第十五条 事業者は、第四条の規定により設ける湿式型の衝撃式削岩機については、当該衝撃式削岩機に係る特定粉じん作業が行われている間、有効に給水を行わなければならない。 |
2 事業者は、前項の特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該特定粉じん作業に従事する間(労働者が当該特定粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の衝撃式削岩機に有効に給水を行うこと等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
(湿潤な状態に保つための設備による湿潤化) |
(湿潤な状態に保つための設備による湿潤化) |
第十六条 事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備により、労働者が当該設備に係る粉じん作業に従事する間、当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保たなければならない。 |
第十六条 事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備により、当該設備に係る粉じん作業が行われている間、当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保たなければならない。 |
2 事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の設備により、粉じんの発生源を湿潤な状態に保つこと等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
(休憩設備) |
(休憩設備) |
第二十三条 (略) |
第二十三条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 粉じん作業に従事した者は、第一項の休憩設備を利用する前に作業衣等に付着した粉じんを除去しなければならない。 |
3 労働者は、粉じん作業に従事したときは、第一項の休憩設備を利用する前に作業衣等に付着した粉じんを除去しなければならない。 |
(掲示) |
|
第二十三条の二 事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。 |
(新設) |
一 粉じん作業を行う作業場である旨 |
|
二 粉じんにより生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 |
|
三 粉じん等の取扱い上の注意事項 |
|
四 次に掲げる場合にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具 |
|
イ 第七条第一項の規定により第四条及び第六条の二から第六条の四までの規定が適用されない場合 |
|
ロ 第七条第二項の規定により第五条から第六条の四までの規定が適用されない場合 |
|
ハ 第八条の規定により第四条の規定が適用されない場合 |
|
ニ 第九条第一項の規定により第四条の規定が適用されない場合 |
|
ホ 第二十四条第二項ただし書の規定により清掃を行う場合 |
|
ヘ 第二十六条の三第一項の場所において作業を行う場合 |
|
ト 第二十七条第一項の作業を行う場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合及び第二十七条第一項ただし書の場合を除く。) |
|
チ 第二十七条第三項の作業を行う場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。) |
|
(清掃の実施) |
(清掃の実施) |
第二十四条 (略) |
第二十四条 (略) |
2 事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び第二十三条第一項の休憩設備が設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については、たい積した粉じんを除去するため、一月以内ごとに一回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法 |
2 事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び前条第一項の休憩設備が設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については、たい積した粉じんを除去するため、一月以内ごとに一回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によ |
によつて清掃を行わなければならない。ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合において、当該清掃に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき(当該清掃の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該清掃に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、その他の方法により清掃を行うことができる。 |
つて清掃を行わなければならない。ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合で当該清掃に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、その他の方法により清掃を行うことができる。 |
(発破終了後の措置) |
(発破終了後の措置) |
第二十四条の二 事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち、発破の作業を行つたときは、作業に従事する者が発破による粉じんが適当に薄められる前に発破をした箇所に近寄ることについて、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ発破をした箇所に近寄つてはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。 |
第二十四条の二 事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち、発破の作業を行つたときは、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ、発破をした箇所に労働者を近寄らせてはならない。 |
(評価の結果に基づく措置) |
(評価の結果に基づく措置) |
第二十六条の三 (略) |
第二十六条の三 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならない。 |
3 前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならない。 |
4 事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(呼吸用保護具の使用) |
(呼吸用保護具の使用) |
第二十七条 事業者は、別表第三に掲げる作業(第三項に規定する作業を除く。)に労働者を従事させる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第五号に掲げる作業を行う場合にあつては、送気マスク又は空気呼吸器に限る。次項において同じ 。)を使用させなければならない。ただし、粉じんの発生源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置、粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備の設置等の措置であつて、当該作業に係る粉じんの発散を防止するために有効なものを講じたときは、この限りでない。 |
第二十七条 事業者は、別表第三に掲げる作業(次項に規定する作業を除く。)に労働者を従事させる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表第三第五号に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあつては、送気マスク又は空気呼吸器に限る。)を使用させなければならない。ただし、粉じんの発生源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置、粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備の設置等の措置であつて、当該作業に係る粉じんの発散を防止するために有効なものを講じたときは、この限りでない。 |
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。ただし、前項ただし書の措置を講じたときは、この限りでない。 |
(新設) |
3 (略) |
2 (略) |
4 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、前項の厚生労働大臣の定めるところにより、同項の測定の結果に応じて、当該請負人に対し、有効な電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
5 労働者は、第七条、第八条、第九条第一項、第二十四条第二項ただし書並びに本条第一項及び第三項の規定により呼吸用保護具の使用を命じられたときは、当該呼吸用保護具を使用しなければならない。 |
3 労働者は、第七条、第八条、第九条第一項、第二十四条第二項ただし書及び前二項の規定により呼吸用保護具の使用を命じられたときは、当該呼吸用保護具を使用しなければならない。 |
(石綿障害予防規則の一部改正)
第十条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(事前調査及び分析調査) |
(事前調査及び分析調査) |
第三条 (略) |
第三条 (略) |
2~5 (略) |
2~5 (略) |
6 事業者は、解体等の作業を行う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示するとともに、次条第一項の作業を行う作業場には、前項の規定による記録の写しを備え付けなければならない。 |
6 事業者は、解体等の作業を行う作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示するとともに、次条第一項の作業を行う作業場には、前項の規定による記録の写しを備え付けなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
7 (略) |
7 (略) |
(石綿含有成形品の除去に係る措置) |
(石綿含有成形品の除去に係る措置) |
第六条の二 事業者は、成形された材料であって石綿等が使用されているもの(石綿含有保温材等を除く。第三項において「石綿含有成形品」という。)を建築物、工作物又は船舶から除去する作業においては、切断等以外の方法により当該作業を実施しなければならない。ただし、切断等以外の方法により当該作業を実施することが技術上困難なときは、この限りでない。 |
第六条の二 事業者は、成形された材料であって石綿等が使用されているもの(石綿含有保温材等を除く。次項において「石綿含有成形品」という。)を建築物、工作物又は船舶から除去する作業においては、切断等以外の方法により当該作業を実施しなければならない。ただし、切断等以外の方法により当該作業を実施することが技術上困難なときは、この限りでない。 |
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、切断等以外の方法により当該作業を実施する必要がある旨を周知させなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。 |
(新設) |
3 事業者は、第一項ただし書の場合において、石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものとして厚生労働大臣が定めるものを切断等の方法により除去する作業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、当該措置(第一号及び第二号に掲げる措置に限る。)と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、第一号及び第二号の措置については、この限りでない。 |
2 事業者は、前項ただし書の場合において、石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものとして厚生労働大臣が定めるものを切断等の方法により除去する作業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 当該作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、前二号に掲げる措置を講ずる必要がある旨を周知させること。 |
(新設) |
(石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置) |
(石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置) |
第六条の三 前条第三項の規定は、事業者が建築物、工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業に労働者を従事させる場合及び当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合について準用する。 |
第六条の三 前条第二項の規定は、事業者が建築物、工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業に労働者を従事させる場合について準用する。 |
第十条 事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(次項及び第五項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等又は石綿含有保温材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。 |
第十条 事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(次項及び第四項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等又は石綿含有保温材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。 |
2 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(第五項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。 |
2 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(第四項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。 |
3 事業者は、前項のおそれがある場所における作業の一部を請負人に請け負わせる場合であって、当該請負人が当該場所で臨時に就業するときは、当該請負人に対し、呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
4 労働者は、事業者から第二項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
3 労働者は、事業者から前項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
5 (略) |
4 (略) |
(石綿等の切断等の作業等に係る措置) |
(石綿等の切断等の作業等に係る措置) |
第十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、石綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずるように努めなければならない。 |
第十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、石綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずるように努めなければならない。 |
一 石綿等の切断等の作業(第六条の二第三項に規定する作業を除く。) |
一 石綿等の切断等の作業(第六条の二第二項に規定する作業を除く。) |
二~四 (略) |
二~四 (略) |
五 前各号に掲げる作業、第六条の二第三項に規定する作業又は第六条の三に規定する作業(以下「石綿等の切断等の作業等」という。)において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業 |
五 前各号に掲げる作業、第六条の二第二項に規定する作業又は第六条の三に規定する作業(以下「石綿等の切断等の作業等」という。)において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業 |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項各号のいずれかに掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、石綿等を湿潤な状態のものとする必要がある旨を周知させなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずるように努めなければならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
第十四条 事業者は、石綿等の切断等の作業等に労働者を従事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具(第六条第二項第一号の規定により隔離を行った作業場所における同条第一項第一号に掲げる作業(除去の作業に限る。次項及び第三十五条の二第二項において「吹付石綿等除去作業」という。)に労働者を従事させるときは、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク(次項及び第三十五条の二第二項において「電動ファン付き呼吸用保護具等」という。)に限る。)を使用させなければならない。 |
第十四条 事業者は、石綿等の切断等の作業等に労働者を従事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具(第六条第二項第一号の規定により隔離を行った作業場所における同条第一項第一号に掲げる作業(除去の作業に限る。第三十五条の二第二項において「吹付石綿等除去作業」という。)に労働者を従事させるときは、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク(同項において「電動ファン付き呼吸用保護具等」という。)に限る。)を使用させなければならない。 |
2 事業者は、石綿等の切断等の作業等の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、呼吸用保護具(吹付石綿等除去作業の一部を請負人に請け負わせるときは、電動ファン付き呼吸用保護具等に限る。)を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
3 (略) |
2 (略) |
4 事業者は、石綿等の切断等の作業等の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣又は保護衣を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
5 労働者は、事業者から第一項及び第三項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
3 労働者は、事業者から前二項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
(立入禁止措置) |
(立入禁止措置) |
第十五条 事業者は、石綿等を取り扱い(試験研究のため使用する場合を含む。以下同じ。)、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、当該作業場において作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
第十五条 事業者は、石綿等を取り扱い(試験研究のため使用する場合を含む。以下同じ。)、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
(局所排気装置等の稼働) |
(局所排気装置等の稼働) |
第十七条 事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が石綿等に係る作業に従事する間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。 |
第十七条 事業者は、第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、石綿等に係る作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。 |
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。 |
(新設) |
3 事業者は、前二項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の稼働時においては、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。 |
2 事業者は、前項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を稼働させるときは、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。 |
(休憩室) |
(休憩室) |
第二十八条 (略) |
第二十八条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 第一項の作業に従事した者は、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。 |
3 労働者は、第一項の作業に従事したときは、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。 |
(使用された器具等の付着物の除去) |
(使用された器具等の付着物の除去) |
第三十二条の二 (略) |
第三十二条の二 (略) |
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に使用した器具、工具、足場等について、廃棄のため、容器等に梱包したときを除き、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(喫煙等の禁止) |
(喫煙等の禁止) |
第三十三条 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。 |
第三十三条 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。 |
2 前項の作業場において作業に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 |
2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 |
(掲示) |
(掲示) |
第三十四条 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。 |
第三十四条 事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 石綿により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 |
二 石綿の人体に及ぼす作用 |
三 (略) |
三 (略) |
四 当該作業場においては保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等 |
四 使用すべき保護具 |
(作業計画による作業の記録) |
(作業計画による作業の記録) |
第三十五条の二 (略) |
第三十五条の二 (略) |
2 事業者は、前項の記録を作成するために必要である場合は、当該記録の作成者又は石綿使用建築物等解体等作業を行う仕事の発注者の労働者(いずれも呼吸用保護具(吹付石綿等除去作業が行われている場所に当該者を立ち入らせるときは、電動ファン付き呼吸用保護具等に限る。)及び作業衣又は保護衣を着用する者に限る。)を第六条第二項第一号及び第六条の二第三項第一号(第六条の三の規定により準用する場合を含む。)の規定により隔離された作業場所に立ち入らせることができる。 |
2 事業者は、前項の記録を作成するために必要である場合は、当該記録の作成者又は石綿使用建築物等解体等作業を行う仕事の発注者の労働者(いずれも呼吸用保護具(吹付石綿等除去作業が行われている場所に当該者を立ち入らせるときは、電動ファン付き呼吸用保護具等に限る。)及び作業衣又は保護衣を着用する者に限る。)を第六条第二項第一号及び第六条の二第二項第一号(第六条の三の規定により準用する場合を含む。)の規定により隔離された作業場所に立ち入らせることができる。 |
(評価の結果に基づく措置) |
(評価の結果に基づく措置) |
第三十八条 (略) |
第三十八条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならない。 |
3 前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならない。 |
4 事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、同項の場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(保護具等の管理) |
(保護具等の管理) |
第四十六条 事業者は、第十条第二項、第十四条第一項及び第三項、第三十五条の二第二項、第三十八条第三項、第四十四条並びに第四十八条第六号(第四十八条の四において準用する場合を含む。次項において同じ 。)に規定する保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管しなければならない。 |
第四十六条 事業者は、第十条第二項、第十四条第一項及び第二項、第三十五条の二第二項、第四十四条並びに第四十八条第六号(第四十八条の四において準用する場合を含む。)に規定する保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管しなければならない。 |
2 事業者は、労働者以外の者が第十条第三項、第十四条第二項及び第四項、第三十八条第四項並びに第四十八条第六号に規定する保護具等を使用したときは、当該者に対し、他の衣服等から隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、必要に応じ、当該保護具等を使用した者(労働者を除く。)に対し他の衣服等から隔離して保管する場所を提供する等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければならない。 |
(新設) |
3 事業者及び労働者は、第一項の保護具等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。 |
2 事業者及び労働者は、前項の保護具等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。 |
4 事業者は、第二項の保護具等を使用した者(労働者を除く。)に対し、当該保護具等であつて、廃棄のため容器等に梱包されていないものについては、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の一部改正)
第十一条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(除染等業務従事者の被ばく限度) |
(除染等業務従事者の被ばく限度) |
第三条 (略) |
第三条 (略) |
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の除染等業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第一項に規定する除染等業務従事者を除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 |
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の除染等業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 |
3 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び除染等業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第二項に規定する女性を除く。)の受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
第四条 (略) |
第四条 (略) |
2 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者のうち妊娠と診断された女性の受ける線量が、妊娠中につき前項各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(線量の測定) |
(線量の測定) |
第五条 (略) |
第五条 (略) |
2 事業者は、前項の規定による線量の測定に加え、除染等業務従事者が除染特別地域等内(平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時を超える場所に限る。第八項、第十項、第十一項及び第十条において同じ。)における除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の測定又は内部被ばくに係る検査を次の各号に定めるところにより行わなければならない。 |
2 事業者は、前項の規定による線量の測定に加え、除染等業務従事者が除染特別地域等内(平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時を超える場所に限る。第八項及び第十条において同じ。)における除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の測定又は内部被ばくに係る検査を次の各号に定めるところにより行わなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
3~8 (略) |
3~8 (略) |
9 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ行われるものを除く。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者が除染等作業により受ける外部被ばくによる線量を第四項から第六項までに定めるところにより測定する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
10 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者が除染特別地域等内における除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の測定又は内部被ばくに係る検査を、第二項各号、第三項及び第七項に定めるところにより行う必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
11 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染特別地域等内における除染等作業を行う場所において、放射線測定器を装着する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(事前調査等) |
(事前調査等) |
第七条 (略) |
第七条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、労働者を除染等作業に従事させる場合には、あらかじめ、第一項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該除染等作業の一部を請負人に請け負わせたときは、当該労働者及び当該請負人)に明示しなければならない。 |
3 事業者は、労働者を除染等作業に従事させる場合には、あらかじめ、第一項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者に明示しなければならない。 |
4 事業者は、労働者を特定汚染土壌等取扱作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二週間ごとに、第二項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該特定汚染土壌等取扱作業の一部を請負人に請け負わせたときは、当該労働者及び当該請負人)に明示しなければならない。 |
4 事業者は、労働者を特定汚染土壌等取扱作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二週間ごとに、第二項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者に明示しなければならない。 |
(作業計画) |
(作業計画) |
第八条 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。次条及び第二十条第一項において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、除染等作業(特定汚染土壌等取扱作業にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の作業計画を定め、かつ、当該作業計画により除染等作業を行わなければならない。 |
第八条 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。以下この条、次条及び第二十条第一項において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、除染等作業(特定汚染土壌等取扱作業にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の作業計画を定め、かつ、当該作業計画により除染等作業を行わなければならない。 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
(診察等) |
(診察等) |
第十一条 (略) |
第十一条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(粉じんの発散を抑制するための措置) |
(粉じんの発散を抑制するための措置) |
第十二条 (略) |
第十二条 (略) |
2 事業者は、除染等作業のうち第五条第二項各号に規定するものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を湿潤な状態にする等粉じんの発散を抑制するための措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(退出者の汚染検査) |
(退出者の汚染検査) |
第十四条 (略) |
第十四条 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
4 第一項の作業場において除染等作業に従事する者(労働者を除く。)は、当該作業場から退去するときは、同項の汚染検査場所において、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。 |
(新設) |
5 前項の者は、同項の検査によりその身体又は装具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、第一項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、同項の作業場から退出してはならない。 |
(新設) |
一 身体が汚染されているときは、その汚染が四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるように洗身等をすること。 |
|
二 装具が汚染されているときは、その装具を脱ぎ、又は取り外すこと。 |
|
(持出し物品の汚染検査) |
(持出し物品の汚染検査) |
第十五条 (略) |
第十五条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 第一項の作業場において除染等作業に従事する者(労働者を除く。)は、当該作業場から持ち出す物品については、持出しの際に、前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。ただし、第一項ただし書の場合は、この限りでない。 |
(新設) |
4 前項の者は、同項の検査により、当該物品が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第二項ただし書の場合は、この限りでない。 |
(新設) |
(保護具) |
(保護具) |
第十六条 (略) |
第十六条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、第一項の除染等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(保護具の汚染除去) |
(保護具の汚染除去) |
第十七条 事業者は、前条第一項の規定により使用させる保護具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるまで汚染を除去しなければ、除染等業務従事者に使用させてはならない。 |
第十七条 事業者は、前条の規定により使用させる保護具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるまで汚染を除去しなければ、除染等業務従事者に使用させてはならない。 |
2 事業者は、前条第一項の除染等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同条第三項の規定に基づく周知により使用する保護具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ洗浄等により四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるまで汚染を除去しなければ使用してはならない旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(喫煙等の禁止) |
(喫煙等の禁止) |
第十八条 事業者は、除染等業務を行うときは、事故由来放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場における除染等業務に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を明示することその他の方法により禁止するとともに、明示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を、あらかじめ、当該者に明示しなければならない。 |
第十八条 事業者は、除染等業務を行うときは、事故由来放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を、あらかじめ、労働者に明示しなければならない。 |
2 前項の作業場において除染等業務に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 |
2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。 |
(特定線量下業務従事者の被ばく限度) |
(特定線量下業務従事者の被ばく限度) |
第二十五条の二 (略) |
第二十五条の二 (略) |
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の特定線量下業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第一項に規定する特定線量下業務従事者を除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 |
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の特定線量下業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 |
3 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び特定線量下業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第二項に規定する女性を除く。)が受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
第二十五条の三 (略) |
第二十五条の三 (略) |
2 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者のうち妊娠と診断された女性の腹部表面に受ける等価線量が、妊娠中につき前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(線量の測定) |
(線量の測定) |
第二十五条の四 (略) |
第二十五条の四 (略) |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
5 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者が特定線量下作業により受ける外部被ばくによる線量を、第二項及び第三項に定めるところにより測定する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
6 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染特別地域等内における特定線量下作業を行う場所においては、放射線測定器を装着する必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
(事前調査等) |
(事前調査等) |
第二十五条の六 (略) |
第二十五条の六 (略) |
2 事業者は、労働者を特定線量下作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二週間ごとに、前項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該作業の一部を請負人に請け負わせたときは、当該労働者及び当該請負人)に明示しなければならない。 |
2 事業者は、労働者を特定線量下作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二週間ごとに、前項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者に明示しなければならない。 |
(診察等) |
(診察等) |
第二十五条の七 (略) |
第二十五条の七 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。 |
(新設) |
附則 |
附則 |
(特定施設等において放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者に関する特例) |
(特定施設等において放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者に関する特例) |
第四条の二 特定施設等において電離放射線障害防止規則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者については、第十一条(同条第一項第三号に係る部分に限る。)、第十四条及び第十五条(同条第一項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合において、第十一条第一項中「除染等業務従事者」とあるのは「電離則第四条第一項の放射線業務従事者(次項及び第十四条において単に「放射線業務従事者」という。)」と、同条第二項中「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第三項中「除染等業務」とあるのは「電離則第二条第三項の放射線業務」と、第十四条第一項中「除染等業務が」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業が」と、「除染等作業」とあるのは「密封されていない放射性物質を取り扱う作業」と、「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第二項及び第三項中「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第四項中「除染等作業」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、第十五条第一項本文中「除染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条第二項ただし書中「第十三条第一項本文」とあるのは「電離則第三十七条第一項本文」と、「除染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条第三項中「除染等作業」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」とする。 |
第四条の二 特定施設等において電離放射線障害防止規則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者については、第十一条(同条第一項第三号に係る部分に限る。)、第十四条及び第十五条(同条第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合において、第十一条第一項中「除染等業務従事者」とあるのは「電離則第四条第一項の放射線業務従事者(次項及び第十四条において単に「放射線業務従事者」という。)」と、同条第二項中「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、第十四条第一項中「除染等業務が」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業が」と、「除染等作業」とあるのは「密封されていない放射性物質を取り扱う作業」と、「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第二項及び第三項中「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、第十五条第一項本文中「除染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条第二項ただし書中「第十三条第一項本文」とあるのは「電離則第三十七条第一項本文」と、「除染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第二条第二項の放射性物質を取り扱う作業」とする。 |
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の電離放射線障害防止規則様式第一号の二の電離放射線健康診断個人票(次項において「旧様式」という。)は、この省令による改正後の電離放射線障害防止規則様式第一号の二の電離放射線健康診断個人票とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


