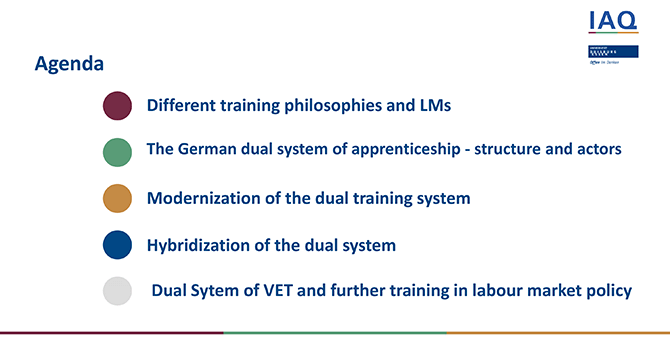特別講演 ドイツにおける労働市場の変化と人材育成

-
- ゲアハルト・ボッシュ(Gerhard BOSCH)
- デュースブルグ=エッセン大学 社会学部 教授/労働・職業資格研究所(IAQ)上級教授
- フォーラム名
- 第138回労働政策フォーラム「労働市場の変化と人材育成─日独比較の考察─」(2025年3月13日)
- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年6月号より転載(2025年5月26日 掲載)
はじめに
本日は、「労働市場の変化と人材育成:日独比較の考察」をテーマにご報告いたします。報告の論題は5つです(シート)。1つめは「異なる訓練の哲学と労働市場」として、国によって異なる職業教育訓練の哲学についてお話しします。訓練の哲学は、労働市場をはじめとする国の制度の中に組み込まれているものです。2つめは、ドイツのデュアルシステムの構造とアクターについてお話しします。3つめが「デュアルシステムの近代化」です。これは大変重要な点で、構造変化のなかAIの普及もあり、デュアルシステムもこれに合わせて近代化する必要があります。4つめは「デュアルシステムのハイブリッド化」で、高等教育との連携について取り上げます。最後に、「労働市場政策における職業教育訓練(VET)デュアルシステムと継続訓練」についてお話しします。
論題1「異なる訓練の哲学と労働市場」
技術は世界共通であってもスキルの構造は異なる
技術には、世界的に共通、または類似しているものがあります。例えば日本の企業でもドイツの企業でも類似の技術を使って機械を作っていますが、企業内の労働者のスキルの構造は全く異なっています。
いくつか国際比較をしてみます。例えばエアバスです。エアバスはドイツ、フランス、スペイン、イギリスなどに工場があります。このうちドイツで組み立てをしているのは熟練労働者で、ほとんどの熟練労働者は少なくとも3年半の訓練を受けています。これに対し、フランス、スペイン、イギリスはOJT(On the Job Training)です。ある程度スキルを持つ労働者が長期のOJTで段階的にスキルを習得します。
また、小売業では、ドイツは営業職を対象に2~3年の小売に関する職業訓練があり、食品や衣料品などについて学びます。一方、フランス、イギリス、米国では非熟練労働者が雇用されています。
もう1つ、レンガ職人を例に欧州での比較を紹介します。ドイツでは3年~3年半の広範な訓練があり、デンマークも同様です。しかし、イタリアとイギリスは訓練期間が1年と短いです。また、ドイツ、デンマークのレンガ職人は図面を読むことや複雑な仕事も理解できますが、イタリア、イギリスではこれは監督者が行う仕事です。
さらに自動車産業を例にとると、ドイツも日本も主力産業ですが、ドイツでは組立ラインの労働者はだいたい3年間の訓練を受けています。一方、日本ではOJTです。組立ラインであれば3年間の訓練は必要ないかもしれませんが、フォルクスワーゲンやBMWではそのような訓練を実施しています。
このように、国によって訓練の理念や概念が大きく異なりますし、労働市場の構造も異なります。
異なる訓練の哲学とVET(職業教育訓練)の類型
ドイツの学者であるGreinertが、欧州におけるVETを3つの基本類型に分類しています。
1つめはドイツの「コーポラティスト・労使協調型」です。このように呼ばれている理由は、労働組合、使用者団体、商工会議所のような中間組織によって監視・管理され、実施されているからです。普通の一般教育とは分かれており、訓練は企業内で主に行われますが、内容は高度に標準化されています。これは日本と大きく異なる点だと思います。
2つめはフランスの「国家中心・官僚型」です。これは国が規制する学校ベースの職業訓練システムで、訓練は実務よりも抽象化、理論化に重点が置かれます。また、訓練により授与される資格証明は学校の種類に応じて格付けされています。
3つめがイギリスの「自由市場経済型」です。訓練の需給は市場によって調整されます。また、養成されるスキルの種類は想定される職場のニーズに応じて決定され、特に標準化されていません。そのため、学校、企業、産業ベースの訓練形態が混在しており、理解するのが困難です。
ここで重要なのは、ドイツの「コーポラティスト・労使協調型」のみが、コミュニケーションや制度との独自のつながりを備えた自律的な社会のサブシステムであるということです。他の2つは、学校・市場という他のシステムによって形成されます。
さらにGreinertは、欧州には見られない4つめの類型として日本の「企業型」を付け加えました。企業型では、技術的な内容よりも業務の社会的文脈に重きが置かれています。この類型では、労働者のコンピテンシー(達成能力)は高いものの、職業の標準化による労働市場の透明性が確保されていません。そのため、技術的な観点からはコンピテンシーを他企業に移転することは可能ですが、労働市場でどのコンピテンシーが存在しているのかがよく知られていないため、実際にはそれほど簡単ではありません。
日本では、個人の意欲や企業に対する無条件の忠誠心により、典型的には企業に一体化する能力が重要視され、それと引き換えに労働者は終身雇用が保証されています。この傾向は特に大企業で顕著で、小さい企業ではそこまでではないかもしれません。
Greinertによると、以上の4つの類型があるということです。しかし、それぞれの国では主流の類型に加えて他の類型の要素も確認できます。したがって、ドイツにおいても純粋なモデルは存在していないということになります。
達成能力(competencies)とスキルに関する様々な概念
こうした様々な類型があるなかで、達成能力やスキルにも様々な概念があります。
Brookmannら3名の研究者が欧州に焦点を当てた2011年の研究論文を紹介します。ドイツでの概念は、熟練労働者は基礎的知識を備え、定義された幅広い職務の労働過程の中で自律的に行動できなければいけないということです。自律的に行動できるということが基本的な概念であり、上司からの継続的な指示がなくても自分の日々の仕事ができるということです。
イギリスでは、許容し得る水準で職務を遂行できる能力です。水準が高いとコストがかかってしまうためそこまで高くはありません。また、必ずしも基礎知識を備えている必要はないため、新しい仕事に対応していくのは難しくなります。
フランスはサヴォアフェール(Savoir faire)というもので、これは知識です。教育制度における上位の段階に進むための知識に重きが置かれており、教育の中で達成能力・スキルが上がっていくという考え方です。
このように、達成能力やスキルといった用語の意味も国や社会によって全く異なるため、一つひとつ意味を理解していく必要があります。
訓練と労働市場モデルとの関連性
訓練と労働市場モデルとの関連性も類型に関係してきます。国際比較の文献によれば、ドイツと日本はそれぞれ職業別労働市場と内部労働市場の模範とされますが、ドイツの職業別労働市場の構成要素は、1つが移転可能かつ透明性のある達成能力を備えた標準化された職務、もう1つが年功序列ではなく資格要件に応じて支払われる標準化された賃金体系です。これは、例えばスキルを持っているシーメンスの熟練労働者がフォルクスワーゲンに移ることができ、同程度の報酬を受け取ることができるということです。年功序列により給料が減るということもありません。3つめがスキル体系に応じた業務の組織化です。スキルに対して報酬が支払われ、業務の組織もスキル体系に対応しています。
一方、日本の内部労働市場の構成要素としては、標準化されていない企業内訓練ということになります。おそらく移転可能だとは思いますが、透明性を欠いています。年功序列や個人の勤務評定に基づく賃金体系、さらに企業内昇進制度を備えた形での業務の組織化が行われています。
両国とも大企業は内部労働市場を備えています。ドイツでも、大企業ではある程度の年功序列もあり、安定しているから残りたいという人は確かにいますが、企業間での異動も可能になっています。その一方、日本では、企業間の移動は困難になっています。
論題2「ドイツのデュアルシステム―構造および主体」
ドイツの教育制度におけるデュアルVETシステム
ドイツの職業教育訓練制度は、デュアルVETシステムが主要なシステムとなっています。327のホワイトカラー・ブルーカラーの職種を対象とする訓練で、重要なことはホワイトカラーも含まれているという点です。
訓練は使用者との徒弟契約から始まるため、まず会社を見つけなければなりません。訓練生は生徒ではなく会社の従業員となり、会社から訓練手当を受け取ります。訓練手当については、労働組合が交渉する団体協約で決まりますが、この数年間でその水準は上がっています。
学習は週3日を企業内で、残り2日を職業学校で行います。学校システムと統合されているわけです。企業内学習では多様な形態がとられています。企業や業界内に独自の訓練センターを設け、OJTを行います。マイスターが企業におり、その人たちが訓練の監督を担います。また、全321職種で上位資格(マイスター、テクニカー、ビジネス管理士など)を得るための標準化された「継続訓練」があります。
このシステムを運営しているのは誰かと言えば、労働組合、使用者団体、商工会議所が国や地方政府の支援を受けて運営しています。国が詳細を決めているわけではなく、決めているのは企業内の認定トレーナーです。またデュアルシステムは制度化されており、標準カリキュラムの開発、企業内や地域などでの訓練の実施、試験と認定などが行われています。
職種プロファイルとカリキュラム
ドイツにおける職業訓練の目標は「認定訓練職種」における専門的な能力の習得で、移転可能なスキルを得ることが基本的な考え方です。「認定職業訓練」とは、ドイツ全土に適用される標準化されたカリキュラムによる2年から4年間の訓練です。2年より短ければそれは認定職業訓練ではありません。これにより職業の構造的な変化から労働者を守ることができ、給与を減らされることなく企業移転が可能になります。
職種プロファイルとカリキュラムは連邦職業教育訓練機構(BIBB)による技術支援を受け、労働組合や使用者との合意に基づき開発されたものとなっています。機構には委員会があり、そこで職種プロファイルを作成します。また作業部会も立ち上がっており、ここに労働組合や使用者団体は経験を持っているマイスターのような人たちを参画させます。
職種プロファイル・カリキュラムの開発を労働組合と使用者の合意に基づいて行う理由は、技術的な専門知識が必要なことや、組合や企業規模の大小、近代的な企業やそうでもない企業などがあり、様々な意見・訓練ニーズがあるからです。
そのため、カリキュラムはどのような企業にも適用できる折衷案的な内容になっています。また、座学部分は16の連邦州がカリキュラムを作成しますが、そのうち3分の2が職業関連の理論、3分の1が語学や数学などの一般教養となっています。
重要なのは、ソーシャルパートナーがカリキュラムを決定するので、その職業を「自らの財産」「自らの職業」と捉え、地域、組織を通じて企業に推奨しているという点です。労働者から受け入れられるためにも、それは重要なことです。
監視、質の保証、試験、資格証明
訓練の監視、質の保証、試験の実施、資格証明の発行は、商工会議所がそれを行う独自のVET部門を持っています。各商工会議所には「職業訓練委員会」が設けられており、委員会は労働組合、使用者、職業学校教員で構成されています。「試験管理委員会」もあり、この3当事者の代表が入っています。
なお、試験管理委員会はボランティアで、協議はおおむね土曜日に行われています。地域数が多く327の職業がありますので、かなりの規模の仕事となることから、当事者にはプロとしての誇りも必要になります。
VET―独自のガバナンスを備えたシステム
このように、地域レベルでのデュアルシステムには労使による強いコミットメントがあり、国の介入はあまり歓迎されていません。つまり企業の訓練意欲によって左右される訓練システムだと言えます。これは強みにも弱点にもなります。企業としては訓練生を雇用しなければならない。毎年50万人以上の新規の訓練生を訓練しなければならず、試験の後、約72%を採用します。残りの約28%は他の会社に行きます。
2022年、企業は84億ユーロをVETに対して支出しました。これに対し、学校や支援策に対する同年の公的支出額は46億3,000万ユーロでした。企業が国よりも多く支出しています。企業の総コストはさらに大きく272億ユーロです。
ただ、コストの69%は、訓練生が訓練期間中に生産に寄与することで回収できています。特に3年目の訓練生はほぼ生産に寄与することができます。コスト圧力は生産性が高まることによって緩和されます。一部の産業(主に建設業)では補助金制度もあります。看護師や高齢者介護、教員など学校ベースでの職業訓練でも同じようなシステムが導入されています。
デュアルVETシステムの成果
デュアルシステムの成果としては、訓練生は社員であり労働者とみなされているので、若年失業率が他国と比較してかなり低いとの文献が多くあります。これは企業に訓練を続けるようにとの圧力があるからです。イタリアやフランスのような学校ベースのシステムの国では若い人たちは外部の人とみなされ、労働組合は社員を保護するのに対し、ドイツでは若い人たちを社内の人とみなすのが大きな違いです。
もう1つの成果として、他国に比べて現場監督者の数が少なくて済む点があげられます。労働者によってスキル構造が異なると監督者がより多く必要になりますが、ドイツの熟練労働者はより複雑な仕事ができますし、エンジニアと同じようなレベルで技術に関して議論することができます。このため現場と経営陣との対等な立場でのコミュニケーションが促進されます。
論題3「デュアルシステムの近代化」
構造変化や「グリーン/DX」により、システムの継続的な近代化を図る必要
3つめの論題はデュアルシステムの近代化です。構造変化が進むなかでシステムの近代化は大変重要です。
近代化のペースは1995年までは緩やかでしたが、95年にソーシャルパートナーが従来の職種の近代化と新規職種の創出の加速化に合意し、2014年から2023年までに111の職種の近代化と5つの新規職種を創設しました。業務の柔軟な組織化のための新たな学習形態も出てきました。また、金属関連職種向けに、付加製造(additive manufacturing)のような任意のモジュールを初期訓練、継続訓練用に作成しました。2021年にはデジタル化、環境保護、労働安全衛生等に関する職種横断的で標準化された職業プロファイルも導入されました。これと並行してマイスターなど上位資格を得るための訓練も近代化されました。
職種の拡大と新たな職種の創出
近代化の具体例として、金属産業では1987年まで45の特化した職種がありました。しかしこれらの職種には重複があるということで1987年には16に減り、2004年から5つになりました。IT分野では新たに4つの職種が生まれ、これらの職種では継続訓練でマスターレベルまで昇進できます。
建設業における職業訓練の構造
また、建設業では16の職種があり、これが建築、土木など3つのグループに分けられましたが、1年目で学ぶ内容はグループが異なっても3分の2が重複しています。これは、労働者はみな工事現場にいるため、互いにやり取りできることが必要だからです。2年目にはより専門性を高めていき、3年目にはさらに内容を特化していきます。職種間での移動も奨励されています。
柔軟な就業形態のための新たな学習形態
私がこの研究を始めたときには、座学などは企業内の研修センターで行われ、訓練生がいろいろものを作っていました。その後、トレーニングの改善やより複雑な製品を作る必要から、場合によっては他の業種と協力をするということもありました。企業における研修センターでは、例えば金属関係の人でも、電気技師と連携をするようなことが行われています。
このコンセプトは「カスタマーアプローチ」もしくは「ビジネスプロセスアプローチ」として知られています。つまり、学習が全体的なものになり、学習形態がビジネス指向になります。プロダクトやサービスの注文がまず来て、それを受注します。その後で、顧客が何を求めているのかを理解しようとします。そして、製品をチームとして作り上げて、それを顧客のもとに届けるという、全体的なプロセスであるということです。
事務職の人たちも関わってきます。例えば、会計や経理、コスト計算などといった要素も含まれてくるためです。このアプローチを、職業訓練校とうまく連携させることを目指しています。非常にデジタル化された企業で行うときは、訓練生はデジタルに関連することについても習います。
論題4「デュアルシステムのハイブリッド化」
高等教育への傾斜
ドイツでも他国と同じように高等教育への傾倒が起きています。これは「エレベーター効果」として知られています。高等教育を受けなかった親が、自分の子どもに高等教育を受けさせたいと考えるようになり、誰かが上に行くと他の人たちもついて行きたくなるということで、このプロセスが加速化してより高いスキルを求めるようになるのです。
ドイツにおけるスキル構造は少しずつ変わってきています。職業訓練を受けた従業員の割合は、1964年は29%でしたが、60年代から80年代に訓練が近代化され、2011年には66.6%まで上昇しました。その後は下がってきており、2022年には60.2%になっています。
その理由は、大学の学位を取ることが増えてきているためで、2022年では13.6%が未熟練労働者、18.6%が高等教育修了者などとなっています。
従業員に占める訓練生の割合も、2007年は6.5%でしたが2022年には4.5%に低下し、2011年以降、高等教育進学者数がデュアルシステム進学者数を上回っています。
デュアルシステムは危機的な状況にあるかもしれませんが、ドイツの職業訓練システムは他国と比べるとまだまだ強力であると言えます。多くの企業は訓練生を採用したいと考えており、良い徒弟に対する採用意欲は高いです。
デュアルスタディ(Dual study):VETと高等教育との組合せ
デュアルシステムをより魅力的なものにするため、多くの企業がVETと学士課程を組み合わせたプログラムを提供しています。大学で学びたいが、同時にVETにも入りたいという人たちのためのもので、確立されたシステムとしてルールもできつつあります。
これは「デュアルスタディ」と呼ばれており、2つの類型があります。1つは、若い人が徒弟契約を企業と結び、訓練手当を受けます。同時に大学にも入学し、最終的に訓練課程と学士課程の2回の試験を受ける形になります。これはかなり要求も厳しく、あまり休みもありません。もう1つは少し軽量のシステムで、学士課程に進みながら訓練手当と実務研修を受けるというものです。こちらは訓練課程の試験はありません。
「デュアルスタディ」は学生にとって負担は倍増しますが、キャリアアップのチャンスが拡大します。このプログラムを経れば資質が高まり、ストレス耐性も高くなるため、企業にとっては魅力的な人材となります。このプログラムで学んでいる学生の割合は上がってきており、高等教育機関に在籍する学生に占めるデュアルスタディ初学者の割合は2022年には7.7%となっています。
高等職業訓練の拡大
ドイツにはドイツ資格枠組み(DQV)があり、各資格は8つのグレードに分かれています。EU諸国にも資格枠組みがあり、レベル6は大学の学士の学位を取った人だけに割り当てられていますが、ドイツではマイスターなども学士号を持っているのと同じレベルにあるとの考えをとっており、同じレベル6に相当する「学士プロフェッショナル」を作りました。マイスターやテクニカー、ビジネス管理士が該当します。また、レベル7に相当する「マスタープロフェッショナル」もあり、こちらはビジネスエコノミストや職業訓練教師などが該当します。
重要なことは、一般教育と職業訓練を平等にするということです。向上訓練支援法という法律がありますが、専門的な継続訓練(最低訓練時間400時間)を行うための助成金/融資制度があり、参加者は2021年には19万2,000人に増加しました。
論題5「労働市場政策における職業教育訓練(VET)デュアルシステムと継続訓練」
ドイツにおける積極的労働市場政策の長い伝統
ドイツには積極的労働市場政策の長い伝統があります。1969年以降、失業者に対する再訓練の資金提供を開始し、新たな職種で2年間の再訓練プログラムに参加する失業者に資金提供を行ってきました。訓練は、デュアルシステムまたは学校システムのカリキュラムの対象職種で、訓練中は失業手当も支給しました。資金はすべて国が提供し、商工会議所が行うような試験と資格証明の取得で完了するようにしました。
2003年にはハルツ改革により訓練優先から就職優先へのパラダイムシフトがありました。資格取得につながる長期で高額の再訓練プログラムが激減し、短期の「ファストフード再訓練」が主流になりました。その後、労働市場におけるスキルのボトルネックやデジタル/グリーン・トランスフォーメーションを背景に、2007年から2023年においても緩やかなパラダイムシフトがありました。また、資格につながる継続訓練への肯定的な評価により、資格取得を目的とする継続訓練が増えました。訓練優先アプローチが復活したことで、失業手当に月額150ユーロを上乗せする訓練手当が導入されました。さらに2024年には、構造変化により従業員の20%以上が再訓練を必要とする企業に対する訓練手当も導入されました。
労働市場政策に基づく継続訓練への参加者数をみると、2000年には資格につながる訓練を受けた労働者が約14万人でしたが、パラダイムシフトがあり2007年には3万5,000人弱まで減りました。その後、新しい法律等ができて増加していますが、2000年以前の高い水準までは戻っていません。これは、現在、労働市場が大変タイトになっており、再訓練を受けなくても新たな職に就ける可能性が高いことや、失業者の中には訓練を受けていない人が非常に多いという問題、言語スキルの不十分な外国人がかなり多いという問題があります。
まとめ
最後にまとめたいと思います。まず、デュアルシステムはソーシャルパートナー間の合意に基づいて構築されています。これは産業界が、学校卒業生のVETを自らの責任であると考えているからです。また、高い訓練基準、経済への定着、キャリアアップのチャンスと継続的な近代化により、国民にもかなり受け入れられています。デュアルシステムは、移転可能な標準を備えた職業労働市場の基盤になっているのです。
デュアルシステムのプラスの効果としては、若年失業率の低下、柔軟な業務の組織化、構造変化の中での速い学習曲線があげられます。一方、問題点としては、学校卒業資格がなく、訓練も受けていない若者の割合が高いことや、大卒者の賃金上昇のほうが職業訓練だけを受けた人よりも高いために、高等教育を受けることの金銭的な魅力のほうが増していることが指摘されています。
プロフィール
ゲアハルト・ボッシュ(Gerhard BOSCH)
デュースブルグ=エッセン大学 社会学部 教授/労働・職業資格研究所(IAQ)上級教授
ケルンで経済学と社会学を学び、1977年にドルトムント大学で博士号、1991年にオスナブリュック大学で教授資格を取得。1993年よりデュースブルグ=エッセン大学社会学部教授。1993年から2006年までゲルゼンキルヒェンの労働・技術研究所副所長を務めた。2007年、デュースブルグ=エッセン大学に労働・職業資格研究所(IAQ)を設立し、2016年まで所長。以降、IAQで上級教授として勤務している。労働市場、職業訓練、労使関係、労働時間、賃金、社会保障を中心に研究しており、著書多数。国際比較研究も多い。また、OECD、欧州委員会、複数の連邦省庁の顧問を務める。