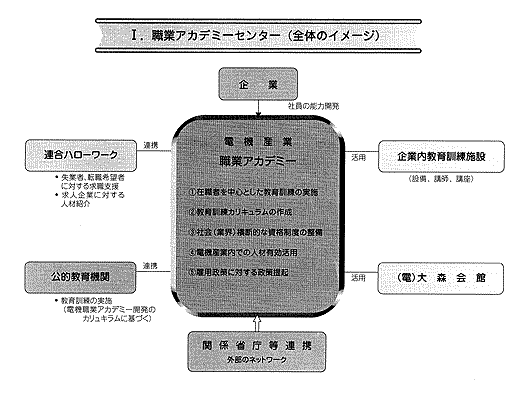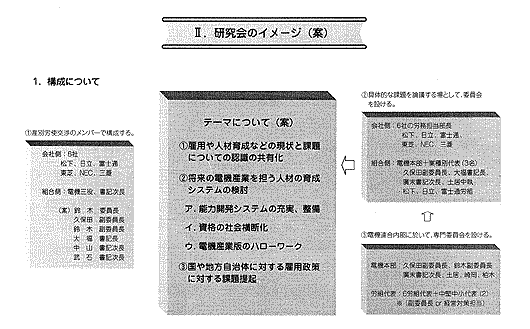配布資料:第14回 旧JIL講演会
IT革命と労働運動
~電機産業の取り組みを中心に~
(2000年12月11日)
電機連合
鈴木勝利
| ●成熟社会の特徴は「制度補完型社会」である。それぞれの制度・システムが相互に補い合いながら成り立つ社会である。唯一つのシステムが単独では成り立たないという意味であり、同時に、結果として出る現象はいくつもの要因が相互に影響し合って生まれるという「複合汚染?」社会なのである。
●したがって、IT革命による労働運動に対する影響もそれ単独では考えられない。その他のさまざまな要因と重なりあって労働運動に影響を与えているという視点が必要である。 |
| I. | IT革命と21世紀の経済・労働環境の分析(図1(PDF:98KB)、図2(PDF:99.7KB)、図3(PDF:288KB)) | |
| |
1. | マクロ経済の環境変化 |
| |
2. | 企業環境の環境変化 |
| |
3. | 組合員意識の変化 |
| |
4. | 失業率の上昇時代 |
| |
||
| II. | 電機産業職業アカデミー構想についての労使研究委員会発足について | |
| |
1. | 産業構造の変化に対応する事業構造改革と人材育成 |
| |
2. | スムースな労働者の移動、職種転換ができるシステムの構築が急務 |
| |
3. | 産業共通の人材育成こそ、個別企業の責任と利益である |
| |
4. | 企業の枠を越えた人材の育成とミスマッチの解消に向けて |
| |
||
| III. | IT化がマクロ経済に及ぼす影響(資料3) | |
| |
1. | 産業革命に匹敵する影響 |
| |
2. | IT産業そのものによる経済効果 |
| |
3. | ITを活用することによる生産性の向上 |
| |
4. | 忍び寄る「負の効果」 |
| |
5. | 今後の流れについて |
| |
||
| IV. | 情報化が電機産業(企業)に与える影響 | |
| |
1. | 成熟分野と成長分野(原因はIT化によるものではなく構造的なものもあるが) |
| |
2. | 事業による「集中と選択」 |
| |
||
| V. | 労働力への影響 | |
| |
1. | 労働市場への影響 |
| |
|
(1) 雇用創出のタイムラグ |
| |
|
(2) 労働力のミスマッチ |
| |
|
(3) 労働力の移動 |
| |
|
(4) 派遣労働者の増加 |
| |
|
(5) 専門職の増加 |
| |
|
(6) 「モノづくり」の育成 |
| |
2. | 働き方への影響 |
| |
|
(1) 就労形態の多様化 |
| |
|
(2) 時間管理からの脱却 |
| |
3. | 処遇への影響 |
| |
|
(1) 企業への貢献の尺度の変化 |
| |
|
(2) 技能のバーゲニング時代へ→転職者の増加 |
| |
||
| VI. | 新しい労働運動の在り方 | |
| |
1. | メンバーズクラブの限界(新しい労働形態への対応) |
| |
|
(1) 正規社員以外の組織化 |
| |
|
(2) その人たちへの影響力は「社会的合意システム」 |
| |
2. | 日常活動の対応策 |
| |
|
(1) 多様な働き方への対応 |
| |
|
(2) 塀の中の労働運動の限界(技能職の減少) |
| |
3. | 情報労連との提携の真意 |
●以上、IT革命が労働運動にどのような影響を与えるのか分析してきたが、今後、 私たちが押さえておかなければならない問題は、マクロでいえば、IT革命そのも のは時代の必然であり否定すべきものではないが、一つに、持て囃される「ニュー ビジネス」も、結果として成功するのはごく一部(非公式にはアメリカにおいても1-2数%程度)であり、甘い幻想を抱かせるべきではないことであり、同時に各企業におけるニュービジネス援助措置についても、「敗者復活」のチャンスが必ずしも保障されている訳ではないことに留意しておく必要がある。二つに、企業における処遇について、生活水準の向上や意識変化に応じて、企業における処遇に「業績・成果・能力」主義が導入されることも当然であるが、高処遇に遇せられる人は全体の20-30%程度であろうから、多数の組合員の処遇の在り方(能力主義を否定するのではなく)についても対応策を考えておかなければならないことである。 ●また、最近話題になる「ストックオプション制度」については、(1)支給基準が公開されていないため、一部の経営者だけが恣意的に決定できること。(2)毎期の決算には計上されないので、これも恣意的な支給を助長する。(3)当然、労使の交渉はおろか協議の対象にもならない(組合の知らないところで組合員の処遇に関わることが行われる)など、問題点が多すぎるので、組合としても十分に留意しておく必要がある。 ● いずれにしても今後、その国の経済力を決定付けるのはIT技術とその手段の有効活用の水準によるのは間違いない。好むと好まらざるとにかかわらずIT技術によって、企業で働く私たちの環境は劇的に変化する。その時に労働組合運動は的確に対応できなければならない。 ◆ 組織化
◆ 組織(運営)論
◆ 日常活動
◆ 処遇(結果の平等と機会の平等)
◆ 雇用
◆ 労使関係
|
電機産業職業アカデミー構想についての労使研究委員会発足について
2000年11月 1.産業構造の変化に対応する事業構造改革と人材育成 今後の経済構造、電機産業の構造また少子高齢化社会構造を考慮すれば、いままでのように多くの人が一生を一社に過ごす時代から、二社・三社を移動する傾向は強まらざるを得ず、そのためにも適応できるシステムを社会にも産業にも整なわせておかなくてはならない。 2.スムースな労働者の移動、職種転換ができるシステムの構築が急務 企業にとっては、事業構造の改革を進める上にも、働く従業員の能力向上、あるには職種転換に伴う適切な人材育成が欠かせないと同じように、組合にとってもまた、組合員の職業能力の向上は、雇用確保の努力に必要不可欠な要素に成っている。 3.産業共通の人材育成こそ、個別企業の責任と利益である 現在行われている各企業の教育訓練制度は、当然のように当該企業の企業文化なり価値観によって進められている。しかし、これからの経済動向や事業構造の改革にとって、個別企業の中だけで通用すれば良しとする考え方は、「雇用確保」や職種の「ミスマッチ」によって、その有効性に限界のあることはあきらかであり、企業を越えた人材の「人を活かす」ことが企業責任になる時代である。 4.企業の枠を越えた人材の育成とミスマッチの解消に向けて そこで、今まで述べてきた課題を解決し、労使それぞれの立場で社会的責任が果たせ、従業員にとっても、自らの能力向上や他社からの求めに応じられる能力開発が実現出来る制度として、次のような電機産業共通の人材育成や人材の有効活用を目的とする「職業アカデミーセン夕ー」の設立を検討していきたい。これはあくまでも一例であり、制度や運営については提案している労使の研究委員会で検討するものである。 以上
|
IT化がマクロ経済に及ぼす影響
| 1.産業革命に匹敵する影響 | |||
| |
(1) | 時間、国境、規制、制度の壁、職種、業界を超えてモノ、カネ、人、情報が流れる。個人と企業との直接的なやり取り。企業間の商取引が変化(GMが仲介手数料ビジネスに進出)する。 | |
| |
(2) | 消費者が最新、大量の情報を容易に入手できる(保険の商品比較、商品の直接販売など、個人向けの商品アプローチが容易)。 | |
| |
(3) | 株式取引、金融商品販売など、金融仲介ビジネスでの「専門性」が変化。 | |
| |
(4) | ネットワークを介して流通、物流コスト、在庫コストが削減される(在庫管理、生産管理が変化)。 | |
| 2.IT産業そのものによる経済効果 | |||
| |
(1) | 凄まじい早さで最新型に更新される情報機器(黒電話が留守番電話機能を持つまでに要した時間は15年、携帯電話の端末更新は 1年)。 | |
| |
(2) | より便利な機能を求める人間の欲望=新機種でなければ不安になる心理 | |
| |
(3) | 誰もが不思議に思わない「ゼロ円」携帯電話の販売価格(通信価格がいまだに高いので販売価格がゼロ円でも機材の費用と販売店へのバックマージンをペイできる) | |
| |
(4) | 中・高校生の小遣いの多寡=カラオケー携帯電話ー携帯電話利用のメール=親の知らないところでの友人とのメールは子供部屋に電話線を引いたのと同じ。電車の中でも迷惑にならない=この現象は、メイルが来ないと不安になり、逆に直接面と向かうと会話は 5分でとぎれる。 | |
| |
(5) | わずかな投資で莫大な利益=優秀なエンジニア一人は「普通のエンジニア 100人に勝る。1枚 100円のCDに10万円の価値を付けるのは「ソフト」。ソフトが欲しいからパソコン、ゲーム機を購入する(テレビ番組を見たいからテレビを買う)。 | |
| |
(6) | やりたいことを「実現できそうだ」というマーケット(カラープリンター、年賀状を自宅で印刷、運動会のビデオをパソコンで編集しDVDを作成)。 | |
| |
(7) | 最新の情報技術を持っていなければ意味がない(証券、銀行業界の金融仲介機能の劇的な費用減少、支店を持たないインターネット銀行の誕生、インターネットを利用した株取引には「営業マンは足枷」=野村證券<松井証券) | |
| |
(8) | 「一発逆転サヨナラ負け」の恐怖感=対抗企業から最新機種がリリースされたら既存商品の価値は半減 | |
| |
(9) | 世界で一番、億万長者エンジニアを生み出したのはマイクロソフト社 (ストックオプションによる社内エンジニア引き止め) シリコンバレーの家屋価格は全米一のレベル |
|
| |
・ | 急増する半導体製造装置への設備投資 最近のナスダックの変調は半導体関連の売れ行きの不透明感が原因( 4年周期の シリコンサイクルか?) |
|
| 3.ITを活用することによる生産性の向上 | |||
| |
(1) | 在庫管理 | |
| |
(2) | 電子取引 | |
| |
(3) | 生産と生活の場が身近になる | |
| |
(4) | 頭脳という生産財を持ち歩く労働者(ピータードラッガー)の登場? | |
| 4.忍び寄る「負の効果」 | |||
| |
(1) | インターネットの落とし穴 | |
| |
|
1) | マスコミに騒がれるとアクセス数は増大する(東芝のクレーマー事件)。 |
| |
|
2) | 「大企業は悪いに決まっている」という意識の弊害。 |
| |
|
3) | 自分に有利な点だけを強調できる=しかも相手のページには反論できない。 |
| |
|
4) | 揚げ足取りの風潮を助長 |
| |
(2) | 正社員による内部告発 | |
| |
|
1) | 匿名による内部告発の容易さ=パソコンなど会社の備品を自宅に持ち帰ることの日常化の中での意識変化(忠誠心の変化?)。逆恨み告発の多発化。 |
| |
|
2) | 著作権保護協会では違法コピー告発を奨励。ある会社では違法コピーに罰金五千万円 |
| |
(3) | 顧客情報の流出=指摘されなければ気が付かない情報漏れ(気が付いた時にはもう遅い) | |
| |
(4) | 「知らぬ間に取り込まれている」個人情報 花粉飛散情報への電話アクセスすると→電話番号表示→電話帳データベース→住所氏名が分かる→「ここに花粉で悩んでいる消費者がいる」ということが業者に分かってしまう。 | |
| |
(5) | 税務署に補足されない知的所有物のインターネット売買(音楽、画像、小説など) | |
| |
(6) | クーリングオフなど既存消費者保護法が適用されないインターネット取引 | |
| |
(7) | ネットワークビジネスを名乗っているが実態はマルチ商法のような詐欺商法 | |
| |
(8) | 違法な物件の取引や詐欺 警察庁刑事局長談「電子メイル上などで暗号が使われた場合について、高度な知識を有した専従職員の確保と機材の整備に務め、最先端の技術を確保していく」 |
|
| |
(9) | 社員が行うメイルのやり取りの傍聴は合法 | |
| |
|
1) | 米国法廷でのケースでは従業員側が敗訴。社内メールの監視ソフトの効果は認めつつも導入には二の足を踏む企業が少なくない。あるメーカーの関係者は「このやり方は、パート社員の私用電話が多いから社外にかける電話をすべて盗聴しようとする発想と同じ。社員教育の徹底の方が効果があるのでは」と語る。 |
| |
|
2) | 社員がどんなホームページを見ているか監視することもある(IBM=違サイト、風俗サイトなどへのアクセスは「懲戒対象」)。 |
| |
・ | 社員のキー入力の頻度を調べるケース=活発に作業しているかを調べる。 | |
| 5.今後の流れについて | |||
| |
(1) | 「中卸」という業種はなくなってしまうのか? | |
| |
(2) | 中間管理職は居なくなってしまうのか? | |
| |
(3) | 情報機器の操作ができなければ無能のレッテルを貼られてしまうのか? | |
| (1) | 情報化戦略担当役員の登場 |
| |
企業戦略の中で「情報」を効率的に管理、向上させることが必要となってきた。 |
| |
|
| (2) | 意思決定の迅速化 |
| |
商品企画から市場投入までの時間短縮 |
| |
|
| (3) | ネットワークとデーターベース |
| |
顧客情報データベースを「誰でも必要なときに」アクセス可能に |
| |
|
| (4) | ナレッジマネジメント |
| |
ノウハウと呼ばれているものを共有できないかという試み |
| |
|
| (5) | 組織のフラット化 |
| |
「事務処理」の合理化・省力化 中間管理職の役割 |
| |
|
| (6) | ビジネスモデル |
| |
特許戦略(知的所有権)の次は、ビジネスモデル (しかしこの流れが本物かどうかは今ひとつ不明) |
| |
|
| (7) | 集中と選択 |
| |
情報機器の全部のレパートリを自社でまかなうのは無理→合従連衡へ 電子商店を開催する=専門会社に作成を依頼し、自社は自社製品関連に注力 |
| |
|
| (8) | 企業倫理 |
| |
製品欠陥が即座に影響を与えかねない 違法行為に対する内部告発 |
| |
|
| (9) | 危機管理モデル |
| |
事故の発生を知ってから対策するのでは遅い トップの判断ミス、対応ミスが連続するのはなぜか? |
| |
|
| (10) | ITコーディネータ |
| |
中堅中小企業がIT技術を使いこなすためには、メーカーだけに頼ってはだめ |
| (1)働き方 | ||
| |
「多様な就業形態を認める」ということは、下記の全てに格差を認めること | |
| |
■ | 給与 |
| |
|
年齢ではなく達成された成果の評価を正当に行う。評価基準は? |
| |
■ | 処遇 |
| |
|
資格の飛び越しが発生。「知っている」だけではなく「できる」が重要 |
| |
■ | 労働時間 |
| |
|
パート、正規従業員との格差は何? |
| |
■ | チームでやることと個人作業の区分けが変化 |
| |
|
仕事のダウンサイジング(いままで部レベルでやっていた作業が個人ベースに) |
| |
||
| (2)処遇条件 | ||
| |
■ | モチベーションをいかに与えるか、がより重要になってくる 高給、ストックオプション、「仕事の代償は仕事」 |
| |
■ | 「必要な人材なら多額の報酬でもOK」という発想が出てくる |
| |
■ | IT技術を持った人材は、そうたくさん人材マーケットにいるわけではない。 |
| |
■ | 人材育成に高額な費用投資を行っても、定着してくれなければ困る |
| |
■ | プロフェショナルな仕事に対する評価を間違えると転職されてしまう |
| |
■ | アウトソーシングした業務を評価する人材は必ず必要 |
| |
■ | 国家戦略として「情報処理資格」を作って来たが、現在ではソフト会社の資格認定のほうが転職には有利とされている。 (たとえばデータベース(オラクル社)、マイクロソフト資格認定) |
| |
||
| (3)派遣労働者 | ||
| |
■ | 新たな就労形態の一つ |
| |
■ | 『その企業の弱点をカバーする』という発想から、部分移管が主流に(一種のアウトソーシングを、社内・工場内で行っている) |
| |
■ | 酷使されている? |
| |
■ | 『やりがい、働きがい』のための能力評価システムが必要 |
| |
||
| (4)テレワーク | ||
| |
■ | コールセンターの需要は急増 |
| |
||
| (5)在宅女性 | ||
| |
■ | 在宅でできる作業自体がどれくらいあるのか? |
| |
■ | 労働時間管理、安全管理など従来にない就業形態 |
| |
||
| (6)デジタル・デバイド | ||
| |
■ | 再教育(特に中高年齢層)の難しさ |
| |
■ | インターネットを活用しているのは中堅層、若年層 |
| |
■ | 自分自身は「デジタル・デバイド」だと思っていないところが問題 |
| |
■ | 部下や秘書にやらせているうちは情報活用のすさまじさを感じられない (たとえば電機連合ではサイボーズの活用で、誰がいつ何をやっているかがわかる) |
| |
■ | 私がわからないのは教えてもらっていないから、と考える層が問題 若者や学ぶ意思のあるものは「わからないのはなぜか、どうしたら理解できるか」を突き詰めて考える。 |
| |
||
| (7)外国人労働者 | ||
| |
■ | 本当に優秀なITエンジニアが、日本に来るのか? スーパーエンジニアは、やぱっり、シリコンバレーが魅力的に写る |
| |
■ | 現在の評価基準(技術水準)で、IT技術者不足を叫ぶのは、いかがなものか? (技術発展によって馬車ー自動車のような、パラダイムシフトが発生するはず) |
| |
■ | インドから米国への技術者流入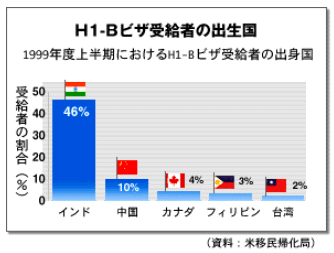 |
IT革命・情報化時代の労働運動(マクロ面からのアプローチ)
| (1)失業 | ||
| |
■ | 必要とされている人材と、流動化している人材との「質」のギャップが最大の問題! |
| |
■ | セーフティネットの整備と言われてはいるが、「何がセーフティネットなのか」はそれぞれ異なる。 |
| |
■ | 求職時期の生活保障だけではなく、再充電・再出発の資金も必要 |
| |
■ | 雇用調整金による「失業させない」政策と、適切な人材の流動性を認めて、再教育に力を入れる政策の両建て? |
| |
||
| (2)労働形態の変化(細分化) | ||
| |
■ | 機会の均等をどのように担保するか |
| |
■ | 職場の変化(細分化)と労働条件 |
| |
■ | QC、ZDなど「高いモチベーション」を維持するには? |
| |
■ | 苦情処理をいかに行うのか? (対応を誤れば、すぐに外部に訴えられる時代) |
| |
||
| (3)教育訓練制度と人材紹介 | ||
| |
■ | 国家政策的な再教育と、民間活用の両立時代 労働組合自体が教育に乗り出す。(米国では一般的に行われている) |
| |
■ | 失業者は適切な情報を受け取るための手段が足りない(情報の不完全さ) 労働組合がその媒介になることは「当然」 |
| |
■ | 福祉(共済)での役割の中に、「失業対策」が考慮される時代 |
| |
||
| (4)インターネットユニオン | ||
| |
■ | どこまで個別の労働問題に対応できるのか? |
| |
■ | 情報伝達や教育には適しているツールとしてのインターネット |
| |
■ | 法的な活動にあたっては、実際の「紙」作業が必要 (労働協約ひとつとってみても、調印作業は必須) |
| |
||
| (5)外国人労働者 | ||
| |
■ | 優秀なエンジニアに来てもらうための施策は適切か? (外国人労働力の使い捨て(?)、既存処遇体系との格差は合理的か) |
| |
■ | 不慣れな部分、社会的差異をカバーするのは会社と組合、地域 |
| (1)従業員の生涯設計 | ||
| |
■ | 再教育(リカレント教育)を人生設計の中に組み込む 自分に何が足りないのかを、外部からわかってもらう(わからせる)方法 |
| |
■ | 人材育成に関する会社側への提言 |
| |
■ | 配置転換を含む「適職」への助言 |
| |
■ | 悩める組合員に対するメンタルケア |
| |
||
| (2)アウトソーシング | ||
| |
■ | ものづくりなど、基本的な技能の継承 |
| |
■ | 基盤技術をもつエンジニア(匠)が尊敬されるような体制作り |
| |
■ | ノウハウ蓄積 |
| |
||
| (3)非正規従業員(派遣労働者) | ||
| |
■ | 職場環境・安全衛生への対応 |
| |
■ | 能力向上への対応 |
| |
■ | 苦情処理体制 |
| |
■ | 派遣労働者の組織化 |
| |
||
| (4)企業危機、守秘義務とセキュリティ | ||
| |
■ | サービス、品質保持体制 職場の最前線情報(そごう、雪印、三菱自動車のケース) |
| |
■ | 「お客様」からのクレームに対する対応のチェック |
| |
■ | 企業(企業内労働組合)の社会的責任の再確認 |
| |
||
| (5)組織化 | ||
| |
■ | インターネットユニオン(いまだ実像ははっきりしないが) |
| |
■ | インターネットを利用した労働運動 困ったことがあった場合の過去事例検索や法律相談 |
| |
■ | ボイコット運動ができない日本の企業内労働組合 →労働問題が発生しているならそれを産別のページに掲載する(?) |
| |
■ | 印刷物(郵送)のコスト⇒直接電子メイルを送ることができれば費用は減少 |