開催報告:第28回労働政策フォーラム
外国人労働者の雇用ルールと企業における活用のあり方
(2008年 1月25日)
目次
- 基調報告 「日本における外国人労働者雇用の現状と課題」
- 渡邊 博顕 JILPT主任研究員
- 解説 「改正雇用対策法の趣旨―新外国人指針を中心にー」
- 尾形
 嗣 厚生労働省 職業安定局外国人雇用対策課長
嗣 厚生労働省 職業安定局外国人雇用対策課長 - 事例報告
- ローソンにおける外国人従業員の採用・雇用の取り組み
曽我野 麻理 株式会社ローソン ヒューマンリソースステーションHR改革リーダー
- システム開発・IT企業における外国人従業員の活用の取り組み
小野田 祐子 TIS株式会社 企画本部人事部長
目次へ
解説・改正雇用対策法の趣旨―新外国人指針を中心にー
厚生労働省 職業安定局外国人雇用対策課長 尾形  嗣
嗣
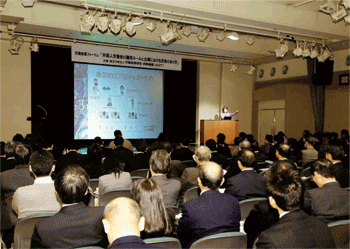
1月25日に東京・築地で開かれた労働政策フォーラム「外国人労働者の雇用ルールと企業における活用のあり方」(JILPT主催)では、改正雇用対策法の施行を受け、その趣旨・内容を解説するほか、外国人労働者の活用事例を紹介し、新しい雇用ルールの下における外国人労働者の活用のあり方について意見交換した。
改正雇用対策法が平成 19( 2007)年の通常国会で成立し、同年 10月1日から施行されている。同法については、外国人を雇った場合の届出の義務化だけが皆さんの頭に入っている印象を受けているが、この機会を利用し、どういう理由で義務化することにしたのかをぜひ理解していっていただければと思う。
まず、その名前からわかるように、この法津は雇用政策の基本に関する法律で、国の政策の方向性が書かれており、今回、外国人の雇用政策についても、国が講ずるべき施策として明記された。専門的・技術的分野の外国人、いわゆる高度人材については、積極的に受け入れる。そして、合法的に働いている外国人の方々は、よりきちんとした雇用管理のもとで働いてもらうということを第一の目標として届出制度が創設されている。
届出を行うことにより、事業主はその人が本当に入管法上、適法に日本で働くことができるか否か、就労できる在留資格であるかどうかということが確認できる。そして、ハローワークに届け出ると、ハローワークから企業が適切に外国人労働者の雇用管理を行うためのサポートが受けられる。
つまり届出制度は、外国人についてきめ細かで適切な雇用管理をしてもらうための一つの手段であるという位置づけである。また、その外国人が何らかの理由によって離職する場合、再就職の支援も必要になるが、きめ細かく再就職を支援していくためにも、ハローワークに個々に届出をすることが必要であり、トータルに見れば企業における外国人の雇用管理の改善を後押しするための法律であることがわかっていただけるであろう。
危惧される不安定雇用
次に、こういった対応を講ずることになった背景・現状について、少しご説明しておきたい。平成 18( 2006)年6月1日現在の外国人雇用状況報告によると、外国人労働者約 22万人のうち派遣・請負といった、いわゆる間接雇用の類型で働いている労働者が約4分の1いる。これを日系人という観点から見ると、4分の3が派遣・請負で働いている。派遣・請負が良いか悪いかということは一概には言えないが、最近のワーキングプアとか格差といった議論の中で、これらが非常に不安定な雇用形態になりがちだということは否定できないところである。
第二に社会保険の加入状況がある。とくに注目すべきは間接雇用での状況で、未加入が非常に多い。平成 14( 2002)年度の厚生労働省委託研究「外国人労働者に対する雇用管理の実態に関する調査研究報告書」(野村総研、従業員 50人以上規模の企業が調査対象)によれば、従業員のほとんどが日系人というような企業では半数が未加入となっている。また、浜松市が実施したサンプリング調査でも、3分の2くらいの外国人労働者が未加入との結果が出ている。
浜松市というのは外国人集住都市会議に加盟している都市で日系人が非常に多く、こういう人々が定住化、永住化しつつある。しかし、社会保険に未加入だと 65歳になっても年金は1円も出ないということになり、現にこういった地域では生活保護を受けている人も出始めている。やはり、これは行政としてどうだろうかということで、地方自治体から国に対し、国としても何とかしてほしいという要望がこの2,3年出されるようになっている。
また、我々が調査したところでは、製造業の下請け分野で働いている日系人の賃金水準が同職種の日本人に比べて7,8割くらいとの結果も出ている。ある特定の分野・カテゴリーに着眼してみると、かなりこういった傾向が強いのではないかと実は懸念している。
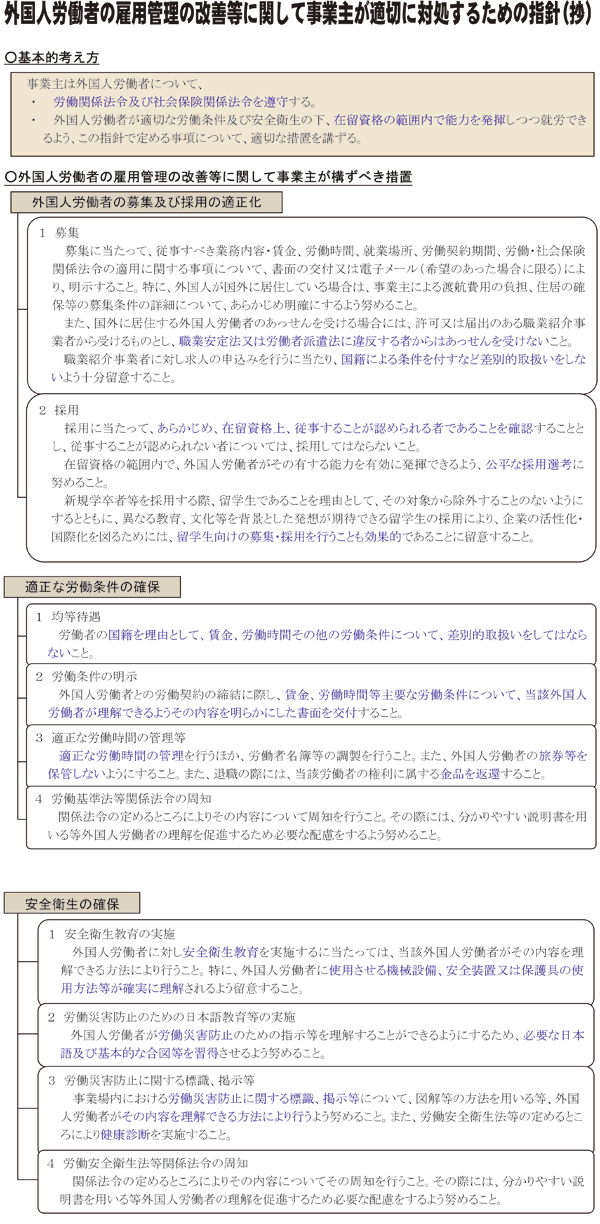
新たな指針も作成
今回の法改正においては、改正雇用対策法に基づき大臣告示として定められた「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(新外国人指針図表)の内容も大きなポイントである。もし労働コストの視点で、この低い労働条件では日本人が来ない、でも外国人なら来てもらえるから雇おうと考えている事業主の方がいたとすれば、ぜひ、この指針をきちんと読んでいただきたい。
もっとも大事なことは、労働条件面での国籍による差別は禁止されているということである。これは労働基準法第三条で罰則つきで担保されている。それから、労働関係法令、社会・労働保険関係法令は国籍を問わず等しく適用されるということである。
当然、外国人が労災に遭えば労災補償がおりるし、失業すれば雇用保険の失業給付が出る。年休や時間外手当についても日本人と同じ扱いを受けなければならない。外国人だと法令に関する知識が日本人のようにあるわけではないので、曖昧になってしまう部分もあるかもしれないが、それは問題であるというのが我々の考えである。
加えて、高度人材の外国人労働者の我が国での就業促進については、行政としても今後ますますその方向で進めていきたいと考えている。我が国企業が国際化の中で生き残っていくためには、そうした外国人の力も必要になってくるのではないか。そのためには、留学生の採用が積極的に行われていい。
「外国人の方も採用します。日本人だけに目を向けているわけではありません。応募さえあれば歓迎です」と言う事業主の方はいくらでもいるが、外国人と日本人を同じ土俵で審査するということは、そもそも外国人の持っている日本人にない部分を過少評価することになる場合もある。留学生向けのアファーマティブ・アクションとまでは言わないが、留学生のハンデになっている部分を考慮してあげつつ、積極的にいい部分を見てあげるような採用の仕方もあるのではないか。そこで新外国人指針では、外国人の能力を発揮しやすい環境の整備もうたっているわけである。
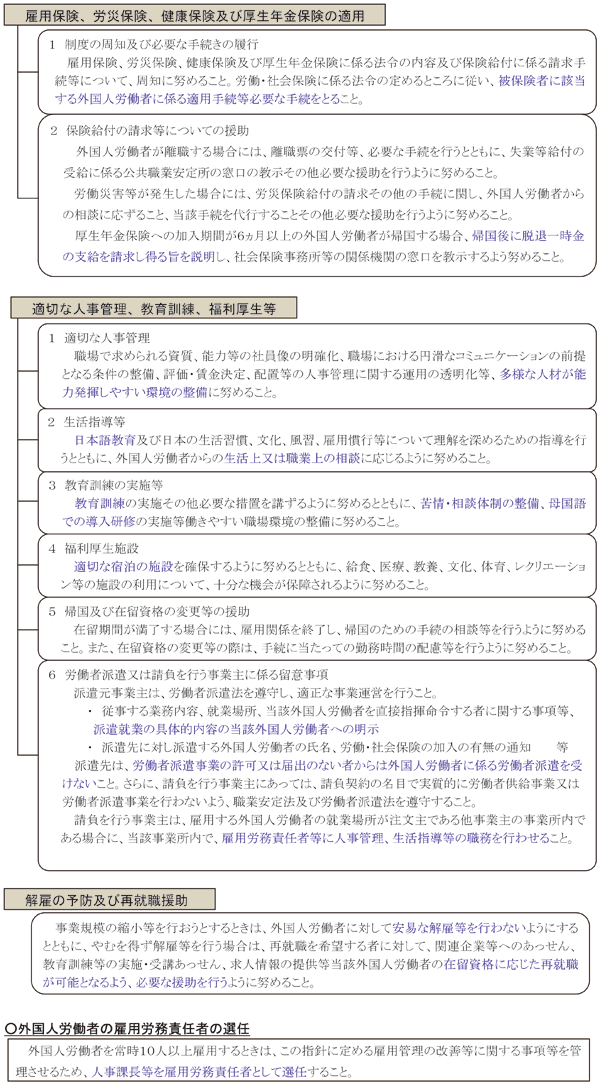
行政のサポート体制
最後に、皆さんが日ごろ外国人の方を労務管理する中で悩みを抱えたり、外国人の方を確保したいという場合のサービスを提供している行政機関を紹介したい。まず一つは、ハローワークの外国人版といってもよいが、「外国人雇用サービスセンター」を東京、大阪、愛知の全国3カ所に置いている。念のため言うと、ここは高度人材のための機関で、高度人材が我が国には必要であり積極的に受け入れるという国の方針に基づいて設置されている。留学生向けの会社説明会なども実施しているので、ぜひ、ご参加いただければと思う。
新外国人指針を通じての指導もハローワークで展開している。同指針に関してご相談などがあれば、ハローワークには外国人専門の担当者を置いているので、ぜひ、お気軽に尋ねていただきたい。またハローワークを束ねている各県の労働局では、外国人専門の雇用管理セミナーも開催している。個々の外国人の雇用管理について、やや専門的な相談をしたい場合には、雇用管理アドバイザーもいるので、ハローワークにぜひ問い合わせていただければと思う。
外国人の雇用管理を前向き・積極的に行っていくことは、外国人の方にとってだけでなく、企業にとっても中長期的には絶対にプラスになる。やや、大所高所に立った話で恐縮だが、そのような観点から、この機会に外国人の雇用ルールを頭に入れて対応していっていただければと思う。


