最近の統計調査結果から2014年5月
統計調査報告
平成25年労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模100人以上)及び総合工事業調査)
規模100人以上の事業所の労働災害の発生状況をみると、度数率(注1)(労働災害発生の頻度)は1.58(前年1.59)、強度率(注2)(労働災害の重さの程度)は0.10(同0.10)、死傷者1人平均の労働損失日数(注3)は63.2日(同63.3日)となった。
(注1)100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。
(注2)1,000延べ実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重さの程度を表す。
(注3)労働災害による死傷者の延べ労働損失日数を死傷者数で除したもの。
労働力調査詳細集計 ―1~3月期平均―
平成26年1~3月期平均の雇用者(役員を除く)(5193万人)のうち、正規の職員・従業員は3223万人で、前年同期に比べ58万人の減少となった。非正規の職員・従業員は1970万人で、前年同期に比べ100万人の増加となった。
非正規の職員・従業員が現職の雇用形態についた主な理由は、男性では「正規の職員・従業員の仕事がないから」とする割合が最も高く(29.0%)、女性では「家計の補助・学費等を得たいから」とする割合が最も高い(26.2%)。
平成26年1~3月期平均の完全失業者(239万人、前年同期に比べ38万人の減少)のうち、失業期間が「1年以上」の者は90万人で、前年同期に比べ19万人の減少となった。
平成25年度・障害者の職業紹介状況等
平成25年度のハローワークを通じた障害者の就職件数は77,883件(対前年度比14.0%増)で、4年連続で過去最高を更新した。障害種別にみると、身体障害者28,307件(同6.5%増)、知的障害者17,649件(同10.1%増)、精神障害者29,404件(同23.2%増)などとなっている。
被保護者調査(注) ―2月分概数―
平成26年2月の生活保護の被保護世帯数は1,598,818世帯、被保護実人員は2,166,381人となった。
(注)生活保護法に基づく保護を受けている世帯及び保護を受けていた世帯の保護の受給状況を把握するための調査である。
国民経済計算 ―平成26年1~3月期・1次速報値―
平成26年1~3月期の実質GDP(国内総生産)の成長率(季節調整済前期比)は1.5%(年率5.9%)となった。
内需、外需別の寄与度は、内需(国内需要)が1.7%、外需(財貨・サービスの純輸出)が-0.3%となった。
図表1:実質GDP成長率と
実質GDP内外需要別寄与度の推移
(平成26年1~3月期次1速報値)
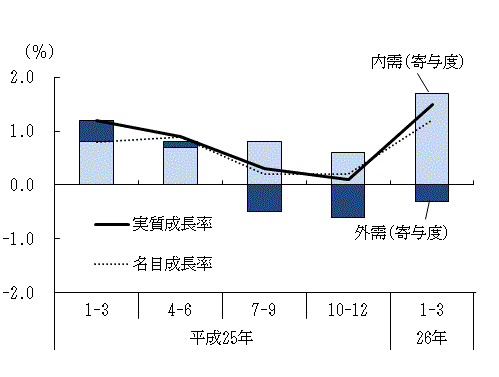
毎月勤労統計調査 ―3月分結果確報・平成25年度分確報―
平成26年3月の現金給与総額は前年同月比0.7%増となった。きまって支給する給与は前年同月比0.2%増(一般労働者0.4%増、パートタイム労働者0.8%増)で、特別に支払われた給与が10.3%増であった。きまって支給する給与の内訳は、所定内給与0.3%減、所定外給与5.8%増である。
実質賃金(総額)は前年同月比1.3%減となった。
製造業の所定外労働時間(季調値)は前月比3.3%増となった。
平成25年度の平均月間現金給与総額は前年度比0.1%増となった。きまって支給する給与は前年度比0.2%減(一般労働者0.3%増、パートタイム労働者0.1%増)で、特別に支払われた給与が1.7%増であった。きまって支給する給与の内訳は、所定内給与は前年度比0.5%減、所定外給与は3.6%増であった。
平成25年度の実質賃金(総額)は前年度比1.0%減となった。
平成25年度の総実労働時間は前年度比0.2%減となった。
平成25年度のパートタイム労働者比率は29.53%で、前年度差0.56ポイントの上昇となった。
平成25年度高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況(平成26年3月末現在)
高校新卒者の就職内定率は98.2%で、前年同期に比べて0.6ポイント上昇となった。
高校新卒者の求人倍率は1.56倍で、前年同期に比べて0.19ポイント上昇となった。
中学新卒者の求人倍率は1.46倍で、前年同期に比べて0.27ポイント上昇となった。
図表2:高校新卒者の就職内定率の推移
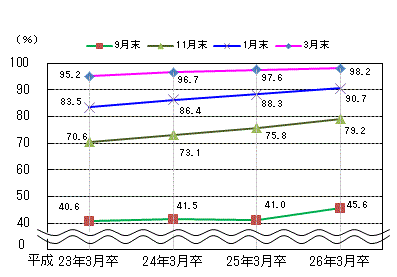
平成25年度大学等卒業者の就職状況調査(平成26年4月1日現在)
大学の就職率は94.4%で、前年同期に比べて0.5ポイント上昇となった。
短期大学(女子学生のみ)の就職率は94.2%で、前年同期に比べて0.5ポイント低下となった。
高等専門学校(男子学生のみ)の就職率は100%で、前年同期と同率となった。
専修学校(専門課程)の就職率は93.0%で、前年同期に比べて1.1ポイント低下となった。
図表3:大学卒業(予定)者の就職(内定)率の推移
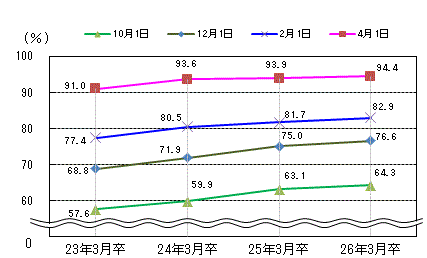
平成25年の労働災害発生状況
平成25年の労働災害による死亡者数は1,030人で、平成24年に比べ63人減少した。
平成25年の労働災害による死傷者数(死亡・休業4日以上)は118,157人で、平成24年に比べ1,419人減少した。
平成25年の重大災害(一度に3人以上の労働者が業務上死傷または病気にかかった災害)は244件で、平成24年に比べ40件減少した。
景気動向指数 ―3月分速報の改訂―
平成26年3月のCI(改訂値・平成22年=100)の一致指数は1.6ポイント上昇の114.5、3ヶ月後方移動平均は0.90ポイントの上昇、7ヶ月後方移動平均は0.86ポイントの上昇となった。一致指数の基調判断は「改善を示している。」(前月とかわらず)となった。なお、先行指数は1.4ポイント下降の107.1、遅行指数は1.4ポイント上昇の118.5となった。
労働力調査(基本集計) ―4月分―
平成26年4月の完全失業率(季調値)は3.6%で、前月と同率となった。男性は3.8%で0.1ポイントの上昇、女性は3.4%で前月と同率となった。
平成26年4月の完全失業者数(季調値)は236万人で、前月と同数となった。
平成26年4月の雇用者数(季調値)は5,559万人で、前月に比べ27万人の減少となった。
一般職業紹介状況 ―4月分―
平成26年4月の有効求人倍率(季調値)は1.08倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇した。
図表4:完全失業率と有効求人倍率の推移(季調値)
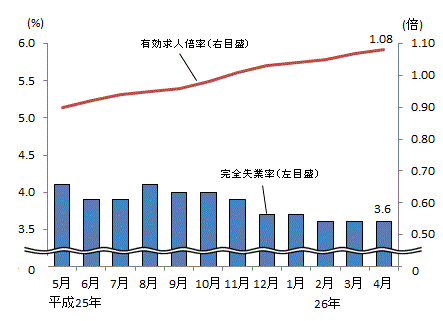
家計調査報告 ―4月分速報―
5月30日(金曜)総務省発表
平成26年4月の二人以上世帯のうち勤労者世帯の実収入は、前年同月比で実質7.1%の減少となった。
うち勤め先収入は、世帯主収入が実質4.9%の減少、配偶者の収入が実質7.3%の減少、他の世帯員収入が実質45.5%の減少となった。
勤労者世帯の消費支出は、前年同月比で実質6.9%の減少となった。
消費者物価指数 ―4月分―
平成26年4月の消費者物価指数(平成22年=100)は、総合指数は103.1となり、前年同月比は3.4%の上昇となった。生鮮食品を除く総合指数は103.0となり、前年同月比は3.2%の上昇となった。
平成26年5月の東京都区部の速報は、総合指数は102.1となり、前年同月比は3.1%の上昇、生鮮食品を除く総合指数は102.0となり、前年同月比は2.8%の上昇となった。
鉱工業生産指数 ―4月分速報―
平成26年4月の鉱工業生産指数(季調値、平成22年=100)は前月比2.5%の低下。製造工業生産予測調査によると、5月上昇の後、6月は低下を予測している。「総じてみれば、生産は横ばい傾向にある。」(前月:持ち直しの動きで推移している)との判断となった。
サービス産業動向調査 ―3月分結果速報―
平成26年3月のサービス産業の月間売上高は35.7兆円、前年同月比5.3%の増加となった。サービス産業の事業従事者数は2842万人で、前年同月比1.0%の増加となった。
平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況
平成25年度の総合労働相談件数は1,050,042件(前年度比1.6%減)、うち民事上の個別労働紛争相談件数は245,783件(同3.5%減)、助言・指導申出件数は10,024件(同3.3%減)、あっせん申請件数は5,712件(同5.5%減)となった。
平成26年企業の賃上げ動向に関するフォローアップ調査(注1)
常用労働者の1人平均賃金の引き上げ状況について、「引き上げる/引き上げた」とする企業の割合は92.2%(平成25年度88.6%)となった。
賃金を引き上げた企業における賃金の引き上げ方法(予定を含む)をみると、定期昇給・賃金構造維持分90.6%(平成25年度93.1%)、ベア(ベースアップ)分46.7%(平成25年度7.7%)、賞与・一時金分41.8%(同38.1%)などとなった。また、ベアを行った企業のうち、ベア分の引上げ額が「1,000円以上」とする割合は80.0%(注2)(同46.5%)となった。
(注1)平成26年の春闘結果等を踏まえた大手企業の賃上げ状況等を把握するために3月に東証一部上場企業1762社を対象として実施された。5月14日までに回答が提出された927社の状況。
(注2)ベア分の引上げ額について回答した企業に占める割合。
毎月勤労統計調査 ―4月分結果速報―
平成26年4月の現金給与総額は前年同月比0.9%増となった。きまって支給する給与は0.2%増(一般労働者0.6%増、パートタイム労働者0.7%増)で、特別に支払われた給与が20.5%増であった。きまって支給する給与の内訳は、所定内給与0.2%減、所定外給与5.1%増である。
実質賃金(総額)は前年同月比3.1%減となった。
製造業の所定外労働時間(季調値)は前月比2.7%減となった。
月例経済報告等
月例経済報告 ―5月―
景気は、緩やかな回復基調が続いているが、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きもみられる。(前月とかわらず)
- 個人消費は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、このところ弱い動きとなっている。(前月とかわらず)
- 設備投資は、増加している。(前月:持ち直している)
- 輸出は、横ばいとなっている。(前月とかわらず)
- 生産は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響もあって、このところ弱含んでいる。(前月:おおむね横ばいとなっている)
- 企業収益は、改善している。企業の業況判断は、このところ慎重となっているが、先行きは改善がみられる。(前月:企業の業況判断は、幅広く改善している。ただし、先行きに慎重な見方となっている。)
- 雇用情勢は、着実に改善している。(前月とかわらず)
- 消費者物価は、緩やかに上昇している。(前月とかわらず)
月例労働経済報告 ―5月―
労働経済面をみると、雇用情勢は、着実に改善している。(前月とかわらず)


