最近の統計調査結果から2008年7月
統計調査報告
平成19年就業構造基本調査
平成19年10月1日現在の15歳以上人口(1億1030万2千人)をふだんの就業状態別にみると、有業者は6597万8千人、無業者は4432万4千人で、平成14年(前回調査)と比べ有業者は96万8千人(1.5%)の増加、無業者は15万9千人(0.4%)の増加となっている。有業者を男女別にみると、男性が3817万5千人、女性が2780万3千人となっている。平成14年と比べると、男性は14万1千人(0.4%)の増加、女性は82万7千人(3.1%)の増加となり、女性の増加が男性を大きく上回っている。
昭和57年10月以降「初職」に就いた者について、初職の雇用形態をみると、非正規就業者として初職に就いた者は年を追うごとに高くなっており、「昭和57年10月~62年9月」では13.5%であったものが、「平成14年10月~19年9月」では43.8%と4割以上を占めている。
景気動向指数 ―5月速報―
5月のCI(速報値・平成17年=100)の一致指数は1.3ポイント上昇し、103.0となったが、3ヶ月後方移動平均は3ヶ月連続でマイナス、7カ月後方移動平均も3ヶ月連続でマイナスとなり、一致指数の基調判断は、「景気はその局面が変化している可能性もあるとみられる」という前月の基調判断を変更する状況にはないとされた。なお、先行指数は92.6で0.2ポイントの下降、遅行指数は103.9で0.2ポイントの上昇となっている。
平成19年団体交渉と労働争議に関する実態調査結果
過去3年間において組合と使用者間で話し合いが持たれた事項別の割合は、「雇用・人事」(81.2%)、「賃金」(78.3%)、「労働時間」(76.3%)などで7割を超えている。
過去3年間において「団体交渉を行った」組合の割合は、69.5%(前回平成14年調査64.6%)となっており、前回調査より4.9ポイント増加している。
過去3年間において「労働争議があった」組合の割合は5.4%(前回6.0%)となっている。
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する特別世論調査
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」の認知度について、「名前も内容も知らない」との回答が60.1%、「名前は聞いたことがあるが、内容までは知らない」が26.6%に上った。
希望する優先度としては、「家庭生活を優先したい」が29.9%、「仕事と家庭生活をともに優先したい」が26.3%などの順となった。
消費者物価指数 ―6月―
消費者物価指数(平成17年=100)は102.2となり、前年同月比で2.0%の上昇、生鮮食品を除く総合指数は102.0となり、前年同月比で1.9%の上昇と、それぞれ9ヶ月連続の上昇となった。
7月の東京都区部は101.5となり、前年同月比で1.6%の上昇、生鮮食品を除く総合指数は101.4となり、前年同月比で1.6%の上昇。
家計調査 ―6月―
7月29日(火曜)総務省発表
二人以上世帯のうち勤労者世帯の実収入は、前年同月比で実質2.1%の減少となり、3ヶ月連続の減少となった。
労働力調査 ―6月―
一般職業紹介状況 ―6月―
平成20年6月の完全失業率(季調値)は4.1%と、前月に比べ0.1ポイントの上昇。男性は4.2%と、前月と同率。女性は4.0%と、前月に比べ0.3ポイントの上昇。
平成20年6月の完全失業者数は265万人と、前年同月差24万人の増加。
平成20年6月の雇用者数(季調値)は、5,528万人と、前月差11万人の増加。
平成20年6月の有効求人倍率(季調値)は0.91倍で、前月を0.01ポイント下回った。
図表1:完全失業率と有効求人倍率の推移
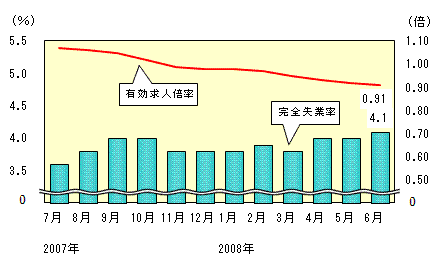
鉱工業生産指数 ―6月速報―
7月30日(水曜)経済産業省発表
鉱工業生産指数(季調値)は前月比2.0%の低下で、製造工業生産予測調査によると、7月、8月とも低下の予測となり、「総じてみれば、生産は弱含みで推移している」との判断となった。
毎月勤労統計調査 ―6月速報―
7月31日(木曜)厚生労働省発表
平成20年6月の現金給与総額(規模5人以上)は前年同月比0.6%減少と減少に転じたが、きまって支給する給与(規模5人以上)は前年同月比0.1%と8ヶ月連続の増加となった。
製造業の所定外労働時間(規模5人以上)の平成20年6月(季調値)は前月比0.8%減少。
日本人の平均余命 ―平成19年簡易生命表―
男の平均寿命は79.19年、女の平均寿命は85.99年と前年と比較して男は0.19年、女は0.18年上回った。
研究会報告等
月例経済報告 ―7月―
景気回復は、足踏み状態にあるが、このところ一部に弱い動きがみられる。(前月とかわらず)
- 輸出、生産は、このところ弱含んでいる。(前月とかわらず)
- 企業収益は、減少している。設備投資は、おおむね横ばいとなっている。(前月とかわらず)
- 個人消費は、おおむね横ばいとなっている。(前月とかわらず)
平成20年版労働経済の分析(労働経済白書)
我が国経済は、2008年に入り景気回復は足踏み。新規学卒者の就職状況は改善しているが、小規模事業所での賃金低下は継続。
1990年代以降、就業形態や賃金制度は大きく変化し、正規以外の従業員が増加するとともに、業績成果主義的賃金制度も拡大。企業の経営環境が厳しかったことから企業の対応は人件費抑制的な視点に傾きがちで、労働者の満足感は長期的に低下。
労働力配置の観点から見た産業構造の高度化の動きは停滞。製造業など高生産分野では人員が削減される一方、サービス業、小売業などでは正規以外の従業員が増加。生産性の低い産業分野に労働力が集中する傾向。
取り組むべき課題として、
- 正規雇用化に向けた支援など働くことを希望する人々に対する雇用機会の確保、
- 高い意欲の発揮と職業能力の開発に向けた適切な雇用管理の実現、
- 高度な産業構造の実現に向けた総合的な取組など、を指摘。
月例労働経済報告 ―7月―
労働経済面をみると、雇用情勢は、厳しさが残るなかで、改善に足踏みがみられる。(前月とかわらず)


