トップページ
分煙効果判定基準策定検討会報告書 平成14年6月
2.分煙対策の評価
1 評価の必要性
先の調査報告でも述べたように、労働省(現厚生労働省)は従前より職場での分煙
対策を進めており、1996年には「職場における喫煙対策のためのガイドライン」
を策定している。また一方、公共の場所においても分煙を実施する施設が徐々に増え
てきているが、その形態は様々であり、形ばかりの分煙対策となっている場合がある
ことも否定できない。これは、これまで科学的な客観的指標による分煙効果を判定す
る基準が示されていなかったのも一因である。
分煙対策は、非喫煙者の受動喫煙による健康影響や不快感の排除、軽減という目的
が達成されて初めて効果的な対策がなされていると判断すべきである。そのためには、
分煙環境をできるだけ適切に、科学的に評価することによって、より効果的な分煙環
境に改善していくことが今後の分煙対策を行っていく上で重要である。
先に述べたように、分煙対策の目的は、受動喫煙による健康影響の防止と同時に、
精神・心理面の問題の改善もある。従って、評価は利用者の精神・心理面の評価及び
室内空気環境の測定による評価の両面が必要である。
また、分煙効果は非喫煙場所の空気環境が汚染されていないことを評価すればその
目的を達しているわけではない。喫煙場所が公共の建物または事業所内であれば、当
然喫煙場所も「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称ビル衛生管理法)」、
「事業所衛生基準規則」の基準を満たした良好な環境に保たれるべきものである。さ
らに言えば、建物から局所排気などによって大気中に排気されたたばこ煙によって周
辺の大気環境を汚染することも好ましくない。
これからの分煙効果の評価は、受動喫煙による健康影響の防止を第一義とするのは
当然であるが、同時に喫煙場所の環境、建物周辺の大気環境も考慮すべきものである。
2 利用者の精神・心理面の評価
分煙対策を行う際には、職場などでは事前に喫煙対策に対するアンケート調査を行
い、その結果に基づいて分煙対策をとった方が協力を得られやすい。一般の公共施設
では、不特定多数の利用者に対するアンケート調査になるので、その実施と分析には
多少の困難を伴うが、喫煙対策に対する利用者の事前の意識を調査しておくことは、
対策後の評価を行う上で重要である。参考資料1(PDF:114KB)に職場で使用される喫
煙対策実施前の調査用紙の一例を示した。公共施設等の状況に応じ、これを参考に質
問票を作成されることが望まれる。
分煙対策を行った場合にはその実施後に、再び利用者の意識調査を行い、喫煙者を
含めた利用者の分煙対策に対する、精神・心理面の満足度を把握することが重要であ
る。参考資料2(PDF:117KB)にその一例を示した。この様な事後評価を定期的に行っ
て、さらに喫煙者、非喫煙者の両者にとってより満足度の高い分煙対策を推進してい
くことが重要である。
3 室内空気環境測定による評価
室内空気環境測定による評価を行うためには、まず室内空気汚染対策の手法の違い
によるそれぞれの特色、評価の指標を何にするか等の知識を得ておくことが必要であ
る。
(1)室内空気汚染対策の原則
分煙対策に限ったことではないが、室内空気汚染物質の除去手段としては、汚染物
質の室内侵入を許さない手段と汚染物質の侵入を許したのちに除去する手段の2つに
大別される。前者は、さらに汚染発生源を除去・隔離する方法と、発生源の性質を変
え無害化する方法の2つに分けられ、後者は、空気清浄機等によって汚染物質を除去
する方法と、換気により室外へ排出する方法の2つに分けられる。
(2)室内空気汚染の4つの対策
(1)発生源を除去する方法
上記4つの方法は、汚染物質に対する働きかけが、列挙した順に積極性が少な
くなるという特徴をもっている。第1番目の方法は、その意味で最も積極的であ
り、この方法が可能な場合もあろうが、通常はかなり困難な対策であると言える。
すなわち、対象とする汚染物質がCO2、VOC(揮発性有機化合物)、臭気な
どの場合、その主要発生源の1つが人及びその活動であることを考えると、十分
な対策はとりえない。たばこ煙の場合には喫煙者の自覚と協力があればある程度
の隔離は可能と思われる。
図1は、オフィスビル室内において喫煙を許している場合と、同じ部屋におい
て喫煙を許さない場合の比較結果を示している。 図より明らかなように、喫煙
を許さない日の粉じん濃度は極めて低く、変動も少ないのに対し、喫煙を許す場
合には、濃度が大きく変動し、ピーク時にはビル衛生管理法の基準(0.15mg/立方
メートル)を大きく超えている。
しかしながら、いつもこの喫煙を許さない方法(施設内の全面禁煙)が使える
わけではない。以下にそれ以外の方法について記述する。
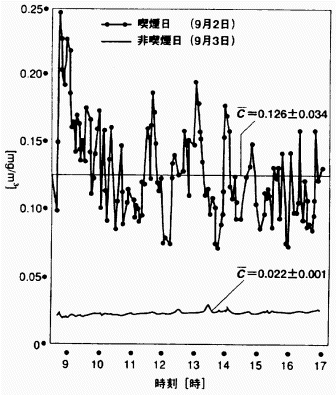 図1 喫煙を禁止することの効果
(2)発生源を無害化する方法
この方法はたばこ煙の場合、余り実用的ではない。
(3)空気清浄機等による汚染物質除去
この方法は、室内に侵入した汚染物質を除去するものである。但し、除去の対
象となる汚染物質が特定されており、さらにその物理化学的挙動特性が十分に知
られていなければならない。従って対象とする汚染物質が単なる浮遊粉じん1種
類の場合のような単純なケースの場合は実用的であると言えるが、VOC(揮発
性有機化合物)、たばこ煙、燃焼排ガス、臭気のように、問題とする汚染物質が
気体やエアロゾルなど様々な化学物質からなる場合には、必ずしも全ての原因物
質を除去できないという欠点を抱えている。また、空気清浄機等の維持管理が不
十分だと、浄化装置の汚染保持容量を越える汚染物質を処理する結果となり、浄
化装置からの汚染の再発生という事態も生ずる。さらに、保持容量を越える処理
をしていなくとも、管理が悪ければ、捉えた汚染物質を保持している部分に微生
物が繁殖する、化学反応を起こすなどして、別な形の汚染を起こす恐れも考えら
れる。また、浮遊した粉じんであっても空気清浄機の中に入らない限り、除去さ
れることはないのが事実であり、この方法にあまり過大な期待はできない。さら
に、使用者によっては、空気清浄機があることにより、精神的な安定を得るとい
った側面も認められないとは言えないが、逆に、空気清浄機に頼りすぎ、換気や
掃除、蒲団の管理など基本的な室内環境整備のための対策を怠るようになるとし
たら問題であるため、この点からも、注意が必要である。
図1 喫煙を禁止することの効果
(2)発生源を無害化する方法
この方法はたばこ煙の場合、余り実用的ではない。
(3)空気清浄機等による汚染物質除去
この方法は、室内に侵入した汚染物質を除去するものである。但し、除去の対
象となる汚染物質が特定されており、さらにその物理化学的挙動特性が十分に知
られていなければならない。従って対象とする汚染物質が単なる浮遊粉じん1種
類の場合のような単純なケースの場合は実用的であると言えるが、VOC(揮発
性有機化合物)、たばこ煙、燃焼排ガス、臭気のように、問題とする汚染物質が
気体やエアロゾルなど様々な化学物質からなる場合には、必ずしも全ての原因物
質を除去できないという欠点を抱えている。また、空気清浄機等の維持管理が不
十分だと、浄化装置の汚染保持容量を越える汚染物質を処理する結果となり、浄
化装置からの汚染の再発生という事態も生ずる。さらに、保持容量を越える処理
をしていなくとも、管理が悪ければ、捉えた汚染物質を保持している部分に微生
物が繁殖する、化学反応を起こすなどして、別な形の汚染を起こす恐れも考えら
れる。また、浮遊した粉じんであっても空気清浄機の中に入らない限り、除去さ
れることはないのが事実であり、この方法にあまり過大な期待はできない。さら
に、使用者によっては、空気清浄機があることにより、精神的な安定を得るとい
った側面も認められないとは言えないが、逆に、空気清浄機に頼りすぎ、換気や
掃除、蒲団の管理など基本的な室内環境整備のための対策を怠るようになるとし
たら問題であるため、この点からも、注意が必要である。
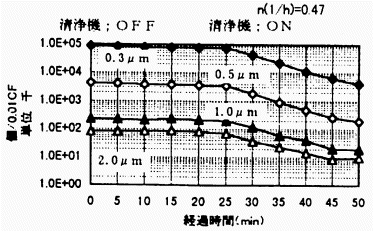 図2 空気清浄機の粉じん除去性能
図2には、空気清浄機運転状況と室内の粉じん濃度の変化を示した。図より、
空気清浄機運転前でも、粉じんは壁などへの吸着や沈降などにより少しずつ濃度
が減少するが、空気清浄機が運転され始めるとその減衰曲線の傾きが急になるこ
とより粉じん除去が有効に行われることがわかる。
図2 空気清浄機の粉じん除去性能
図2には、空気清浄機運転状況と室内の粉じん濃度の変化を示した。図より、
空気清浄機運転前でも、粉じんは壁などへの吸着や沈降などにより少しずつ濃度
が減少するが、空気清浄機が運転され始めるとその減衰曲線の傾きが急になるこ
とより粉じん除去が有効に行われることがわかる。
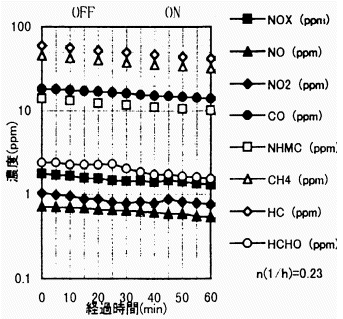 図3 実験的に発生させたガス状物質に対する空気清浄機の効果
一方、図3は、同じ空気清浄機でもガス状物質に対して用いられたときの測定
結果である。この場合は、空気清浄機の運転の如何にかかわらず、各ガス状物質
の濃度は、壁等への吸着によるわずかな減衰を示すのみである。
以上より、空気清浄機をたばこ煙処理に適用したとしても、たばこ煙の粒子状
成分しか除去できないことになり、ガス状物質は未処理のまま空気中に再放出さ
されることになる。なお、最近は、活性炭、光触媒、ゼオライト、ホタテ貝の貝
殻、お茶の葉などが、ホルムアルデヒド等の一部の化学物質の除去に効果がある
と言われるようになってきているが、実験室の小さなチャンバー内などではある
程度の効果が認められても、実空間で即効的な有効性が証明されたケースは殆ど
ないと言って良い。
従って、いわゆる「分煙機」なるものには、単なる空気清浄機しか備えていな
いものが多いが、このような分煙機により処理された空間が「喫煙室」とされて
いることには、多大の問題があると言える。
(4)換気による方法
最後に、換気による室内空気中の汚染物質除去は、最も消極的な方法ではある
が、汚染物質がガス状物質であろうと粒子状物質であろうと、また、それらの汚
染物質の挙動等がそれほどよく分かっていなくとも、さらには除去しなければな
らない汚染物質が何種類あろうとも確実に全ての汚染物質を室外へ排除できると
いう長所を持っている。特に、たばこ煙、VOC(揮発性有機化合物)、燃焼排
ガス、臭気のような複雑な特性を持った汚染物質の除去法としては、最も費用が
かからず、また実用性の高い方法と言える。ただし、この方法は換気される外気
の汚染物質の濃度が、室内空気中にある汚染物質の濃度より低いことが前提とな
っている。
図3 実験的に発生させたガス状物質に対する空気清浄機の効果
一方、図3は、同じ空気清浄機でもガス状物質に対して用いられたときの測定
結果である。この場合は、空気清浄機の運転の如何にかかわらず、各ガス状物質
の濃度は、壁等への吸着によるわずかな減衰を示すのみである。
以上より、空気清浄機をたばこ煙処理に適用したとしても、たばこ煙の粒子状
成分しか除去できないことになり、ガス状物質は未処理のまま空気中に再放出さ
されることになる。なお、最近は、活性炭、光触媒、ゼオライト、ホタテ貝の貝
殻、お茶の葉などが、ホルムアルデヒド等の一部の化学物質の除去に効果がある
と言われるようになってきているが、実験室の小さなチャンバー内などではある
程度の効果が認められても、実空間で即効的な有効性が証明されたケースは殆ど
ないと言って良い。
従って、いわゆる「分煙機」なるものには、単なる空気清浄機しか備えていな
いものが多いが、このような分煙機により処理された空間が「喫煙室」とされて
いることには、多大の問題があると言える。
(4)換気による方法
最後に、換気による室内空気中の汚染物質除去は、最も消極的な方法ではある
が、汚染物質がガス状物質であろうと粒子状物質であろうと、また、それらの汚
染物質の挙動等がそれほどよく分かっていなくとも、さらには除去しなければな
らない汚染物質が何種類あろうとも確実に全ての汚染物質を室外へ排除できると
いう長所を持っている。特に、たばこ煙、VOC(揮発性有機化合物)、燃焼排
ガス、臭気のような複雑な特性を持った汚染物質の除去法としては、最も費用が
かからず、また実用性の高い方法と言える。ただし、この方法は換気される外気
の汚染物質の濃度が、室内空気中にある汚染物質の濃度より低いことが前提とな
っている。
 図4 換気の効果
図4は、窓を締め切ると、換気率が0.07回/時となる極めて気密性が高い建物
内部における、壁から発生してくるラドンガス濃度の経時変動を示したものであ
る。ほとんど換気(空気の入れ替わり)がない状況であるため、ラドンガス濃度
は上がり続け、2日半後には、飽和状態に達する。しかしながら、そのような状
況で、窓を開けると濃度は直ちに0に近い状況まで下がることがわかる。すなわ
ち、換気の効果は絶大であるといえる。
これまで述べてきた換気は、「希釈換気」と呼ばれるもので、室内に発生した
たばこ煙のような汚染物質は、室内に拡散することを前提にしているものである。
一方、汚染物質が拡散する前に換気フードのようなもので補足し室外に排気して
しまえば、少ない換気量で効果的に室内空気を清浄に保つことができるので、き
わめて有効な方法である。このような換気方法を「局所換気」と呼び、最も典型
的な例が、厨房の換気である。厨房のように、汚染の発生源が、定まったところ
に固定されているときは効果的である。発生源が定まらなかったり、時には移動
したりするたばこ煙の場合には、適用しにくい方法とも考えられるが、逆に考え
れば、たばこ煙という移動発生源を、フードの下に位置させることができれば極
めて好都合ともいえるため、今後の分煙対策の一つとして、考えられる方法であ
る。
(5)まとめ
室内空気汚染物質の除去手段としては、以下の4つに分けられる。
ア)汚染発生源を除去、隔離する方法
イ)発生源の性質を変え、無害化する方法
ウ)空気清浄機等によって汚染物質を除去する方法
エ)換気による方法
ア)は、最も根本的で理想的は方法であるが、いつでも適用可能とは限らない。
イ)の方法は、たばこ煙汚染除去には適用できない。
ウ)の方法は、たばこ煙中の粒子状物質の除去には効果があるが、ガス状物質
については有効な除去はなされていない。なお、最近、活性炭や光触媒等を利用
した一部のガス状物質を除去できるタイプの空気清浄機が出回ってきているが、
その効果は未だ不十分である。
エ)の方法は、最も消極的に見える方法であるが、あらゆる場合に適用可能な
実用性の高い方法である。局所換気システムと組み合わせると特に効果的である。
(3)評価のための測定項目の選定
分煙対策が効果的に行なわれているかどうかを判断するためには、喫煙場所や非喫
煙場所の室内空気環境中の喫煙由来物質の濃度を測定することにより定量的な評価を
行うことが必要である。
そのためには、測定対象項目を選定する必要がある。前述したようにたばこ煙中に
は多くの化学物質が存在するが、ここで言う測定対象項目は、あくまで分煙対策の評
価を行うための適切な指標となるもので直接的に生体に悪影響を及ぼす物質の測定を
行うものではない。
測定対象項目を選定するに当たって、米国の国立科学アカデミー(NAS,national
academy of sciences,1990)により示されている環境たばこ煙(ETS, Environment
Tobacco Smoke)の暴露評価のマーカーの満足すべき要件が参考となる。以下に、環
境たばこ煙(以下ETSと略)の暴露評価のマーカーの満足すべき要件の4項目を示した。
I.ETSに特異的であること(たばこ以外に当該化学物質の発生源がない)
II.喫煙率が低くても室内で容易に検知できること
(発生濃度が低くても検出できる)
III.発生割合が、たばこの種類(銘柄)に大きく依存しないこと
(多くの銘柄からほぼ同じ割合で発生する)
IV.ほかのETS構成物質と一定の割合にあること
(他の化学物質濃度がある程度推測できる)
また、既存の文献から室内環境濃度へのETSの寄与率(当該物質の喫煙場所の空気中
濃度に対するたばこ煙から発生した当該物質の割合)を表14にまとめた。ニコチンは
100%がETS由来であり、特異性の点で非常に有効なマーカーである。その次が吸
入性浮遊粉塵(RSP)で寄与率は50%であるが測定・分析が比較的容易であるためマー
カーとしての価値もある。その他の化学物質は寄与率が低く、他の要因による寄与が
あり、特異性に欠けるためマーカーとしてはあまり有効ではないと考えられる。
表14 室内環境濃度へのETSからの寄与率(1)
図4 換気の効果
図4は、窓を締め切ると、換気率が0.07回/時となる極めて気密性が高い建物
内部における、壁から発生してくるラドンガス濃度の経時変動を示したものであ
る。ほとんど換気(空気の入れ替わり)がない状況であるため、ラドンガス濃度
は上がり続け、2日半後には、飽和状態に達する。しかしながら、そのような状
況で、窓を開けると濃度は直ちに0に近い状況まで下がることがわかる。すなわ
ち、換気の効果は絶大であるといえる。
これまで述べてきた換気は、「希釈換気」と呼ばれるもので、室内に発生した
たばこ煙のような汚染物質は、室内に拡散することを前提にしているものである。
一方、汚染物質が拡散する前に換気フードのようなもので補足し室外に排気して
しまえば、少ない換気量で効果的に室内空気を清浄に保つことができるので、き
わめて有効な方法である。このような換気方法を「局所換気」と呼び、最も典型
的な例が、厨房の換気である。厨房のように、汚染の発生源が、定まったところ
に固定されているときは効果的である。発生源が定まらなかったり、時には移動
したりするたばこ煙の場合には、適用しにくい方法とも考えられるが、逆に考え
れば、たばこ煙という移動発生源を、フードの下に位置させることができれば極
めて好都合ともいえるため、今後の分煙対策の一つとして、考えられる方法であ
る。
(5)まとめ
室内空気汚染物質の除去手段としては、以下の4つに分けられる。
ア)汚染発生源を除去、隔離する方法
イ)発生源の性質を変え、無害化する方法
ウ)空気清浄機等によって汚染物質を除去する方法
エ)換気による方法
ア)は、最も根本的で理想的は方法であるが、いつでも適用可能とは限らない。
イ)の方法は、たばこ煙汚染除去には適用できない。
ウ)の方法は、たばこ煙中の粒子状物質の除去には効果があるが、ガス状物質
については有効な除去はなされていない。なお、最近、活性炭や光触媒等を利用
した一部のガス状物質を除去できるタイプの空気清浄機が出回ってきているが、
その効果は未だ不十分である。
エ)の方法は、最も消極的に見える方法であるが、あらゆる場合に適用可能な
実用性の高い方法である。局所換気システムと組み合わせると特に効果的である。
(3)評価のための測定項目の選定
分煙対策が効果的に行なわれているかどうかを判断するためには、喫煙場所や非喫
煙場所の室内空気環境中の喫煙由来物質の濃度を測定することにより定量的な評価を
行うことが必要である。
そのためには、測定対象項目を選定する必要がある。前述したようにたばこ煙中に
は多くの化学物質が存在するが、ここで言う測定対象項目は、あくまで分煙対策の評
価を行うための適切な指標となるもので直接的に生体に悪影響を及ぼす物質の測定を
行うものではない。
測定対象項目を選定するに当たって、米国の国立科学アカデミー(NAS,national
academy of sciences,1990)により示されている環境たばこ煙(ETS, Environment
Tobacco Smoke)の暴露評価のマーカーの満足すべき要件が参考となる。以下に、環
境たばこ煙(以下ETSと略)の暴露評価のマーカーの満足すべき要件の4項目を示した。
I.ETSに特異的であること(たばこ以外に当該化学物質の発生源がない)
II.喫煙率が低くても室内で容易に検知できること
(発生濃度が低くても検出できる)
III.発生割合が、たばこの種類(銘柄)に大きく依存しないこと
(多くの銘柄からほぼ同じ割合で発生する)
IV.ほかのETS構成物質と一定の割合にあること
(他の化学物質濃度がある程度推測できる)
また、既存の文献から室内環境濃度へのETSの寄与率(当該物質の喫煙場所の空気中
濃度に対するたばこ煙から発生した当該物質の割合)を表14にまとめた。ニコチンは
100%がETS由来であり、特異性の点で非常に有効なマーカーである。その次が吸
入性浮遊粉塵(RSP)で寄与率は50%であるが測定・分析が比較的容易であるためマー
カーとしての価値もある。その他の化学物質は寄与率が低く、他の要因による寄与が
あり、特異性に欠けるためマーカーとしてはあまり有効ではないと考えられる。
表14 室内環境濃度へのETSからの寄与率(1)
| 一酸化炭素 |
15% |
| アンモニア |
3% |
| ホルムアルデヒド |
5% |
| オゾン |
0% |
| 窒素酸化物 |
12% |
| 吸入性浮遊粉塵(RSP) |
50% |
| メタン系炭化水素 |
5% |
| 塩素化炭化水素 |
0% |
| ベンゼン |
35% |
| 二酸化硫黄 |
20% |
| ニコチン |
100% |
| ベンツピレン |
5% |
| 微生物、細菌等 |
0% |
吸入性浮遊粉塵(RSP)の寄与率は50%であるが、さらにその寄与率を高めるために
たばこ煙中のタール成分などの不揮発成分に注目をして、吸入性浮遊粉塵(RSP)を適
当な溶媒に抽出した後、その紫外波長分析成分や蛍光分析成分などの値を測定項目と
したUV-PM(ultraviolet particulate matter)、F-PM(fluorescent particulate
matter)、Sol-PM(solanesol particulate matter)がマーカーとして注目されてい
る。
ニコチンは空気中でガス状と粒子状で存在し、ガス状のニコチンは、発生直後から
壁などへの吸着による減衰が激しいためマーカーの要件IVを満たさないが、比較的発
生直後であれば良いマーカーとなる。
その他、CO、CO2、VOCについてはETSのマーカーとして良好であるという報告はほ
とんど見られなかった。
文献のレビューを行った結果、環境たばこ煙(ETS)の分煙効果を評価するための
測定項目として挙げられたものを表15にまとめた。
このうち、特異性という点からはニコチン濃度、RSP濃度(吸入性浮遊粉じん)、
UV-PM濃度(RSPの紫外波長分析成分)、F-PM濃度(RSPの蛍光波長分析成分)、Sol-PM
濃度(RSPの紫外波長分析成分)の他、3−EP(3−Etenylpyridine)濃度が有効と
考えられる。
表15 環境たばこ煙(ETS)評価のための測定項目等の文献レビューのまとめ
( 3)〜10))文献番号
| |
測定項目 |
測定方法 |
分析方法 |
備考 |
海
外 |
RSP |
ろ過捕集 |
重量分析 |
|
| ニコチン |
固体捕集 |
ガスクロマトグラフ(NPD検出器) |
|
| 一酸化炭素 |
CO測定器 |
直読 |
|
| 二酸化炭素 |
CO2測定器 |
直読 |
|
| UV-PM |
ろ過捕集 |
液体クロマトグラフ(UV検出器) |
RSP試料利用 |
| F-PM |
ろ過捕集 |
液体クロマトグラフ(蛍光検出器) |
RSP試料利用 |
| Sol-PM |
ろ過捕集 |
液体クロマトグラフ(UV検出器) |
RSP試料利用 |
| 3-EP |
固体捕集 |
ガスクロマトグラフ |
文献が少ない |
国
内 |
RSP |
粉塵計 |
直読/換算値 |
|
| 一酸化炭素 |
検知管 |
直読 |
|
なお、RSP濃度は、ETS以外の粉じんの影響も受けるため他の測定項目との相関が必
ずしも良くないが、化学的な処理等がされない単純な量(ろ過捕集―重量分析)であ
るため一つの比較値としての意味から測定項目とすべきであろう。
さらに、3−EP濃度は、文献が少ないが、他の測定項目との相関がよいとされてい
るため測定項目として有効と思われるが、今後の検討が必要である。
また、測定・分析の点からはUV-PM濃度、F-PM濃度、Sol-PM濃度、3-EP濃度につい
ては、特殊な測定器具や液体クロマトグラムなど高価な分析装置の他、専門的な技術
も必要になるため容易に行うことはできない。またニコチンは、発生直後から急速に
環境中濃度が減衰すること、分析にガスクロマトグラムを用いることから、評価のマ
ーカーとして利用するには難点が残る。一方、測定・分析の簡便さの点では既に事務
所内の粉じん濃度を測定するために使用されている光散乱方式を用いた粉塵計による
RSP濃度の測定が有効な方法である。
全く開放された屋外の公共の場における測定による評価に関する文献は見られなか
った。
参考文献
0) 池田耕一:「室内空気汚染の現状と対策」日刊工業新聞社刊、1998
1) L.C.Holcomb, J.F.Pedelty: The impact of ventilation on indoor air
quality; Environmental tobacco smoke as a point source, proceeding of the
annual meeting, air & waste management association, 84th. vol.3, 1-19,
1991
2) 労働省安全衛生部環境改善室監修:職場における喫煙対策Q&A、中央労働災害
防止協会、p35、1998
TOP
トップページ
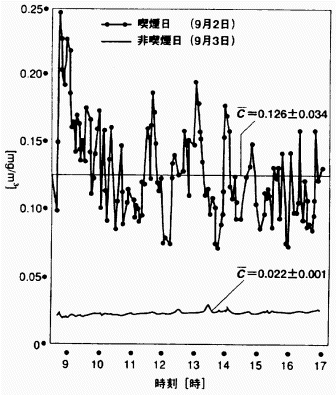 図1 喫煙を禁止することの効果
(2)発生源を無害化する方法
この方法はたばこ煙の場合、余り実用的ではない。
(3)空気清浄機等による汚染物質除去
この方法は、室内に侵入した汚染物質を除去するものである。但し、除去の対
象となる汚染物質が特定されており、さらにその物理化学的挙動特性が十分に知
られていなければならない。従って対象とする汚染物質が単なる浮遊粉じん1種
類の場合のような単純なケースの場合は実用的であると言えるが、VOC(揮発
性有機化合物)、たばこ煙、燃焼排ガス、臭気のように、問題とする汚染物質が
気体やエアロゾルなど様々な化学物質からなる場合には、必ずしも全ての原因物
質を除去できないという欠点を抱えている。また、空気清浄機等の維持管理が不
十分だと、浄化装置の汚染保持容量を越える汚染物質を処理する結果となり、浄
化装置からの汚染の再発生という事態も生ずる。さらに、保持容量を越える処理
をしていなくとも、管理が悪ければ、捉えた汚染物質を保持している部分に微生
物が繁殖する、化学反応を起こすなどして、別な形の汚染を起こす恐れも考えら
れる。また、浮遊した粉じんであっても空気清浄機の中に入らない限り、除去さ
れることはないのが事実であり、この方法にあまり過大な期待はできない。さら
に、使用者によっては、空気清浄機があることにより、精神的な安定を得るとい
った側面も認められないとは言えないが、逆に、空気清浄機に頼りすぎ、換気や
掃除、蒲団の管理など基本的な室内環境整備のための対策を怠るようになるとし
たら問題であるため、この点からも、注意が必要である。
図1 喫煙を禁止することの効果
(2)発生源を無害化する方法
この方法はたばこ煙の場合、余り実用的ではない。
(3)空気清浄機等による汚染物質除去
この方法は、室内に侵入した汚染物質を除去するものである。但し、除去の対
象となる汚染物質が特定されており、さらにその物理化学的挙動特性が十分に知
られていなければならない。従って対象とする汚染物質が単なる浮遊粉じん1種
類の場合のような単純なケースの場合は実用的であると言えるが、VOC(揮発
性有機化合物)、たばこ煙、燃焼排ガス、臭気のように、問題とする汚染物質が
気体やエアロゾルなど様々な化学物質からなる場合には、必ずしも全ての原因物
質を除去できないという欠点を抱えている。また、空気清浄機等の維持管理が不
十分だと、浄化装置の汚染保持容量を越える汚染物質を処理する結果となり、浄
化装置からの汚染の再発生という事態も生ずる。さらに、保持容量を越える処理
をしていなくとも、管理が悪ければ、捉えた汚染物質を保持している部分に微生
物が繁殖する、化学反応を起こすなどして、別な形の汚染を起こす恐れも考えら
れる。また、浮遊した粉じんであっても空気清浄機の中に入らない限り、除去さ
れることはないのが事実であり、この方法にあまり過大な期待はできない。さら
に、使用者によっては、空気清浄機があることにより、精神的な安定を得るとい
った側面も認められないとは言えないが、逆に、空気清浄機に頼りすぎ、換気や
掃除、蒲団の管理など基本的な室内環境整備のための対策を怠るようになるとし
たら問題であるため、この点からも、注意が必要である。
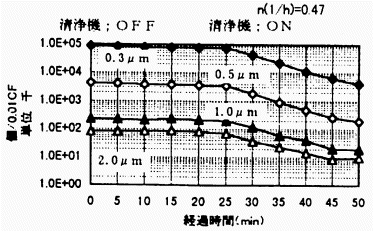 図2 空気清浄機の粉じん除去性能
図2には、空気清浄機運転状況と室内の粉じん濃度の変化を示した。図より、
空気清浄機運転前でも、粉じんは壁などへの吸着や沈降などにより少しずつ濃度
が減少するが、空気清浄機が運転され始めるとその減衰曲線の傾きが急になるこ
とより粉じん除去が有効に行われることがわかる。
図2 空気清浄機の粉じん除去性能
図2には、空気清浄機運転状況と室内の粉じん濃度の変化を示した。図より、
空気清浄機運転前でも、粉じんは壁などへの吸着や沈降などにより少しずつ濃度
が減少するが、空気清浄機が運転され始めるとその減衰曲線の傾きが急になるこ
とより粉じん除去が有効に行われることがわかる。
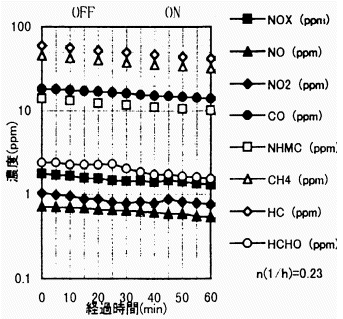 図3 実験的に発生させたガス状物質に対する空気清浄機の効果
一方、図3は、同じ空気清浄機でもガス状物質に対して用いられたときの測定
結果である。この場合は、空気清浄機の運転の如何にかかわらず、各ガス状物質
の濃度は、壁等への吸着によるわずかな減衰を示すのみである。
以上より、空気清浄機をたばこ煙処理に適用したとしても、たばこ煙の粒子状
成分しか除去できないことになり、ガス状物質は未処理のまま空気中に再放出さ
されることになる。なお、最近は、活性炭、光触媒、ゼオライト、ホタテ貝の貝
殻、お茶の葉などが、ホルムアルデヒド等の一部の化学物質の除去に効果がある
と言われるようになってきているが、実験室の小さなチャンバー内などではある
程度の効果が認められても、実空間で即効的な有効性が証明されたケースは殆ど
ないと言って良い。
従って、いわゆる「分煙機」なるものには、単なる空気清浄機しか備えていな
いものが多いが、このような分煙機により処理された空間が「喫煙室」とされて
いることには、多大の問題があると言える。
(4)換気による方法
最後に、換気による室内空気中の汚染物質除去は、最も消極的な方法ではある
が、汚染物質がガス状物質であろうと粒子状物質であろうと、また、それらの汚
染物質の挙動等がそれほどよく分かっていなくとも、さらには除去しなければな
らない汚染物質が何種類あろうとも確実に全ての汚染物質を室外へ排除できると
いう長所を持っている。特に、たばこ煙、VOC(揮発性有機化合物)、燃焼排
ガス、臭気のような複雑な特性を持った汚染物質の除去法としては、最も費用が
かからず、また実用性の高い方法と言える。ただし、この方法は換気される外気
の汚染物質の濃度が、室内空気中にある汚染物質の濃度より低いことが前提とな
っている。
図3 実験的に発生させたガス状物質に対する空気清浄機の効果
一方、図3は、同じ空気清浄機でもガス状物質に対して用いられたときの測定
結果である。この場合は、空気清浄機の運転の如何にかかわらず、各ガス状物質
の濃度は、壁等への吸着によるわずかな減衰を示すのみである。
以上より、空気清浄機をたばこ煙処理に適用したとしても、たばこ煙の粒子状
成分しか除去できないことになり、ガス状物質は未処理のまま空気中に再放出さ
されることになる。なお、最近は、活性炭、光触媒、ゼオライト、ホタテ貝の貝
殻、お茶の葉などが、ホルムアルデヒド等の一部の化学物質の除去に効果がある
と言われるようになってきているが、実験室の小さなチャンバー内などではある
程度の効果が認められても、実空間で即効的な有効性が証明されたケースは殆ど
ないと言って良い。
従って、いわゆる「分煙機」なるものには、単なる空気清浄機しか備えていな
いものが多いが、このような分煙機により処理された空間が「喫煙室」とされて
いることには、多大の問題があると言える。
(4)換気による方法
最後に、換気による室内空気中の汚染物質除去は、最も消極的な方法ではある
が、汚染物質がガス状物質であろうと粒子状物質であろうと、また、それらの汚
染物質の挙動等がそれほどよく分かっていなくとも、さらには除去しなければな
らない汚染物質が何種類あろうとも確実に全ての汚染物質を室外へ排除できると
いう長所を持っている。特に、たばこ煙、VOC(揮発性有機化合物)、燃焼排
ガス、臭気のような複雑な特性を持った汚染物質の除去法としては、最も費用が
かからず、また実用性の高い方法と言える。ただし、この方法は換気される外気
の汚染物質の濃度が、室内空気中にある汚染物質の濃度より低いことが前提とな
っている。
 図4 換気の効果
図4は、窓を締め切ると、換気率が0.07回/時となる極めて気密性が高い建物
内部における、壁から発生してくるラドンガス濃度の経時変動を示したものであ
る。ほとんど換気(空気の入れ替わり)がない状況であるため、ラドンガス濃度
は上がり続け、2日半後には、飽和状態に達する。しかしながら、そのような状
況で、窓を開けると濃度は直ちに0に近い状況まで下がることがわかる。すなわ
ち、換気の効果は絶大であるといえる。
これまで述べてきた換気は、「希釈換気」と呼ばれるもので、室内に発生した
たばこ煙のような汚染物質は、室内に拡散することを前提にしているものである。
一方、汚染物質が拡散する前に換気フードのようなもので補足し室外に排気して
しまえば、少ない換気量で効果的に室内空気を清浄に保つことができるので、き
わめて有効な方法である。このような換気方法を「局所換気」と呼び、最も典型
的な例が、厨房の換気である。厨房のように、汚染の発生源が、定まったところ
に固定されているときは効果的である。発生源が定まらなかったり、時には移動
したりするたばこ煙の場合には、適用しにくい方法とも考えられるが、逆に考え
れば、たばこ煙という移動発生源を、フードの下に位置させることができれば極
めて好都合ともいえるため、今後の分煙対策の一つとして、考えられる方法であ
る。
(5)まとめ
室内空気汚染物質の除去手段としては、以下の4つに分けられる。
ア)汚染発生源を除去、隔離する方法
イ)発生源の性質を変え、無害化する方法
ウ)空気清浄機等によって汚染物質を除去する方法
エ)換気による方法
ア)は、最も根本的で理想的は方法であるが、いつでも適用可能とは限らない。
イ)の方法は、たばこ煙汚染除去には適用できない。
ウ)の方法は、たばこ煙中の粒子状物質の除去には効果があるが、ガス状物質
については有効な除去はなされていない。なお、最近、活性炭や光触媒等を利用
した一部のガス状物質を除去できるタイプの空気清浄機が出回ってきているが、
その効果は未だ不十分である。
エ)の方法は、最も消極的に見える方法であるが、あらゆる場合に適用可能な
実用性の高い方法である。局所換気システムと組み合わせると特に効果的である。
(3)評価のための測定項目の選定
分煙対策が効果的に行なわれているかどうかを判断するためには、喫煙場所や非喫
煙場所の室内空気環境中の喫煙由来物質の濃度を測定することにより定量的な評価を
行うことが必要である。
そのためには、測定対象項目を選定する必要がある。前述したようにたばこ煙中に
は多くの化学物質が存在するが、ここで言う測定対象項目は、あくまで分煙対策の評
価を行うための適切な指標となるもので直接的に生体に悪影響を及ぼす物質の測定を
行うものではない。
測定対象項目を選定するに当たって、米国の国立科学アカデミー(NAS,national
academy of sciences,1990)により示されている環境たばこ煙(ETS, Environment
Tobacco Smoke)の暴露評価のマーカーの満足すべき要件が参考となる。以下に、環
境たばこ煙(以下ETSと略)の暴露評価のマーカーの満足すべき要件の4項目を示した。
I.ETSに特異的であること(たばこ以外に当該化学物質の発生源がない)
II.喫煙率が低くても室内で容易に検知できること
(発生濃度が低くても検出できる)
III.発生割合が、たばこの種類(銘柄)に大きく依存しないこと
(多くの銘柄からほぼ同じ割合で発生する)
IV.ほかのETS構成物質と一定の割合にあること
(他の化学物質濃度がある程度推測できる)
また、既存の文献から室内環境濃度へのETSの寄与率(当該物質の喫煙場所の空気中
濃度に対するたばこ煙から発生した当該物質の割合)を表14にまとめた。ニコチンは
100%がETS由来であり、特異性の点で非常に有効なマーカーである。その次が吸
入性浮遊粉塵(RSP)で寄与率は50%であるが測定・分析が比較的容易であるためマー
カーとしての価値もある。その他の化学物質は寄与率が低く、他の要因による寄与が
あり、特異性に欠けるためマーカーとしてはあまり有効ではないと考えられる。
表14 室内環境濃度へのETSからの寄与率(1)
図4 換気の効果
図4は、窓を締め切ると、換気率が0.07回/時となる極めて気密性が高い建物
内部における、壁から発生してくるラドンガス濃度の経時変動を示したものであ
る。ほとんど換気(空気の入れ替わり)がない状況であるため、ラドンガス濃度
は上がり続け、2日半後には、飽和状態に達する。しかしながら、そのような状
況で、窓を開けると濃度は直ちに0に近い状況まで下がることがわかる。すなわ
ち、換気の効果は絶大であるといえる。
これまで述べてきた換気は、「希釈換気」と呼ばれるもので、室内に発生した
たばこ煙のような汚染物質は、室内に拡散することを前提にしているものである。
一方、汚染物質が拡散する前に換気フードのようなもので補足し室外に排気して
しまえば、少ない換気量で効果的に室内空気を清浄に保つことができるので、き
わめて有効な方法である。このような換気方法を「局所換気」と呼び、最も典型
的な例が、厨房の換気である。厨房のように、汚染の発生源が、定まったところ
に固定されているときは効果的である。発生源が定まらなかったり、時には移動
したりするたばこ煙の場合には、適用しにくい方法とも考えられるが、逆に考え
れば、たばこ煙という移動発生源を、フードの下に位置させることができれば極
めて好都合ともいえるため、今後の分煙対策の一つとして、考えられる方法であ
る。
(5)まとめ
室内空気汚染物質の除去手段としては、以下の4つに分けられる。
ア)汚染発生源を除去、隔離する方法
イ)発生源の性質を変え、無害化する方法
ウ)空気清浄機等によって汚染物質を除去する方法
エ)換気による方法
ア)は、最も根本的で理想的は方法であるが、いつでも適用可能とは限らない。
イ)の方法は、たばこ煙汚染除去には適用できない。
ウ)の方法は、たばこ煙中の粒子状物質の除去には効果があるが、ガス状物質
については有効な除去はなされていない。なお、最近、活性炭や光触媒等を利用
した一部のガス状物質を除去できるタイプの空気清浄機が出回ってきているが、
その効果は未だ不十分である。
エ)の方法は、最も消極的に見える方法であるが、あらゆる場合に適用可能な
実用性の高い方法である。局所換気システムと組み合わせると特に効果的である。
(3)評価のための測定項目の選定
分煙対策が効果的に行なわれているかどうかを判断するためには、喫煙場所や非喫
煙場所の室内空気環境中の喫煙由来物質の濃度を測定することにより定量的な評価を
行うことが必要である。
そのためには、測定対象項目を選定する必要がある。前述したようにたばこ煙中に
は多くの化学物質が存在するが、ここで言う測定対象項目は、あくまで分煙対策の評
価を行うための適切な指標となるもので直接的に生体に悪影響を及ぼす物質の測定を
行うものではない。
測定対象項目を選定するに当たって、米国の国立科学アカデミー(NAS,national
academy of sciences,1990)により示されている環境たばこ煙(ETS, Environment
Tobacco Smoke)の暴露評価のマーカーの満足すべき要件が参考となる。以下に、環
境たばこ煙(以下ETSと略)の暴露評価のマーカーの満足すべき要件の4項目を示した。
I.ETSに特異的であること(たばこ以外に当該化学物質の発生源がない)
II.喫煙率が低くても室内で容易に検知できること
(発生濃度が低くても検出できる)
III.発生割合が、たばこの種類(銘柄)に大きく依存しないこと
(多くの銘柄からほぼ同じ割合で発生する)
IV.ほかのETS構成物質と一定の割合にあること
(他の化学物質濃度がある程度推測できる)
また、既存の文献から室内環境濃度へのETSの寄与率(当該物質の喫煙場所の空気中
濃度に対するたばこ煙から発生した当該物質の割合)を表14にまとめた。ニコチンは
100%がETS由来であり、特異性の点で非常に有効なマーカーである。その次が吸
入性浮遊粉塵(RSP)で寄与率は50%であるが測定・分析が比較的容易であるためマー
カーとしての価値もある。その他の化学物質は寄与率が低く、他の要因による寄与が
あり、特異性に欠けるためマーカーとしてはあまり有効ではないと考えられる。
表14 室内環境濃度へのETSからの寄与率(1)