戻る
第1部 我が国のものづくり基盤技術の現状と課題
第1章 経済のグローバル化と我が国の製造業
(3)競争力強化に向けた製造産業の挑戦
我が国の製造産業は、幅広い課題に直面しているものの、21世紀の製造業
を担う元気な企業によって解決に向けた様々な取組が始まっている。
○経営戦略
製造業の競争力強化のためには、経営資源の選択と集中を一層進めること
により事業活動全般の効率化を図ることが肝要。
また、企業によっては単なる素材の提供に止まらず、最適解(ソリューシ
ョン)を提供することや、製品の差別化を進めることにより、競争力強化を
図っている。
(具体的事例)
(1)<企業の枠を超えて事業を統合・再編し、経営資源を成長分野に再配置>
電力用電線事業を持つA社とB社は、電力用電線の需要減少と同事業の赤字
の拡大が見込まれることから、平成13年に電力用電線部門をそれぞれ本体か
ら切り離し、新会社の下で統合し、生産拠点の集約・再編、重複設備の廃棄を
行った。この設備廃棄に伴って発生した余剰人員は、光ファイバー、化合物半
導体等の成長分野に配置転換した。
(2)<情報システム部門を別会社として独立>
大手鉄鋼メーカーA社では、将来の鉄鋼需要動向を、自動車の販売動向等に
関するデータを駆使して予想してきたため、データの処理・予測能力が培われ
た。A社では、こうした能力は外部にも応用が可能と考え、情報システムの外
部への販売を開始し、当該部門を分社化した。独立したB社はA社の情報シス
テム関連業務のアウトソーシング先となりつつ、迅速な意思決定の下、外部へ
の事業を積極的に展開している。
(3)<液晶用視野角拡大フィルムの分野におけるマテリアルソリューション>
化学メーカーA社は、他社との競争に敗れ、一旦は液晶パネルフィルム市場
から撤退した。しかし、A社の研究陣は、液晶パネルメーカーとの議論を通じ、
新しい液晶方式(TFT方式)が必要になる可能性が高いといち早く判断。液
晶パネルメーカーの潜在的なニーズを研究員自ら収集し、地道な研究を4年以
上継続するとともに、液晶パネルメーカーの協力も得て、視野角を拡大したフ
ィルムの開発に成功。
○研究開発による技術革新(イノベーション)
従来は研究活動の成果が円滑に事業化に繋がらない点が課題となるケース
が多かったが、近年は、応用研究、開発研究に重点を置きつつ、テーマの絞
り込みを重視する企業が増え、欧米と比べ不十分ではあるものの、大学等外
部研究機関との産学研究も進みつつある。また、研究開発によって大きな成
果が期待される分野において、様々な取組が行われている。
(具体的事例)
(1)<大学等との共同研究を強化>
総合化学メーカーA社は、探索的な研究では、外部研究機関へのアウトソー
シングは独自研究と比べて2.5倍から3倍程度コスト効率の向上が可能な場
合があるとし、海外の大学と材料科学領域で包括的な研究開発提携を行ったの
に加え、国内においても、次世代の革新的技術の創成を目的として、学を中核
とした複数の企業との連携を進めている。
(2)<材料分野における研究開発−次世代モバイル用表示技術(プラスチックを
利用した液晶の開発)>
モバイル機器用液晶画面として、プラスチック基板を用いた液晶ディスプレ
イが期待されているが、各社が個別に研究開発を推進する場合、投資コストを
回収できなくなる恐れがある。そこで、表示デバイス基板のプラスチック化を
図る企業が協力し、大学や独立行政法人とも共同して研究を推進することを決
定。政府も共同研究施設の設置を支援し、平成14年、大学の敷地内で研究施
設の建設を開始することとしている。
(3)<環境分野における研究開発−燃料電池>
水素と酸素を反応させて電気を取り出す燃料電池は、次世代低公害車の動力
源や家庭内電源として期待される。特に燃料電池自動車については、主メーカ
ーが激しい開発競争を展開しており、我が国の一部自動車メーカーが平成15
年に、試験的な販売を行うことを表明している。また、我が国では燃料電池自
動車の早期実用化を目指し、自動車メーカーの参加を広く募り大規模な実証実
験を行うほか、標準の策定に必要なデータの蓄積を行っている。
○知的財産権に係る戦略的対応
費用対効果を重視した知的財産の管理、事業の海外展開戦略に対応した技
術管理の徹底、技術流出の防止などが行われている。また、模倣品に対する
官民の様々な取組が具体化しつつある。
(具体的事例)
(1)<コア技術のブラックボックス化>
製造装置やコア部品を内製化し、現地工場へ持ち込む。ソフトウエアについ
てはプロテクト化、あるいはコードを開示しない。製造装置の制御ノウハウを、
基板として装置内に組み込むことにより対応。
(2)<従業員によるノウハウ流出防止>
技術・ノウハウを細分化し全容を知り得る者の数を極力少なくすることで対
応。退職時にノウハウを具体的に特定した上で、当該ノウハウに係る守秘義務
を契約上明確化。人材流出を防ぐためにストックオプション付与で対応。
(3)<中国等の模倣品に対する対策>
日本自動車工業会及び日本ベアリング工業会は、中国にミッションを派遣し、
中国政府に権利侵害品の取締の強化を要請した。加えて、平成14年4月は、
官民一体となって権利侵害品対策を実施するための産業界横断的組織として、
「国際知的財産保護フォーラム」が発足した。
○生産の事業手法における新たな潮流
商品のリードタイムの短縮、効率的な調達、顧客情報の管理などを目的と
したITの活用が行われている。また、中国等アジアにおいて生産能力が強
化される中で、国内において多品種少量・高付加価値製品の生産体制を実現
する取組が行われている。
(具体的事例)
(1)<製品開発におけるCAD/CAM/CAEの活用>
CAD/CAM/CAE(ITを活用した製品設計・試作・製造)の導入は、
設計や製造作業を効率化させ、リードタイムの短縮するもの。例えば、0年代
後半に自動車メーカーは相次いでCAEを導入し、外観デザイン決定から発売
まで約40ヵ月だった日本企業の平均的開発リードタイム(欧米は当時平均
40カ月)が、90年代末には約20ヵ月あるいはそれ以下に短縮されるよう
になった。
(用語)
CAD(Computer Aided Design)は、コンピュータを利用して設計図を作
るシステム。CAM(Computer Aided Manufacturing)は、コンピュータを利
用して製品を製造するシステムである。
CAE(Computer Aided Engineering)は、設計から製造、試験までの一連
の作業をコンピュータを利用して一元的に管理するシステムである。3次元
CAD/CAMとは、立体図に基づいたデザイン、製造を意味する。
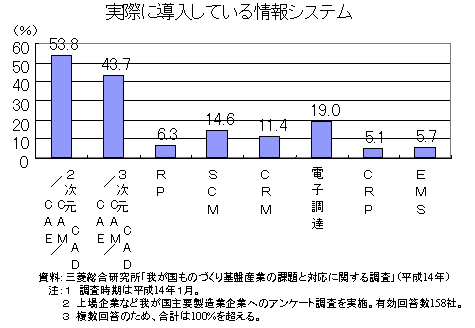 (2)<サプライ・チェーン・マネジメント:SCM(Supply Chain Managementの
導入>
SCMは、従来企業の様々な部門が独自に調達、生産等の計画を立てていた
のを廃止し、部門間で情報を共有することにより製品の管理を最適化するもの
であり、商品を無駄なくジャストインタイム方式で供給する事を可能とするも
の。
例えば、アパレル大手A社は、関連する国内62メーカーと協力し、週末の
店頭での売れ筋情報を即座にフィードバックし、今後の売れ筋を予測して週初
に工場へ発注をかけ、次の週末までには店頭へ配送する、という発注から納品
まで約一週間でこなす体制を構築した。なお、売上に占める国産繊維製品の比
率は70%にも上っており、国内繊維産業の一つの方向性を示している。
(2)<サプライ・チェーン・マネジメント:SCM(Supply Chain Managementの
導入>
SCMは、従来企業の様々な部門が独自に調達、生産等の計画を立てていた
のを廃止し、部門間で情報を共有することにより製品の管理を最適化するもの
であり、商品を無駄なくジャストインタイム方式で供給する事を可能とするも
の。
例えば、アパレル大手A社は、関連する国内62メーカーと協力し、週末の
店頭での売れ筋情報を即座にフィードバックし、今後の売れ筋を予測して週初
に工場へ発注をかけ、次の週末までには店頭へ配送する、という発注から納品
まで約一週間でこなす体制を構築した。なお、売上に占める国産繊維製品の比
率は70%にも上っており、国内繊維産業の一つの方向性を示している。
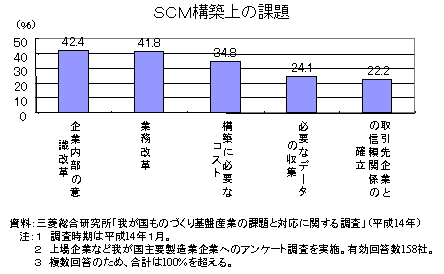 (3)<デジタル化と熟練技能>
熟練技能を分析してデジタル情報に変換することができれば熟練技能を習得
できなくとも誰でも利用できるようになるが、熟練技能は完全にデジタル化で
きるものではなく、デジタル化が容易でない技能は、かえって希少性が高まる。
さらに、顧客ニーズ、設計変更等に機動的に対応する上で熟練技能は重要な
武器であり、新しい技術開発・商品開発を生み出す源でもある。例えば、A社
は業界に先駆けてCAD/CAMを積極的に導入する一方で、CAD/CAM
では対応できない1/100ミリ単位以下の精巧な仕上げや、最後の人間の目によ
る確認行程は、多数の熟練技能者が手作業で行っており、高度に進化したIT
技術と技能が両立していることがA社の強みとなっている。
(3)<デジタル化と熟練技能>
熟練技能を分析してデジタル情報に変換することができれば熟練技能を習得
できなくとも誰でも利用できるようになるが、熟練技能は完全にデジタル化で
きるものではなく、デジタル化が容易でない技能は、かえって希少性が高まる。
さらに、顧客ニーズ、設計変更等に機動的に対応する上で熟練技能は重要な
武器であり、新しい技術開発・商品開発を生み出す源でもある。例えば、A社
は業界に先駆けてCAD/CAMを積極的に導入する一方で、CAD/CAM
では対応できない1/100ミリ単位以下の精巧な仕上げや、最後の人間の目によ
る確認行程は、多数の熟練技能者が手作業で行っており、高度に進化したIT
技術と技能が両立していることがA社の強みとなっている。
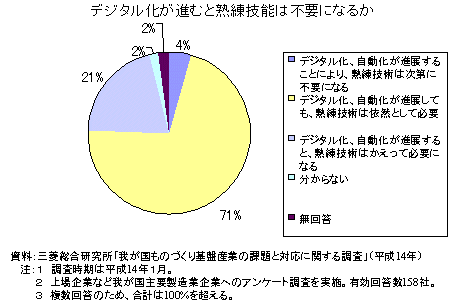 (4)<セル生産方式>
セル生産方式は、少人数の作業者が複数の工程をこなして規模の小さいライ
ンを運営する方式であり、在庫が大幅に削減されるのに加え、作業員一人一人
が別の製品を製造することができるため、多品種少量生産に適しているもので
ある。
例えば、精密機器メーカーA社の複写機工場では、セル生産方式の導入によ
り、中間在庫が従来の20日から7〜8日分に減少、完成品在庫も従来の2ヵ
月から約1ヵ月分へと半減し、結果として中級モデルで4割、高級モデルで3
割の生産性向上を果たしている。
(4)<セル生産方式>
セル生産方式は、少人数の作業者が複数の工程をこなして規模の小さいライ
ンを運営する方式であり、在庫が大幅に削減されるのに加え、作業員一人一人
が別の製品を製造することができるため、多品種少量生産に適しているもので
ある。
例えば、精密機器メーカーA社の複写機工場では、セル生産方式の導入によ
り、中間在庫が従来の20日から7〜8日分に減少、完成品在庫も従来の2ヵ
月から約1ヵ月分へと半減し、結果として中級モデルで4割、高級モデルで3
割の生産性向上を果たしている。
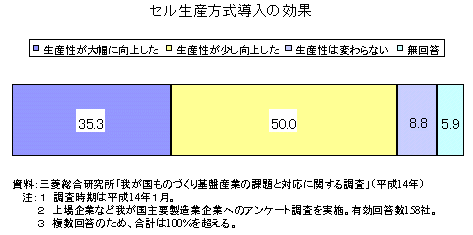 (5)<モジュール化>
モジュール化は単機能の部品を、共通のインターフェイスの下に組み合わせ、
セットメーカーの予定した一定の機能を実現する手法であり、コスト低減、品
質の安定化等にメリットがある。IT産業のみならず、昨今では、自動車産業
でも部品点数削減等、軽量化等の面からモジュール化が浸透しつつある。
例えば、自動車メーカーB社では、モジュール化した工程において原価低減
効果は約5%、不良発生件数は5分の1、生産性(組立て時間)は10%向上
したが、一方、技術のブラックボックス化等を懸念する指摘もある。
(5)<モジュール化>
モジュール化は単機能の部品を、共通のインターフェイスの下に組み合わせ、
セットメーカーの予定した一定の機能を実現する手法であり、コスト低減、品
質の安定化等にメリットがある。IT産業のみならず、昨今では、自動車産業
でも部品点数削減等、軽量化等の面からモジュール化が浸透しつつある。
例えば、自動車メーカーB社では、モジュール化した工程において原価低減
効果は約5%、不良発生件数は5分の1、生産性(組立て時間)は10%向上
したが、一方、技術のブラックボックス化等を懸念する指摘もある。
TOP
戻る
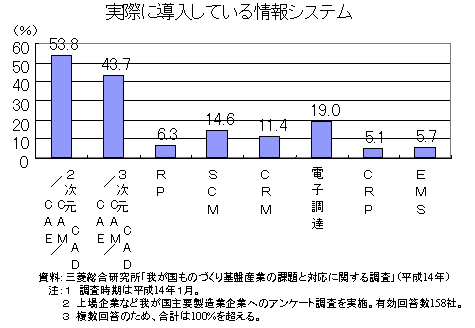 (2)<サプライ・チェーン・マネジメント:SCM(Supply Chain Managementの
導入>
SCMは、従来企業の様々な部門が独自に調達、生産等の計画を立てていた
のを廃止し、部門間で情報を共有することにより製品の管理を最適化するもの
であり、商品を無駄なくジャストインタイム方式で供給する事を可能とするも
の。
例えば、アパレル大手A社は、関連する国内62メーカーと協力し、週末の
店頭での売れ筋情報を即座にフィードバックし、今後の売れ筋を予測して週初
に工場へ発注をかけ、次の週末までには店頭へ配送する、という発注から納品
まで約一週間でこなす体制を構築した。なお、売上に占める国産繊維製品の比
率は70%にも上っており、国内繊維産業の一つの方向性を示している。
(2)<サプライ・チェーン・マネジメント:SCM(Supply Chain Managementの
導入>
SCMは、従来企業の様々な部門が独自に調達、生産等の計画を立てていた
のを廃止し、部門間で情報を共有することにより製品の管理を最適化するもの
であり、商品を無駄なくジャストインタイム方式で供給する事を可能とするも
の。
例えば、アパレル大手A社は、関連する国内62メーカーと協力し、週末の
店頭での売れ筋情報を即座にフィードバックし、今後の売れ筋を予測して週初
に工場へ発注をかけ、次の週末までには店頭へ配送する、という発注から納品
まで約一週間でこなす体制を構築した。なお、売上に占める国産繊維製品の比
率は70%にも上っており、国内繊維産業の一つの方向性を示している。
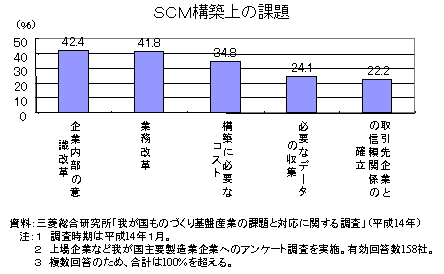 (3)<デジタル化と熟練技能>
熟練技能を分析してデジタル情報に変換することができれば熟練技能を習得
できなくとも誰でも利用できるようになるが、熟練技能は完全にデジタル化で
きるものではなく、デジタル化が容易でない技能は、かえって希少性が高まる。
さらに、顧客ニーズ、設計変更等に機動的に対応する上で熟練技能は重要な
武器であり、新しい技術開発・商品開発を生み出す源でもある。例えば、A社
は業界に先駆けてCAD/CAMを積極的に導入する一方で、CAD/CAM
では対応できない1/100ミリ単位以下の精巧な仕上げや、最後の人間の目によ
る確認行程は、多数の熟練技能者が手作業で行っており、高度に進化したIT
技術と技能が両立していることがA社の強みとなっている。
(3)<デジタル化と熟練技能>
熟練技能を分析してデジタル情報に変換することができれば熟練技能を習得
できなくとも誰でも利用できるようになるが、熟練技能は完全にデジタル化で
きるものではなく、デジタル化が容易でない技能は、かえって希少性が高まる。
さらに、顧客ニーズ、設計変更等に機動的に対応する上で熟練技能は重要な
武器であり、新しい技術開発・商品開発を生み出す源でもある。例えば、A社
は業界に先駆けてCAD/CAMを積極的に導入する一方で、CAD/CAM
では対応できない1/100ミリ単位以下の精巧な仕上げや、最後の人間の目によ
る確認行程は、多数の熟練技能者が手作業で行っており、高度に進化したIT
技術と技能が両立していることがA社の強みとなっている。
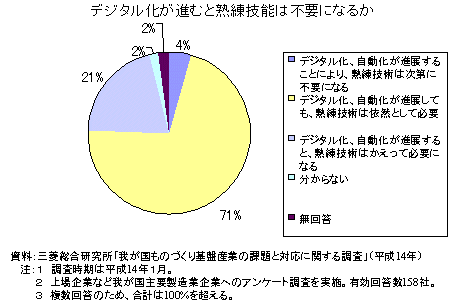 (4)<セル生産方式>
セル生産方式は、少人数の作業者が複数の工程をこなして規模の小さいライ
ンを運営する方式であり、在庫が大幅に削減されるのに加え、作業員一人一人
が別の製品を製造することができるため、多品種少量生産に適しているもので
ある。
例えば、精密機器メーカーA社の複写機工場では、セル生産方式の導入によ
り、中間在庫が従来の20日から7〜8日分に減少、完成品在庫も従来の2ヵ
月から約1ヵ月分へと半減し、結果として中級モデルで4割、高級モデルで3
割の生産性向上を果たしている。
(4)<セル生産方式>
セル生産方式は、少人数の作業者が複数の工程をこなして規模の小さいライ
ンを運営する方式であり、在庫が大幅に削減されるのに加え、作業員一人一人
が別の製品を製造することができるため、多品種少量生産に適しているもので
ある。
例えば、精密機器メーカーA社の複写機工場では、セル生産方式の導入によ
り、中間在庫が従来の20日から7〜8日分に減少、完成品在庫も従来の2ヵ
月から約1ヵ月分へと半減し、結果として中級モデルで4割、高級モデルで3
割の生産性向上を果たしている。
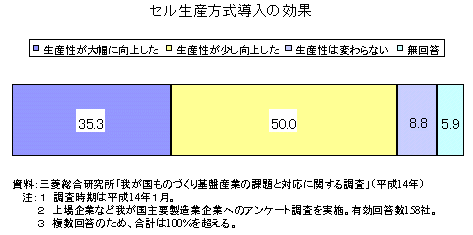 (5)<モジュール化>
モジュール化は単機能の部品を、共通のインターフェイスの下に組み合わせ、
セットメーカーの予定した一定の機能を実現する手法であり、コスト低減、品
質の安定化等にメリットがある。IT産業のみならず、昨今では、自動車産業
でも部品点数削減等、軽量化等の面からモジュール化が浸透しつつある。
例えば、自動車メーカーB社では、モジュール化した工程において原価低減
効果は約5%、不良発生件数は5分の1、生産性(組立て時間)は10%向上
したが、一方、技術のブラックボックス化等を懸念する指摘もある。
(5)<モジュール化>
モジュール化は単機能の部品を、共通のインターフェイスの下に組み合わせ、
セットメーカーの予定した一定の機能を実現する手法であり、コスト低減、品
質の安定化等にメリットがある。IT産業のみならず、昨今では、自動車産業
でも部品点数削減等、軽量化等の面からモジュール化が浸透しつつある。
例えば、自動車メーカーB社では、モジュール化した工程において原価低減
効果は約5%、不良発生件数は5分の1、生産性(組立て時間)は10%向上
したが、一方、技術のブラックボックス化等を懸念する指摘もある。