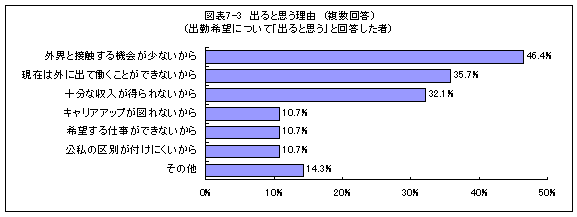戻る
(別添)
平成13年度家内労働等実態調査結果の概要
〜情報通信機器の活用による在宅就業実態調査〜
II 在宅就業者個人調査
1 在宅就業者に関する一般的事項
回答のあった在宅就業者の男女比は、男性29.3%、女性70.1%であった。配偶者の有
無については、男性の65.5%、女性の76.0%が配偶者ありであった。
年齢構成は30代が43.7%、40代が33.3%で、平均年齢は41.2歳であった。男性は40代
(36.4%)が最多で、平均年齢は44.5歳であったのに対し、女性は30代(50.2%)が最多で、
平均年齢は39.8歳であった。
同居の子供については、回答者の60.8%が「ある」と回答し、末子が6歳までの未就
学児である者の割合は26.1%であった。これを男女別で見ると、男性では同居の子供
ありが48.2%、末子未就学が18.2%であるのに対し、女性では同居の子供ありが66.5%、
末子未就学が29.7%と、いずれも女性の方が割合が高かった。
在宅就業を始めてからの期間は、「2〜3年未満」(23.5%)と「10年以上」(22.7%)が
やや高い割合を示しているが、ほぼ全カテゴリに均等に分布していた。
在宅就業を始めた理由としては、男性は「自分のペースで柔軟・弾力的に働けるた
め」が最多であるのに対し、女性は「育児や介護等、家事と仕事の両立のため」が最
多であった。
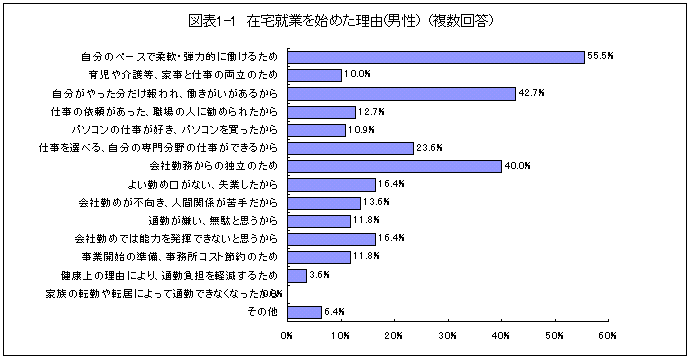
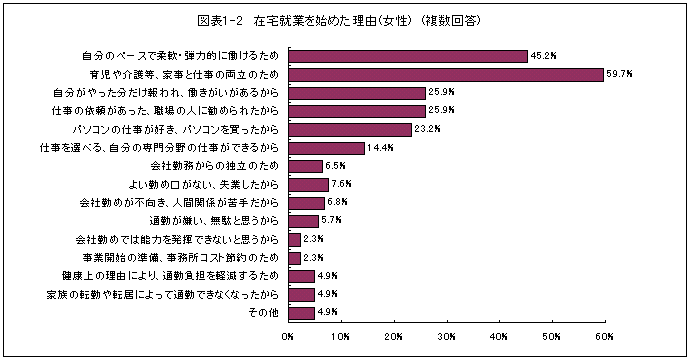 2 在宅就業に関する事項
(1) 現在実施している主な職種
現在実施している主な職種としては、男性では「設計、製図、デザイン」、「シ
ステム設計、プログラミング」が多く、女性では「文書入力」、「設計、製図、デ
ザイン」、「データ入力」が多い。
2 在宅就業に関する事項
(1) 現在実施している主な職種
現在実施している主な職種としては、男性では「設計、製図、デザイン」、「シ
ステム設計、プログラミング」が多く、女性では「文書入力」、「設計、製図、デ
ザイン」、「データ入力」が多い。
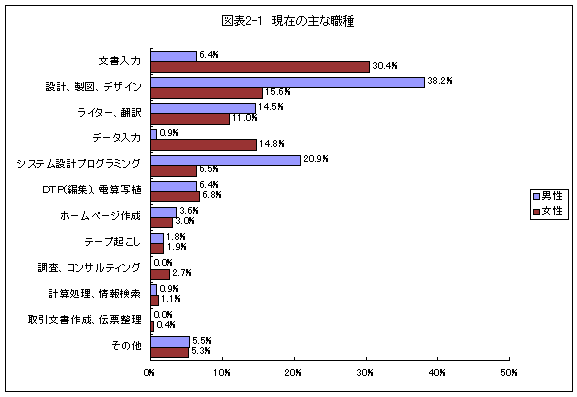 (2) 在宅就業を始めるに当たっての準備内容
在宅就業を始めるに当たっての準備内容(複数回答)としては、「OA機器の購入」、
ついで「ソフトウエアの購入」が多かった。また、女性で多かったのは「机等備品
の購入」であった。
準備にかかった費用はばらつきが見られるが、全体的に男性の方がかかった費用
は高く、100万円を超える者は男性29.1%、女性8.0%であった。
(2) 在宅就業を始めるに当たっての準備内容
在宅就業を始めるに当たっての準備内容(複数回答)としては、「OA機器の購入」、
ついで「ソフトウエアの購入」が多かった。また、女性で多かったのは「机等備品
の購入」であった。
準備にかかった費用はばらつきが見られるが、全体的に男性の方がかかった費用
は高く、100万円を超える者は男性29.1%、女性8.0%であった。
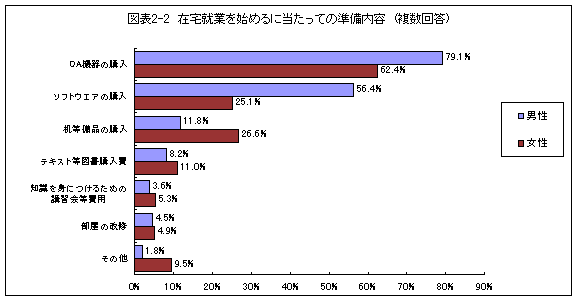 (3) 仕事の依頼主の見つけ方
仕事の依頼主の見つけ方(複数回答)としては、「以前の勤め先」、「仕事仲間の
情報、紹介」、「以前の勤め先関係の知人の紹介」など、知人等を通じて仕事の依
頼主を見つける者の割合が高かった。一方、「求人広告への応募」、「仲介的な会
社・個人」、「インターネットの情報」など、不特定多数を対象とした募集媒体の
利用率はあまり高くなかった。
(3) 仕事の依頼主の見つけ方
仕事の依頼主の見つけ方(複数回答)としては、「以前の勤め先」、「仕事仲間の
情報、紹介」、「以前の勤め先関係の知人の紹介」など、知人等を通じて仕事の依
頼主を見つける者の割合が高かった。一方、「求人広告への応募」、「仲介的な会
社・個人」、「インターネットの情報」など、不特定多数を対象とした募集媒体の
利用率はあまり高くなかった。
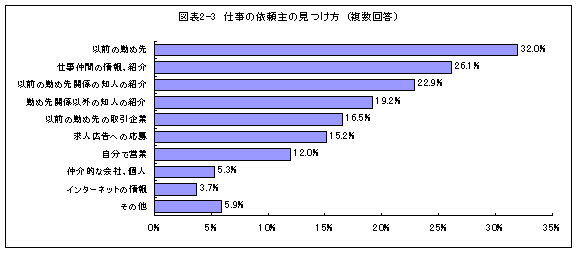 3 仕事の実施状況
在宅就業による年収・年商の概算を男女別で見ると、男性は高所得層に、女性は低
所得層にピークが存在しており、149万円までの層が男性では21.8%であるのに対し、
女性では68.1%に及ぶ。また、500万円を超える層を男女別で見ると、男性26.4%に対
し、女性では3.8%に留まり、男女間格差が大きい。
3 仕事の実施状況
在宅就業による年収・年商の概算を男女別で見ると、男性は高所得層に、女性は低
所得層にピークが存在しており、149万円までの層が男性では21.8%であるのに対し、
女性では68.1%に及ぶ。また、500万円を超える層を男女別で見ると、男性26.4%に対
し、女性では3.8%に留まり、男女間格差が大きい。
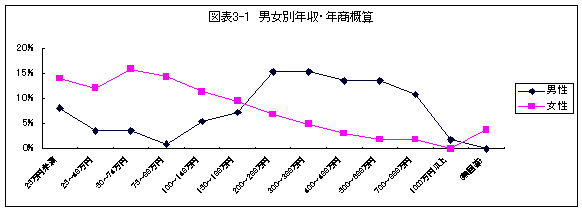
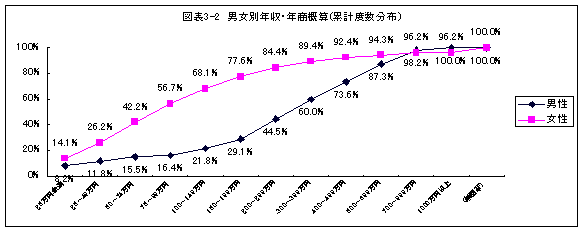 平成14年2月中の在宅就業の仕事の実施状況を見ると、就業日数は「21日以上」
(男性32.7%、女性20.2%)、「14〜21日未満」(男性42.7%、女性38.4%)で、男性の方
が就業日数は長い傾向にあり、また、仕事をした日の1日当たりの平均就業時間は
「10時間以上」(男性22.7%、女性9.5%)、「8時間〜10時間未満」(男性31.8%、女性
11.8%)と、同じく男性の方が長い傾向にある。このように、1ヶ月当たりの就業延
べ時間数にも男女間でかなりの格差が認められ、年収・年商レベルの格差の要因の
一つになっている。
4 契約及び報酬に関する事項
仕事の契約方法(複数回答)としては、「口頭」が最多で、ついで「電子メール」で
あった。書面による契約(「契約書方式」、「伝票形式」、「メモ程度」)はどの方式
も同程度であった。
平成14年2月中の在宅就業の仕事の実施状況を見ると、就業日数は「21日以上」
(男性32.7%、女性20.2%)、「14〜21日未満」(男性42.7%、女性38.4%)で、男性の方
が就業日数は長い傾向にあり、また、仕事をした日の1日当たりの平均就業時間は
「10時間以上」(男性22.7%、女性9.5%)、「8時間〜10時間未満」(男性31.8%、女性
11.8%)と、同じく男性の方が長い傾向にある。このように、1ヶ月当たりの就業延
べ時間数にも男女間でかなりの格差が認められ、年収・年商レベルの格差の要因の
一つになっている。
4 契約及び報酬に関する事項
仕事の契約方法(複数回答)としては、「口頭」が最多で、ついで「電子メール」で
あった。書面による契約(「契約書方式」、「伝票形式」、「メモ程度」)はどの方式
も同程度であった。
 仕事の報酬単位(複数回答)としては、「出来高」(67.2%)が最多で、「実際の所要
時間」(22.9%)がこれに続く。仕事の報酬決定手順(複数回答)は、「依頼主が設定す
る」(53.1%)が最多で、「依頼主が設定し、必要があれば交渉」(31.5%)と「自分で提
示し、依頼主と調整」(28.8%)が同程度であった。
5 トラブルに関する事項
依頼主とのトラブルは、男性の29.1%、女性の16.7%が経験している。
トラブルの内容としては「報酬の支払い」が最多で、「仕事の納期」、「依頼され
る仕事の量」がこれに続く。トラブル対応としては、男性は「直接会って交渉」、
「電話で交渉」が多いが、女性は「電話で交渉」が最多で、ついで「直接会って交渉」
である。
仕事の報酬単位(複数回答)としては、「出来高」(67.2%)が最多で、「実際の所要
時間」(22.9%)がこれに続く。仕事の報酬決定手順(複数回答)は、「依頼主が設定す
る」(53.1%)が最多で、「依頼主が設定し、必要があれば交渉」(31.5%)と「自分で提
示し、依頼主と調整」(28.8%)が同程度であった。
5 トラブルに関する事項
依頼主とのトラブルは、男性の29.1%、女性の16.7%が経験している。
トラブルの内容としては「報酬の支払い」が最多で、「仕事の納期」、「依頼され
る仕事の量」がこれに続く。トラブル対応としては、男性は「直接会って交渉」、
「電話で交渉」が多いが、女性は「電話で交渉」が最多で、ついで「直接会って交渉」
である。
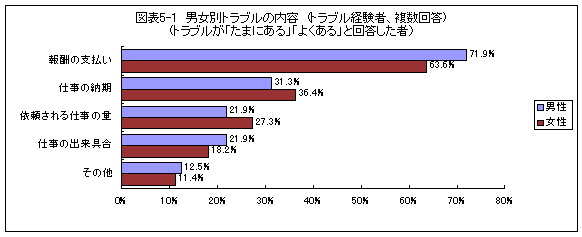
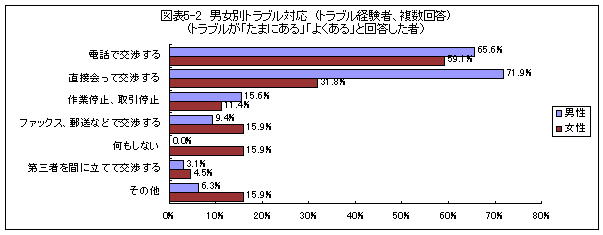 今困っていること(複数回答)は、「仕事の確保」が最多で、ついで「単価が安いこ
と」、「ハード、ソフトウエアのレベルアップ」であった。
今困っていること(複数回答)は、「仕事の確保」が最多で、ついで「単価が安いこ
と」、「ハード、ソフトウエアのレベルアップ」であった。
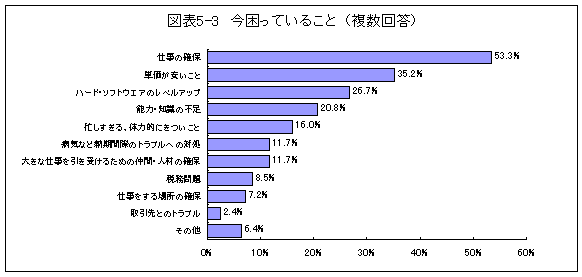 6 健康管理及び能力開発に関する事項
(1) 健康管理
「肩こり」は、「かなり感じている」(男性18.2%、女性36.1%)、「やや感じてい
る」(男性31.8%、女性35.7%)の両者を合わせると、男性の半数、女性の7割が自覚
症状を訴えている。「眼精疲労」では、「かなり感じている」(男性25.5%、女性
33.1%)、「やや感じている」(男性40.9%、女性43.7%)の両者を合わせると、男女と
も4分の3が自覚症状を訴えている。「腰痛」では、「かなり感じている」
(男性10.0%、女性13.7%)、「やや感じている」(男31.8%、女性30.0%)の両者を合わ
せると、男女とも4割が自覚症状を訴えている。
治療・通院率は「かなり感じている」グループの方が「やや感じている」グルー
プより高いものの、大多数の回答者は治療・通院をしていない。
(2) 能力開発
在宅就業に必要な能力は、「勤務先での仕事経験、研修などを通じて」修得した
者が男女とも最も多い。
6 健康管理及び能力開発に関する事項
(1) 健康管理
「肩こり」は、「かなり感じている」(男性18.2%、女性36.1%)、「やや感じてい
る」(男性31.8%、女性35.7%)の両者を合わせると、男性の半数、女性の7割が自覚
症状を訴えている。「眼精疲労」では、「かなり感じている」(男性25.5%、女性
33.1%)、「やや感じている」(男性40.9%、女性43.7%)の両者を合わせると、男女と
も4分の3が自覚症状を訴えている。「腰痛」では、「かなり感じている」
(男性10.0%、女性13.7%)、「やや感じている」(男31.8%、女性30.0%)の両者を合わ
せると、男女とも4割が自覚症状を訴えている。
治療・通院率は「かなり感じている」グループの方が「やや感じている」グルー
プより高いものの、大多数の回答者は治療・通院をしていない。
(2) 能力開発
在宅就業に必要な能力は、「勤務先での仕事経験、研修などを通じて」修得した
者が男女とも最も多い。
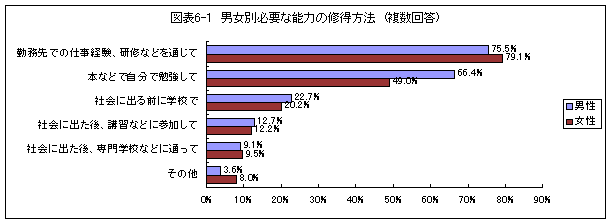 知識・技能の向上のための取組を行っているのは男性の80.9%、女性の55.5%であ
り、実施内容は「ソフトウエアの学習」(男性79.8%、女性71.2%)が最多であった。
能力開発の実施方法としては、「書籍、雑誌、関連情報などによる自己学習」が
最多で、「仕事関係者、仲間との情報交換」がこれに続く。
知識・技能の向上のための取組を行っているのは男性の80.9%、女性の55.5%であ
り、実施内容は「ソフトウエアの学習」(男性79.8%、女性71.2%)が最多であった。
能力開発の実施方法としては、「書籍、雑誌、関連情報などによる自己学習」が
最多で、「仕事関係者、仲間との情報交換」がこれに続く。
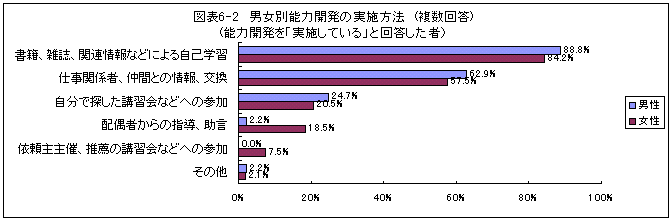 (3) 他の在宅就業者との交流
他の在宅就業者との交流の機会については、男性の64.5%、女性の53.6%が「必要
だと思う」と回答した。「必要だと思う」と回答した者に対し交流への積極性を尋
ねたところ、男性では「積極的」(14.1%)、「比較的積極的」(33.8%)の両者で半数
近くを占めたのに対し、女性では「あまり積極的でない」(47.5%)、「消極的」
(19.1%)の両者で3分の2に及んだ。
交流に「積極的」、「比較的積極的」と回答した者に、仲間とどのように接触し
ているかを尋ねたところ、男性では「電話や電子メールによる接触」(50.0%)が主
流であったが、女性では「仲間とグループを作って共同受注を行う等の活動をして
いる」(34.0%)が最多であった。
一方、「あまり積極的でない」、「消極的」と回答した者に仕事グループや人的
ネットワーク等の交流に参加する条件を複数回答で尋ねたところ、「近くで行われ
る」(56.5%)が最も多く、ついで「インターネット上での交流」(38.9%)であった。
7 在宅就業に係る将来展望
(1) 在宅就業の継続希望
在宅就業の継続希望については、「ぜひ続けたい」(55.5%)と「できれば続けた
い」(31.5%)を合わせると、ほぼ9割が継続希望を持っていた。
一方、「迷っている」、「やめたい」と回答した者は合わせて11.2%おり、その
理由(複数回答)としては、「収入が少ない、不安定だから」が最多であった。
(3) 他の在宅就業者との交流
他の在宅就業者との交流の機会については、男性の64.5%、女性の53.6%が「必要
だと思う」と回答した。「必要だと思う」と回答した者に対し交流への積極性を尋
ねたところ、男性では「積極的」(14.1%)、「比較的積極的」(33.8%)の両者で半数
近くを占めたのに対し、女性では「あまり積極的でない」(47.5%)、「消極的」
(19.1%)の両者で3分の2に及んだ。
交流に「積極的」、「比較的積極的」と回答した者に、仲間とどのように接触し
ているかを尋ねたところ、男性では「電話や電子メールによる接触」(50.0%)が主
流であったが、女性では「仲間とグループを作って共同受注を行う等の活動をして
いる」(34.0%)が最多であった。
一方、「あまり積極的でない」、「消極的」と回答した者に仕事グループや人的
ネットワーク等の交流に参加する条件を複数回答で尋ねたところ、「近くで行われ
る」(56.5%)が最も多く、ついで「インターネット上での交流」(38.9%)であった。
7 在宅就業に係る将来展望
(1) 在宅就業の継続希望
在宅就業の継続希望については、「ぜひ続けたい」(55.5%)と「できれば続けた
い」(31.5%)を合わせると、ほぼ9割が継続希望を持っていた。
一方、「迷っている」、「やめたい」と回答した者は合わせて11.2%おり、その
理由(複数回答)としては、「収入が少ない、不安定だから」が最多であった。
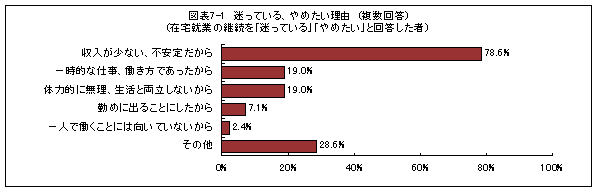 (2) 子育て時期後の出勤勤務希望
未就学児童がいる女性(末子年齢6歳以下)の子育て時期後の出勤勤務の希望につ
いては、「絶対出たくない」 (1.3%)、「できれば出たくない」(57.7%)の合計で6
割近くに及び、その理由(複数回答)としては、「時間の自由がきかない」、「家を
空けたくない」が多かった。
(2) 子育て時期後の出勤勤務希望
未就学児童がいる女性(末子年齢6歳以下)の子育て時期後の出勤勤務の希望につ
いては、「絶対出たくない」 (1.3%)、「できれば出たくない」(57.7%)の合計で6
割近くに及び、その理由(複数回答)としては、「時間の自由がきかない」、「家を
空けたくない」が多かった。
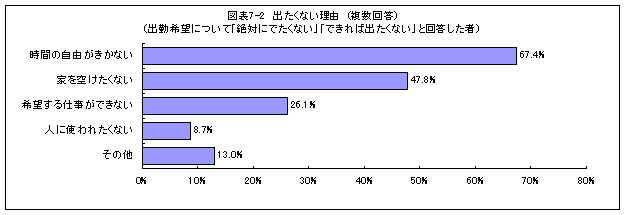 一方、出勤勤務を希望する者は35.9%であり、「出ると思う」理由(複数回答)と
しては、「外界と接触する機会が少ない」、「現在は外に出て働くことができな
い」、「十分な収入が得られない」が多かった。
一方、出勤勤務を希望する者は35.9%であり、「出ると思う」理由(複数回答)と
しては、「外界と接触する機会が少ない」、「現在は外に出て働くことができな
い」、「十分な収入が得られない」が多かった。
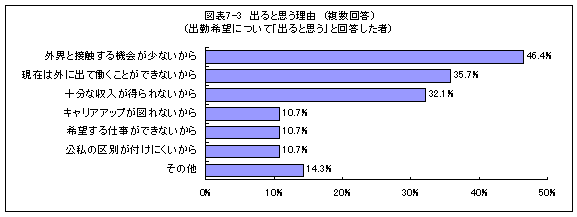
TOP
戻る
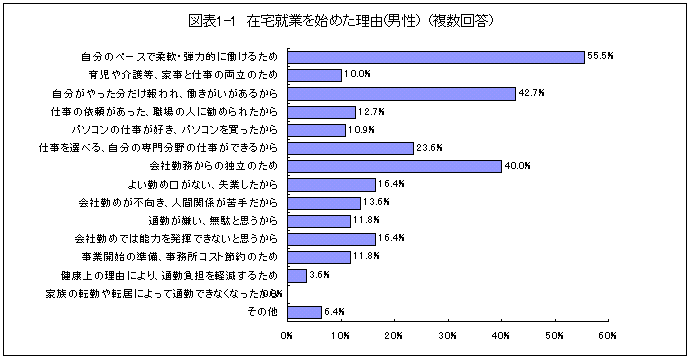
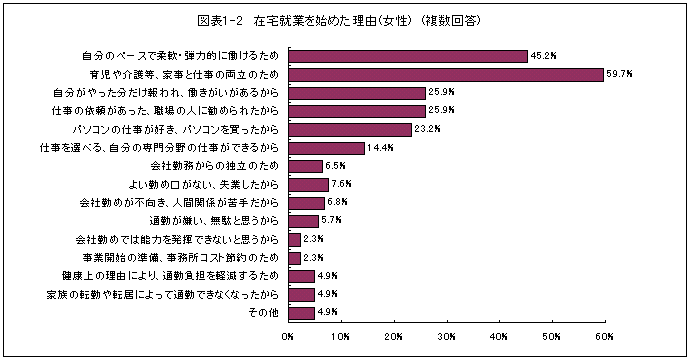 2 在宅就業に関する事項
(1) 現在実施している主な職種
現在実施している主な職種としては、男性では「設計、製図、デザイン」、「シ
ステム設計、プログラミング」が多く、女性では「文書入力」、「設計、製図、デ
ザイン」、「データ入力」が多い。
2 在宅就業に関する事項
(1) 現在実施している主な職種
現在実施している主な職種としては、男性では「設計、製図、デザイン」、「シ
ステム設計、プログラミング」が多く、女性では「文書入力」、「設計、製図、デ
ザイン」、「データ入力」が多い。
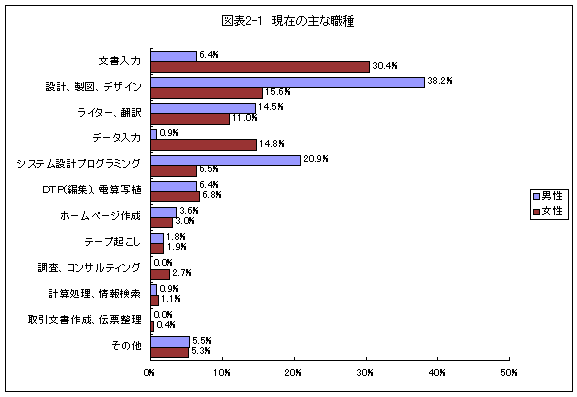 (2) 在宅就業を始めるに当たっての準備内容
在宅就業を始めるに当たっての準備内容(複数回答)としては、「OA機器の購入」、
ついで「ソフトウエアの購入」が多かった。また、女性で多かったのは「机等備品
の購入」であった。
準備にかかった費用はばらつきが見られるが、全体的に男性の方がかかった費用
は高く、100万円を超える者は男性29.1%、女性8.0%であった。
(2) 在宅就業を始めるに当たっての準備内容
在宅就業を始めるに当たっての準備内容(複数回答)としては、「OA機器の購入」、
ついで「ソフトウエアの購入」が多かった。また、女性で多かったのは「机等備品
の購入」であった。
準備にかかった費用はばらつきが見られるが、全体的に男性の方がかかった費用
は高く、100万円を超える者は男性29.1%、女性8.0%であった。
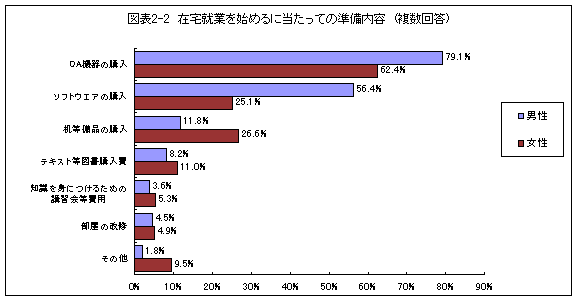 (3) 仕事の依頼主の見つけ方
仕事の依頼主の見つけ方(複数回答)としては、「以前の勤め先」、「仕事仲間の
情報、紹介」、「以前の勤め先関係の知人の紹介」など、知人等を通じて仕事の依
頼主を見つける者の割合が高かった。一方、「求人広告への応募」、「仲介的な会
社・個人」、「インターネットの情報」など、不特定多数を対象とした募集媒体の
利用率はあまり高くなかった。
(3) 仕事の依頼主の見つけ方
仕事の依頼主の見つけ方(複数回答)としては、「以前の勤め先」、「仕事仲間の
情報、紹介」、「以前の勤め先関係の知人の紹介」など、知人等を通じて仕事の依
頼主を見つける者の割合が高かった。一方、「求人広告への応募」、「仲介的な会
社・個人」、「インターネットの情報」など、不特定多数を対象とした募集媒体の
利用率はあまり高くなかった。
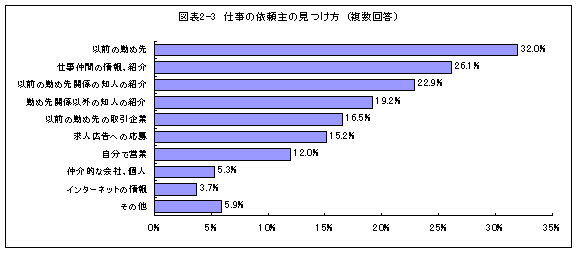 3 仕事の実施状況
在宅就業による年収・年商の概算を男女別で見ると、男性は高所得層に、女性は低
所得層にピークが存在しており、149万円までの層が男性では21.8%であるのに対し、
女性では68.1%に及ぶ。また、500万円を超える層を男女別で見ると、男性26.4%に対
し、女性では3.8%に留まり、男女間格差が大きい。
3 仕事の実施状況
在宅就業による年収・年商の概算を男女別で見ると、男性は高所得層に、女性は低
所得層にピークが存在しており、149万円までの層が男性では21.8%であるのに対し、
女性では68.1%に及ぶ。また、500万円を超える層を男女別で見ると、男性26.4%に対
し、女性では3.8%に留まり、男女間格差が大きい。
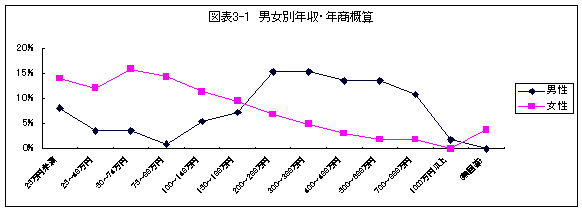
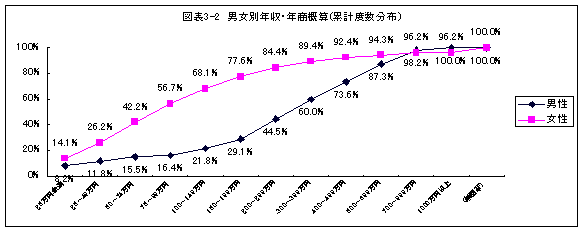 平成14年2月中の在宅就業の仕事の実施状況を見ると、就業日数は「21日以上」
(男性32.7%、女性20.2%)、「14〜21日未満」(男性42.7%、女性38.4%)で、男性の方
が就業日数は長い傾向にあり、また、仕事をした日の1日当たりの平均就業時間は
「10時間以上」(男性22.7%、女性9.5%)、「8時間〜10時間未満」(男性31.8%、女性
11.8%)と、同じく男性の方が長い傾向にある。このように、1ヶ月当たりの就業延
べ時間数にも男女間でかなりの格差が認められ、年収・年商レベルの格差の要因の
一つになっている。
4 契約及び報酬に関する事項
仕事の契約方法(複数回答)としては、「口頭」が最多で、ついで「電子メール」で
あった。書面による契約(「契約書方式」、「伝票形式」、「メモ程度」)はどの方式
も同程度であった。
平成14年2月中の在宅就業の仕事の実施状況を見ると、就業日数は「21日以上」
(男性32.7%、女性20.2%)、「14〜21日未満」(男性42.7%、女性38.4%)で、男性の方
が就業日数は長い傾向にあり、また、仕事をした日の1日当たりの平均就業時間は
「10時間以上」(男性22.7%、女性9.5%)、「8時間〜10時間未満」(男性31.8%、女性
11.8%)と、同じく男性の方が長い傾向にある。このように、1ヶ月当たりの就業延
べ時間数にも男女間でかなりの格差が認められ、年収・年商レベルの格差の要因の
一つになっている。
4 契約及び報酬に関する事項
仕事の契約方法(複数回答)としては、「口頭」が最多で、ついで「電子メール」で
あった。書面による契約(「契約書方式」、「伝票形式」、「メモ程度」)はどの方式
も同程度であった。
 仕事の報酬単位(複数回答)としては、「出来高」(67.2%)が最多で、「実際の所要
時間」(22.9%)がこれに続く。仕事の報酬決定手順(複数回答)は、「依頼主が設定す
る」(53.1%)が最多で、「依頼主が設定し、必要があれば交渉」(31.5%)と「自分で提
示し、依頼主と調整」(28.8%)が同程度であった。
5 トラブルに関する事項
依頼主とのトラブルは、男性の29.1%、女性の16.7%が経験している。
トラブルの内容としては「報酬の支払い」が最多で、「仕事の納期」、「依頼され
る仕事の量」がこれに続く。トラブル対応としては、男性は「直接会って交渉」、
「電話で交渉」が多いが、女性は「電話で交渉」が最多で、ついで「直接会って交渉」
である。
仕事の報酬単位(複数回答)としては、「出来高」(67.2%)が最多で、「実際の所要
時間」(22.9%)がこれに続く。仕事の報酬決定手順(複数回答)は、「依頼主が設定す
る」(53.1%)が最多で、「依頼主が設定し、必要があれば交渉」(31.5%)と「自分で提
示し、依頼主と調整」(28.8%)が同程度であった。
5 トラブルに関する事項
依頼主とのトラブルは、男性の29.1%、女性の16.7%が経験している。
トラブルの内容としては「報酬の支払い」が最多で、「仕事の納期」、「依頼され
る仕事の量」がこれに続く。トラブル対応としては、男性は「直接会って交渉」、
「電話で交渉」が多いが、女性は「電話で交渉」が最多で、ついで「直接会って交渉」
である。
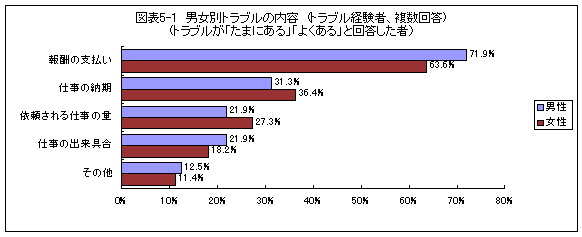
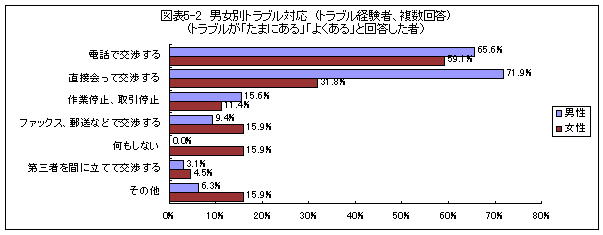 今困っていること(複数回答)は、「仕事の確保」が最多で、ついで「単価が安いこ
と」、「ハード、ソフトウエアのレベルアップ」であった。
今困っていること(複数回答)は、「仕事の確保」が最多で、ついで「単価が安いこ
と」、「ハード、ソフトウエアのレベルアップ」であった。
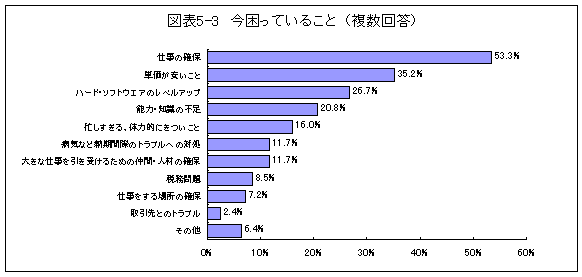 6 健康管理及び能力開発に関する事項
(1) 健康管理
「肩こり」は、「かなり感じている」(男性18.2%、女性36.1%)、「やや感じてい
る」(男性31.8%、女性35.7%)の両者を合わせると、男性の半数、女性の7割が自覚
症状を訴えている。「眼精疲労」では、「かなり感じている」(男性25.5%、女性
33.1%)、「やや感じている」(男性40.9%、女性43.7%)の両者を合わせると、男女と
も4分の3が自覚症状を訴えている。「腰痛」では、「かなり感じている」
(男性10.0%、女性13.7%)、「やや感じている」(男31.8%、女性30.0%)の両者を合わ
せると、男女とも4割が自覚症状を訴えている。
治療・通院率は「かなり感じている」グループの方が「やや感じている」グルー
プより高いものの、大多数の回答者は治療・通院をしていない。
(2) 能力開発
在宅就業に必要な能力は、「勤務先での仕事経験、研修などを通じて」修得した
者が男女とも最も多い。
6 健康管理及び能力開発に関する事項
(1) 健康管理
「肩こり」は、「かなり感じている」(男性18.2%、女性36.1%)、「やや感じてい
る」(男性31.8%、女性35.7%)の両者を合わせると、男性の半数、女性の7割が自覚
症状を訴えている。「眼精疲労」では、「かなり感じている」(男性25.5%、女性
33.1%)、「やや感じている」(男性40.9%、女性43.7%)の両者を合わせると、男女と
も4分の3が自覚症状を訴えている。「腰痛」では、「かなり感じている」
(男性10.0%、女性13.7%)、「やや感じている」(男31.8%、女性30.0%)の両者を合わ
せると、男女とも4割が自覚症状を訴えている。
治療・通院率は「かなり感じている」グループの方が「やや感じている」グルー
プより高いものの、大多数の回答者は治療・通院をしていない。
(2) 能力開発
在宅就業に必要な能力は、「勤務先での仕事経験、研修などを通じて」修得した
者が男女とも最も多い。
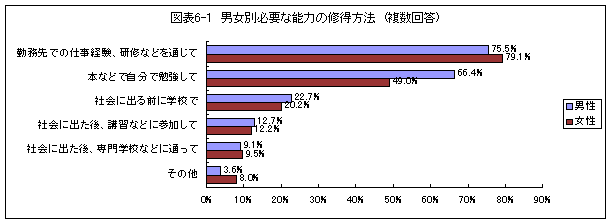 知識・技能の向上のための取組を行っているのは男性の80.9%、女性の55.5%であ
り、実施内容は「ソフトウエアの学習」(男性79.8%、女性71.2%)が最多であった。
能力開発の実施方法としては、「書籍、雑誌、関連情報などによる自己学習」が
最多で、「仕事関係者、仲間との情報交換」がこれに続く。
知識・技能の向上のための取組を行っているのは男性の80.9%、女性の55.5%であ
り、実施内容は「ソフトウエアの学習」(男性79.8%、女性71.2%)が最多であった。
能力開発の実施方法としては、「書籍、雑誌、関連情報などによる自己学習」が
最多で、「仕事関係者、仲間との情報交換」がこれに続く。
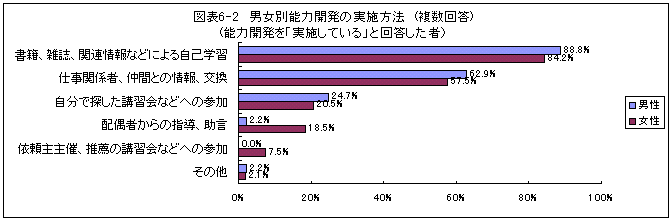 (3) 他の在宅就業者との交流
他の在宅就業者との交流の機会については、男性の64.5%、女性の53.6%が「必要
だと思う」と回答した。「必要だと思う」と回答した者に対し交流への積極性を尋
ねたところ、男性では「積極的」(14.1%)、「比較的積極的」(33.8%)の両者で半数
近くを占めたのに対し、女性では「あまり積極的でない」(47.5%)、「消極的」
(19.1%)の両者で3分の2に及んだ。
交流に「積極的」、「比較的積極的」と回答した者に、仲間とどのように接触し
ているかを尋ねたところ、男性では「電話や電子メールによる接触」(50.0%)が主
流であったが、女性では「仲間とグループを作って共同受注を行う等の活動をして
いる」(34.0%)が最多であった。
一方、「あまり積極的でない」、「消極的」と回答した者に仕事グループや人的
ネットワーク等の交流に参加する条件を複数回答で尋ねたところ、「近くで行われ
る」(56.5%)が最も多く、ついで「インターネット上での交流」(38.9%)であった。
7 在宅就業に係る将来展望
(1) 在宅就業の継続希望
在宅就業の継続希望については、「ぜひ続けたい」(55.5%)と「できれば続けた
い」(31.5%)を合わせると、ほぼ9割が継続希望を持っていた。
一方、「迷っている」、「やめたい」と回答した者は合わせて11.2%おり、その
理由(複数回答)としては、「収入が少ない、不安定だから」が最多であった。
(3) 他の在宅就業者との交流
他の在宅就業者との交流の機会については、男性の64.5%、女性の53.6%が「必要
だと思う」と回答した。「必要だと思う」と回答した者に対し交流への積極性を尋
ねたところ、男性では「積極的」(14.1%)、「比較的積極的」(33.8%)の両者で半数
近くを占めたのに対し、女性では「あまり積極的でない」(47.5%)、「消極的」
(19.1%)の両者で3分の2に及んだ。
交流に「積極的」、「比較的積極的」と回答した者に、仲間とどのように接触し
ているかを尋ねたところ、男性では「電話や電子メールによる接触」(50.0%)が主
流であったが、女性では「仲間とグループを作って共同受注を行う等の活動をして
いる」(34.0%)が最多であった。
一方、「あまり積極的でない」、「消極的」と回答した者に仕事グループや人的
ネットワーク等の交流に参加する条件を複数回答で尋ねたところ、「近くで行われ
る」(56.5%)が最も多く、ついで「インターネット上での交流」(38.9%)であった。
7 在宅就業に係る将来展望
(1) 在宅就業の継続希望
在宅就業の継続希望については、「ぜひ続けたい」(55.5%)と「できれば続けた
い」(31.5%)を合わせると、ほぼ9割が継続希望を持っていた。
一方、「迷っている」、「やめたい」と回答した者は合わせて11.2%おり、その
理由(複数回答)としては、「収入が少ない、不安定だから」が最多であった。
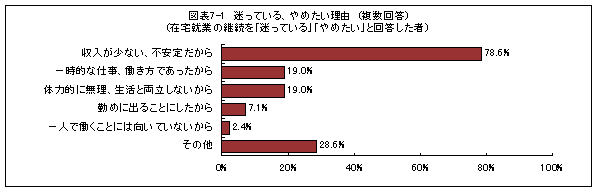 (2) 子育て時期後の出勤勤務希望
未就学児童がいる女性(末子年齢6歳以下)の子育て時期後の出勤勤務の希望につ
いては、「絶対出たくない」 (1.3%)、「できれば出たくない」(57.7%)の合計で6
割近くに及び、その理由(複数回答)としては、「時間の自由がきかない」、「家を
空けたくない」が多かった。
(2) 子育て時期後の出勤勤務希望
未就学児童がいる女性(末子年齢6歳以下)の子育て時期後の出勤勤務の希望につ
いては、「絶対出たくない」 (1.3%)、「できれば出たくない」(57.7%)の合計で6
割近くに及び、その理由(複数回答)としては、「時間の自由がきかない」、「家を
空けたくない」が多かった。
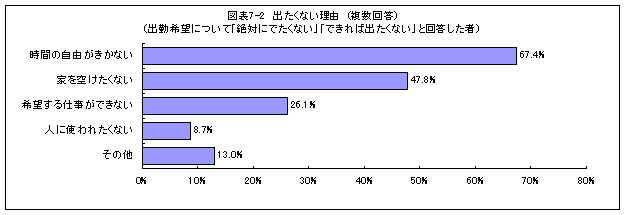 一方、出勤勤務を希望する者は35.9%であり、「出ると思う」理由(複数回答)と
しては、「外界と接触する機会が少ない」、「現在は外に出て働くことができな
い」、「十分な収入が得られない」が多かった。
一方、出勤勤務を希望する者は35.9%であり、「出ると思う」理由(複数回答)と
しては、「外界と接触する機会が少ない」、「現在は外に出て働くことができな
い」、「十分な収入が得られない」が多かった。