戻る
(別添)
平成13年度家内労働等実態調査結果の概要
〜情報通信機器の活用による在宅就業実態調査〜
I 発注者調査
1 事業所に関する事項
業種別で最も多かったのは「情報サービス・調査」(34.1%)で、「出版印刷」(27.8
%)、「デザイン・設計」(22.5%)がこれに続く。
常用労働者数別規模では「5〜29人」(58.7%)が最も多く、「0人」(2.1%)、「1〜4
人」(21.6%)を合わせると、全体の8割以上が29人未満規模であった。
2 発注に関する事項
(1) 在宅就業者への発注開始時期及び理由
在宅就業者への仕事の発注を開始した時期は「1998年〜2000年」(23.5%)が最多
で、「2001年以降」(6.6%)を含めると、1998年(平成10年)以降に発注を開始した
ものは、全体の3割を占める。「1995年〜1997年」(19.1%)を含めると、1995年(平
成7年)以降に発注を開始したものは、全体の約半数に及ぶ。
在宅就業者への仕事の発注を開始した理由(2つ以内の複数回答)としては、「専
門的業務への対応」、「繁忙期への対応」が多い。
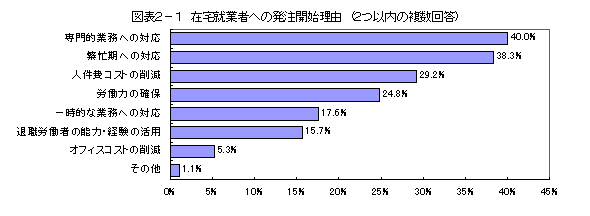 (2) 在宅就業者への発注量の多い仕事内容
発注量の多い仕事内容(3つまでの複数回答)は、「設計、製図、デザイン」、
「文書入力」、「データ入力」が上位を占めた。
(2) 在宅就業者への発注量の多い仕事内容
発注量の多い仕事内容(3つまでの複数回答)は、「設計、製図、デザイン」、
「文書入力」、「データ入力」が上位を占めた。
 3 仕事を発注する在宅就業者の募集・選考に関する事項
(1) 在宅就業者の募集ルート・手段、選考方法
在宅就業者の募集ルートとしては、「社員からの紹介」、「募集せずに会社から
直接依頼」、「本人の売り込み」、「退職(予定)者からの応募、申し出」、「在宅
就業者からの紹介」、「取引先からの紹介」などが多かった。一方、「新聞広告、
情報誌」、「インターネット」といった、不特定多数を対象とした募集媒体の利用
率は低かった。
3 仕事を発注する在宅就業者の募集・選考に関する事項
(1) 在宅就業者の募集ルート・手段、選考方法
在宅就業者の募集ルートとしては、「社員からの紹介」、「募集せずに会社から
直接依頼」、「本人の売り込み」、「退職(予定)者からの応募、申し出」、「在宅
就業者からの紹介」、「取引先からの紹介」などが多かった。一方、「新聞広告、
情報誌」、「インターネット」といった、不特定多数を対象とした募集媒体の利用
率は低かった。
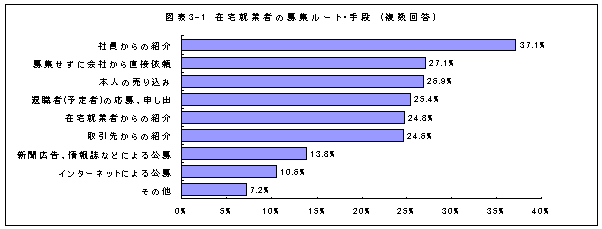 在宅就業者の選考方法(複数回答)では「面接試験」(47.2%)が最多であり、「実
技試験」(27.3%)、「書類審査」(24.4%)がこれに続く。
選考に当たって重視する点としては、「責任感、信頼性」、「当該職種の経験」、
「高度な能力、熟練度」、「仕事への意欲、積極性」などが多かった。
在宅就業者の選考方法(複数回答)では「面接試験」(47.2%)が最多であり、「実
技試験」(27.3%)、「書類審査」(24.4%)がこれに続く。
選考に当たって重視する点としては、「責任感、信頼性」、「当該職種の経験」、
「高度な能力、熟練度」、「仕事への意欲、積極性」などが多かった。
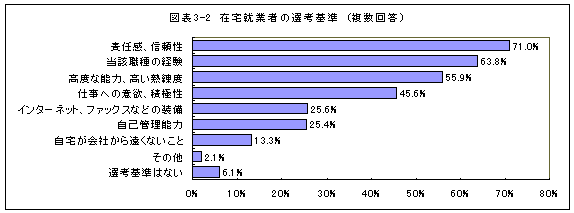 (3) 選考後の在宅就業者への仕事の発注形態及び取引停止の事前予告の状況
選考後の仕事の発注形態は、「恒常・定期的に発注」が38.6%、「仕事毎に選考、
契約する」が30.9%、「登録型」が25.6%であった。
「恒常・定期的に発注」及び「登録型」としている者のうち、約半数が取引停止
を事前に予告をしている。うち約半数が1ヶ月以上前に予告を行っていたが、直前
に通告するものも見られた。
(3) 選考後の在宅就業者への仕事の発注形態及び取引停止の事前予告の状況
選考後の仕事の発注形態は、「恒常・定期的に発注」が38.6%、「仕事毎に選考、
契約する」が30.9%、「登録型」が25.6%であった。
「恒常・定期的に発注」及び「登録型」としている者のうち、約半数が取引停止
を事前に予告をしている。うち約半数が1ヶ月以上前に予告を行っていたが、直前
に通告するものも見られた。
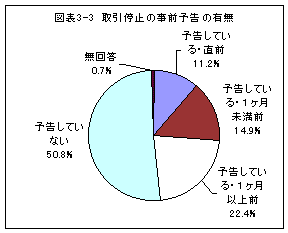 4 契約条件に関する事項
(1) 契約の締結方法
契約は、初回契約時は半数近くが書面(「契約書方式」、「伝票形式」、「メモ程
度」)で交わす一方で、「口頭」も40.7%あった。「電子メール」による契約は11.2%
であった。
一方、2回目以降の契約方法(複数回答)では、「電子メール」や「口頭」など、
より簡便な方法へシフトする傾向が見られる。
4 契約条件に関する事項
(1) 契約の締結方法
契約は、初回契約時は半数近くが書面(「契約書方式」、「伝票形式」、「メモ程
度」)で交わす一方で、「口頭」も40.7%あった。「電子メール」による契約は11.2%
であった。
一方、2回目以降の契約方法(複数回答)では、「電子メール」や「口頭」など、
より簡便な方法へシフトする傾向が見られる。
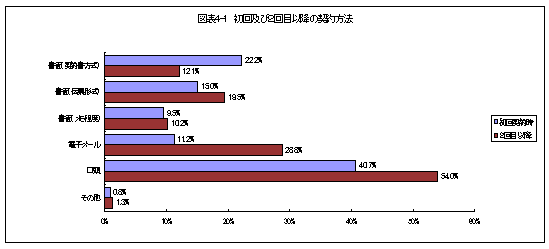 (2) 報酬額の設定
報酬額の単位は、「出来高」(79.9%)が最多で、以下「実際の所要時間」(12.1%)、
「出来高から換算した所要時間」(7.6%)であった。
報酬設定にあたり重視する事項(複数回答)は、「仕事の難易度」、「在宅就業者
の実績、能力」、「同業者の地域相場」などが多い。
報酬の支払時期は、「1ヶ月に一度」(60.6%)が最多である一方、納品の都度(1
ヶ月超)も15.0%見られた。報酬の支払いは、「銀行口座振り込み」(86.7%)が最も
多い。
(2) 報酬額の設定
報酬額の単位は、「出来高」(79.9%)が最多で、以下「実際の所要時間」(12.1%)、
「出来高から換算した所要時間」(7.6%)であった。
報酬設定にあたり重視する事項(複数回答)は、「仕事の難易度」、「在宅就業者
の実績、能力」、「同業者の地域相場」などが多い。
報酬の支払時期は、「1ヶ月に一度」(60.6%)が最多である一方、納品の都度(1
ヶ月超)も15.0%見られた。報酬の支払いは、「銀行口座振り込み」(86.7%)が最も
多い。
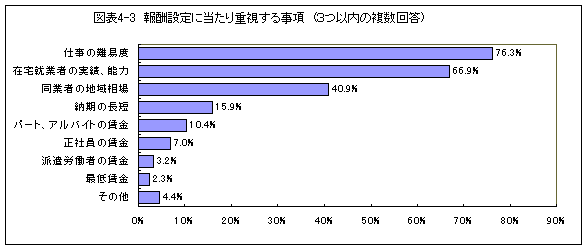 (3) 納期及び納品方法
納期は「業務上の要請に合わせ決定」(50.2%)が最多で、「管理者と在宅就業者が
調整、合意の上設定」(33.9%)がこれに続く。文書入力作業に関し納品方法を尋ねた
ところ、ネット利用のイメージに反し、69.3%が「フロッピーディスク」と回答した。
(4) 成果物の評価
成果物の評価は、「定まったやり方で行っている」(10.0%)、「成果のチェック
などを通じて評価している」(66.7%)を合わせると8割弱が実施しており、報酬単価
や次回の仕事発注にかなりの割合で影響を及ぼしている。
(3) 納期及び納品方法
納期は「業務上の要請に合わせ決定」(50.2%)が最多で、「管理者と在宅就業者が
調整、合意の上設定」(33.9%)がこれに続く。文書入力作業に関し納品方法を尋ねた
ところ、ネット利用のイメージに反し、69.3%が「フロッピーディスク」と回答した。
(4) 成果物の評価
成果物の評価は、「定まったやり方で行っている」(10.0%)、「成果のチェック
などを通じて評価している」(66.7%)を合わせると8割弱が実施しており、報酬単価
や次回の仕事発注にかなりの割合で影響を及ぼしている。
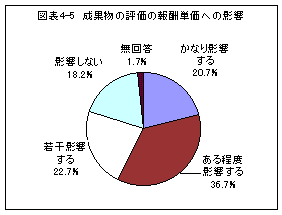
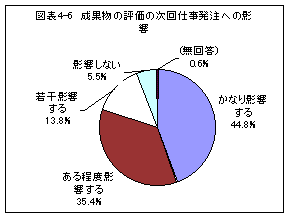 5 健康管理・能力開発
健康診断は、大多数が実施していなかった。
在宅就業者の能力開発については、85.6%が「関心がある」と回答したものの、実施
主体については75.5%が「個人で行うべきである」としており、実際に能力開発を行
っているのは26.5%に留まった。
6 トラブル対応
(1) 問い合わせ・苦情管理体制
在宅就業者からの問い合わせや苦情管理に関しては、「専任者を配置している」
(19.7%)、「個々の業務担当者が管理している」(47.0%)であり、「特にいない」は
33.3%であった。
在宅就業の管理台帳は、「備え付けてある」ものが40.3%で、半数強は備え付け
ていなかった。
(2) 発注に係る問題点及び在宅就業者とのトラブル
在宅就業者の発注にかかる問題点(複数回答)としては、「仕事の成果に個人差が
大きい」、「優秀な人材の確保が難しい」など、個人の能力に関連する事項が多く、
ついで「必要な時に必要な仕事量をやってもらえない」であった。
5 健康管理・能力開発
健康診断は、大多数が実施していなかった。
在宅就業者の能力開発については、85.6%が「関心がある」と回答したものの、実施
主体については75.5%が「個人で行うべきである」としており、実際に能力開発を行
っているのは26.5%に留まった。
6 トラブル対応
(1) 問い合わせ・苦情管理体制
在宅就業者からの問い合わせや苦情管理に関しては、「専任者を配置している」
(19.7%)、「個々の業務担当者が管理している」(47.0%)であり、「特にいない」は
33.3%であった。
在宅就業の管理台帳は、「備え付けてある」ものが40.3%で、半数強は備え付け
ていなかった。
(2) 発注に係る問題点及び在宅就業者とのトラブル
在宅就業者の発注にかかる問題点(複数回答)としては、「仕事の成果に個人差が
大きい」、「優秀な人材の確保が難しい」など、個人の能力に関連する事項が多く、
ついで「必要な時に必要な仕事量をやってもらえない」であった。
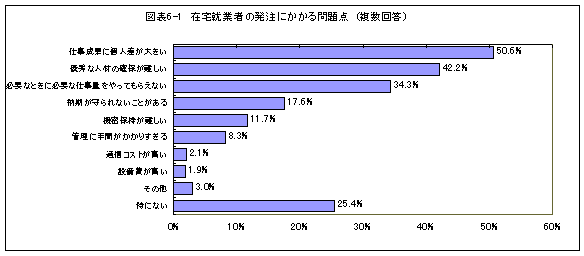 在宅就業者とのトラブルは、「たまにある」(22.9%)及び「よくある」(0.8%)を合
わせて、23.7%が経験している。トラブルの内容としては「仕事の出来具合」、「仕
事の納期」が多い。
在宅就業者とのトラブルは、「たまにある」(22.9%)及び「よくある」(0.8%)を合
わせて、23.7%が経験している。トラブルの内容としては「仕事の出来具合」、「仕
事の納期」が多い。
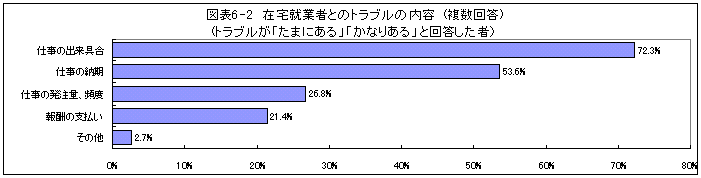 トラブルへの対処方法としては、「説明、説得を行った」が最も多く、「在宅就
業者の言い分をよく聞いた上で納得のいく方法をとった」、「仕事発注を打ち切る
こととした」がこれに続く。
トラブルへの対処方法としては、「説明、説得を行った」が最も多く、「在宅就
業者の言い分をよく聞いた上で納得のいく方法をとった」、「仕事発注を打ち切る
こととした」がこれに続く。
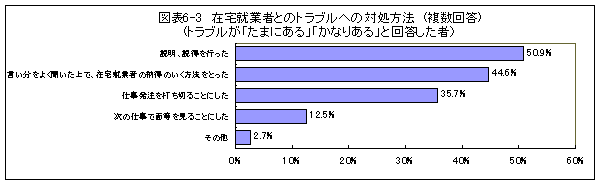 7 在宅就業者への発注の将来展望
過去3年間の発注量の変化は、「増えた」(34.1%)、「変わらない」(33.5%)、「減
った」(32.4%)が拮抗している。
今後の発注量見込みは「現状維持」(38.1%)が最多で、「拡大させる」(32.2%)と合
わせると7割に及び、「減少させる」(7.6%)、「中止する」(0.6%)はあわせても1割に
満たない。「わからない」は21.4%であった。
7 在宅就業者への発注の将来展望
過去3年間の発注量の変化は、「増えた」(34.1%)、「変わらない」(33.5%)、「減
った」(32.4%)が拮抗している。
今後の発注量見込みは「現状維持」(38.1%)が最多で、「拡大させる」(32.2%)と合
わせると7割に及び、「減少させる」(7.6%)、「中止する」(0.6%)はあわせても1割に
満たない。「わからない」は21.4%であった。
TOP
戻る
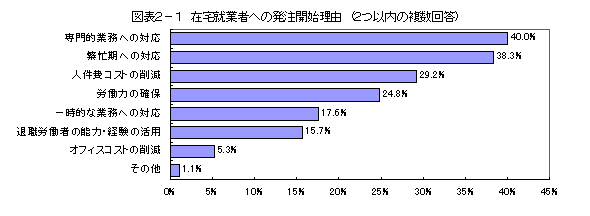 (2) 在宅就業者への発注量の多い仕事内容
発注量の多い仕事内容(3つまでの複数回答)は、「設計、製図、デザイン」、
「文書入力」、「データ入力」が上位を占めた。
(2) 在宅就業者への発注量の多い仕事内容
発注量の多い仕事内容(3つまでの複数回答)は、「設計、製図、デザイン」、
「文書入力」、「データ入力」が上位を占めた。
 3 仕事を発注する在宅就業者の募集・選考に関する事項
(1) 在宅就業者の募集ルート・手段、選考方法
在宅就業者の募集ルートとしては、「社員からの紹介」、「募集せずに会社から
直接依頼」、「本人の売り込み」、「退職(予定)者からの応募、申し出」、「在宅
就業者からの紹介」、「取引先からの紹介」などが多かった。一方、「新聞広告、
情報誌」、「インターネット」といった、不特定多数を対象とした募集媒体の利用
率は低かった。
3 仕事を発注する在宅就業者の募集・選考に関する事項
(1) 在宅就業者の募集ルート・手段、選考方法
在宅就業者の募集ルートとしては、「社員からの紹介」、「募集せずに会社から
直接依頼」、「本人の売り込み」、「退職(予定)者からの応募、申し出」、「在宅
就業者からの紹介」、「取引先からの紹介」などが多かった。一方、「新聞広告、
情報誌」、「インターネット」といった、不特定多数を対象とした募集媒体の利用
率は低かった。
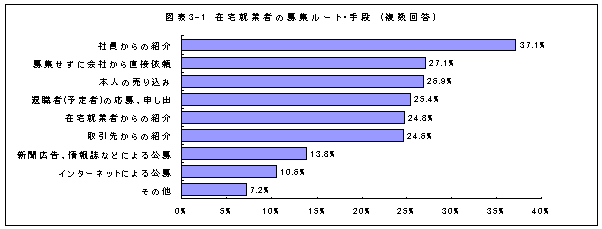 在宅就業者の選考方法(複数回答)では「面接試験」(47.2%)が最多であり、「実
技試験」(27.3%)、「書類審査」(24.4%)がこれに続く。
選考に当たって重視する点としては、「責任感、信頼性」、「当該職種の経験」、
「高度な能力、熟練度」、「仕事への意欲、積極性」などが多かった。
在宅就業者の選考方法(複数回答)では「面接試験」(47.2%)が最多であり、「実
技試験」(27.3%)、「書類審査」(24.4%)がこれに続く。
選考に当たって重視する点としては、「責任感、信頼性」、「当該職種の経験」、
「高度な能力、熟練度」、「仕事への意欲、積極性」などが多かった。
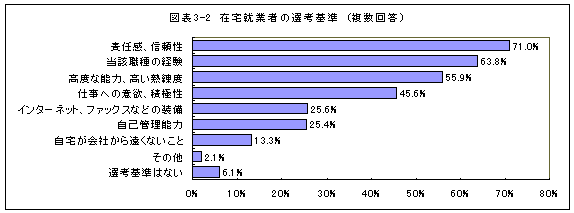 (3) 選考後の在宅就業者への仕事の発注形態及び取引停止の事前予告の状況
選考後の仕事の発注形態は、「恒常・定期的に発注」が38.6%、「仕事毎に選考、
契約する」が30.9%、「登録型」が25.6%であった。
「恒常・定期的に発注」及び「登録型」としている者のうち、約半数が取引停止
を事前に予告をしている。うち約半数が1ヶ月以上前に予告を行っていたが、直前
に通告するものも見られた。
(3) 選考後の在宅就業者への仕事の発注形態及び取引停止の事前予告の状況
選考後の仕事の発注形態は、「恒常・定期的に発注」が38.6%、「仕事毎に選考、
契約する」が30.9%、「登録型」が25.6%であった。
「恒常・定期的に発注」及び「登録型」としている者のうち、約半数が取引停止
を事前に予告をしている。うち約半数が1ヶ月以上前に予告を行っていたが、直前
に通告するものも見られた。
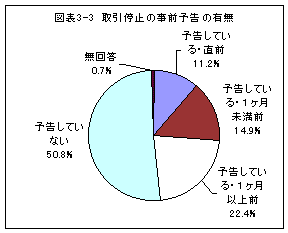 4 契約条件に関する事項
(1) 契約の締結方法
契約は、初回契約時は半数近くが書面(「契約書方式」、「伝票形式」、「メモ程
度」)で交わす一方で、「口頭」も40.7%あった。「電子メール」による契約は11.2%
であった。
一方、2回目以降の契約方法(複数回答)では、「電子メール」や「口頭」など、
より簡便な方法へシフトする傾向が見られる。
4 契約条件に関する事項
(1) 契約の締結方法
契約は、初回契約時は半数近くが書面(「契約書方式」、「伝票形式」、「メモ程
度」)で交わす一方で、「口頭」も40.7%あった。「電子メール」による契約は11.2%
であった。
一方、2回目以降の契約方法(複数回答)では、「電子メール」や「口頭」など、
より簡便な方法へシフトする傾向が見られる。
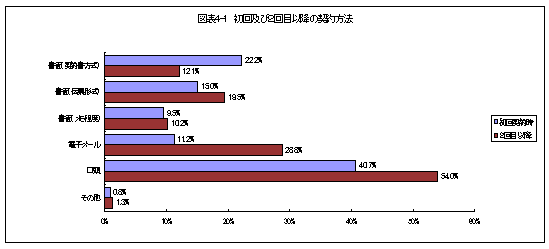 (2) 報酬額の設定
報酬額の単位は、「出来高」(79.9%)が最多で、以下「実際の所要時間」(12.1%)、
「出来高から換算した所要時間」(7.6%)であった。
報酬設定にあたり重視する事項(複数回答)は、「仕事の難易度」、「在宅就業者
の実績、能力」、「同業者の地域相場」などが多い。
報酬の支払時期は、「1ヶ月に一度」(60.6%)が最多である一方、納品の都度(1
ヶ月超)も15.0%見られた。報酬の支払いは、「銀行口座振り込み」(86.7%)が最も
多い。
(2) 報酬額の設定
報酬額の単位は、「出来高」(79.9%)が最多で、以下「実際の所要時間」(12.1%)、
「出来高から換算した所要時間」(7.6%)であった。
報酬設定にあたり重視する事項(複数回答)は、「仕事の難易度」、「在宅就業者
の実績、能力」、「同業者の地域相場」などが多い。
報酬の支払時期は、「1ヶ月に一度」(60.6%)が最多である一方、納品の都度(1
ヶ月超)も15.0%見られた。報酬の支払いは、「銀行口座振り込み」(86.7%)が最も
多い。
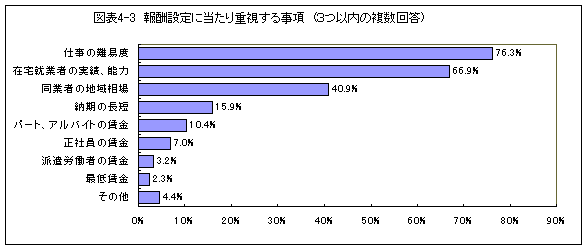 (3) 納期及び納品方法
納期は「業務上の要請に合わせ決定」(50.2%)が最多で、「管理者と在宅就業者が
調整、合意の上設定」(33.9%)がこれに続く。文書入力作業に関し納品方法を尋ねた
ところ、ネット利用のイメージに反し、69.3%が「フロッピーディスク」と回答した。
(4) 成果物の評価
成果物の評価は、「定まったやり方で行っている」(10.0%)、「成果のチェック
などを通じて評価している」(66.7%)を合わせると8割弱が実施しており、報酬単価
や次回の仕事発注にかなりの割合で影響を及ぼしている。
(3) 納期及び納品方法
納期は「業務上の要請に合わせ決定」(50.2%)が最多で、「管理者と在宅就業者が
調整、合意の上設定」(33.9%)がこれに続く。文書入力作業に関し納品方法を尋ねた
ところ、ネット利用のイメージに反し、69.3%が「フロッピーディスク」と回答した。
(4) 成果物の評価
成果物の評価は、「定まったやり方で行っている」(10.0%)、「成果のチェック
などを通じて評価している」(66.7%)を合わせると8割弱が実施しており、報酬単価
や次回の仕事発注にかなりの割合で影響を及ぼしている。
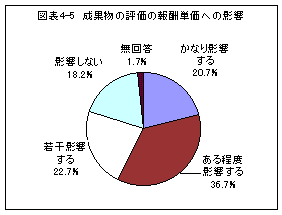
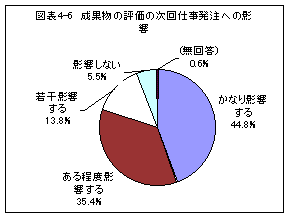 5 健康管理・能力開発
健康診断は、大多数が実施していなかった。
在宅就業者の能力開発については、85.6%が「関心がある」と回答したものの、実施
主体については75.5%が「個人で行うべきである」としており、実際に能力開発を行
っているのは26.5%に留まった。
6 トラブル対応
(1) 問い合わせ・苦情管理体制
在宅就業者からの問い合わせや苦情管理に関しては、「専任者を配置している」
(19.7%)、「個々の業務担当者が管理している」(47.0%)であり、「特にいない」は
33.3%であった。
在宅就業の管理台帳は、「備え付けてある」ものが40.3%で、半数強は備え付け
ていなかった。
(2) 発注に係る問題点及び在宅就業者とのトラブル
在宅就業者の発注にかかる問題点(複数回答)としては、「仕事の成果に個人差が
大きい」、「優秀な人材の確保が難しい」など、個人の能力に関連する事項が多く、
ついで「必要な時に必要な仕事量をやってもらえない」であった。
5 健康管理・能力開発
健康診断は、大多数が実施していなかった。
在宅就業者の能力開発については、85.6%が「関心がある」と回答したものの、実施
主体については75.5%が「個人で行うべきである」としており、実際に能力開発を行
っているのは26.5%に留まった。
6 トラブル対応
(1) 問い合わせ・苦情管理体制
在宅就業者からの問い合わせや苦情管理に関しては、「専任者を配置している」
(19.7%)、「個々の業務担当者が管理している」(47.0%)であり、「特にいない」は
33.3%であった。
在宅就業の管理台帳は、「備え付けてある」ものが40.3%で、半数強は備え付け
ていなかった。
(2) 発注に係る問題点及び在宅就業者とのトラブル
在宅就業者の発注にかかる問題点(複数回答)としては、「仕事の成果に個人差が
大きい」、「優秀な人材の確保が難しい」など、個人の能力に関連する事項が多く、
ついで「必要な時に必要な仕事量をやってもらえない」であった。
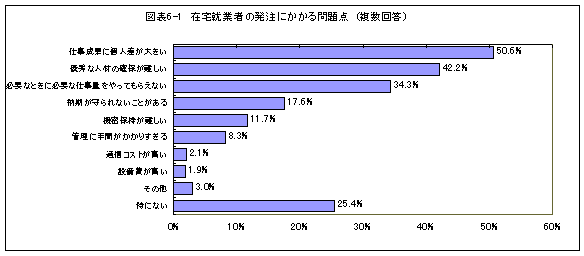 在宅就業者とのトラブルは、「たまにある」(22.9%)及び「よくある」(0.8%)を合
わせて、23.7%が経験している。トラブルの内容としては「仕事の出来具合」、「仕
事の納期」が多い。
在宅就業者とのトラブルは、「たまにある」(22.9%)及び「よくある」(0.8%)を合
わせて、23.7%が経験している。トラブルの内容としては「仕事の出来具合」、「仕
事の納期」が多い。
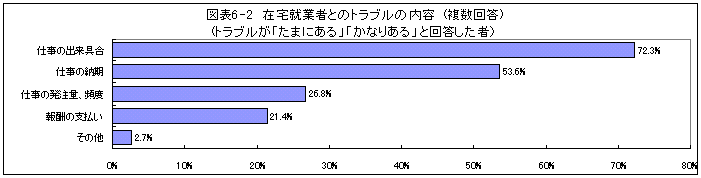 トラブルへの対処方法としては、「説明、説得を行った」が最も多く、「在宅就
業者の言い分をよく聞いた上で納得のいく方法をとった」、「仕事発注を打ち切る
こととした」がこれに続く。
トラブルへの対処方法としては、「説明、説得を行った」が最も多く、「在宅就
業者の言い分をよく聞いた上で納得のいく方法をとった」、「仕事発注を打ち切る
こととした」がこれに続く。
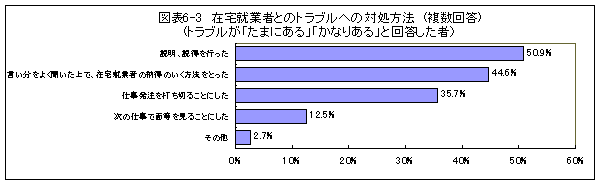 7 在宅就業者への発注の将来展望
過去3年間の発注量の変化は、「増えた」(34.1%)、「変わらない」(33.5%)、「減
った」(32.4%)が拮抗している。
今後の発注量見込みは「現状維持」(38.1%)が最多で、「拡大させる」(32.2%)と合
わせると7割に及び、「減少させる」(7.6%)、「中止する」(0.6%)はあわせても1割に
満たない。「わからない」は21.4%であった。
7 在宅就業者への発注の将来展望
過去3年間の発注量の変化は、「増えた」(34.1%)、「変わらない」(33.5%)、「減
った」(32.4%)が拮抗している。
今後の発注量見込みは「現状維持」(38.1%)が最多で、「拡大させる」(32.2%)と合
わせると7割に及び、「減少させる」(7.6%)、「中止する」(0.6%)はあわせても1割に
満たない。「わからない」は21.4%であった。