欧州における高齢者雇用の現状と政策:日本
日本の高齢者雇用
—政策と現状
- カテゴリー:高齢者雇用
- フォーカス:2006年11月
1. 進行する少子高齢化
日本の65歳以上人口は2005年10月1日時点で20.04%となり、全人口に占める割合(高齢化率)が初めて2割を超えた。また、2002年に厚生労働省職業安定局が行った推計では、労働力人口全体は2002年の6689万人から、2015年には6600万人に、さらに2025年には6300万人へと減少し続けるという見通しが示されている。うち15~29歳の労働力人口は2002年の1486万人が2025年には1080万人と20年ほどの間に約400万人減少していくと予想され、30~59歳の労働力人口は2002年の4273万人から2025年の3980万人へと約300万人減ると見られている。一方、60歳以上の労働力人口は、2002年の929万人から2015年には1270万人にまで増加し、その後2025年にかけて減少はするものの、より若い層の労働力人口ほどは減っていかないと予想されている。
少子高齢化の進行に伴う若・壮年労働力の減少は、社会保障制度、とりわけ公的年金制度を揺るがすことが懸念される。図表1は厚生労働省が発表している、厚生年金保険の被保険者数と受給者数の長期見通しである。1990年には被保険者6.6人で1人の受給者を支えていたが、現状の制度が続くと仮定した場合、2010年になると被保険者2.4人で1人の受給者を支えざるをえなくなり、さらに2030年には1人の受給者を支える被保険者の数が2.2人と1990年の3分の1にまで減少する。
図表1:被保険者と受給者の見通し
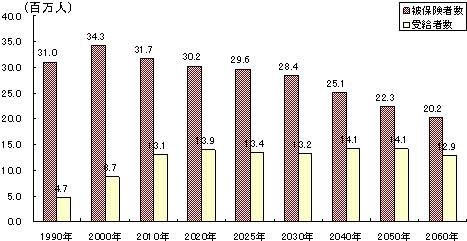
参考資料:「厚生年金・国民年金2004年財政再計算結果」
2.少子高齢化に対応した制度改革
少子高齢化の進行に伴い予想される問題に対応するため、日本では関連する制度の改革が相次いで行われた。公的年金制度については、負担と給付のバランスをとるため、1994年に老齢基礎年金部分の支給開始年齢を2001年から段階的に引き上げることが、2000年には報酬比例部分(老齢厚生年金)の支給年齢を2013年から段階的に引き上げていくことがそれぞれ決まった(図表2)。さらに2004年には、(1)将来の保険料水準を固定した上で、その範囲内でまかなえるように給付水準を調整する仕組みの導入、(2)60歳代前半の在職老齢年金について在職中の一律2割支給を廃止、(3)65歳以降の老齢厚生年金について繰下げ制度(=支給開始年齢を遅らせることで1年あたりの支給額を加算できる制度)導入、などの制度の見直しが行われた。
| 基礎年金部分 | 報酬比例部分 | ||
|---|---|---|---|
| 2001年 | 61歳 | 2013年 | 61歳 |
| 2004年 | 62歳 | 2016年 | 62歳 |
| 2007年 | 63歳 | 2019年 | 63歳 |
| 2010年 | 64歳 | 2022年 | 64歳 |
| 2013年 | 65歳 | 2025年 | 65歳 |
注:女性は上記のスケジュールから5年遅れで実施される
以上のような公的年金制度の見直し、なかでも年齢支給開始年齢の段階的な引き上げとともに、より高年齢に至るまでの就業機会の確保が求められるようになる。就業機会の確保にあたって大きな役割を果たすと考えられるのは、労働者がこれまで勤続してきた企業により長期にわたって雇用される継続雇用の仕組みである。この仕組みの確立を主な目的として、2004年に高齢者の雇用機会拡大を推進するための高年齢者等雇用安定法が見直された。その結果、企業は2006年4月から、老齢基礎年金の支給開始年齢までの雇用延長(定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止)が義務付けられ、継続雇用制度の対象から一部の従業員を除外するためには、労使協定を結ぶことが必要となった(ただし、大企業は2009年まで、中小企業は2011年まで就業規則による一部除外が可能)。そのほか、離職する高齢者に対する求職活動支援書の作成・交付や、募集・採用の上限年齢を設定する際の理由の明示が、企業に求められるようになった。
3.これまでの継続雇用の状況と今後の課題
高年齢者等雇用安定法の施行により、高齢者の就業機会確保や継続雇用の状況はこれから大きく変わっていく可能性があるが、これまでの企業の取り組みはどうであったか。まずは厚生労働省が2004年に実施した『高年齢者就業実態調査』の結果を概観しておこう。
定年制がある事業所のうち67.5%(全体の50.2%)には、勤務延長制度または再雇用制度を設けている。また、再雇用制度または勤務延長制度がある事業所を100%とした場合、再雇用制度を実施している事業所が77.7%、勤務延長制度を実施している事業所が40.4%を占めており、日本企業における継続雇用の主流が定年時にいったん雇用契約を打ち切った上での再雇用であることを確認することができる。
再雇用または勤務延長といった継続雇用制度の適用者については、「原則として希望者全員」という回答は、継続雇用制度を設ける事業所の23.3%にとどまり、4分の3近くの事業所は希望者のなかから適用者を選定している。希望者のなかから適用者を選定する事業所のなかでは、「会社が特に必要と認めたものに限る」というところが61.9%を占めており、何らかの選定基準を設けて適用者を選定しているところ(「会社が定めた選定基準に適するもの全員」)は13.5%に過ぎなかった。
企業が継続雇用後の就業条件をどのように設定しているかについては、財団法人高年齢者雇用開発協会が2002年に実施した「企業の高齢者諸施策の実態に関する調査」(従業員30人以上の企業が対象、回答企業数4416社)が詳細を明らかにしている。継続雇用を実施している3290社のうち、継続雇用後の従業員の仕事内容を「定年時の仕事」としている企業は77.0%、勤務職場を「定年時の職場」としている企業は実に93.6%に達する。所定労働時間についても、「定年前とほぼ同じ水準」と回答した企業が85.6%を占めている。ただし、継続雇用後の身分・役職、給与・賞与といった処遇面については、変更を行う企業が大半である。身分・役職については「嘱託社員」へと移行するという企業が71.7%で、「正社員(役職を継続)」あるいは「正社員(役職なし)」といったように、定年前と変わらず正社員として継続雇用した従業員を取り扱うという回答はいずれも15%前後にとどまる。また、給与・賞与については、「定年前と同じ水準」で継続雇用した従業員を処遇しているところは17.1%と2割にも満たず、「定年前の6~8割」で処遇するという企業が45.9%、さらに水準を引き下げて「定年前の4~6割」で処遇するという回答が20.3%でこれに次ぐ。
継続雇用制度に関連する人事労務管理についてみていくと、現在の日本企業における継続雇用は、仕事の内容や就業時間は定年前とほぼ同様、その上で処遇については定年前から水準を引き下げるという形で行われているケースが多いことがわかる。この形で継続雇用が十分に実現できれば、適職開発や新たな作業方法の導入など継続雇用に伴う様々な施策を新たに実施する必要が無く、しかもこれまでよりも低い人件費負担で同様のアウトプットを期待できるため、企業からすれば最も継続雇用のメリットが大きくなると捉えられているものと見られる。しかし、高年齢者等雇用安定法で基礎年金支給開始年齢までの雇用延長が義務化され、またこれから多様な形で継続雇用に対する従業員のニーズが広がると予想されることから、企業側もより多くの継続雇用の実施を迫られていくであろう。その場合には、定年時と同様の就業内容を継続雇用の条件とするという、これまでの主流パターンにこだわるのが難しくなってくる。こうした事態に備えて、企業と従業員の双方にメリットとなるような人事労務管理のあり方を模索していくことが、企業にとって今後重要な課題となろう。
2006年11月 フォーカス: 欧州における高齢者雇用の現状と政策
- 総論: 欧州の高齢者雇用対策と日本
- ドイツ: 早期退職から高齢者雇用へ―高齢化社会への対応
- フランス: 早期退職が根強い文化
- デンマーク: 福祉国家を維持しつつ高齢者雇用を促進
- 日本: 日本の高齢者雇用-政策と現状-


