労働紛争・解決システム・労使関係:韓国
韓国の労使紛争解決システムと労使関係
(本稿は、韓国外国語大学法科大学教授イ・ジョン氏がJILPTの国際シンポジウムのために執筆した論文をJILPTの責任において要約したものである。)
Ⅰ はじめに
韓国では、1953年に、韓国労働法の四本柱ともいえる、勤労基準法、労働組合法、労働争議調整法、労働委員会法が制定された。しかし、制定当時は、日本植民地時代や米軍政時代を経て朝鮮戦争に繋がる政治的変革期だったために、労働法案の内容に関する十分な議論や検討を行われずに、植民地時代に適用されていた旧日本労働法をモデルにして草案が作られた。そのために、韓国労働法の体系や内容をみると、当時はもちろん現在に至るまで日本の法制度に極めて似ている。それは労使紛争解決システムにおいても例外ではない。例えば、韓国でも日本と同様に、労働争議や不当労働行為のような集団紛争を解決するための労働委員会制度をはじめ、勤労基準法に違反する行為を監督・是正するための勤労監督官制度と、最終的かつフォーマルな労働紛争解決機関として裁判制度を置いている。
もっとも、これらの中では、次第に韓国の風土に合わせる形にその機能が変化したものもある。例えば、労働委員会の場合は、同制度が導入された当時には日本の労働委員会とほぼ同じ機能を果していたが、その後、個別的紛争である不当解雇事件まで取り扱うように再編された。その結果、本来であるならば不当労働行為などの集団的紛争の解決が労働委員会の中心的業務であるはずだが、現在は不当解雇事件のような個別紛争の解決にウェイトが置かれる逆転現象が生じている。しかし、労働委員会は沿革的に集団紛争の解決を前提に設計された制度であるだけに、解雇事件のような個別紛争を解決するには生来的限界がある。そこで、最近は、司法改革の一環として、労働委員会制度の再編や労働裁判制度の導入など、労使紛争解決システムを再編しようとする議論が盛んに行われている。
そこで、以下では、現在の労使紛争解決システムの全体像・実態・問題点などについて紹介・分析した上で、労使紛争システムの見直しをめぐる最近の動きについて概説する。
Ⅱ労使紛争解決機関の概観
1.労働委員会
労働委員会は、公益・労・使をそれぞれ代表する同数の委員からなり、主として労働争議に対する調整業務と不当労働行為や不当解雇に対する判定業務などを行う独立行政機関である。労働委員会は、当初は不当労働行為の救済や労働争議の調整を主たる任務としていたが、1989年の勤労基準法改正の際に個別的な解雇紛争まで取り扱うようになった。労働委員会は、中央労働委員会(以下、中労委)、地方労働委員会(以下、地労委)、特別労働委員会の3種類があり、中労委(ソウルに1カ所)と地労委(地方に12カ所)は労働部長官の下に設置されており、特別労働委員会としては交通部長官の下に船員労働委員会(11カ所)が設けられている。労働委員会は、裁判所とは異なり、労使紛争を迅速でかつ低廉に解決するために出訴期間を短くするほか(注1)、弁護士に代わって比較的に費用の安い公認労務士(注2)による代理を認めている。
労働委員会における紛争処理手続は、労使当事者が地労委に対して救済の申立や調整を申請することから始まる。地労委の決定や判定に不服のある当事者は、中労委に再審査を求めることができる。労働委員会は、審問の結果、申立事実の全部または一部について理由があると判定したときは、その全部または一部に対して救済命令を発し、理由がないと判定したときには、棄却命令を発する。中労委の決定や判定に不服のある当事者は、さらに行政裁判所に行政処分取消訴訟を提起することができる。
労働委員会における紛争処理状況をみると、判定事件・調整事件ともに1988・89年をピークとして徐々に減少する傾向となっている。この時期に労使紛争が急増したのは、政治的民主化の影響を受けて大規模の労働争議が発生したためであり(注3)、その後は労使関係の沈静化に伴い労働争議(調整事件)は激減している。しかし、90年代後半の金融危機を経験してからは雇用調整に伴うリストラ解雇事件が急激に増え、現在は労働委員会に持ち込まれる事件の約7~8割を解雇事件が占めている(注4)。労働委員会では和解による解決を進めているために、審判事件の半数は和解によって終結している。また、労働委員会における紛争処理期間は平均70日であり、中労委への再審査を求める比率は55.9%、行政訴訟を提起する比率は38.2%となっている(いずれも2004年の統計である)。
2.裁判所(注5)
韓国では、日本と同様に、労使紛争を専属管轄する特別裁判所は存在せず、解雇を含む労使紛争は、一般民事事件とともに裁判手続を通じて処理されている。裁判手続は、日本と同じく「3審制」となっており、その他に仮処分手続、民事調停手続、審理手続、救済内容などにおいても、日本とほとんど変わりがない。
中労委の決定や判定に対する取消を求める行政訴訟を提起する場合は、日本と異なり、行政裁判所が第一審となる。行政裁判所の控訴審は高等裁判所であり、その上告審は最高裁判所である。したがって、労働委員会における紛争処理手続は、地労委→中労委→行政裁判所→高等裁判所→最高裁判所といった「5審制」となる。
裁判所は、訴額2000万ウォン以下の事件を担当する「小額裁判部」と軽微または簡単な事件を担当する「単独裁判部」、また比較的争点が複雑な事件を担当する「合意部」の三つに分かれている。民事裁判手続における労働関係事件の受理件数をみると、賃金関係が最も多い14676件を占めており、その次が損害賠償関係で1859件、退職金関係が848件、解雇関係が202件の順となっている(注6)。一方、行政裁判手続における労働事件の受理件数をみると、2000年に400件強に過ぎなかったものが、2001年以後は500件を超えるなど益々増えている。
韓国では、以上の一般裁判手続とは別に、憲法裁判所が設けられている点でも日本とは異なる。憲法裁判所は、法律の違憲有無、弾劾、政党の解散、国家機関および地方自治団体相互間の権限争議、憲法訴願などを審判するために、1988年に設立された特別裁判所である(憲法裁判所法第2条)。同裁判所は、1989年1月25日、初の違憲判決を下して以来、これまで数多くの違憲判決を出しており、なかには労働関係法令に関するものもかなり多い。
3.その他
労使紛争を処理している行政機関としては、労働委員会の他に「勤労監督官」がある。これは、基本的に勤基法をはじめ、労働関係法令に違反する行為を監督する監督機関ではあるが、実際には労使紛争を処理する機能も果たしている。勤労監督官は、勤労基準法などに違反した使用者に対して、25日以内にこれを是正するよう行政命令を発し、場合によっては、法律が定める一定の範囲内で司法警察官の職務権限を行使することも可能である(勤基法104条5項)(注7)。
労働監督機関に関する職制は、まず、労働部長官所属の下に地方労働庁(6カ所)が設けられており、その地方労働庁(長)所属の下に、さらに地方労働事務所(35カ所)が設けられている。各地方労働事務所において、勤労監督業務に従事している監督官の数は、2004年現在、573人となっている。
しかし、勤労監督官は、あくまで労働者の申立に基づき勤基法などに違反した行為を摘発・是正する監督機関である。したがって、勤労監督官は、特に労使当事者(特に使用者)がイニシアチブをもって円満な解決を図る紛争処理機関とはいい難い。そればかりではなく、法律に明らかに反する行為はともかく、整理解雇のような精緻な判断を要する事案を果たして監督官が判断できるかは大いに疑問である。もちろん、専門的知識をもつ有能な監督官なら、このような解雇事件に対応できるかも知れない。しかし、現実の監督官とは短期間の交替制や専門教育の不足などによって必ずしもそういった能力をもっているとは限らない。それだけではなく、数的にも限られているため、監督官が、個別的労働関係事項から集団的労使関係事項に至る夥しい事件に対応できるというのは、現実的に期待し難い。
その他にも、男女雇用平等法の実現や同法上の紛争を調整するための「雇用平等委員会」が各地方の労働庁に設置されており(男女雇用平等法第27条~29条)、また男女差別事項に対する調査・是正勧告その他男女間の差別を改善するための「男女差別改善委員会」が女性部長官の下に設けられている(男女差別禁止および救済に関する法律第9条~20条)。しかし、これらの行政機関は、勤労監督官と同様に、基本的には労働関係法令に違反する行為を摘発・是正するのが主たる目的であるため、労使紛争処理機関としては制限的な役割しか果たしていない。
| 機関の種類 | 機能 | |
|---|---|---|
| 行政機関 | 労働委員会 | 判定業務(不当労働行為・不当解雇) 調整業務(労働争議の調停・仲裁) |
| 勤労監督官 | 勤労基準法などの違反行為の摘発・是正 | |
| 雇用平等委員会 | 男女雇用平等法の実現や同法上の紛争の調整 | |
| 司法機関 | 一般裁判所 | 民事裁判手続、仮処分、民事調停 |
| 行政裁判所 | 行政処分の取消訴訟(第一審) | |
| 憲法裁判所 | 法令に対する違憲審査 | |
Ⅲ労使紛争解決システムの問題点と見直し
1.労働委員会制度
労使紛争解決システムの中心に据えられた労働委員会は、労働争議の調整や不当労働行為の救済を始め、解雇紛争のような個別紛争に至るまで様々な労使紛争を解決し、労使平和に大きく寄与したことは否定できない。しかし、労働委員会は、本来、集団的労使紛争を解決するために導入された制度だったために、同委員会が解雇紛争のような個別的権利紛争を処理するには様々な問題が生じている(注8)。その他にも、全般的な問題として、韓国では、すべての労働委員会が中央政府(労働部)の管理下に置かれており、また現行法の中には国や政府機関が介入する余地を残している規定すらある(注9)。また、労使紛争を専門的に解決するための労働問題専門家が少ないことも問題点として指摘されている。特に、最近には不当解雇事件などの個別紛争が増加しているにもかかわらず、審査官の数は従前のままであるために、審査官1人が担当する件数は年間170件を超え(注10)、事件処理が遅延している原因の一つとなっている。
そこで、労使関係制度先進化研究委員会(注11)は、2003年の「労使関係法・制度先進化方案」という報告書において、上記の専門家の確保を含めた様々な改善策を具体的に提示し、将来の労働委員会の改革に反映しようとしている。
2.裁判制度
労使紛争の発生ルートは異なってもその終着駅は裁判所である。例えば、労災補償をめぐる紛争は、勤労福祉公団→労災保険審査委員会→(不服)→行政裁判所→ 高等裁判所(特別部)→最高裁判所の順となり、不当労働行為事件や不当解雇事件は、地労委→中労委→(不服)→行政裁判所→ 高等裁判所(特別部)→最高裁判所の順となる。その他の紛争(賃金、解雇、損害賠償など)は、地方裁判所→高等裁判所(民事部)→最高裁判所の順となる。
労使紛争解決の流れ
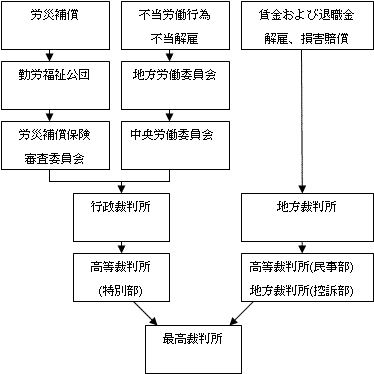
このように、労災事件や不当労働行為、解雇事件の場合は、実際に「5審制」となっており、不当解雇事件の場合は、労働委員会を通じて裁判に救済を求める手続と直接地方裁判所の民事裁判手続に訴えることもできる。その結果、多くの労働事件(特に解雇事件)の場合は、こうした5段階に辿り着くまでは権利義務関係が確定されないから、その間雇用関係が不安定な状態となる問題が生じている。そればかりでなく、労働事件が裁判所と労働委員会において並列に進められる結果、両機関の判断が異なる場合は、どちらの判断を優先すべきかなどのもっとややこしい問題が生じうる。その他にも、民事裁判手続は基本的に一般の民事事件の解決を前提としているために、労働関係の特殊性を反映している複雑な事件には十分対応できないという問題点も指摘されている。
そこで、司法改革委員会は、2004年12月、長期的に労働事件の特殊性を考慮して労働事件を効率的かつ専門的に解決するための専門裁判所または専門裁判部の設置を提案した(注12)。
この提案を受けて、同委員会の中に「労働紛争解決制度委員会」が組織され、そこでは労働裁判所の導入や労働委員会の改変など労使紛争解決システム全体に対する見直しを検討している。しかし、これらの問題をめぐっては、労使団体や政府、労働部、労働委員会、裁判所の利害関係が絡んでいるのでなかなかコンセンサスを得られないのが現状である(注13)。
このような中で、ソウルの中央地方裁判所では、「労働事件専門調停委員会」制度を導入し、今年9月1日から労働事件に対する調停的解決を図る試みがスタートした。同委員会は、労働問題に詳しい33人の学者や弁護士などからなり、2005年にはソウル中央地裁において試験的に稼動してみてその結果がよければ2006年からは全国的に拡大する計画である。
3.勤労監督制度
現行労働法は、賃金不払や不当解雇、不当労働行為について刑事処罰規定を定めている。したがって、労働者は、これらの行為をした使用者を勤労監督官に陳情、告訴、告発をして、その是正を求めることができる。地方の勤労監督署における紛争処理状況をみると、2004年の場合、全国の監督署に受理された件数は214564件であり、そのうち、行政処理が107755件として最も多く、司法処理が92178件、対象外が7462件となっている。違反の内容は、賃金関係の金品清算関連事件が96.7%として圧倒的に多く、不当解雇事件や不当労働事件は1923件と1165件に過ぎない。
このように、勤労監督官が処理する事件をみると、賃金絡みの金品清算事件に集中しており、最近になっては、景気後退や雇用調整の影響もあって受理件数が増えている。その結果、勤労監督官1人が年間担当する事件の数も290件に達し、監督官の業務量の過負荷や平均処理日数の遅延(平均処理日数は51日)が問題となっている。そこで、勤労監督官が本来の機能を果すようにするためには、労働問題に関する専門知識や経験を有する監督官を如何に確保するかが最大の課題となっている。
Ⅳおわりに
現在の労働紛争解決システムができてからもう半世紀が経っている。その間、労働委員会や裁判所そして勤労監督官は、労使紛争の解決において「三役」ともいわれるほど、それぞれの役割を十分に果してきたといえる。しかし、近来は、企業の国際化や雇用の多様化、組合組織率の低下が進む中、労使紛争の様子も変化している。例えば、従来ならば、解雇または賃金関係の紛争や不当労働行為絡みの紛争が多かったのに対して、最近は、非正規職労働者の雇用問題やセクハラ、労働条件の変更問題に至るまで紛争が多様化している。このような変化は、現在の労使紛争解決システムができた当時には予測もできなかったので、次第に紛争処理において乖離が生じている。こうした背景に労働委員会の再編し、労働裁判所を導入しようとする論調が高まっている。しかし、労働裁判所の導入をめぐっては労使団体をはじめ各界の意見が一致しておらず、また、労働裁判所を導入するとしてもその審級をどうするか(第一審の地裁レベルで設置するかあるいは第二審の高裁レベルで設置するか)、また事物管轄の範囲はどうするか、労働委員会との関係はどのように定立するかなどの様々な課題が残されている(注14)。そのほかにも、労働裁判所がその機能を発揮するためには労働問題に詳しい労働専門裁判官を確保しなければならないが、そのような人材をどのように確保するかも問題となる。したがって、前述した労使紛争解決システムの見直しは、現在進行している司法改革とも密接な関係にあるので、その成り行きが注目される。
("This work was supported by Hankuk University of Foreign Studies Research Fund of 2005")
注
- 地労委への申立は、違法行為があった日から3カ月以内に行わなければならず、地労委の決定または命令に不服のある場合は、その決定または命令が送達されてから10日以内に中労委に再審査を申請しなければならない。さらに、中労委の決定または命令に対する取消訴訟は、その決定または命令送達の日から15日以内に行政裁判所(第一審)に提起しなければならない。
- 公認労務士とは、日本の「社会保険労務士」にあたる労働問題専門家であり、主に諸行政機関に提出または申告する業務や書類の作成、訴訟代理、労働相談などを行っている。2005年10月現在、登録されている公認労務士は639人であり、そのうち、372人が開業している。
- 韓国は、1987年から1988年にわたってかつて経験したこともない多くの労使紛争が発生したが、そのきっかけとなったのが1987年のいわゆる「民主化宣言」である。同宣言は、文字通りに政治民主化の宣言に過ぎないけれども、その波及効果は経済や社会・労働分野にいたるまで大きかった。労働分野に限っていうと、永年にわたり労働組合の念願だった組合活動に対する制限規定が廃止され、労働組合運動が活発になる契機となった。
- 労働委員会における救済申立状況(件)
出所:中央労働委員会区分 2002年 2003年 2004年 計 8024 6799 7606 不当労働行為 1787 1332 1262 不当解雇など 5348 5246 6163 その他 889 221 181 - 韓国では、憲法裁判所以外のすべての裁判所を「法院」と呼んでいる。
- 民事裁判手続に受理された労働関係事件の内訳は以下のとおりである(2003年)。
出所:裁判所行政処事件区分 解雇 賃金 退職金 損害賠償 計 単独裁判部 16 1284 107 1603 3010 合意部 159 234 40 37 470 小額裁判部 27 13158 701 219 14105 合計 202 14676 848 1859 17589 - 韓国では、日本とは異なり、不当解雇や不当労働行為を厳しい処罰規定をもって禁止している。したがって、使用者が、不当解雇禁止規定に違反した場合は5年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処せられ、また、不当労働行為禁止規定に違反した場合は2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処せられる。
- 韓国労働委員会の現状と課題に関する詳細は、李?『解雇紛争解決の法理』(信山社、2001)294頁参照。
- 例えば、労働委員会法第8条によれば、労働関係業務に15年または10年以上の経験のある者は一定の要件の下で、中労委や地労委の公益審判委員または公益調整委員になるようになっており、実際に労働委員会の常勤委員の中にはこのようなケースも多い。
- 中労委の場合、審査官10人が1714件を処理し、一人当たり170件以上を担当している。いずれも2004年の統計である。
- 「労使関係制度先進化研究委員会」とは、現政権が出帆した当時の公約の一つである労使関係の先進化を図るために、2003年5月に組織された研究組織である。同組織は、労働問題に詳しい15人の学者が集まり、3カ月という実に短い期間で労使関係のあり方を検討した後、労働法全般にわたる改善策を「労使関係法・制度先進化方案」という報告書にまとめられた。現政権は、同報告書に関する労使当事者や各界の意見を聞いたうえで、立法に乗り出す方針である。
- 司法改革委員会『司法改革のための建議文』(2004.12.31)11頁。
- 労働裁判所の導入に対する各界の立場をみると、労働委員会は自らの組織を代替する形での労働裁判所の導入に反対しており、経営者団体も労働裁判所の導入には基本的に反対している。これに対して、労働組合団体は労働裁判所の導入を歓迎している。
- 労働裁判所の導入に伴う問題点に関する分析については、イ・ジョンほか『労働裁判所の導入における法的争点と課題』(韓国労働研究院、2005年)参照。
2006年1月 フォーカス: 労働紛争・解決システム・労使関係
- 日本: 日本における労働紛争の解決-最近の展開とその背景、および将来の展望
- 韓国: 韓国の労使紛争解決システムと労使関係
- アメリカ: アメリカにおける個別雇用紛争解決
- ドイツ: 労働、雇用関係における紛争解決:ドイツの事例
関連情報
- 海外労働情報 > フォーカス:掲載年月からさがす > 2006年以前 > 2006年の記事一覧
- 労使関係に関する報告書
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > 韓国の記事一覧
- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > 韓国
- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > 韓国


